公開日:2025.11.04
更新日:2025.11.04
ファクタリング利用中に「差し押さえ」は起きる?税金滞納が招くリスクと法人経営者がすべき回避策を解説
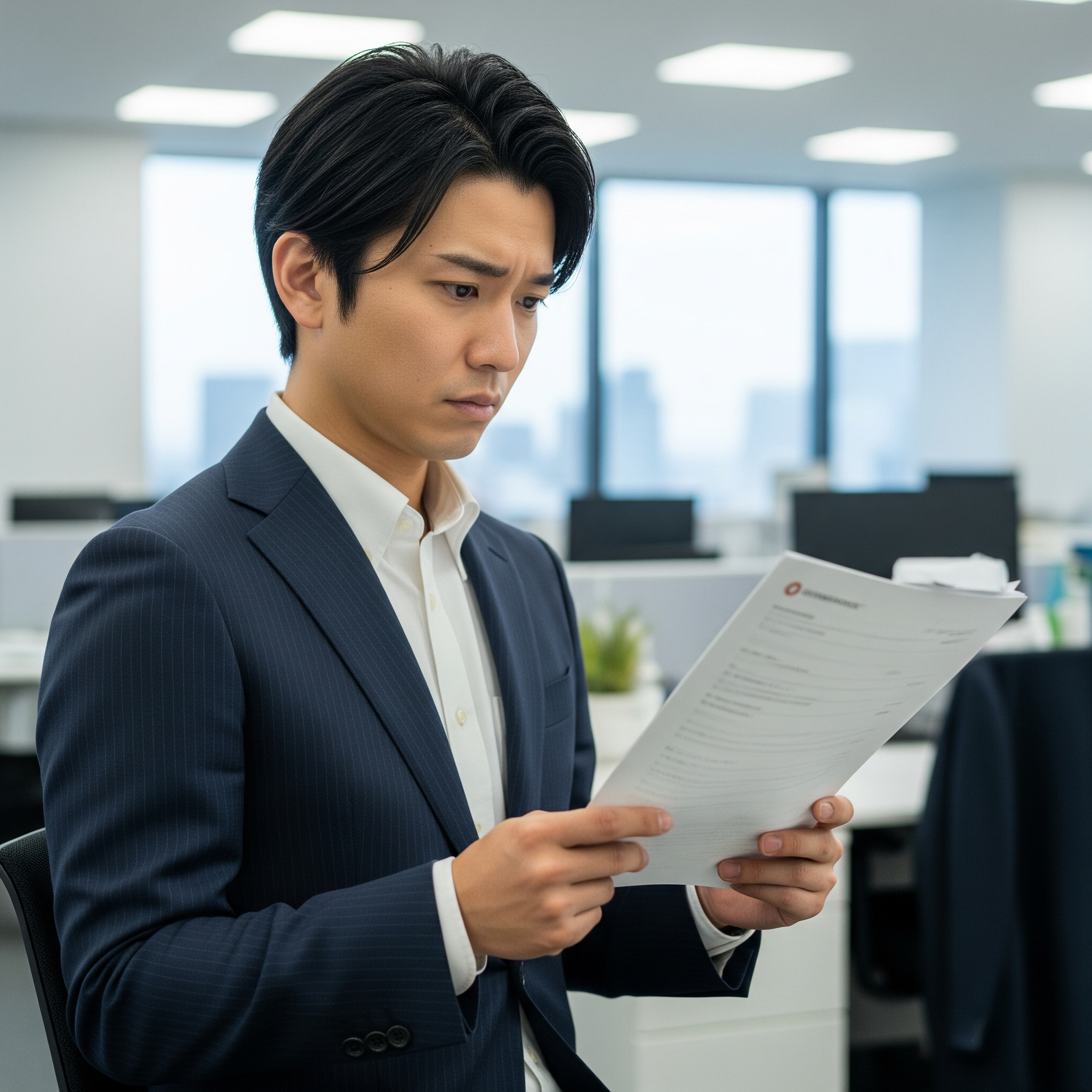
「ファクタリングで資金調達したのに、税金を滞納して差し押さえ通知が来たらどうなる?」
「売却したはずの売掛金まで、差し押さえの対象になってしまうのか?」
資金繰りに悩む法人経営者様にとって、「差し押さえ」は事業の存続に関わる深刻な問題です。特にファクタリングを利用中の場合、その法的な扱いは複雑で、不安を感じている方も少なくありません。
結論から言えば、ファクタリング利用中であっても、特定の条件下(特に税金滞納など)では差し押さえが実行されるリスクは存在します。しかし、そのリスクはファクタリングの契約形態(2社間・3社間)や、法的な対抗要件によって大きく変わります。
この記事では、法人経営者様が知っておくべき以下の点を、金融と法律の専門家が徹底的に解説します。
- ファクタリング中の売掛金と差し押さえ、法的にどちらが優先されるのか?
- 税金滞納や債務不履行で差し押さえに至る具体的な流れ
- 2社間と3社間で異なる差し押さえリスクの決定的違い
- 万が一の事態を回避し、事業を守るための具体的な防止策
- 差し押さえリスクのない安全な資金調達法(ビジネスローン等)
※この記事は法人(株式会社、合同会社など)の経営者様を対象としています。個人事業主様の資金調達(ファクタリング)については、別サイト「HTファクタリング」をご参照ください。
※ファクタリングの基本については、まずはこちらの記事をご覧ください。
『ファクタリングの仕組みとは?メリット・デメリットや利用の流れを解説』
- ファクタリング利用中でも、税金滞納などを理由に資産(預金口座や売掛金)が差し押さえられるリスクはあります。
- 「2社間」は売掛先への通知がないため、入金口座が差し押さえられやすい一方、「3社間」は債権譲渡通知(対抗要件)により、売掛金自体が差し押さえ対象外となる可能性が高いです。
- 一般債権者の差し押さえより、税務署(国税)の差し押さえが優先されるケースが多く、最も注意が必要です。
- 差し押さえを回避するには、税務署への早期相談(分納・猶予)や、債権譲渡登記の活用が有効です。
- HTファイナンスでは、差し押さえリスクのない法人向けビジネスローンもご提案しています。
税金滞納や資金繰り悪化による差し押さえの不安は、早期の対策が鍵となります。HTファイナンスは、法人経営者様専門の金融コンサルタントとして、最適な資金調達プランをご提案します。(※個人事業主様は対象外となります)
まずは無料で借入枠を診断するファクタリング利用中の差し押さえ
ファクタリングを活用している企業でも、特定の状況下では、資産や売掛金が差し押さえられるリスクが存在します。まずは、差し押さえの基本と、ファクタリング利用中における差し押さえリスクについて理解しましょう。
差し押さえの仕組み
差し押さえとは、債権者が債務者の財産を強制的に確保する法的手続きです。民事執行法に基づき、債権者は債務者が支払いを行わない場合、裁判所に申立てを行い、債務者の財産を差し押さえることができます。(参考:民事執行法)
差し押さえの対象となる財産は、多岐にわたります。現金や預金口座、不動産、動産(車両や設備など)、そして売掛金などの債権も含まれます。差し押さえられた財産は、債務者が自由に処分できなくなり、最終的には競売などにより換金され、債権者への支払いに充てられます。
企業が、税金や社会保険料を滞納した場合、税務署や年金事務所などの公的機関も、特別な手続きで差し押さえを行う権限を持っています。これは、国税徴収法などの特別法に基づくもので、裁判所の判決なしに差し押さえが可能です。(参考:国税徴収法)
ファクタリングと差し押さえの関係性
ファクタリングは、企業が保有する売掛金を買取業者(ファクタリング会社)に売却して、即時に資金化するサービスです。ファクタリングには、2社間方式と3社間方式があり、それぞれ差し押さえリスクが異なります。
2社間ファクタリングでは、売掛金の所有権はファクタリング会社に移りますが、売掛先(債務者)には通知されません。このため、売掛先は元の債権者(ファクタリング利用企業)に支払いを行います。この場合、売掛金が入金された後、ファクタリング会社への支払いが行われる前に、差し押さえが入るリスクがあります。
一方、3社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡通知が行われ、支払先がファクタリング会社に変更されます。この場合、債権譲渡が適切に通知された売掛金は、差し押さえ対象から外れることになります。
差し押さえが発生する主な原因
ファクタリング利用中に差し押さえが発生する主な原因は、税金や社会保険料の滞納です。法人税、消費税、固定資産税といった税金のほか、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料を滞納した場合には、税務署や年金事務所が差し押さえを実施することがあります。
また、金融機関やリース会社への債務の返済が滞った場合にも、差し押さえが行われる可能性があります。この場合、債権者が裁判所に申し立てを行い、債務名義を取得した上で差し押さえを実行します。
取引先や従業員に対する支払いが長期間滞った場合も、裁判などの法的手続きを経て差し押さえに至るケースがあります。特に、取引先が経営危機に陥った際には、急に未払い金の請求が発生し、差し押さえにつながる場合もあるため注意が必要です。
これらの債務が一定期間支払われず、かつ債権者からの督促に応じない場合、差し押さえの条件が整ったと判断され、法的手続きが開始されます。
債権譲渡と差し押さえはどちらが優先される?
ファクタリング(債権譲渡)と差し押さえが競合した場合、どちらが優先されるのでしょうか。これは「どちらが先に対抗要件を備えたか」というタイミングで決まります。特に対象が「税金滞納」か「一般債権(借入金など)」かで、その効力が異なります。
勝敗を決める「対抗要件」とは
対抗要件とは、債権を譲り受けたこと(ファクタリング会社が買い取ったこと)を、債務者(売掛先)や第三者(差し押さえをする税務署や他の債権者)に法的に主張するための要件です。
民法第467条では、以下のいずれかが必要と定められています。
- 債務者(売掛先)への通知・承諾:確定日付ある証書(内容証明郵便など)で「債権を譲渡しました」と通知し、それが売掛先に到達する。(主に3社間ファクタリングで利用)
- 債権譲渡登記:法務局に債権譲渡の事実を登記する。(主に2社間ファクタリングで対抗要件を備えるために利用)
(参考:法務省『債権譲渡登記制度の概要』)
この「対抗要件を備えた日(時刻)」と「差押通知が売掛先に到達した日(時刻)」を比較し、早い方が優先されます。
【図解】差し押さえと債権譲渡の優先順位
ケース①:債権譲渡が差し押さえより先(対抗要件あり)
(登記または通知が完了)
すでに対抗要件を備えた債権譲渡が完了しているため、売掛金はファクタリング会社の資産となり、差し押さえは原則として無効となります。
ケース②:差し押さえ通知が債権譲渡より先
差し押さえ通知が売掛先に到達した時点で債権は凍結されます。その後の債権譲渡は差し押さえに劣後するため、ファクタリングは実行できません。
最も危険な「税金滞納」の優先度
一般債権者(銀行や取引先)による差し押さえは、上記(ケース①)の通り、対抗要件を備えたファクタリングが優先されます。
しかし、税金(国税・地方税)の滞納は例外です。国税徴収法では、税金は他のあらゆる債権に優先する(法定納期限が早い方が優先)と定められています。仮にファクタリング(債権譲渡登記)が完了していても、そのファクタリングの対象となった売掛金の「法定納期限」よりも前に滞納している税金があった場合、税務署は登記後であっても差し押さえを実行できるとされています。
これが、2社間ファクタリングで売掛金が入金された口座が、即座に税務署に差し押さえられる最大の理由です。
すでに滞納・督促が発生している場合の対処法
もし、すでに税金を滞納していたり、督促状が届いていたりする場合、差し押さえは目前に迫っています。この状況でファクタリングを利用する際は、以下の点に注意が必要です。
最優先は「税務署への相談」
最も重要なのは、ファクタリング会社を探すことよりも先に、管轄の税務署(または役所)の徴収担当窓口へ相談に行くことです。
誠実に納税の意思を示し、現状の資金繰りを説明すれば、「換価の猶予」(差し押さえ財産の売却を待ってもらう)や「納税の猶予」、「分割納付(分納)」といった相談に応じてもらえる可能性が十分にあります。
(参考:国税庁『国税を納付できない方へ』)
この交渉が成立すれば、差し押さえを一時的に回避し、その間にファクタリングや他の資金調達で納税資金を確保する時間が生まれます。
ファクタリング会社への正直な申告
税金滞納の事実を隠してファクタリング契約を結ぶのは絶対に避けてください。これは契約違反にあたり、万が一発覚した場合、即時買い戻し(一括返済)を求められたり、悪質な場合は詐欺(詐害行為)として法的措置を取られたりするリスクがあります。
信頼できるファクタリング会社であれば、滞納の事実を正直に伝えた上で、税務署との交渉と並行して手続きを進めるなど、最善策を一緒に考えてくれるはずです。
ファクタリングの種類別の差し押さえのリスク
ファクタリングの方式によって、差し押さえられるリスクや影響は大きく異なります。ここでは、主要なファクタリング方式ごとのリスクを詳しく見ていきましょう。
2社間ファクタリングにおける差し押さえのリスク
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社と利用企業の間だけで取引が完結する方式です。売掛先(債務者)には債権譲渡の通知を行わないため、売掛先は引き続き利用企業に支払いを行います。
この方式の最大のリスクは、売掛金が利用企業の口座に一旦入金された後、差し押さえが行われる可能性があることです。法的には売掛金の所有権はファクタリング会社に移転していますが、第三者対抗要件を備えていないケースが多いため、債権者から見れば差し押さえ可能な資産と判断されやすくなります。
また、利用企業が破産手続きに入った場合、適切な対抗要件を備えていないと、ファクタリング取引が否認される可能性もあります。これにより、既に支払われた資金の返還を求められるリスクもあります。
2社間ファクタリングを利用する場合は、入金後すぐにファクタリング会社への送金を行うか、債権譲渡登記などの対抗要件を備えることが重要です。
3社間ファクタリングと差し押さえのリスク
3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先に対して債権譲渡通知を送付します。これにより、売掛先は直接ファクタリング会社に支払いを行うようになります。
この方式の最大のメリットは、債権譲渡通知によって第三者対抗要件が備わるため、適切に手続きが行われていれば、売掛金が差し押さえられるリスクが大幅に減少する点です。債権の所有権がファクタリング会社に移転したことが、法的に明確になるためです。
ただし、注意すべき点もあります。債権譲渡通知の日付が、差し押さえ命令よりも後の場合、差し押さえが優先されます。また、債権譲渡が詐害行為(債権者を害する目的で行われた行為)と判断されると、取り消される可能性もあります。
3社間ファクタリングを利用する場合でも、税金や社会保険料などの優先債権への支払いを疎かにしないことが重要です。優先債権は、一般的な債権譲渡よりも優先される場合があります。
ファクタリング利用中の差し押さえの流れ
ファクタリング利用中に差し押さえが行われる場合、どのような手続きで進むのかを理解しておくことは重要です。差し押さえのプロセスを知ることで、適切な対応策を講じることができます。
税金滞納による差し押さえの流れ
税金滞納による差し押さえは、国税徴収法や地方税法に基づいて行われます。その手続きの流れは、以下のようになります。
まず、納付期限を過ぎると、税務署や自治体から督促状が送付されます。督促状の発送から通常10日以上経過すると、差し押さえが可能になります。督促状を無視すると、次に財産調査が行われます。税務署は金融機関や売掛先に対して調査を行い、差し押さえ可能な財産を特定します。
その後、差し押さえ予告通知が送られることがあります。これは、法的義務ではありませんが、多くの場合、実際の差し押さえ前に予告が行われます。予告に応じない場合、実際の差し押さえ通知(差押通知書)が債務者と第三債務者(銀行や売掛先)に送付されます。
差し押さえられた財産は、最終的に換価(現金化)されます。銀行預金の場合はそのまま徴収されますが、売掛金の場合は入金後に徴収されます。差し押さえられた金額が税金の滞納額を超える場合、超過分は返還されます。
民事訴訟に基づく差し押さえの流れ
民事訴訟に基づく差し押さえは、民事執行法に従って行われます。その流れは、次のようになります。
まず、債権者が裁判所に訴訟を提起し、判決または支払督促などの債務名義を取得します。この債務名義を基に、債権者は裁判所に対して強制執行の申立てを行います。申立てを受けた裁判所は、債務者の財産に関する情報を収集し、差押命令を発します。
差押命令は、債務者と第三債務者(銀行や売掛先)に送達されます。送達を受けた第三債務者は、債務者への支払いを停止し、裁判所が指定する供託所に支払いを行う義務が生じます。最終的に、供託された金銭は債権者に交付されます。
民事訴訟に基づく差し押さえの場合、複数の債権者がいると、原則として差押命令が送達された順番に優先権が与えられます。ただし、抵当権などの担保権が設定されている場合は、その優先順位に従います。
差し押さえ後の対応
差し押さえを受けた後でも、状況を改善するための対応策はいくつかあります。
税金滞納による差し押さえの場合、税務署との分割納付の交渉が可能です。誠意をもって交渉し、現実的な分割納付計画を提示すれば、差し押さえの解除や緩和が認められることがあります。財産の差し押さえが事業継続を著しく困難にする場合、換価の猶予を申請できる場合もあります。
民事訴訟による差し押さえの場合は、債権者との直接交渉が重要です。分割返済の提案や、一部支払いによる差し押さえ解除の交渉などが考えられます。複数の債権者がいる場合は、弁護士の協力を得て、債務整理や民事再生などの法的手続きを検討することも選択肢となります。
いずれの場合も、差し押さえ後は、速やかに専門家(税理士や弁護士)に相談することが重要です。早期の対応が、状況改善の鍵となります。また、今後の再発防止のためにも、税金の納付計画や資金繰り計画を見直すことが必要です。
ファクタリング利用中の差し押さえを避けるための対策
ファクタリング利用中に、差し押さえリスクを最小限に抑えるためには、事前の対策と適切な契約形態の選択が重要です。ここでは、具体的な対策方法を紹介します。
適切なファクタリング方式の選択
差し押さえリスクを考慮すると、3社間ファクタリングが安全な選択となります。3社間方式では、売掛先に債権譲渡通知が送られるため、第三者対抗要件が備わり、売掛金がファクタリング会社の所有物であることが法的に明確になります。
2社間ファクタリングを選択する場合は、債権譲渡登記を行うことでリスクを軽減できます。登記には費用がかかりますが、確実な対抗要件を備えることで、差し押さえリスクを大幅に低減できます。
また、信頼性の高いファクタリング会社を選ぶことも重要です。実績があり、法的手続きを正確に行う会社を選ぶことで、後々のトラブルを避けることができます。契約前に会社の評判や口コミを調査し、可能であれば複数の会社から見積もりを取ることをおすすめします。
税金・公共料金の優先的な支払い
税金や社会保険料などの公的債務は、滞納すると、強制徴収権により比較的短期間で差し押さえに発展するリスクがあります。このため、これらの支払いは最優先で行うべきです。
企業の資金繰りが厳しい場合でも、税金の納付を後回しにするのではなく、分割納付の相談を早めに行うことが重要です。税務署や年金事務所は、誠意を持って相談する企業に対しては、分割納付に応じることが多いものです。
また、年間の税金納付スケジュールを把握し、資金繰り計画に組み込むことも大切です。特に、消費税や法人税などの大きな支払いに備えて、計画的に資金を確保しておくことで、納税時の資金ショートを防ぐことができます。
専門家への早期の相談
資金繰りに不安がある場合は、早めに税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法的リスクを評価し、適切な対応策を提案してくれます。
財務管理の徹底も、差し押さえリスクを減らす重要な要素です。売掛金の回収状況を常に把握し、入金予定を明確にすることで、計画的な資金繰りが可能になります。また、月次決算を行い、定期的に財務状況をチェックする習慣をつけることも大切です。
資金繰り表の作成と定期的な更新も有効です。最低でも3ヶ月先までの入金・出金予定を把握していれば、資金ショートを事前に察知し、対策を講じることができます。特に、税金の納付期限は資金繰り表に必ず記載し、準備を怠らないようにしましょう。
ファクタリング(特に2社間)の差し押さえリスクや債権譲渡登記のコストがご不安な法人経営者様には、売掛金を譲渡しない「ビジネスローン」が最適です。HTファイナンスなら、無担保・無保証、最短即日で事業資金をサポートします。
ビジネスローンの詳細を見てみる代替手段としての安全な資金調達法
ファクタリングの差し押さえリスクが心配な場合、他の資金調達方法も検討する価値があります。状況に応じた安全な選択肢を見ていきましょう。
ビジネスローン
ビジネスローンは、一般的に担保や個人保証を必要としない融資です。審査は、主に事業の収益性や返済能力に基づいて行われます。このタイプの融資には、ファクタリングと比較していくつかの重要なメリットがあります。
まず、売掛金の譲渡が不要なため、債権譲渡に関わる法的リスクがありません。融資金は完全に企業の資産となり、その使途も自由度が高いです。また、定期的な返済計画が立てられるため、計画的な資金管理が可能になります。
さらに、ファクタリングと異なり、取引先に資金調達の事実が知られることがないため、企業の信用に影響を与えません。近年は審査のスピード化も進んでおり、最短数日で融資を受けられるケースも増えています。
ビジネスローンは、特に、安定した売上があり、一時的な資金需要がある企業や、ファクタリングの手数料負担が大きいと感じる企業に適しています。(ビジネスローンの審査基準や上限額について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。)
公的融資制度
公的融資制度は、政府や自治体が、中小企業の資金調達を支援するために設けた制度です。民間金融機関と比較して低金利で、審査基準も比較的緩やかなことが特徴です。
日本政策金融公庫の融資は、創業融資や小規模事業者向け融資など、目的に応じた複数のメニューがあります。また、自治体の制度融資も各地で実施されており、地域の経済状況に応じた支援が受けられます。
これらの公的融資は、経営セーフティ共済(倒産防止共済)などのセーフティネットと併用することで、より安定した財務基盤を構築できます。経営セーフティ共済は、取引先の倒産など不測の事態に備えるための制度で、掛金は税制優遇の対象にもなります。
公的融資制度を活用する際は、地域の商工会議所や商工会、中小企業支援センターなどに相談するのが効果的です。専門のアドバイザーが、企業の状況に合った融資制度を紹介してくれます。
まとめ
ファクタリング利用中の差し押さえリスクは、適切な知識と対策により大幅に軽減できることを解説してきました。特に、3社間ファクタリングの選択や債権譲渡登記の活用は、法的なリスクを減らす効果的な方法です。また、税金など公的債務の優先的な支払いや早期の専門家相談も、重要な対策となります。
資金繰りに悩む法人経営者の方は、ファクタリング以外にもビジネスローンや公的融資制度など、複数の選択肢を検討することをおすすめします。どの方法が最適かは企業の状況によって異なりますので、専門家に相談しながら最適な資金調達策を見つけてください。
この記事でご紹介しているHTファイナンスのサービス(ビジネスローン)は【法人限定】です。
個人事業主・フリーランスの方で資金調達(ファクタリング等)をお急ぎの場合は、誠に恐れ入りますが、グループサイトである「HTファクタリング(個人事業主専門)」をご利用くださいますようお願いいたします。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
急な資金需要や差し押さえリスクの回避には、迅速かつ安全なビジネスローンが適しています。HTファイナンスのビジネスローンは、法人様限定で「無担保・無保証」、最短即日の資金調達を実現します。
銀行実務経験豊富な専門家が、貴社の状況をヒアリングし、ファクタリングのリスクと比較した上で最適なプランをご提案します。差し押さえの不安を解消し、安定した事業継続を目指す経営者様は、まずはお気軽にご相談ください。









