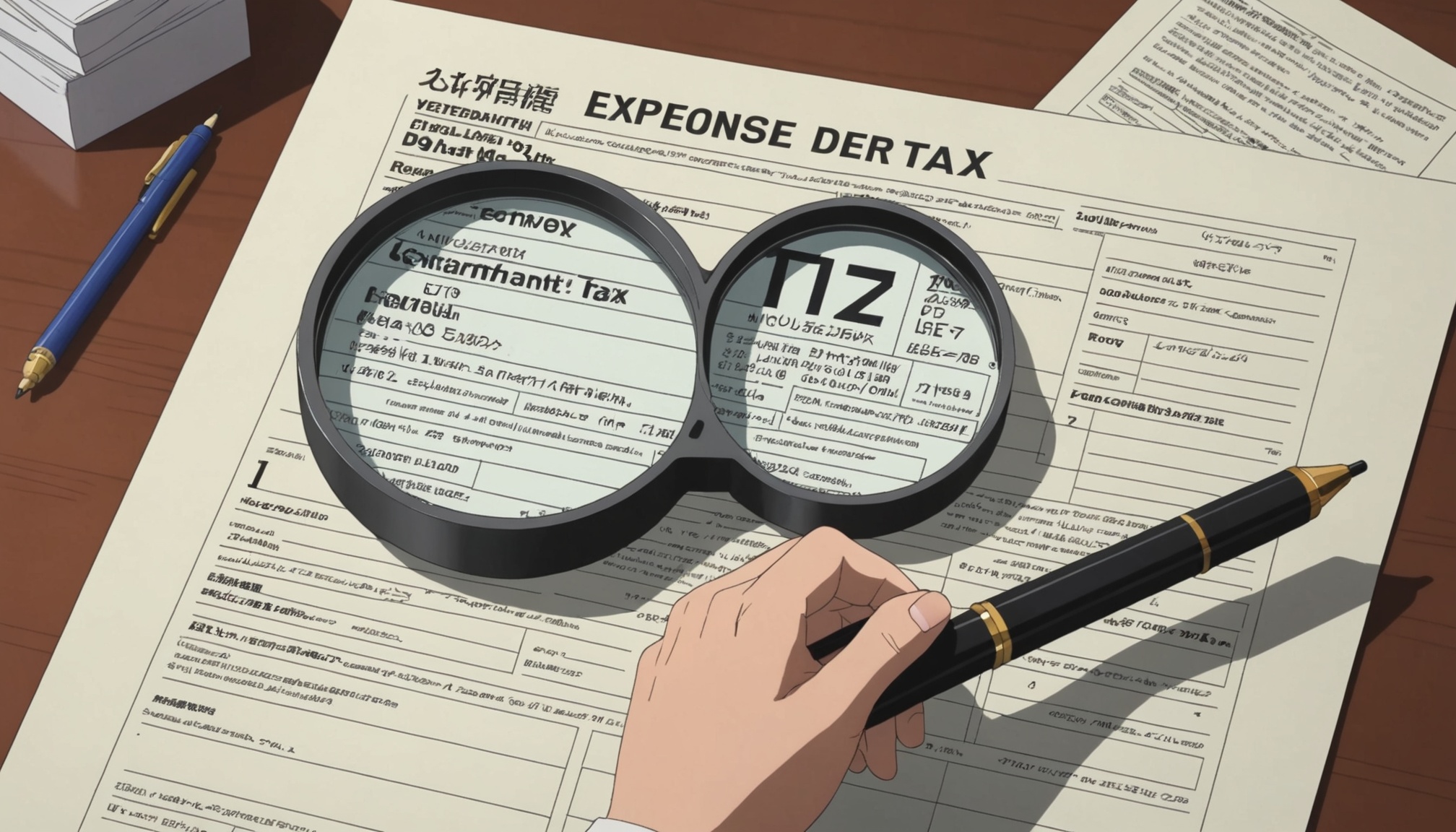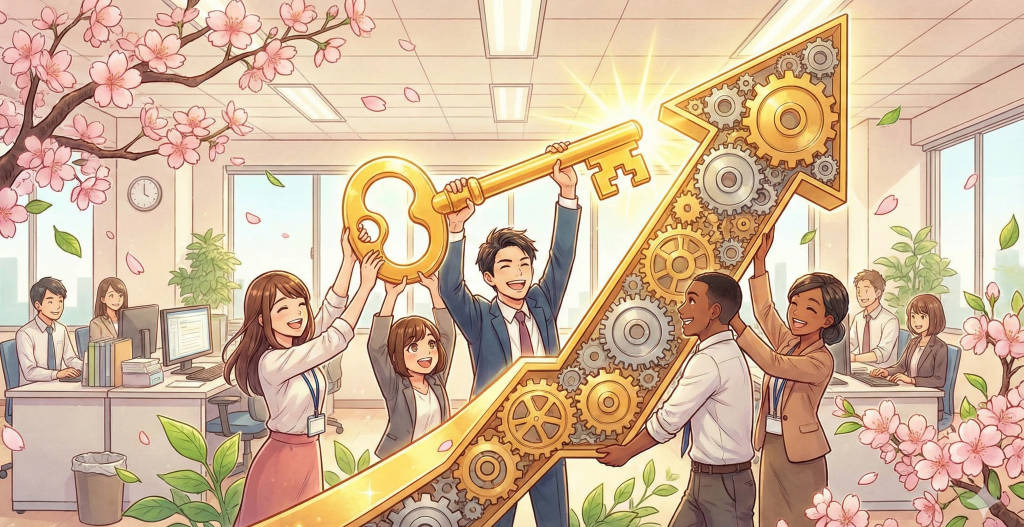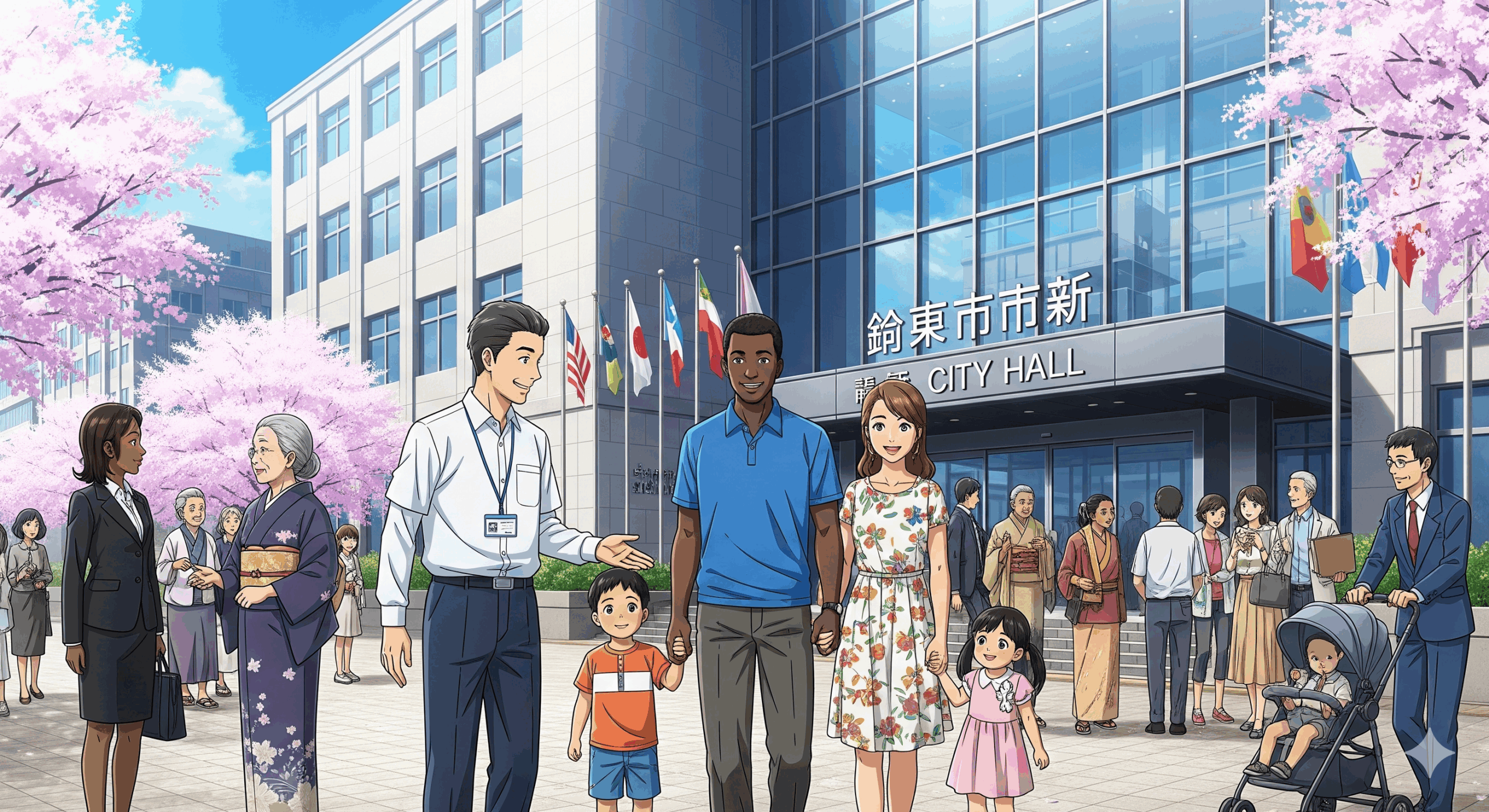公開日:2025.10.01
更新日:2025.10.31
アフリカにおける大豆関連産業の育成について

【はじめに】
私たちは、横浜で開催されたTICAD9(Tokyo International Conference on African Development=アフリカ開発会議)の一環で、ケニヤのナイロビに本部を置くAGRA(Alliance for a Green Revolution in Africa=アフリカの緑の革命のための同盟)主催のセミナーに令和7年8月21日に参加し、上記のテーマのスピーチを行いました。内容を紹介しようと思います。
近年、アフリカにおける大豆産業の拡大が、食料安全保障や雇用創出の観点から大きな注目を集めています。アフリカ全体の人口はおよそ13億人に達し、平均年齢が若く、2030年以降も継続的な経済成長が見込まれます。その一方で、飼料・加工食品としての大豆の需要が急伸しており、特に家禽や水産養殖の拡大に大きく寄与しているのが現状です。世界的には大豆が年間約3億5千万トン程度生産されているとの推計がありますが、アフリカではそのうちの数%にすぎず、生産の伸びしろが大きい市場としても知られています。この提案では、アフリカの大豆産業の特徴や5つの課題、そして解決へ導く4つの方向性を整理し、さらにESGの観点や中小企業が参入する際の資金調達の可能性についても紹介します。
【第1章:アフリカの大豆産業の現状と将来性】
アフリカ大陸全体での大豆生産量は、統計的には約390万~420万トン前後と推定されます。主要国としては南アフリカが2.7百万トン、ナイジェリアが1.2百万トン程度と目立つものの、ザンビアやジンバブエ、マラウイなど他国でも生産拡大が試みられています。人口増加率が平均2.5%程度と高水準の地域も多く、将来的な食料需要の急増が見込まれる中、タンパク質源としての大豆に対する期待は十分に高いです。
さらに、アフリカでは家禽と水産養殖の成長率が他地域よりも速く、一部推計によれば鶏肉消費は年平均5%以上の伸びが見込まれる国もあります。これは、より安価かつタンパク質豊富な食肉需要が増え、その飼料原料となる大豆への需要が引き上げられる構造です。
豆腐や豆乳などの消費に関しても、都市部における健康志向の高まりにより徐々に広がりを見せています。大豆産業は農業・食品・飼料・加工など多様なバリューチェーンをカバーするため、地域の中小企業がかかわりやすい点も大きな特徴です。
【第2章:5つの課題】
本格的にアフリカの大豆産業を育成するためには、以下の5つの課題を念頭に置くことが重要です。国や地域によって程度は異なりますが、多くの生産地が類似のハードルに直面しています。
- 生産性向上
小規模農家による生産が主体であり、機械化が遅れている点が大きな問題です。品種改良や肥料・農薬の適正使用も十分に浸透していません。アフリカ域内の平均単収はおよそ1,300kg/haで、世界平均の半分程度とされています。適切なインプット(種子、肥料、農薬)と基本的な農機具導入だけでも、現行の単収を20~30%程度向上できる可能性があるとの専門家の試算があります。
- インフラ整備
農道や灌漑設備、倉庫、サイロなどの基礎インフラが不足している地域が多く、収穫後の乾燥や保管、輸送段階でのロスが25%にもなります。これは国際平均の13%のほぼ2倍と推計され、生産物の品質低下や市場アクセスの遅れにもつながっています。
3.製品加工能力
大豆を粉砕するためのクラッシャーや搾油設備、食品や飼料への加工設備が十分ではなく、多くの国が大豆加工製品を輸入に頼っているのが現状です。こうした設備投資の遅れは、中小加工事業者が十分に育たない一因にもなっています。
- 市場アクセスと品質標準
生産農家は買い付け業者や中間業者に依存するケースが多く、価格交渉力を持ちにくい状況です。国や地域によって品質基準がばらばらで、統一的な検査や等級付けが十分に機能していません。その結果、品質の高い大豆を作っても付加価値が得られにくく、農家のモチベーション向上を阻む一因にもなっています。
- 金融及び資金補助
多くの小規模農家や地域の中小企業は担保力の乏しさや高リスクの認識から、銀行融資を受けにくい構造的課題があります。生産資材を購入するための運転資金や、倉庫・加工設備を整えるための設備資金が得られにくく、結果として作付面積の拡大や性能向上を図ることができません。中長期的に契約生産方式の普及や協同組合の強化が求められています。
【第3章:解決策の4つの方向性】
上述した5つの課題を解決するためには、以下4つの方向性が実務レベルで特に有効と考えられています。中小企業が資金調達を検討する上でも、投資先や融資先の事業計画にこのような要素を取り入れると評価が高まるでしょう。
- 生産地隣接インフラ設置
まず、インフラ整備は生産効率を上げると同時に、収穫後ロスを大幅に減らす効果があります。農道や倉庫、サイロを整備し、収穫後に適切な保管ができれば、ロス率を10~15%まで下げられるという試算もあります。さらに農家に隣接した小型の粉砕・搾油設備・加工施設(モジュール型設備)を導入することで、不要な輸送コストやタイムロスを削減し、生産者の収益改善が期待できます。
2.金融支援
金融面でのサポート体制を強化することは、生産の安定化と設備投資の促進に繋がります。例えば、以下のような支援施策が挙げられます。
- 生産資材購入のための事前融資(Inputs Credit)やマイクロファイナンス
- 収穫後の在庫金融(倉庫証券発行など)
- 売掛債権融資(ファクタリングの活用)
- 協同組合や契約生産方式による貸付リスクの低減
特に契約生産方式は、買い手がある程度の購入量や価格を事前に保証することで、農家の確実な収益が見込めます。この仕組みにより、金融機関側も貸付リスクを軽減できるため、金利が下がりやすくなります。アフリカ現地に進出を考える中小企業にとっても、こうした信用環境を整備することは重要です。
- 技術移転と人材育成
大豆の単収を向上するためには、品種改良や病害虫対策、適正肥料の投与など科学的なアプローチが不可欠です。海外から高収量品種を導入し、地域に適合する形で育てるためには、継続的な試験栽培とモニタリングが求められます。さらに輪作システムの普及や雑草管理技術、栽培暦の共有など、基礎的な営農指導を行う人材育成が欠かせません。加えて、加工施設の運営管理に関わる人材もOJTをベースに育成プログラムを実施する必要があります。この点で、農業大学や研究機関、NGO、関連事業法人などと連携し、現地の若者や女性たちを研修するプロジェクトが各地で行われ始めています。こうした取り組みは、地域経済の活性化と雇用創出の両面にメリットがあります。
- 市場政策と高付加価値化
大豆を単に大量生産するだけでなく、高付加価値製品へと転換する施策は、長期的に経済的リターンを高める上で不可欠です。豆乳、豆腐、中間原料、機能性成分であるイソフラボンやプロテイン原料への加工など、製品ラインナップを拡大することで、国内外の富裕層市場や都市部の健康志向層をターゲットにできます。また、品質保証のためにISOやHACCP、GMP、HALAL、Kosherなどの国際認証を取得すると、取引先企業の信用度が向上し、融資の際の評価も高くなる傾向があります。 たとえば、「Mash Soy」のようなエグミや青臭さを抑えた中間加工製品は、最終製品化(大豆コロッケや植物性ソース)において使い勝手がよく、都市部への販路拡大を図りやすいといえます。中小企業がこうした加工技術と付加価値化のノウハウを持つ現地パートナーと協力することも、非常に有望な手段です。
【第4章:アフリカ大豆産業への海外企業のかかわり方と資金調達】
海外企業がアフリカの大豆ビジネスに参入するには、いくつかの具体的な戦略が考えられます。ビジネスモデルの選択にあたっては、適切な資金調達スキームを組み合わせることが鍵となります。
■投資対象の選定
- 小規模生産者や協同組合との連携:生産者に対してマイクロファイナンスや技術提供を行い、将来的に安定的な原料確保を図る
- 既存農場の買収や共同経営:大規模商業生産のノウハウを取り入れ、インフラ整備と合わせて大幅な生産性向上を目指す
- 加工事業への投資:粉砕・搾油・豆腐・豆乳等の設備導入や研究開発に注力し、高付加価値製品を国内外へ供給
■資金調達の多角化
- 国際開発金融機関との連携:アフリカ開発銀行(AfDB)などを通じて、低金利融資や信用保証を得る
- 現地銀行やマイクロファイナンス機関の活用:契約生産の仕組みを嚆矢(こうし)に、貸付条件を有利に交渉する
- クラウドファンディングやインパクト投資:環境・社会的課題の解決を掲げる事業として、投資家からの資金を集める
- 補助金・助成金プログラム:海外投資を促進する自国の援助機関や国際機関の補助金制度を活用
■リスクマネジメント
- 政治・通貨リスク:為替ヘッジや輸出保険などを活用し、投資額を保護
- 天候リスク:灌漑設備の整備や品種改良により、天候不順による生産性低下の影響を最小化
- 流通リスク:現地の専門家とのパートナーシップや現地法人設立によって物流ルートを安定化
【第5章:ESG視点と社会的インパクト】
アフリカの大豆産業を支援・育成することは、ESG(Environment, Social, Governance)の観点からも非常に価値があります。食糧安全保障の確立や女性や若年層の雇用創出につながり、長期的な社会安定に寄与するためです。さらに持続可能なフードバリューチェーンを構築することで、バリューチェーン全体でのCO₂排出量削減や、地域コミュニティの生活水準向上にも貢献できます。
■環境面(Environment)
- 土壌改良:大豆は土壌に窒素を固定するため、輪作における土壌改良効果が期待できる。
- エネルギー効率化:小規模農家が太陽光や熱交換などによる再生可能エネルギーを利用できれば、CO₂排出量の削減につながります。
- 水資源管理:適切な灌漑設備の導入で、水の無駄を減らし、同時に収量の安定にもつなげられる。
■社会面(Social)
- 雇用創出:農業・加工・流通など大豆バリューチェーン全体で新たな雇用が生まれる。
- 女性や若年層の活躍推進:農作業から加工まで、女性や若年層が担う役割が大きいため、収入向上と地位向上が実現しやすい
- 栄養改善:大豆製品の普及が進めば、地域住民のタンパク質摂取に寄与
■ガバナンス(Governance)
- 協同組合の強化:透明性ある運営と決定プロセスが農家の利益最大化に寄与する。
- 転売・買い占め防止策:適正な価格設定と流通ルート整備によって、脆弱な生産者の損失を防ぐ。
- 国際認証の取得:品質基準や衛生管理を徹底し、輸出市場の拡大と金融信用力を高める。
こうしたESGの切り口は、欧米やアジアの投資家からも重視されており、資金調達を行う際にも事業価値向上に関してもアピールポイントとなります。特に女性雇用や若者の技術訓練を明確化することで、インパクト投資ファンドやクラウドファンディングを活用しやすくなります。
【第6章:まとめ】
アフリカの大豆は、すでに単なる農産物としての枠を超え、多角的な成長が見込まれる戦略的な産業分野に成長しています。小規模農家が主力となり、まだまだ生産性は低いままですが、人口増加とそれに伴う食料・飼料の需要増を背景に、地域の潜在力は非常に大きいです。
5つの課題である「生産性向上」「インフラ整備」「製品加工能力」「市場アクセスと品質標準」「金融及び資金補助」を的確に把握し、4つの解決策「生産地近隣インフラ」「金融支援」「技術移転と人材育成」「市場政策と高付加価値化」をバランスよく同時に推進できれば、生産者・加工業者・流通業者・投資家・金融事業者・消費者いずれにとっても有益な、新たなビジネス機会が広がるはずです。
実際、倉庫や道路などのインフラ投資で収穫後ロスを半減できれば、それだけで市場に出回る大豆量が大幅に増え、農家の収入も上がります。また、契約生産が制度化されれば、農家は安心して作付面積を拡大し、融資も受けやすくなります。さらに高付加価値製品の加工技術を確立することにより、最終消費者向けの製品ラインアップが格段に増え、都市部や海外富裕層市場へのアクセスが容易となります。
このように、アフリカ大豆産業の振興は、ESG投資の観点からも有意義であり、地域の社会・経済・環境にポジティブなインパクトを与えられます。海外企業の参入に際しては、契約生産やマイクロファイナンス、補助金の活用など、さまざまな資金調達の仕組みがあります。事前に現地パートナーとの連携体制を構築し、リスク管理と事業計画をしっかりと練り上げることで、比較的少額の投資からでも大きなリターンを狙うことが可能です。 私たちは、こうした大豆産業への参入や資金調達戦略を検討する皆さまに向けて、事務局の設置やスキームづくりのサポートなど、総合的なコンサルティングが提供できます。
アフリカにおける大豆の可能性はまだまだ計り知れないほど大きく、今後さらに多くの企業・投資家にとって重要な市場になっていくでしょう。さまざまな事業者と協力しながら、アフリカでの大豆ビジネスを新たな収益源として育てていくことが可能です。
その為には、「5つの課題と4つの解決策」を同時並行的にバランスよく遂行する、**成長産業へのシフトを目指すための全体像(ビッグピクチャー)**を設計し、各分野の専門家や専門企業を一つのプラットフォームに集約したチーム組成することで、効率的なプロジェクト推進を図らなければいけません。バラバラなプロジェクトを一つに束ねるプラットフォームが必須です。
アフリカは、かつての「開発が遅れている大陸」というイメージから大きく変わりつつあります。大豆は、タンパク質不足や栄養不良を解消するだけでなく、地域経済と企業成長を一気に押し上げる推進力となり得ます。こうした視点を大切にしながら、中長期的かつ継続的な取り組みを進めていけば、必ずや大きな成果が伴うはずです。食卓の安全と地域の繁栄を両立させるアフリカ大豆産業の未来に注目していきたいと思います。