公開日:2025.10.23
更新日:2025.10.23
給料の支払いが遅れたときに利息はどのくらいかかってくる?対応の仕方や未然の防止方法を解説
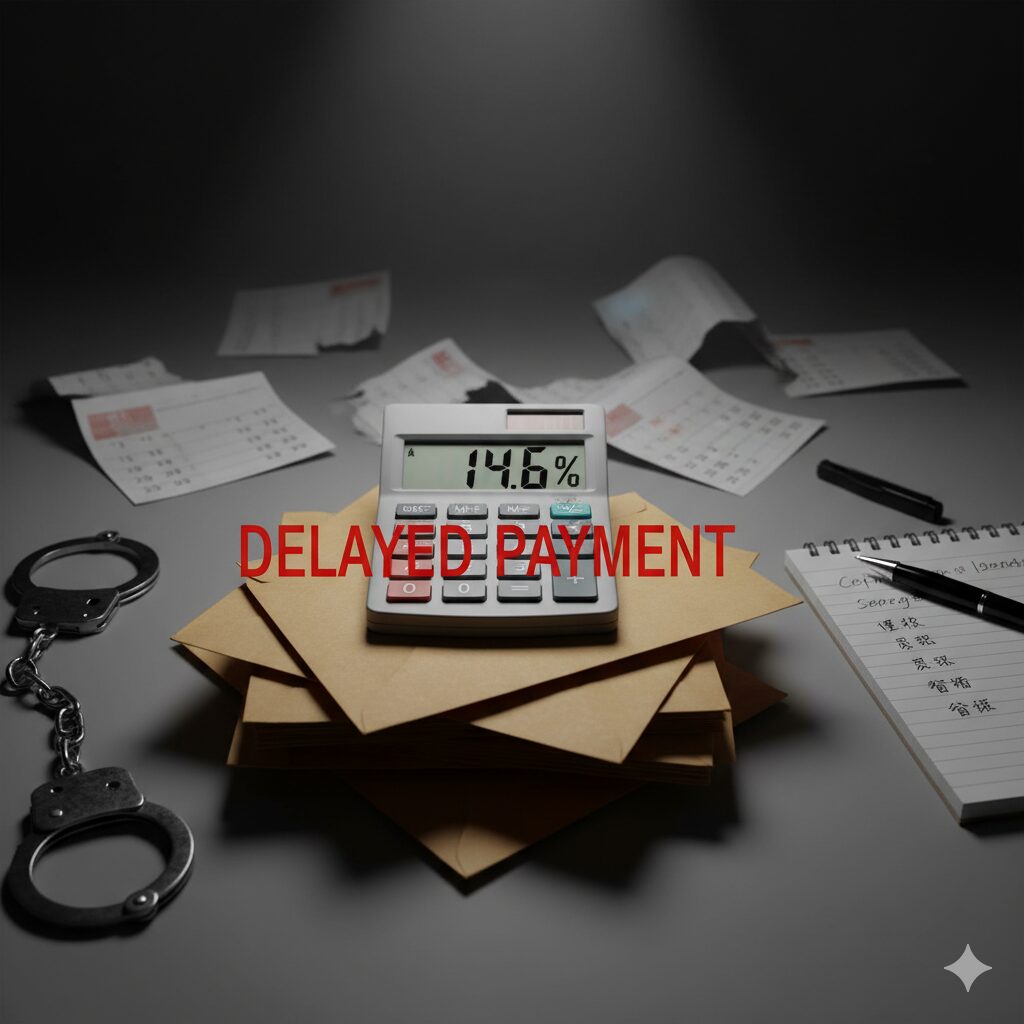
経営者からすると、従業員への給料支払いは最優先事項ですが、資金繰りの悪化や事務手続きのミスなどにより、どうしても給料の支払いが遅れてしまう場合があります。実は、給料の支払い遅延は、単なる信頼関係の問題で終わる話ではありません。法律で定められた遅延利息(遅延損害金)の支払い義務が発生するのです。
在職中の従業員への給料支払い遅延と退職後の未払い賃金では、適用される法律や利率が異なります。特に退職後は、年14.6%という高い利率が課せられるため、早急な対応が求められます。
本記事では、給料支払いの遅延時に発生する利息の計算方法や支払い義務、遅延が発生したときの適切な対応方法、そして何より遅延を未然に防ぐための実践的な方法を詳しく解説します。
給料支払い遅延時に発生する法的義務
給料の支払いが遅れると、単に従業員との信頼関係が損なわれるだけでなく、法的な責任も生じます。まずは、基本的な法的義務について理解しましょう。
給料遅延時の遅延利息(遅延損害金)とは
給料の支払いが遅れた場合、雇用主には遅延利息(法律上は遅延損害金と呼ばれます)を支払う義務が発生します。これは、労働者の権利を守るために法律で定められたもので、支払いを怠ると法的責任を問われる可能性があります。
遅延利息は単なるペナルティではなく、労働者が本来受け取るべき賃金が遅れることによる経済的不利益を補償する性質を持っています。つまり、労働者の生活を守るための重要な仕組みです。
利息の発生は、労働者側からの請求がなくても、支払いが遅れた時点で自動的に発生します。そのため、経営者は遅延が発生した場合、労働者から請求されていなくても、法律上は利息を含めた支払いを行う義務があります。
労働基準法における賃金支払いの5原則
給料の支払いに関しては、労働基準法第24条で、次の5つの原則が定められています。
| 通貨払いの原則 | 賃金は、通貨で支払うこと |
| 直接払いの原則 | 賃金は、直接労働者に支払うこと |
| 全額払いの原則 | 賃金は、その全額を支払うこと |
| 毎月払いの原則 | 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと |
| 定期払いの原則 | 賃金は、一定の期日を定めて支払うこと |
この中でも、給料遅延に直接関わるのは、4番目と5番目の原則です。企業は、給料支払日を就業規則などで明確に定め、その日に確実に支払いを行わなければなりません。支払期日の遵守は法的義務であり、これを守らない場合、労働基準法違反として罰則の対象になることもあります。
給料の支払いが遅れた場合、労働者は労働基準監督署に申告することができ、調査が入る可能性もあります。そのため、経営者は単に遅延利息を支払えば済む問題ではなく、法令遵守の観点からも、給料の遅延には細心の注意を払う必要があります。
給料の支払いが遅れたときの利息(遅延損害金)の計算方法
給料支払いが遅延した場合、状況によって適用される法律や利率が異なります。在職中と退職後で大きく計算方法が変わるため、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
在職中と退職後の利率の違い
給料支払いの遅延が発生した場合、従業員が在職中か退職後かによって、適用される法律と利率が異なります。利率の差は非常に大きいため、特に退職者への未払い賃金には注意が必要です。
在職中の従業員に対する給料支払いが遅延した場合は、民法の規定が適用されます。2020年4月の民法改正により、法定利率は年3%となっています(改正前は年5%でした)。これは、比較的低い利率と言えるでしょう。
一方、退職後の従業員に対する未払い賃金については、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)が適用され、年14.6%という高い利率が設定されています。これは、在職中の約5倍もの利率であり、未払い金額が大きい場合は、短期間でも相当な利息が発生することになります。
| 状況 | 適用法律 | 利率 | 計算期間 |
|---|---|---|---|
| 在職中 | 民法 | 年3% | 支払予定日の翌日から実際の支払日まで |
| 退職後 | 賃金の支払の確保等に関する法律 | 年14.6% | 退職日の翌日から実際の支払日まで |
退職後の高い利率は、退職者の生活保障という観点から設定されています。退職後は、新たな収入源を確保するまでの期間があり、その間の生活資金として、退職金や未払い賃金が重要な役割を果たすためです。
遅延利息の具体的な計算方法
遅延利息の計算は、未払い給料の金額、適用利率、遅延日数の3つの要素に基づいて行われます。計算式を正確に理解することで、発生する可能性のある遅延利息の金額を把握できます。
在職中の従業員に対する遅延利息の計算式は、次のようなものです。
未払い給料×3%×(遅延日数÷365)
一方、退職後の従業員に対する遅延利息の計算式は、次のようになります。
未払い給料×14.6%×(遅延日数÷365)
なお、閏年(うるうどし)の場合は、365日を366日に修正して計算します。また、遅延日数は、支払予定日の翌日から実際の支払日までをカウントします。
具体的な計算例を挙げてみましょう。例えば、未払い給料が10万円で、在職中の従業員に対して4日間支払いが遅れた場合は、次のような計算になります。
100,000円×3%×(4日÷365日)=約32.9円
同じく10万円の未払い給料でも、退職後の従業員に対して30日間支払いが遅れた場合は、次のように計算されます。
100,000円×14.6%×(30日÷365日)=約1,200円
このように、退職後の未払い賃金に対する遅延利息は、在職中に比べて金額が大きくなりますので、特に注意が必要です。また、未払い金額が大きい場合や遅延期間が長期にわたる場合は、遅延利息も比例して増加します。
給料の支払いが遅れたときの対応方法
給料の支払いが遅れてしまった場合、経営者はどのように対応すべきでしょうか。適切な対応は、従業員との信頼関係を維持し、法的なリスクを最小限に抑えるために重要です。
従業員への誠実な説明
給料の支払いが遅延した場合、最初に行うべきことは、従業員への誠実な説明です。透明性のある迅速な対応が、信頼関係を維持する鍵となります。
遅延が判明した時点で、直ちに全従業員に対して状況を説明する機会を設けましょう。この際、遅延の原因、支払いの見込み時期、今後の再発防止策などを具体的に伝えることが重要です。曖昧な説明や言い訳めいた対応は、かえって従業員の不信感を高める結果となります。
特に注意すべき点として、一部の従業員にだけ支払いを行うなど、不平等な対応は避けるべきです。やむを得ず優先順位をつける場合でも、その基準を明確にし、全従業員に対して説明する必要があります。
また、遅延利息(遅延損害金)についても自主的に説明し、支払う意思があることを示しましょう。法律上の義務として支払う必要があるものですが、従業員から請求されるまで触れないといった姿勢は避けるべきです。
法的リスクへの対処
給料支払いの遅延は、労働基準法違反となる可能性があるため、適切な法的対応も必要です。法的リスクを最小化するための対応を検討しましょう。
まず、遅延が発生した場合、その原因を明確に記録しておくことが重要です。不可抗力による遅延なのか、単純なミスによるものなのかによって、後の対応や法的な評価が変わってくる可能性があります。
従業員から労働基準監督署への申告があった場合に備え、給料支払いの遅延に関する経緯や対応の記録を整理しておきましょう。実際に調査が入った場合は、誠実に対応し、改善策を示すことが重要です。
また、給料の遅延が常態化している場合や、支払いの見込みが立たない場合は、弁護士等の専門家に相談することも検討すべきです。場合によっては、従業員との間で支払い計画について合意を形成することで、一時的な猶予を得られる可能性もあります。
最後に、退職者への未払い賃金については、特に注意が必要です。退職後の未払い賃金に対する遅延利息は、年14.6%と高率であり、放置すると大きな負担となります。退職者からの請求があった場合は、優先的に対応することを検討すべきでしょう。
給料の支払い遅延を未然に防ぐためのポイント
給料の支払い遅延は、発生してからの対応よりも、未然に防ぐことが最も重要です。経営者として実践できる予防策について、具体的に見ていきましょう。
資金繰り管理の徹底
給料支払いの遅延を防ぐには、まず適切な資金繰り管理が不可欠です。計画的な資金管理によって、給料支払日に必要な資金を確保できるようにしましょう。
具体的には、毎月の給料支払日の少なくとも1週間前には、必要な資金が確保できているか確認する習慣をつけることが重要です。これにより、資金不足が予想される場合に、早めに対策を講じることができます。
また、資金繰り表を作成し、定期的に更新することで、将来の資金の流れを予測しやすくなります。特に季節変動の大きい業種では、繁忙期と閑散期の収支バランスを考慮した計画が必要です。
さらに、緊急時のための資金として、給料の3〜6ヶ月分程度の運転資金を常に確保しておくことも検討すべきです。これにより、一時的な売上減少や予期せぬ出費があっても、給料の支払いに影響が出にくくなります。
給与振込システムの効率化
給料の支払い遅れは、単に資金不足だけでなく、事務手続きのミスや遅れによっても発生しえます。効率的な給与支払いシステムの導入で、こうしたリスクを減らすことが可能です。
まず、給与計算から振込依頼までの一連の流れを明確に文書化し、担当者が不在の場合でも、滞りなく進められるようにしておきましょう。特に、給与計算の締め日から振込日までのスケジュールを具体的に定め、各段階での確認ポイントを明確にすることが重要です。
また、給与計算ソフトやクラウド型の給与システムを導入することで、計算ミスや入力ミスのリスクを低減できます。これらのシステムは、銀行振込データの作成も自動化できるため、手作業による転記ミスも防止できます。
さらに、給与振込を複数の担当者でダブルチェックする体制を整えることも効果的です。特に、振込金額の確認や振込日の設定などの重要ポイントは、必ず複数の目で確認するようにしましょう。
大企業であれば、給与前払いサービスの導入も検討の余地があります。これにより、従業員は給料日前でも一部の給与を受け取ることができるため、万が一の遅延時にも影響を最小限に抑えられます。
遅延利息が発生しない特殊な事例
給料の支払いが遅れたとしても、すべてのケースで遅延利息が発生するわけではありません。例外的な状況や特殊なケースについて理解しておくことも重要です。
法的に認められる例外事例
法律上、一定の条件下では、給料支払いの遅延に対して遅延利息が発生しないケースがあります。法的な例外事例を把握することで、不必要な混乱を避けることができます。
まず、天災地変などの不可抗力による遅延の場合は、状況によっては、遅延利息の支払い義務が免除されることがあります。例えば、大規模な自然災害により銀行システムが停止し、振込が物理的に不可能だった場合などが該当します。
また、会社が法的整理(民事再生や破産手続き)に入っている場合も、通常の遅延利息の計算方法とは異なる取り扱いになることがあります。この場合は、法的手続きの中で、債権者(従業員を含む)への支払いが調整されることになります。
さらに、給料の支払いに関して労使間で争いがあり、その金額や支払い義務自体が労働委員会や裁判所で係争中である場合も、単純に遅延利息が発生するとは限りません。最終的な判断が出るまでは、遅延利息の計算も確定しないケースがあります。
労使合意による支払い条件の変更をした場合
経営状況の悪化などにより、一時的に給料の全額支払いが困難な場合、労使間の合意による対応が可能なケースもあります。ただし、これには慎重な手続きが必要です。
例えば、一時的な経営危機を乗り切るために、労使協議の上で給料の一部を後払いにする合意ができた場合、その合意内容に基づいた支払いは、遅延とはみなされない可能性があります。ただし、このような合意は、書面で明確に残し、すべての従業員の真の同意を得ることが極めて重要です。
また、就業規則の変更により、給料支払日そのものを変更する場合も、適切な手続きを踏めば可能です。ただし、この場合も従業員に不利益な変更となるため、労働者の理解と協力を得るプロセスが必要となります。
さらに、会社の存続が危ぶまれるような深刻な経営危機の場合、労使が協力して会社再建に取り組むために、特別な合意を形成するケースもあります。こうした場合でも、合意の内容と期間を明確にし、できる限り早期に通常の給料支払いに戻る計画を示すことが重要です。
ただし、労使合意があったとしても、その内容が労働基準法の基本原則に著しく反する場合は、法的に無効となる可能性があります。特に、従業員の生活に重大な影響を与えるような長期間の給料未払いは、たとえ合意があっても、問題となる可能性が高いことに注意が必要です。
給料の支払いが遅れそうなときの支援先
給料の支払い遅延に関する問題に直面したとき、適切な支援やアドバイスを受けられる外部リソースについて知っておくことは重要です。経営者が活用できるリソースを紹介します。
公的支援制度
給料支払いの遅延を防ぐためには、資金繰りの改善が不可欠です。公的支援制度を活用することで、一時的な資金不足を乗り切れる可能性があります。
まず、日本政策金融公庫の融資制度があります。特に、小規模事業者向けの小規模事業者経営改善資金(マル経融資)は、商工会議所などの推薦を受けることで、比較的低金利で資金を調達できる可能性があります。
また、各都道府県や市区町村でも、地域の中小企業向けの融資制度を設けていることが多いくあります。これらは、地域経済の活性化を目的としているため、地元企業に対して有利な条件を提示していることもあります。
さらに、経営状況が悪化している場合は、中小企業再生支援協議会による支援も検討の余地があります。財務状況の分析から再生計画の策定まで、専門家のサポートを受けながら、経営改善に取り組むことができます。
専門家
給料支払いの遅延問題は、経営全体の課題と深く関連していることが多いため、専門家の助言を求めることも重要な選択肢です。
まず、資金繰りの改善については、税理士や中小企業診断士などの財務の専門家に相談することが効果的です。キャッシュフロー改善のための具体的なアドバイスや、経営計画の見直しなどについてサポートを受けられます。
また、給料支払いの遅延に関連する法的な問題については、社会保険労務士や弁護士への相談が有効です。特に、労働基準監督署からの調査があった場合や、従業員との間でトラブルが発生している場合は、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
中小企業の場合、よろず支援拠点を活用するのも一つの方法です。各都道府県に設置されているこの支援機関では、経営上のさまざまな課題について無料で相談できます。必要に応じて、適切な専門家を紹介してもらうこともできます。
さらに、商工会議所や商工会の経営相談窓口も、地域に密着した支援を提供しています。同業者の情報や地域の金融機関とのつながりなど、地域特有の情報を得られる点が強みです。
まとめ
給料支払いの遅延は、単なる事務的な問題ではなく、法的義務や従業員との信頼関係に関わる重要な経営課題です。在職中の従業員に対しては年3%、退職後の従業員に対しては年14.6%という遅延利息が発生するため、特に退職者への未払い賃金には注意が必要です。
遅延が発生した場合は、従業員への誠実な説明と迅速な対応が不可欠です。しかし、最も重要なのは、計画的な資金繰り管理や給与システムの効率化など、遅延を未然に防ぐための対策です。資金繰りに課題がある場合は、公的支援制度の活用や専門家への相談も検討しましょう。従業員の生活を支える給料の確実な支払いは、健全な企業経営の基本であることを忘れないでください。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
給料支払いの遅延を防ぐためには、安定した資金繰りの確保が何よりも重要です。突発的な資金需要や一時的な資金不足に対応するには、スピーディーかつ柔軟な融資サービスの利用が効果的です。中でも、HTファイナンスの無担保無保証で利用できるビジネスローンは、独自の審査基準を設けており、給料支払いなどの緊急性の高い資金需要に対応できるシステムを整えています。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないためにも、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。









