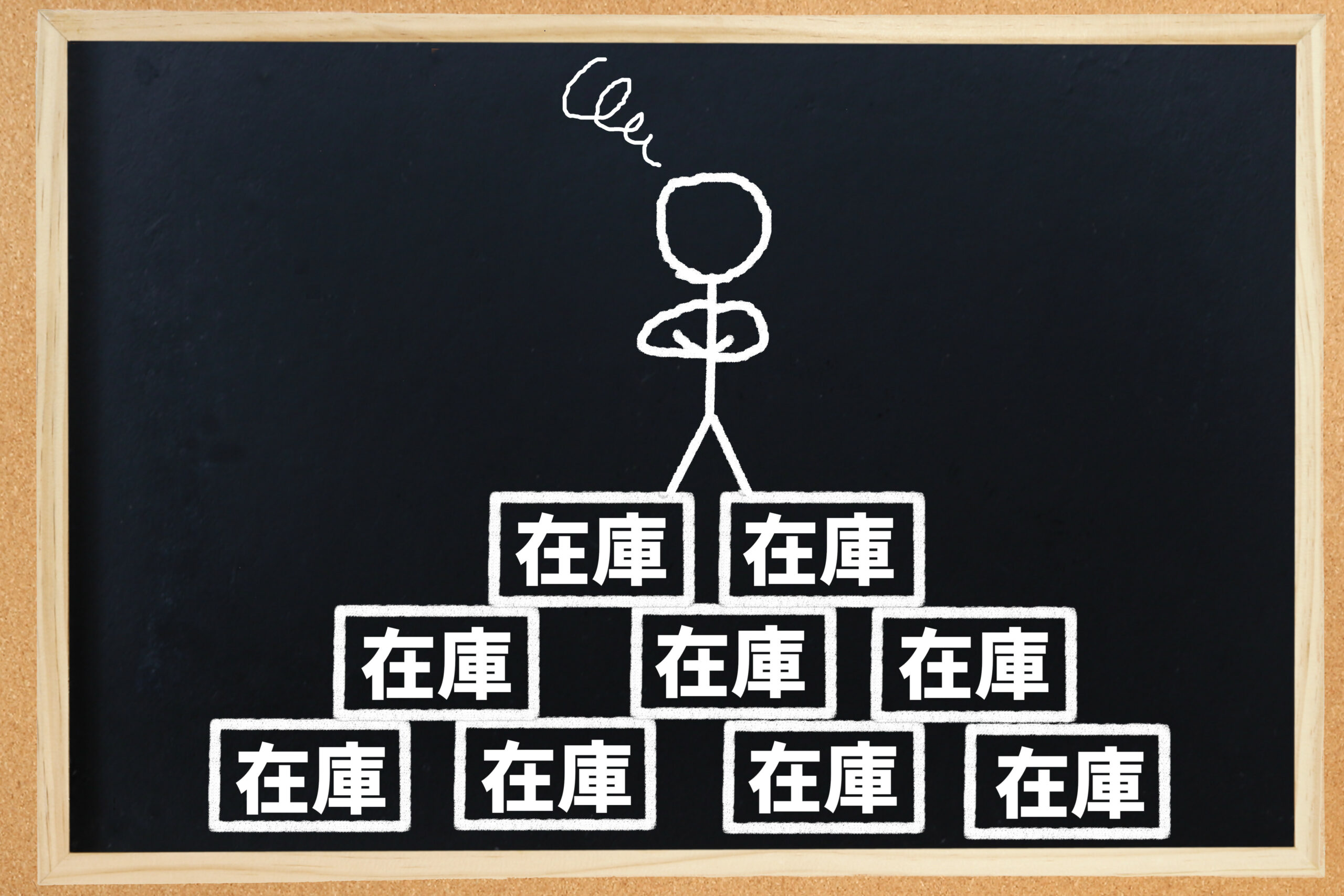公開日:2025.11.04
更新日:2025.11.04
ターミナルバリューはどのような計算式で求まる?DCF法や計算・活用の注意点も紹介

企業価値評価をするにあたって、長期的な企業価値を数字で表す方法として、ターミナルバリューという考え方が重要になります。ターミナルバリューによって、企業における直近の将来のキャッシュフローを予測することができます。
本記事では、企業価値評価の重要な指標であるターミナルバリューについて、基本的な計算式から応用まで詳しく解説します。DCF法(割引キャッシュフロー法)における位置づけや、実際の計算方法、設定すべきパラメーターの考え方まで、実務で活用できる知識を提供します。
- ターミナルバリューとは、DCF法で企業価値を計算する際、「予測期間以降」に企業が生み出す価値の合計を指します。
- 計算式は「永久成長率モデル」$FCF × (1 + g) / (WACC – g)$ が一般的です。
- 計算結果は、割引率(WACC)や永久成長率(g)の設定次第で大きく変動するため、慎重な設定が求められます。
- M&Aや長期投資の判断において、企業の永続的な価値を測る重要な指標となります。
企業価値を高めるための設備投資やM&A(合併・買収)には、迅速な資金調達が不可欠です。
HTファイナンスは、無担保・無保証で、成長戦略を支える事業資金をご支援します。
※審査は最短即日・オンライン完結
ターミナルバリューとは
ターミナルバリューは、企業価値評価において非常に重要な概念です。企業の将来キャッシュフローを予測する際に使用される指標となります。
ターミナルバリューの基本
ターミナルバリューとは、企業価値評価においてDCF法(割引キャッシュフロー法)を用いる際に、予測期間終了後の価値を表す指標です。一般的に、企業のキャッシュフローを5年から10年程度の期間で詳細に予測しますが、その先の将来については、個別に予測することが困難です。
そこで登場するのがターミナルバリューであり、予測期間以降に発生する全てのフリーキャッシュフロー(FCF)の現在価値の合計として計算されます。これは、企業が永続的に事業を継続すると仮定して算出される価値です。
企業の長期的な成長可能性を数値化するという点で、ターミナルバリューは、企業価値評価において極めて重要な役割を果たしています。
企業価値評価におけるターミナルバリューの重要性
企業価値評価においてターミナルバリューが重要視される理由は、その金額が、企業価値全体に占める割合が非常に大きいためです。多くの場合、企業価値評価において、ターミナルバリューは全体の60〜80%を占めることもあります。
DCF法による企業価値評価では、予測期間中の各年度のフリーキャッシュフローの現在価値と、ターミナルバリューの現在価値を合計して算出します。そのため、ターミナルバリューの設定次第で、企業価値評価が大きく変動する可能性があります。
こうした特性から、ターミナルバリューは企業価値評価における最も重要な要素の一つとされており、慎重かつ適切な設定が求められるのです。
ターミナルバリューを使用する理由
企業価値評価において、ターミナルバリューを使用する主な理由は、将来の不確実性に対処するためです。企業の将来キャッシュフローを永続的に個別予測することは、現実的に不可能であり、一定の仮定に基づいた計算方法が必要になります。
また、ターミナルバリューを使用することで、企業の長期的な成長性や持続可能性を評価に反映させることができます。短期的な業績変動に左右されず、企業の本質的な価値を捉えるという点で、投資家や経営者にとって有用な指標となります。
さらに、M&A(合併・買収)や事業評価においても、ターミナルバリューは、買収価格の妥当性を判断する重要な基準となります。企業の永続的な価値を適切に評価するためには、ターミナルバリューの概念が不可欠なのです。
ターミナルバリューの計算式
ターミナルバリューを計算するには、いくつかの方法があります。ここでは、主要な計算式とその背後にある考え方について解説します。
成長なしモデルの計算式
ターミナルバリューを計算する最もシンプルな方法は、成長なしモデル(永続価値モデル)です。このモデルでは、予測期間終了後のフリーキャッシュフロー(FCF)が、将来にわたって一定であると仮定します。
成長なしモデルにおけるターミナルバリューの計算式は、次のようになります。
ターミナルバリュー=最終年度のFCF÷割引率
この式では、最終年度(予測期間の最後の年)のフリーキャッシュフローを割引率で割ることで、永続的に同じキャッシュフローが続くと仮定した場合の現在価値を計算します。割引率には通常、加重平均資本コスト(WACC)が用いられます。
例えば、最終年度のFCFが1,000万円、WACCが10%の場合、ターミナルバリューは1,000万円÷0.1=1億円となります。
安定したキャッシュフローが見込める成熟企業の評価において、このモデルは特に有効です。成長余地が限られた業界や、市場シェアが安定している企業の評価に適しています。
永久成長率モデルの計算式
より現実的なモデルとして、永久成長率モデル(ゴードン成長モデル)があります。このモデルでは、予測期間終了後のフリーキャッシュフローが、一定の率で永続的に成長すると仮定します。
永久成長率モデルにおけるターミナルバリューの計算式は、次のようになります。
ターミナルバリュー=最終年度のFCF×(1+永久成長率)÷(割引率-永久成長率)
ここでの永久成長率は、企業のフリーキャッシュフローが将来にわたって成長し続けると想定される率です。一般的に、長期的な経済成長率や業界の成長率を参考に、0〜3%程度の値が設定されることが多いでしょう。
例えば、最終年度のFCFが1,000万円、WACCが10%、永久成長率が2%の場合、ターミナルバリューは1,000万円×(1+0.02)÷(0.1-0.02)=1,020万円÷0.08=1億2,750万円となります。
成長性のある企業の評価には、この永久成長率モデルが適しています。特に、新興市場や成長産業に属する企業の評価において有効です。
割引率(WACC)の計算式
ターミナルバリューの計算において、割引率の設定は非常に重要です。一般的に使用される割引率は、加重平均資本コスト(WACC、Weighted Average Cost of Capital)です。
WACCの計算式は、次のようになります。
WACC=(自己資本コスト×自己資本比率)+(負債コスト×負債比率×(1-法人税率))
自己資本コストは、株主が期待するリターン(期待収益率)を表し、一般的にCAPM(資本資産価格モデル)などを用いて計算されます。負債コストは、企業が資金調達のために支払う利子率を指します。
例えば、自己資本コストが12%、自己資本比率が60%、負債コストが5%、負債比率が40%、法人税率が30%の場合は、次のように計算されます。
WACC=(12%×60%)+(5%×40%×(1-30%))=7.2%+1.4%=8.6%
このようにして計算されたWACCは、企業の資金調達構成とリスクを反映した割引率となります。企業の資本構成に合わせた正確なWACCの計算が、信頼性の高いターミナルバリュー算出の鍵となります。
DCF法におけるターミナルバリューの活用
ターミナルバリューは、DCF法(割引キャッシュフロー法)による企業価値評価の中で、重要な役割を果たします。ここでは、DCF法におけるターミナルバリューの活用方法について詳しく見ていきましょう。
DCF法とは
DCF法は、企業が将来生み出すと予想されるフリーキャッシュフロー(FCF)を現在価値に割り引くことで、企業価値を算出する評価方法です。この方法は、企業の本質的な価値を測定する上で、最も理論的に優れたアプローチとされています。
DCF法による企業価値評価は、一般的に次のステップで行われます。
- 将来の一定期間(通常5〜10年)のフリーキャッシュフローを予測する
- 予測期間以降の価値(ターミナルバリュー)を計算する
- 予測されたキャッシュフローとターミナルバリューを適切な割引率で現在価値に割り引く
- これらの現在価値の合計を求め、企業価値とする
キャッシュフローの将来予測に基づく評価という点が、DCF法の最大の特徴であり強みです。会計上の利益ではなく、実際に企業に流入するキャッシュに着目するため、より実態に即した評価が可能になります。
予測期間とターミナルバリューの関係
DCF法における予測期間の設定は、ターミナルバリューの信頼性に大きく影響します。予測期間は、企業が安定した成長段階に達するまでの期間を考慮して設定するのが一般的です。
短すぎる予測期間を設定すると、企業の成長ポテンシャルを十分に反映できない可能性があります。逆に、長すぎる予測期間は、予測の信頼性が低下するリスクがあります。
多くの場合、企業は、5〜7年程度で安定した成長段階に入ると考えられますが、業界や企業の特性によっては、より長い予測期間が適切な場合もあります。例えば、新興企業やイノベーションを伴う事業では、安定期に入るまでに10年以上かかることもあります。
企業の成長ステージに応じた予測期間の設定が、ターミナルバリューの精度を高める重要なポイントです。予測期間が適切に設定されていれば、ターミナルバリューは、より正確に企業の長期的価値を表すことができます。
ターミナルバリューを現在価値に割り引く方法
ターミナルバリューは、予測期間の最終年度時点での価値を表しています。そのため、企業価値評価において現在の価値として加算するには、適切に割り引く必要があります。
ターミナルバリューの現在価値は、次の式で計算されます。
ターミナルバリュー現在価値=ターミナルバリュー÷(1+割引率)^予測期間年数
例えば、5年間の予測期間を設定し、5年後のターミナルバリューが1億円、割引率(WACC)が10%の場合は、次のように計算します。
ターミナルバリュー現在価値=1億円÷(1+0.1)^5=1億円÷1.61051=約6,209万円
このように、ターミナルバリューは、予測期間の長さに応じて割り引かれます。予測期間が長いほど、割引の効果は大きくなり、ターミナルバリューの現在価値は小さくなります。
正確な割引計算による現在価値化は、企業価値評価の信頼性を確保する上で不可欠です。ターミナルバリューが企業価値の大部分を占めることが多いため、この計算は特に慎重に行う必要があります。
ターミナルバリューの計算式における永久成長率の設定
永久成長率は、ターミナルバリュー計算における重要なパラメーターです。適切な永久成長率の設定方法と、考慮すべき点について解説します。
永久成長率の適切な範囲
永久成長率は、企業のフリーキャッシュフローが、予測期間終了後も永続的に成長し続けると仮定する際の成長率です。この値の設定は、慎重に行う必要があります。
一般的に、永久成長率は、長期的な経済成長率を超えないように設定するのが原則です。なぜなら、どんな企業も、長期的には経済全体の成長率を超えて永続的に成長することは難しいと考えられるためです。
多くの評価では、永久成長率は以下の範囲で設定されることが多いでしょう。
| 業界の特性 | 成長率 |
|---|---|
| 成熟した市場や安定した業界 | 0〜2% |
| 成長市場や発展途上の業界 | 2〜3% |
| 特殊なケース(新技術など) | 3〜5%(非常に限定的) |
経済の長期的な成長率を考慮した設定が、現実的な永久成長率の目安となります。例えば、先進国のGDP成長率が長期的に1.5〜2.5%程度であれば、それを超える永久成長率の設定は慎重に検討すべきです。
業界特性や市場状況を踏まえた永久成長率
永久成長率は、業界の特性や市場状況によって大きく異なります。適切な永久成長率を設定するためには、対象企業が属する業界の成長性や、市場の成熟度を十分に考慮する必要があります。
成熟した業界(伝統的な製造業、公共サービスなど)では、永久成長率は低く設定されるのが一般的です。これらの業界では、市場の拡大余地が限られており、インフレ率程度の成長しか見込めないケースが多いためです。
一方、成長業界(テクノロジー、ヘルスケアなど)では、比較的高い永久成長率が正当化されることもあります。ただし、どんな成長産業も永続的に高成長を維持することは難しいため、長期的には経済全体の成長率に収束すると考えるのが現実的です。
また、グローバル展開の可能性や新規市場への進出余地も、永久成長率の設定に影響します。未開拓市場への拡大余地がある企業は、相対的に高い永久成長率が正当化される可能性があります。
永久成長率設定のリスクと感度分析
永久成長率の設定は、企業価値評価に大きな影響を与えるため、そのリスクを理解し、適切に対処することが重要です。永久成長率がわずかに変化するだけでも、ターミナルバリューは大きく変動する可能性があります。
例えば、永久成長率を1%から2%に変更するだけで、割引率が10%の場合、ターミナルバリューは約12.5%増加します。(例えば、100÷(10%-1%)=1,111→100÷(10%-2%)=1,250)
このようなリスクに対処するためには、感度分析が有効です。永久成長率を複数のシナリオで変化させ、企業価値評価がどのように変動するかを分析することで、評価の頑健性を確認できます。
一般的な感度分析では、基本シナリオに加えて、楽観的シナリオと悲観的シナリオを設定します。例えば、基本シナリオが永久成長率2%なら、悲観的シナリオでは1%、楽観的シナリオでは3%といった具合です。
複数のシナリオによる感度分析の実施は、企業価値評価の信頼性を高め、投資判断をより堅固なものにするために不可欠です。永久成長率の設定には常に不確実性が伴うことを認識し、幅を持った評価を心がけることが重要です。
企業価値評価(バリュエーション)は重要ですが、実際の成長には戦略的な「投資」が欠かせません。
「銀行融資が間に合わない」「追加の運転資金が必要」など、資金調達でお困りならHTファイナンスにご相談ください。
※元銀行員の専門家が貴社の財務戦略をサポートします
ターミナルバリュー計算における実務上の注意点
ターミナルバリュー計算を実務で活用する際の注意点や、陥りがちな問題点について解説します。
計算式の選択における判断基準
ターミナルバリュー計算において、どの計算式を選択するかは、評価対象企業の特性によって異なります。適切な計算式の選択は、評価の信頼性に直結する重要な判断です。
成長なしモデルは、以下のような企業に適しています。
- 成熟した市場で事業を展開している企業
- 市場シェアが安定している企業
- 大きな成長が見込めない業界の企業
- キャッシュフローが安定している企業
一方、永久成長率モデルは、以下のような企業に適しています。
- ある程度の成長余地がある企業
- インフレによる価格上昇が見込める企業
- 新興市場に進出している企業
- 技術革新によって市場拡大が期待できる企業
企業の成長段階と業界特性に合わせた選択が、ターミナルバリュー計算において、最も重要なポイントです。評価対象企業の将来性を冷静に分析し、最も現実的なモデルを選択することが求められます。
割引率設定における注意点
割引率(WACC)の設定は、ターミナルバリュー計算の精度に大きく影響します。適切な割引率を設定するためには、以下の点に留意する必要があります。
まず、自己資本コストの算出においては、適切なリスクプレミアムの設定が重要です。リスクプレミアムは、市場リスクプレミアムと企業固有のリスク(ベータ値で表される)から構成されますが、特に新興企業や非上場企業の場合、適切なベータ値の設定が難しい場合があります。
次に、資本構成(自己資本比率と負債比率)は、理想的な資本構成や業界平均を参考にするのが一般的です。特に再構築中の企業や、将来的に資本構成の変更が予想される場合は、注意が必要です。
また、グローバルに事業を展開している企業の場合、各国の金利水準やリスクプレミアムが異なるため、地域ごとの加重平均を考慮した割引率の設定が必要になることもあります。
企業のリスク特性を正確に反映した割引率を設定することが、信頼性の高いターミナルバリュー計算の基盤となります。割引率が1%変化するだけでも、ターミナルバリューは大きく変動するため、慎重な検討が求められます。
現実的な前提条件の設定
ターミナルバリュー計算における前提条件の設定は、評価結果の信頼性を左右する重要な要素です。現実的な前提条件を設定するためには、次のようなアプローチが有効です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 過去のトレンド分析 | 企業の過去の成長率や収益性の推移を分析し、将来予測の基礎とします。ただし、過去の実績が将来も継続するとは限らないため、環境変化も考慮する必要があります。 |
| 2. 業界分析 | 対象企業が属する業界の成長見通しや競争環境を分析します。業界レポートやアナリストの見解を参考にすることで、より客観的な前提条件を設定できます。 |
| 3. 複数シナリオの検討 | 基本シナリオに加えて、楽観的シナリオと悲観的シナリオを設定し、評価の幅を把握します。これにより、不確実性の高い前提条件が評価結果に与える影響を理解できます。 |
| 4. ベンチマーク比較 | 類似企業の評価指標(EBITDA倍率やPERなど)と比較することで、ターミナルバリュー計算の結果が合理的な範囲内にあるかを確認します。 |
客観的なデータに基づく前提条件の設定が、説得力のあるターミナルバリュー計算の鍵となります。楽観的すぎる前提条件は、評価の信頼性を損なうため、保守的な視点も含めたバランスの取れた分析が重要です。
ターミナルバリューを活用した企業価値評価を行う場面
ターミナルバリューを用いた企業価値評価を、実際のビジネスシーンで活用する方法について解説します。
M&Aにおけるターミナルバリューの活用
M&A(合併・買収)においては、ターミナルバリューの考え方が、買収価格の妥当性評価に重要な役割を果たします。買収対象企業の適正価値を算出する際、DCF法は最も信頼性の高い方法の一つとされています。
M&Aにおいて、ターミナルバリューは次のような点で効果的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. シナジー効果の反映 | 買収によるシナジー効果は、予測期間のキャッシュフローだけでなく、ターミナルバリューにも反映させる必要があります。例えば、永久成長率を若干高めに設定したり、最終年度のマージン改善を想定したりすることで、長期的なシナジー効果を評価に組み込むことができます。 |
| 2. 複数シナリオの検討 | 買収の意思決定においては、基本シナリオだけでなく、統合が順調に進まないケースや市場環境の変化などを想定した複数のシナリオでターミナルバリューを計算し、リスク評価を行うことが重要です。 |
| 3. 買収プレミアムの検証 | 市場価格に対するプレミアムが妥当かどうかを検証する際に、ターミナルバリューの前提条件(永久成長率や最終年度のマージンなど)を精査することで、プレミアムの合理性を説明することができます。 |
長期的な価値創造を見据えた買収判断には、ターミナルバリューの考え方が不可欠です。特に、高額な買収プレミアムを支払う場合は、それに見合うターミナルバリューが創出できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
投資判断におけるターミナルバリューの活用
投資家やアナリストにとって、ターミナルバリューの概念は、投資判断の重要な指標となります。株式投資や事業投資において、長期的な価値創造を評価する際に、ターミナルバリューの考え方が役立ちます。
投資判断におけるターミナルバリューの活用方法には、以下のようなものがあります。
| 活用場面 | 内容 |
|---|---|
| 1. 成長株の評価 | 高成長企業の株式評価では、現在の利益水準だけでなく、将来の持続的な成長可能性が重要です。ターミナルバリューの概念を用いることで、短期的な業績変動に左右されない長期的な企業価値を評価できます。例えば、一時的に利益が低くても、将来の高い成長性が期待できる企業の価値を適切に評価することができます。 |
| 2. 配当割引モデルとの連携 | 配当割引モデル(DDM)においても、永続成長率を用いたターミナルバリューの考え方が応用されています。特に安定配当企業の評価において有効です。 |
| 3. 投資ポートフォリオの構築 | 企業の長期的価値創造能力を評価するターミナルバリューの概念は、長期投資を前提としたポートフォリオ構築に役立ちます。短期的なボラティリティよりも、長期的な企業価値の成長に着目した投資戦略の基盤となります。 |
長期投資における本質的価値の評価には、ターミナルバリューの考え方が不可欠です。市場の短期的な変動に左右されず、企業の本質的な価値に基づいた投資判断を行うことで、長期的に安定したリターンを目指すことができます。
まとめ
本記事では、企業価値評価における重要な指標であるターミナルバリューについて詳しく解説しました。ターミナルバリューは、予測期間終了後の企業価値を表す指標であり、DCF法による企業価値評価において、60〜80%という大きな比重を占めています。
計算方法には、成長なしモデルと永久成長率モデルがあり、企業の成長段階や業界特性に応じて適切なモデルを選択することが重要です。また、割引率(WACC)の設定や永久成長率の選択は、評価結果に大きな影響を与えるため、現実的な前提条件に基づいた慎重な検討が必要です。
企業価値評価を行う際は、ターミナルバリューの計算に影響するパラメーターについて感度分析を行い、評価の頑健性を確認することをお勧めします。M&Aや投資判断においても、ターミナルバリューの考え方を活用することで、長期的な価値創造に基づいた意思決定が可能になります。
HTファイナンスのビジネスローン
企業価値を高めるための適切な成長投資、事業拡大に必要な資金調達をスピーディーに行いたい方へ。
HTファイナンスは、東大卒・元三菱銀行の統括責任者(三坂大作)が、銀行実務とコンサルティングの経験を活かし、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策(無担保融資・ファクタリング等)をご提案します。
※スピーディーで柔軟な審査体制で、成長資金を迅速にお届けします。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
M&Aなどの事業拡大のチャンスを逃さないためにも、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。