公開日:2025.11.05
更新日:2025.11.05
補助金に税金はかかる?課税と非課税の区分や会計処理の注意点についても解説
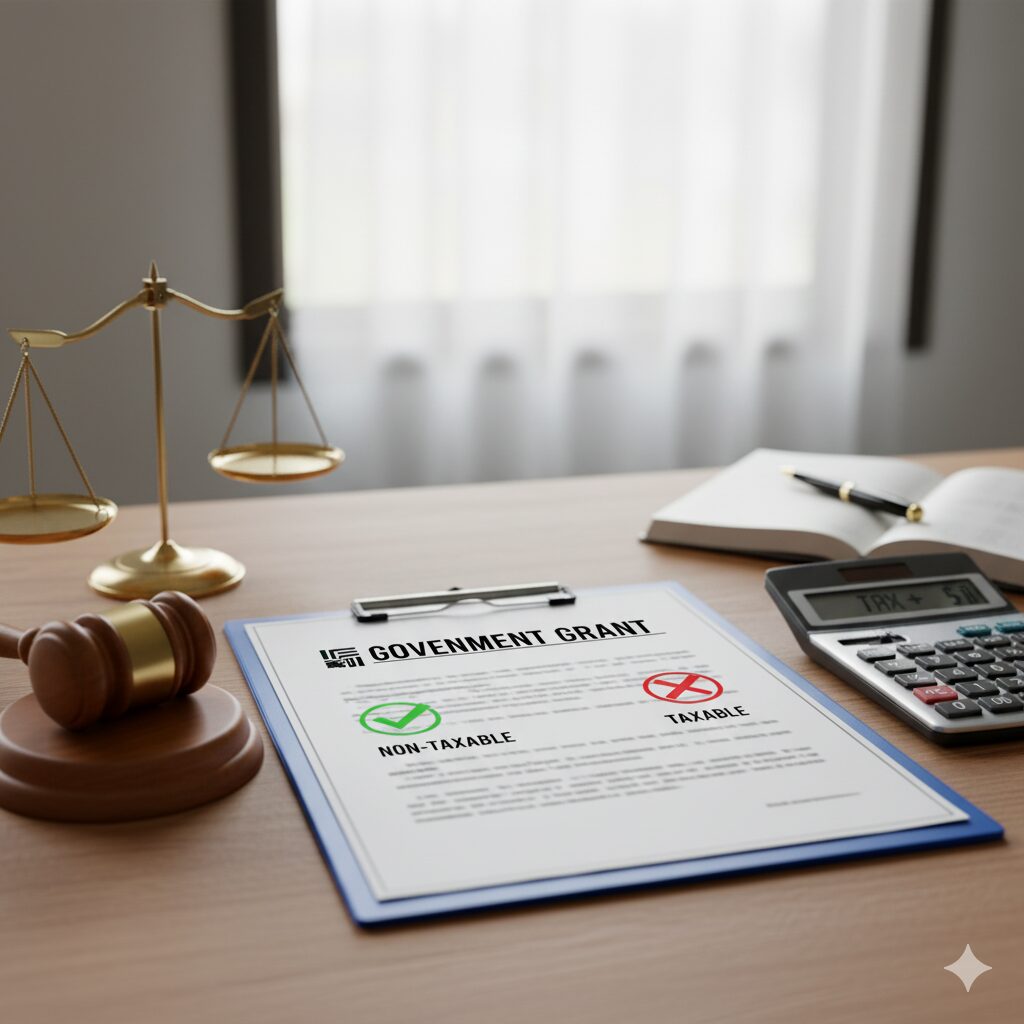
事業を営む中で、様々な補助金制度を活用しているかもしれません。実は、補助金には課税対象となるものと非課税のものがあり、種類によって税務上の扱いが異なります。さらに、会計処理においても注意すべきポイントがいくつか存在します。
この記事では、補助金にかかる税金の基礎知識から、具体的な課税・非課税の区分、適切な会計処理の方法、そして固定資産取得時の圧縮記帳など、補助金に関する税務のポイントを詳しく解説します。
この記事のポイント
- 補助金は原則として法人税・所得税の**課税対象(雑収入)**です。
- 補助金自体は対価性がないため、**消費税は不課税(課税対象外)**となります。
- 設備投資に使う補助金は「**圧縮記帳**」の活用で、初年度の税負担を将来に繰り延べできます。
- 収益計上のタイミングは入金時ではなく、原則「**交付決定日**」が基準です。
補助金だけでなく、資金調達全般でお悩みではありませんか?
「補助金は手続きが複雑…」「入金まで時間がかかる…」など、資金調達に関するお悩みはHTファイナンスにご相談ください。まずは最短60秒で結果がわかる「借入枠診断」をお試しください。
無料で借入枠診断を試してみる補助金と税金の関係
まずは、補助金と税金の関係について説明します。
補助金に対する税金の考え方
補助金は、基本的に事業活動に関連する収入として税務上で捉えられます。つまり、多くの補助金は、法人税や所得税の課税対象となるのです。
法人の場合は、「営業外収益」や「雑収入」として計上し、個人事業主の場合は、確定申告で「事業所得」や場合によっては「雑所得」として申告することになります。
一方で、消費税に関しては、異なる扱いとなります。補助金は、一般的に対価性がないものとされるため、消費税の課税対象外(不課税)となります。つまり、補助金に対して消費税を納める必要はありません。
法人と個人事業主での税務上の取り扱いの違い
法人と個人事業主では、補助金の税務上の取り扱いに若干の違いがあります。
法人の場合、受け取った補助金は、会計上「営業外収益」や「雑収入」などの科目で計上し、法人税の課税対象となります。法人税率は、事業規模によって異なりますが、法人税・地方法人税・法人住民税・事業税など合わせて、約30%程度の税負担となることが一般的です。
一方、個人事業主の場合は、事業に関連する補助金は「事業所得」として所得税の課税対象となります。事業所得は他の所得と合算され、累進課税率が適用されるため、その年の総所得金額によって税率が変わってきます。
どちらの場合も、補助金の目的や性質によって会計処理が異なる可能性があるため、案件ごとに適切な処理を検討する必要があります。
補助金の課税・非課税区分
補助金には、課税対象となるものと非課税となるものがあります。ここでは、その区分を詳しく見ていきましょう。
課税対象となる主な補助金
一般的に、事業活動に関連する補助金は、課税対象となります。具体的には、以下のようなものが代表的です。
まず、設備投資に対する補助金は、課税対象となります。これには、中小企業の設備投資を支援するものや、環境対応設備導入のための補助金などが含まれます。
また、事業収入の減少を補償するための補助金も課税対象です。例えば、新型コロナウイルス関連の持続化給付金や事業復活支援金なども課税対象となります。
雇用関連の助成金も課税対象です。雇用調整助成金や労働者の資格取得支援のための助成金なども、事業活動に関連する収入として課税対象に分類されることを覚えておきましょう。
非課税となる主な補助金
一方で、すべての補助金が課税対象となるわけではありません。次のような補助金は、非課税とされています。
まず、生活支援を目的とした個人向けの補助金は、非課税となることが多いでしょう。例えば、児童手当や特別定額給付金などは非課税です。
また、社会保障制度に基づく給付金も非課税となります。失業給付や傷病手当金などがこれに該当します。
さらに、災害被災者向けの支援金なども非課税とされています。被災者生活再建支援金などは、生活再建のための支援であり、所得を構成しないものとして非課税扱いとなります。
これらの非課税補助金は、基本的に個人の生活支援や福祉を目的としたものであり、事業活動とは直接関連しないものとなっています。
課税・非課税の判断が難しい補助金
補助金の中には、課税か非課税かの判断が難しいケースもあります。このような場合の判断基準について説明します。
まず、その補助金の目的と性質を確認することが重要です。事業活動に関連する経済的利益をもたらすものであれば、基本的に課税対象と考えられます。
次に、交付元の交付要綱や実施要領などの公式文書を確認します。これらの文書に、税務上の取り扱いが明記されていることもあります。
また、過去の類似の補助金の取り扱い事例も参考になります。税務署や管轄の経済産業局などに問い合わせることで、正確な課税区分を確認できる場合もあります。
グレーゾーンの判断は専門的知識を要するため、不明な場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。誤った判断による申告漏れは、後々追徴課税などのリスクにつながる可能性があります。
補助金の会計処理方法
補助金を受け取った際の適切な会計処理は、正確な財務諸表の作成と税務申告において重要です。
基本的な収益計上の考え方
補助金の会計処理において、基本的な収益計上の考え方を理解しておくことが重要です。
一般的に、補助金は、「雑収入」または「営業外収益」として計上します。特に事業活動に密接に関連する補助金でも、本業の売上とは区別するため、営業外収益として処理するのが一般的です。
収益計上のタイミングについては、原則として「交付決定日」を基準とします。交付決定通知を受け取った時点で権利が確定するため、その時点で収益計上するのが適切です。
ただし、補助金の種類や性質によっては、実際に補助対象となる経費が発生した時点や、補助金が入金された時点で計上するケースもあります。収益と費用の対応関係を考慮した処理が必要な場合もあるでしょう。
経費補填型補助金の処理
経費補填型の補助金とは、すでに支出した経費や、今後支出する経費を補填するために交付される補助金です。この場合の会計処理には特徴があります。
例えば、研究開発費や広告宣伝費などの経費に対する補助金の場合、経費発生と補助金交付の時期にずれが生じることがあります。この場合、経費が先に発生し、後から補助金が交付されるケースが多いでしょう。
この場合の会計処理としては、経費発生時には、まず通常通り経費として計上します。その後、補助金の交付が決定した時点で、対応する補助金を収益として計上します。
多くの経営者が悩むポイントとして、補助金と対応する経費の期ずれがあります。例えば、前年度に発生した経費に対して、当年度に補助金が交付される場合などです。この場合でも、原則として交付決定があった事業年度で収益計上します。
補助金に関連する帳簿記入の例
実際の帳簿記入例を見ながら、補助金の会計処理について具体的に理解しましょう。
まず、補助金の交付が決定した時点での仕訳です。補助金の交付決定通知を受け取った時点で、次のような仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 未収入金 100万円 | 雑収入 100万円 |
次に、実際に補助金が入金された時点での仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 100万円 | 未収入金 100万円 |
設備投資に対する補助金の場合、圧縮記帳を適用するならば、以下のような仕訳となります(圧縮記帳については後述します)。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 未収入金 100万円 | 固定資産圧縮損 100万円 |
正確な会計処理のための証憑書類の保管も重要です。補助金の交付決定通知書、補助金の入金を確認できる通帳のコピー、補助対象経費の支払いを証明する領収書など、関連する書類はすべて保管しておきましょう。
固定資産取得と圧縮記帳
設備投資に対する補助金を受け取った場合、税負担を平準化するための特別な処理方法があります。(圧縮記帳(固定資産圧縮損)の詳しい仕組みについては、こちらの記事でも解説しています。)
圧縮記帳の仕組み
圧縮記帳とは、固定資産の取得や改良のために交付された補助金等について、その補助金相当額を固定資産の取得価額から差し引いて、帳簿価額を減額する会計処理のことです。
補助金:300万円
補助金収入 300万円
(別途、減価償却費が発生)
税負担が一時的に急増する
補助金:300万円
補助金収入 300万円
固定資産圧縮損 300万円 (損金)
→ 2つが相殺される
(設備の帳簿価額が700万円に減額され、
将来の減価償却費が減ることで課税が繰り延べられる)
例えば、1,000万円の設備を導入し、300万円の補助金を受け取った場合、圧縮記帳を適用すると、その設備の帳簿価額は700万円となります。
圧縮記帳の最大のメリットは、税負担の繰り延べ効果です。補助金を受け取った年度に一度に課税されるのを避け、減価償却費の減少を通じて税負担を将来に分散させることができます。
特に、高額な設備投資に対する補助金を受けた場合、一時的な課税所得の増加を抑えられるため、資金繰りの面でも有利に働きます。また、法人税率の引き下げが予想される場合には、将来の低い税率で課税されることになるため、税負担の総額を抑える効果も期待できます。(参考:国税庁「No.5605 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳」)
圧縮記帳の適用方法
圧縮記帳を適用するには、いくつかの手続きが必要です。具体的な適用方法を見ていきましょう。
まず、圧縮記帳には、「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があります。直接減額方式は、固定資産の帳簿価額を直接減額する方法で、最も一般的に利用されています。一方、積立金方式は、固定資産の帳簿価額はそのままに、貸借対照表の純資産の部に「圧縮積立金」を計上する方法です。
圧縮記帳の適用には、確定申告書に「圧縮記帳に関する明細書」を添付する必要があります。また、法人の場合は、圧縮記帳を適用する旨を株主総会等で決議し、その議事録を保管しておくことも重要です。
圧縮記帳の適用時期は、原則として固定資産を取得した事業年度ですが、補助金の交付が翌事業年度になる場合には、一定の要件のもとで繰り延べが認められています。
圧縮記帳を適用する際の注意点
圧縮記帳の適用にあたっては、いくつかの注意点があります。
まず、すべての補助金が圧縮記帳の対象となるわけではありません。固定資産の取得や改良を直接の目的としない補助金(運転資金に対する補助金など)は対象外です。
また、圧縮記帳を適用すると、その後の減価償却費が減少するため、会計上の利益は増加します。これにより、財務諸表上の利益率や自己資本比率などの経営指標に影響を与える可能性があります。
さらに、圧縮記帳を適用した固定資産を売却する場合、圧縮記帳分が利益に上乗せされるため、想定以上の譲渡益が発生する可能性があります。将来の固定資産売却も視野に入れた税務計画が必要です。
圧縮記帳の適用には、専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な設備投資や複数の補助金を組み合わせるケースでは、最適な税務戦略を立てることが重要です。
補助金の「入金待ち」や「つなぎ資金」でお困りですか?
補助金は魅力的ですが、交付決定から入金まで数ヶ月かかるケースも少なくありません。HTファイナンスのビジネスローンなら、無担保・無保証で最短即日のご融資も可能です。事業チャンスを逃さないための「つなぎ資金」としてご活用ください。
まずは無料で借入枠診断(最短60秒)補助金に関する税務上の注意点
補助金を受け取る際には、税務上いくつかの注意点があります。ここでは、実務上の重要ポイントを解説します。
申告漏れを防ぐための管理のコツ
補助金の申告漏れは、後々の税務調査で指摘されるリスクがあります。これを防ぐための管理方法を紹介します。
まず、補助金の交付決定通知や入金記録など、すべての関連書類を体系的に整理・保管することが重要です。特に、交付決定通知書、交付申請書、実績報告書、補助金の入金を確認できる通帳のコピーなどは必ず保管しましょう。
また、補助金専用の台帳を作成し、申請から入金、確定申告までの流れを一元管理することも効果的です。複数の補助金を受け取っている場合は、特に重要となります。
補助金の交付時期と会計年度の把握も欠かせません。交付決定と実際の入金が異なる会計年度にまたがる場合、適切な会計処理と申告が必要になります。決算前に受け取る予定の補助金をリスト化し、漏れがないかチェックする習慣をつけましょう。
補助金と消費税の関係
補助金と消費税の関係は、多くの方が混乱しやすいポイントです。正確な理解が必要です。
前述のとおり、補助金自体は消費税の課税対象外(不課税)です。しかし、補助金で購入した物品やサービスに係る消費税の取り扱いには注意が必要です。(参考:国税庁「No.6481 国内取引の課税標準」)
例えば、補助金の交付額に消費税分が含まれているケースがあります。この場合、補助対象経費に含まれる消費税分について、消費税の仕入税額控除を適用すると、補助金と消費税の二重の恩恵を受けることになります。
多くの補助金制度では、消費税の仕入税額控除を受ける予定の事業者に対しては、補助対象経費から消費税分を除外することを求めています。補助金申請時の消費税の取り扱いについては、各補助金の交付要綱等で確認するか、交付元に直接問い合わせることをお勧めします。
複数年度にわたる補助金の処理
複数年度にわたって交付される補助金の処理には、特有の注意点があります。
まず、複数年度にわたる事業に対する補助金の場合、各年度の交付決定に基づいて、その年度ごとに収益計上するのが原則です。一括して収益計上するのではなく、交付決定のあった年度ごとに区分して処理します。
また、前払いで受け取った補助金で、翌年度以降の経費に充当する場合は、「前受金」や「長期前受金」として処理し、実際に経費が発生する年度で収益に振り替えるケースもあります。
複数年度の補助金を適切に管理するためには、各年度の交付決定額、実際の交付額、対象となる経費などを明確に区分した台帳を作成することが有効です。また、税理士などの専門家と相談しながら、適切な会計処理方針を決定することをお勧めします。
事業計画に補助金を利用する際のポイント
補助金を上手に活用するためには、税務面だけでなく、事業計画全体での位置づけを考える必要があります。
補助金への依存の回避
補助金は、事業の一時的な支援として有効ですが、過度に依存することにはリスクがあります。そのリスク回避策を考えましょう。
まず、補助金は、恒久的な収入源ではありません。多くの補助金制度は期間限定であり、政策の変更によって突然終了する可能性もあります。そのため、補助金に頼らない収益構造の構築が重要です。
具体的には、補助金で導入した設備や開発した商品・サービスが、補助金終了後も持続的に収益を生み出せるかを事前に検討することが大切です。投資回収計画を立てる際には、補助金がない場合のシナリオも想定しておきましょう。
また、複数の収益源を持つことで、特定の補助金に依存するリスクを分散させることも効果的です。本業の収益力強化を最優先としながら、補助金はあくまで成長を加速させるための追加的な手段と位置づけるべきでしょう。(補助金以外の資金調達方法や緊急時の資金繰り対策も併せて確認しておきましょう。)
補助金に関する計画的な税務処理
補助金を活用する際には、中長期的な税務計画も重要です。効果的な税務計画のポイントを見ていきましょう。
まず、補助金による収入増加が見込まれる年度は、可能な範囲で経費の前倒しや設備投資を検討することで、課税所得の増加を抑える工夫ができます。ただし、不自然な経費計上は、税務調査のリスクを高めるため、事業上の合理性を確保することが前提です。
また、固定資産の取得に関わる補助金では、前述の圧縮記帳を活用して税負担の平準化を図ることが有効です。圧縮記帳の適用可否を早めに検討し、必要な手続きを準備しておきましょう。
さらに、複数年度にわたる事業計画では税率変更の影響も考慮する必要があります。例えば、法人税率の引き下げが予想される場合、可能な範囲で収益認識を将来に繰り延べる方策も検討価値があります。
補助金申請前の相談
補助金の申請を検討する段階から、税務の専門家に相談することで、多くのメリットが得られます。
補助金申請前の税務相談では、受給後の税負担や会計処理を事前に把握できるため、資金計画をより正確に立てることができます。特に高額な補助金の場合、税金の支払いに必要な資金を予め確保しておくことが重要です。
また、複数の補助金制度から最適なものを選ぶ際にも、税務面からの比較検討が役立ちます。例えば、同じ金額の補助金でも、課税される補助金と非課税の補助金では、実質的な経済効果が大きく異なります。
補助金の種類によって最適な会計処理方法が異なるため、申請前に税理士などの専門家と相談し、事業計画全体の中で補助金をどう位置づけるかを検討することをお勧めします。これにより、補助金の効果を最大化しつつ、税務リスクを最小化することができるでしょう。
まとめ
補助金の税務処理について、課税・非課税の区分、会計処理方法、圧縮記帳の活用法、そして税務上の注意点を解説してきました。補助金は、基本的に法人税・所得税の課税対象となりますが、生活支援目的のものは非課税となるケースもあります。また、固定資産取得のための補助金では、圧縮記帳を活用することで税負担を分散できます。
補助金を活用する際は、単に受給するだけでなく、適切な会計処理と税務申告を行うことが重要です。不明点があれば税理士などの専門家に相談し、補助金の効果を最大化しながら、税務リスクを最小化する戦略を立てましょう。
緊急の資金ニーズに。最短即日の無担保・無保証融資
補助金の申請と並行して、当面の運転資金や急な資金需要にお応えするのがHTファイナンスのビジネスローンです。元銀行員・認定支援機関の専門家が、御社の状況に最適な資金調達プランをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
今すぐ無料で相談・診断する








