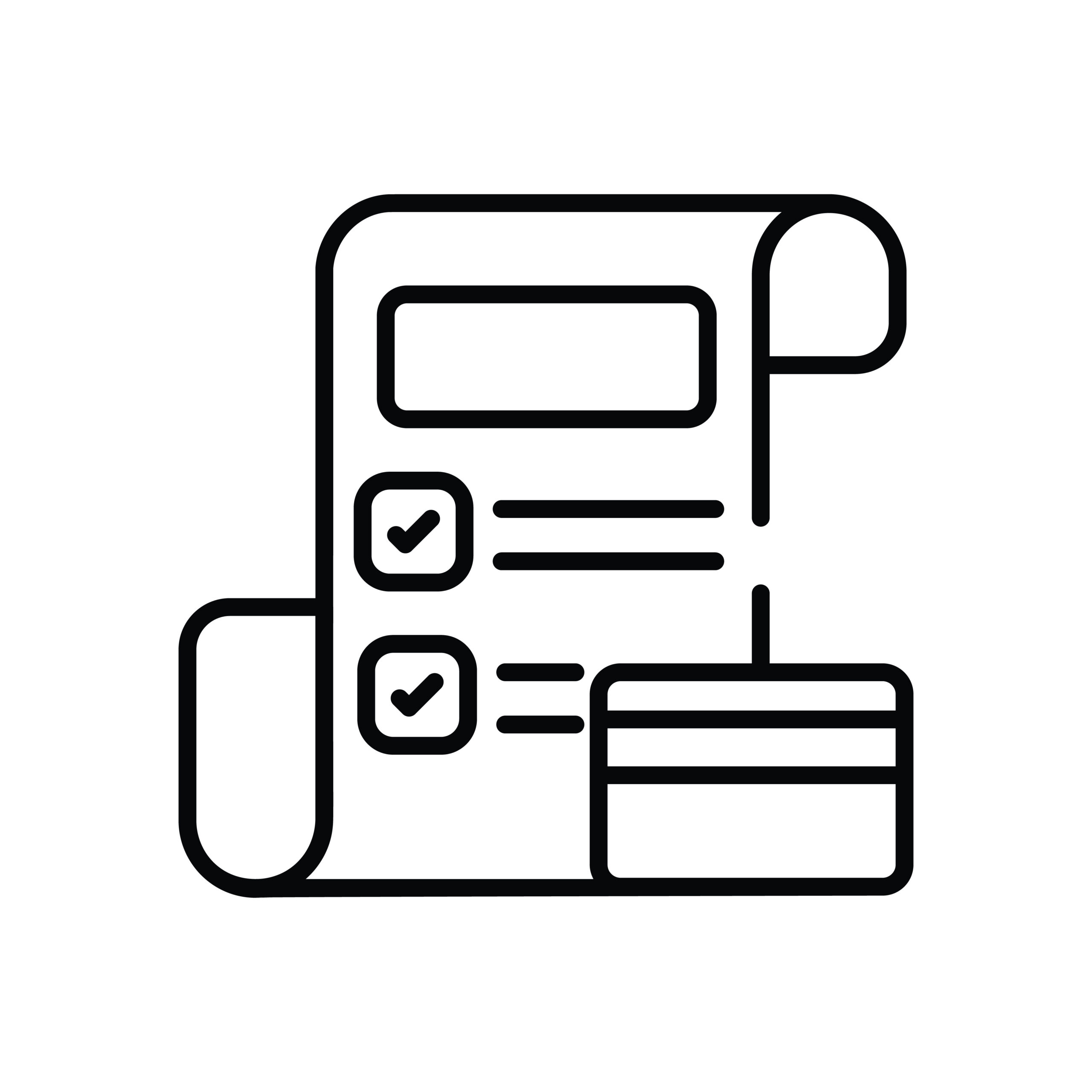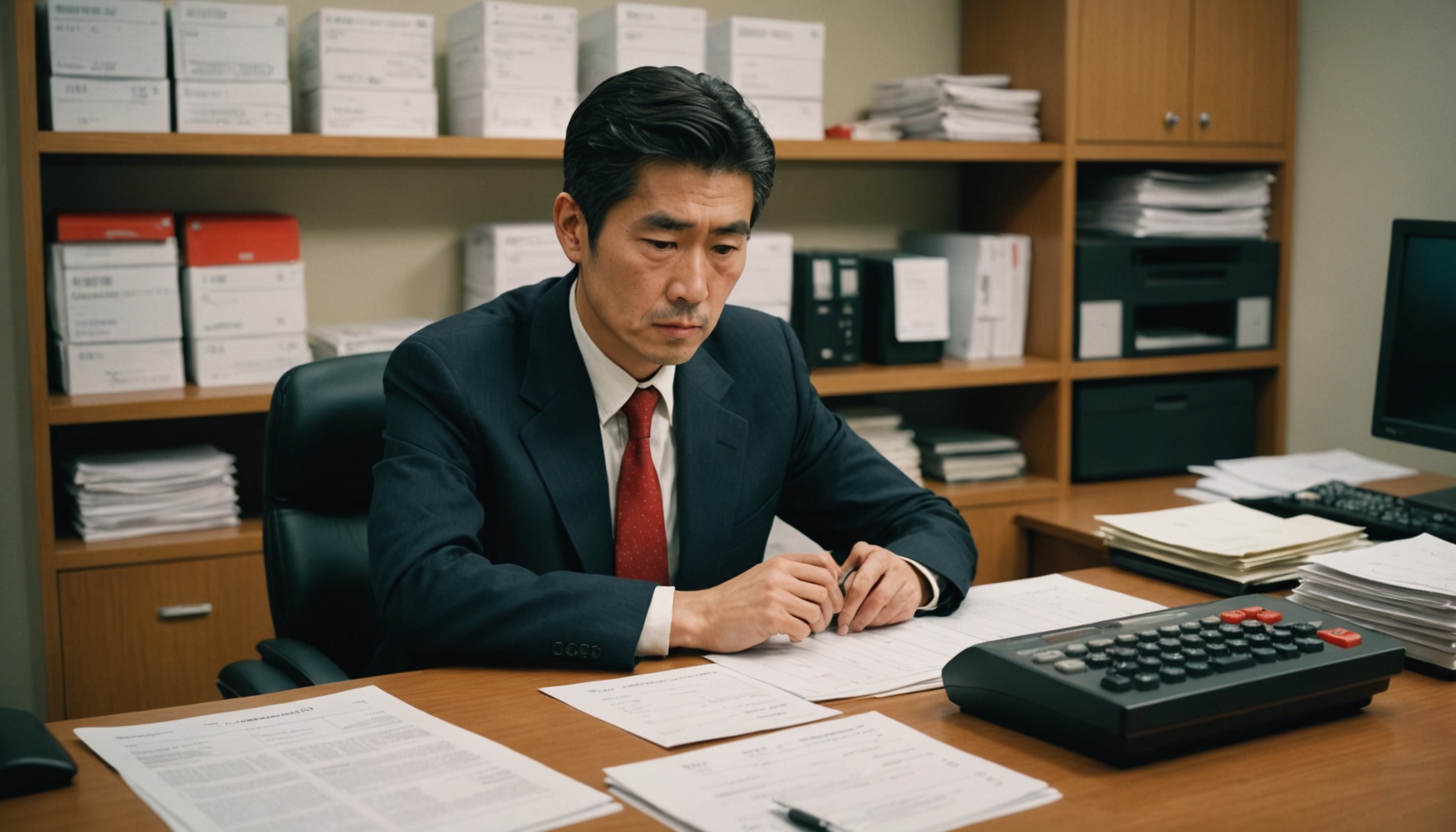公開日:2025.11.13
更新日:2025.11.13
借金の取り立て代行は個人で行える?やり方や注意点、債権回収の法的手段についても紹介

借金の回収がうまくいかず、対応に困っている方がいるかもしれません。「お金を返してくれない」といった状況で、個人で取り立てを考えることもあるでしょう。しかし、借金の取り立てには法律で決められたルールがあり、個人で安易に他人の債権回収を行うことはできません。
この記事では、合法的に借金回収を行う方法や、専門家に依頼するメリット、債権回収の法的手段について解説します。また、取り立て行為における注意点やリスクについても触れ、トラブルを避けるために必要な知識を提供します。
この記事で解決できる悩み
- 他人の借金取り立て代行は、弁護士法やサービサー法違反になる可能性があり、**個人では原則NG**です。
- 自分自身の債権(貸したお金)であれば、内容証明郵便や訴訟など、**合法的な回収方法**があります。
- 【法人様】債権回収の遅れで資金繰りが悪化している場合、回収を待つより**無担保ビジネスローン**で即時資金確保する方が合理的です。
- 【個人事業主様】売掛金の回収にお困りの場合、債権を売却して即日資金化する「**ファクタリング**」が有効な手段です。
借金の取り立て代行とは
借金の取り立て代行とは、債権者に代わって第三者が債務者から返済を受ける業務を指します。これは、単なる「お金を回収する」という行為以上に、法律で厳しく規制された業務です。
取り立て代行の仕組み
取り立て代行の仕組みは、債権者が債権回収の権限を第三者に委託し、その第三者が債務者に対して返済を請求するというものです。正規の取り立て代行業者は、債権回収会社や弁護士などの専門家が担当します。
これらの専門家は、法律に基づいた手続きを踏んで債権回収を行います。たとえば、まず督促状の送付から始め、それでも返済がない場合は裁判所を通じた法的手段に移行するというステップを踏みます。
専門家による適切な債権回収手続きは、債権者の権利を守りながらも、債務者のプライバシーや尊厳を侵害しないよう配慮されています。
法律で定められた取り立ての制限
日本では、取り立て行為は「貸金業法」や「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」などによって厳しく規制されています。これらの法律では、以下のような制限が設けられています。
取り立ての時間帯に関する制限があり、基本的に午後9時から午前8時までの取り立ては禁止されています。また、債務者の職場への取り立て連絡や、第三者への債務内容の漏洩も禁止されています。
さらに、脅迫的な言動や執拗な取り立ても違法行為とされ、これらの行為を行った場合、刑事罰の対象となる可能性があります。法律に基づく正当な権利行使であっても、その方法には厳格な制限があることを理解する必要があります。
個人が借金の取り立て代行を行えるか
個人が他人の借金の取り立て代行を行うことについては、法律上の厳しい制限があります。この点を正確に理解することが、トラブルを避けるために重要です。
取り立て代行の法律による制限
日本の法律では、債権回収業務(いわゆる取り立て業務)を行えるのは、基本的に法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)、弁護士、または債権者本人に限られています。これは、「債権管理回収業に関する特別措置法」によって定められています。
個人が第三者の債権回収を代行することは、この法律や、弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じる弁護士法第72条(非弁行為)に抵触する可能性が高く、無許可で債権回収業を営むことは違法とされています。罰則として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
法的リスクを避けるためには、自分の債権については自分で回収するか、正規の専門家に依頼することが重要です。
自分の債権回収は可能
一方で、自分自身の債権(あなたが貸したお金の返済請求)については、債権者本人として一定の範囲内で回収活動を行うことは可能です。ただし、その方法や範囲には制限があります。
自分の債権回収を行う場合でも、脅迫や強要といった行為は犯罪となります。また、相手のプライバシーを侵害するような方法での取り立ても問題になる可能性があります。
法律の範囲内で行える自分の債権回収の方法としては、直接交渉、内容証明郵便の送付、少額訴訟の提起などがあります。これらの方法は、後述する「個人でできる合法的な債権回収方法」で詳しく説明します。
お悩み別:あなたが今すぐ検討すべき選択肢
悩み: 回収の遅れで自社の資金繰りが悪化している。
解決策: 回収を待つストレスより、まずは**無担保・無保証のビジネスローン**で安定資金を確保し、本業に集中することを推奨します。
悩み: 取引先からの入金(売掛金)が遅れている。
解決策: その売掛債権を売却し、即日現金化できる「**ファクタリング**」が有効です。HTファクタリングは個人事業主様も対応可能です。
悩み: 友人や知人にお金を貸したが返してくれない。
解決策: この記事で解説する「内容証明郵便」や「少額訴訟」などの法的手続きをご参照ください。(弁護士・司法書士への相談をお勧めします)
個人でできる合法的な債権回収方法
自分の債権を回収する場合、いくつかの合法的な方法があります。これらの方法を適切に活用することで、効果的に債権回収を進めることができます。
直接交渉による回収
最も基本的な債権回収方法は、債務者と直接交渉することです。この方法では、相手と話し合いの場を設け、返済計画について合意を目指します。
交渉の際は、威圧的な態度を取らず、冷静かつ理性的に対応することが重要です。また、交渉内容や合意事項は必ず書面に残し、双方が署名することで後のトラブルを防ぐことができます。
円満な解決を目指す姿勢を持つことで、相手も誠実に対応してくれる可能性が高まります。また、分割返済などの柔軟な提案をすることで、完全な回収が難しい場合でも、一部回収の道が開けることがあります。
内容証明郵便の活用
直接交渉がうまくいかない場合、内容証明郵便を送付することも効果的な方法です。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便には、債務の内容、返済を求める金額、支払期限などを明記します。法的手続きに移行する前の最終通告として送付することで、債務者に返済の必要性を強く認識させることができます。
また、内容証明郵便の送付は、後に法的手続きを取る際の証拠としても重要な役割を果たします。裁判所に「返済を求める努力をした」という事実を示す証拠となるため、必ず控えを保管しておきましょう。
債権譲渡による回収
なお、事業者が持つ売掛債権(取引先に請求する権利)を譲渡して資金化することは、一般的に「債権譲渡(ファクタリング)」と呼ばれ、法的に認められた資金調達および債権回収の手段です。
債権譲渡とは、自分が持っている債権(貸したお金を返してもらう権利)を第三者に売却することです。この方法では、債権の額面より低い金額で売却することが一般的ですが、確実に一定額を回収できるメリットがあります。
債権譲渡を行う場合は、債務者に対して債権譲渡通知を行う必要があります。この通知がなければ、債務者は譲渡の事実を知らないまま、元の債権者に返済してしまう可能性があるためです。
債権回収の専門業者への譲渡は、自分で回収する手間を省きつつ、ある程度の金額を確保できる現実的な選択肢です。ただし、譲渡価格は債権額の数十%程度になることが多いため、その点は理解しておく必要があります。
個人事業主・フリーランス様へ
その「売掛債権」、HTファクタリングが買い取ります!
取引先に知られずに、最短即日で資金化が可能です。面倒な債権回収のストレスから解放され、本業に集中しませんか?
相殺による債務消滅
相殺とは、お互いに債権債務の関係がある場合、それらを差し引きして精算する方法です。例えば、AさんがBさんに10万円の貸し金があり、同時にBさんからAさんへの5万円の貸し金がある場合、相殺すればAさんのBさんに対する債権は5万円になります。
相殺を行うには、相手方に相殺の意思表示を行う必要があります。これは、口頭でも有効ですが、後のトラブルを避けるために書面で行うことが望ましいでしょう。
相殺は、自分も相手に対して債務を負っている場合に特に有効な方法です。法的にも認められた債権回収方法であり、双方の債務を効率的に解消することができます。
法的手段による債権回収の流れ
直接交渉や内容証明郵便での請求が功を奏さない場合、法的手段に訴えることになります。法的手段による債権回収には一定の手順があり、それぞれの段階で適切な対応が求められます。
支払督促の申立て
支払督促とは、裁判所を通じて債務者に支払いを命じる手続きです。通常の訴訟と比べて手続きが簡略化されており、費用も抑えられるというメリットがあります。
支払督促の申立ては、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所で行います。申立てに必要な書類には、支払督促申立書、債権の発生原因を証明する資料(契約書や借用書など)があります。
手続きの簡便さと費用対効果から、少額の債権回収に適した方法です。ただし、債務者が異議申立てを行うと通常の訴訟手続きに移行するため、その点は理解しておく必要があります。
少額訴訟の場合
少額訴訟は、60万円以下の金銭債権について、原則として1回の期日で審理を終える簡易な訴訟手続きです。通常の訴訟よりも短期間で決着がつくため、比較的少額の債権回収に適しています。
少額訴訟を提起するには、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。必要な書類には、訴状、債権の発生原因を証明する資料、その他関連する証拠があります。
少額訴訟のメリットは、短期間で結論が出ることと、手続きが比較的簡単なことです。ただし、年間で、同じ裁判所に対して10件までしか申し立てることができないという制限があります。
通常訴訟の場合
支払督促や少額訴訟が適さない場合、通常訴訟を提起することになります。通常訴訟は、金額の制限がなく、複雑な事案にも対応できる本格的な裁判手続きです。
通常訴訟を提起するには、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提出します。訴状には、当事者の情報、請求の趣旨、請求の原因などを記載します。また、債権の発生原因や金額を証明する証拠も提出する必要があります。
証拠の収集と整理が重要となる手続きです。裁判で勝訴するためには、債権の存在と金額を明確に証明できる証拠が不可欠です。契約書、借用書、メールやLINEでのやり取りなど、あらゆる証拠を保全しておきましょう。
判決後の強制執行
裁判で勝訴しても、相手が自主的に支払わない場合は、強制執行の手続きが必要になります。強制執行とは、裁判所の命令に基づいて債務者の財産を差し押さえ、それを換価して債権を回収する手続きです。
強制執行を申し立てるには、債務名義(判決や支払督促など)を取得した上で、債務者の財産に関する情報を集める必要があります。主な強制執行の方法には、不動産執行、動産執行、債権執行(預金や給与の差押え)などがあります。
強制執行は、専門的な知識が必要な手続きであるため、弁護士に依頼することが一般的です。また、債務者に差し押さえるべき財産がない場合(いわゆる「債務者が無資力の場合」)は、強制執行を行っても回収できない可能性があることも理解しておく必要があります。
取り立てを専門家に代行してもらうメリット
債権回収を自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで多くのメリットがあります。特に、複雑なケースや高額な債権の場合は、専門家の力を借りることを検討すべきでしょう。
弁護士に代行してもらうメリット
弁護士は、法律の専門家として、債権回収に関する豊富な知識と経験を持っています。弁護士に依頼することで、法的に適切な手続きを踏んだ効果的な債権回収が可能になります。
弁護士は、内容証明郵便の作成から、訴訟の提起、強制執行の申立てまで、一連の法的手続きを代行してくれます。また、債務者との交渉も弁護士が行うことで、感情的になりがちな直接対話のリスクを避けることができます。
法的権限と専門知識の活用により、自分では対応が難しい複雑なケースでも、効果的に債権回収を進めることができます。特に、債務者が法人である場合や、債権額が高額な場合には、弁護士の専門的なアドバイスが大きな助けとなります。
債権回収会社に代行してもらうメリット
債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を受けて債権回収業務を行う専門業者です。これらの会社は、債権回収のノウハウを持ち、効率的な回収を実現します。
債権回収会社は、債権の買取りや回収の委託を受け付けています。債権を買い取ってもらう場合は、債権額より低い金額での売却となりますが、確実に一定額を回収できるメリットがあります。一方、回収を委託する場合は、成功報酬型の手数料体系が一般的です。
効率的かつ専門的な回収活動が、債権回収会社の強みです。彼らは、債務者の所在確認や資産調査のノウハウを持ち、法律の範囲内で効果的なアプローチを行います。また、複数の債権をまとめて委託することで、回収コストを抑えることも可能です。
司法書士に代行してもらうメリット
司法書士は、140万円以下の債権については簡易裁判所での訴訟代理権を持っています。このため、比較的少額の債権回収では、弁護士よりも費用を抑えつつ、専門的なサポートを受けられる可能性があります。
司法書士は、内容証明郵便の作成、支払督促の申立て、少額訴訟の提起など、債権回収に必要な法的手続きをサポートします。また、債務者との交渉や和解契約の作成なども行ってくれます。
コストパフォーマンスの高いサポートが司法書士の強みです。特に、個人間の少額貸付やサービス提供後の未払い料金の回収など、比較的シンプルなケースでは、司法書士のサポートが効果的かつ経済的な選択となるでしょう。
借金の取り立てにおける禁止行為
債権回収を行う際には、法律で禁止されている行為があります。これらの行為を行うと、刑事罰や民事上の責任を問われる可能性があるため、十分に注意する必要があります。
違法な取り立て行為
債権回収における違法行為には、主に以下のようなものがあります。これらの行為は、貸金業法や刑法などで禁止されており、罰則の対象となります。
まず、暴力や脅迫を用いた取り立ては明確な違法行為です。「払わないと家族に危害を加える」などの脅迫的な言動は、恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性があります。
法律違反のリスクを認識し、いかなる場合も暴力や脅迫に訴えてはいけません。また、深夜や早朝の取り立て、執拗な取り立て、職場への連絡、第三者への債務内容の漏洩なども違法とされる行為です。
違法行為による罰則
取り立てにおける違法行為を行った場合、様々な法的責任を問われる可能性があります。これらの罰則を理解し、法律の範囲内で適切に債権回収を行うことが重要です。
刑事罰としては、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)、恐喝罪(10年以下の懲役)、暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)などが適用される可能性があります。また、無許可で債権回収業を営んだ場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
民事上の責任としては、違法な取り立て行為により相手に精神的苦痛を与えた場合、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。このような損害賠償請求を受けると、本来回収すべき債権よりも、多額の賠償金を支払わなければならないケースもあります。
適法な取り立ての範囲
債権回収を行う際には、法律の範囲内で適切に行動することが重要です。適法な取り立ての範囲を理解し、それを守ることで、トラブルを避けながら効果的に債権回収を進めることができます。
適法な取り立ての基本的なルールとしては、相手の人格を尊重すること、平穏な生活を乱さないこと、プライバシーを侵害しないことが挙げられます。具体的には、平日の昼間に連絡すること、相手が応対できない場合は無理に話を続けないこと、第三者に債務の内容を漏らさないことなどが重要です。
適切なコミュニケーションの維持は、円滑な債権回収の鍵です。債務者を責めるのではなく、共に解決策を探るという姿勢で接することで、相手も誠実に対応してくれる可能性が高まります。また、すべてのやり取りは記録に残し、後のトラブルに備えることも大切です。
債権回収を成功させるためのポイント
債権回収を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを意識することで、回収の可能性を高めることができます。
証拠の確保と保全
債権回収において、最も重要なことの一つが、適切な証拠の確保と保全です。債権の存在を証明できる証拠がなければ、法的手段を用いても回収は困難になります。
借用書や契約書は必ず作成し、安全な場所に保管しておきましょう。電子データの場合はバックアップを取っておくことも重要です。また、返済の約束や交渉の経緯に関するメールやLINEなどのやり取りも、スクリーンショットを撮るなどして保存しておきましょう。
契約時の明確な文書化は、後のトラブルを防ぐ最も効果的な方法です。金銭を貸す際には、金額、返済期限、利息(ある場合)、返済方法などを明記した借用書を作成し、債務者の署名をもらっておくことが理想的です。
早期での対応
債権回収では、問題が発生した際の早期対応が非常に重要です。返済が遅れ始めたら、すぐに連絡を取り、状況を確認することが回収成功の鍵となります。
時間が経過するほど、債務者の状況が変わったり、資産が散逸したりする可能性が高まります。また、債権には時効があり、一定期間が経過すると請求権が消滅してしまう可能性もあります。一般的に、貸金債権の時効は5年ですが、状況によって異なる場合もあります。
問題の初期段階での対応が、最終的な回収率を大きく左右します。返済遅延の兆候が見られたら、すぐに債務者と連絡を取り、返済計画の見直しや分割払いの提案など、柔軟な対応を検討しましょう。
【法人経営者の方へ】
債権の回収を待つ間の「キャッシュフローの枯渇」こそが、経営における最大のリスクです。自社の資金繰りに不安がある場合は、回収の努力と並行して、ビジネスローンで当座の資金を確保するという選択肢を強く推奨します。資金に余裕を持つことで、焦らずに法的手続きや交渉を進めることができます。
交渉スキルの向上
債権回収における交渉は、回収成功の可能性を大きく左右します。効果的な交渉スキルを身につけることで、友好的な関係を維持しながら、債権を回収する可能性が高まります。
交渉の際は、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話を進めることが重要です。また、相手の言い分にも耳を傾け、状況を理解した上で、双方が納得できる解決策を模索しましょう。
柔軟な返済プランの提案も効果的な交渉術の一つです。一括返済が難しい場合は、分割払いや返済期限の延長など、債務者の状況に合わせた提案をすることで、部分的にでも回収できる可能性が高まります。
まとめ
借金の取り立て代行は、法律で厳しく規制されている行為です。個人が他人の債権回収を代行することは基本的にできませんが、自分の債権については、法律の範囲内で様々な回収方法があることがわかります。
効果的な債権回収のためには、まず直接交渉や内容証明郵便などの穏当な方法を試み、それでも解決しない場合は、法的手段を検討することが重要です。どの段階でも、違法な取り立て行為は避け、証拠の確保と早期対応を心がけましょう。複雑なケースや高額な債権の場合は、弁護士や債権回収会社などの専門家に相談することで、効率的かつ適法な回収が可能になります。
法的手続きより先に、経営の安定化を。
債権回収には時間とコストがかかります。回収を待つ間に経営が傾く前に、まずはHTファイナンスの**無担保・無保証ビジネスローン**をご検討ください。最短即日で必要な運転資金を確保し、経営の安定を取り戻しましょう。
最短1分「借入枠診断」はこちら