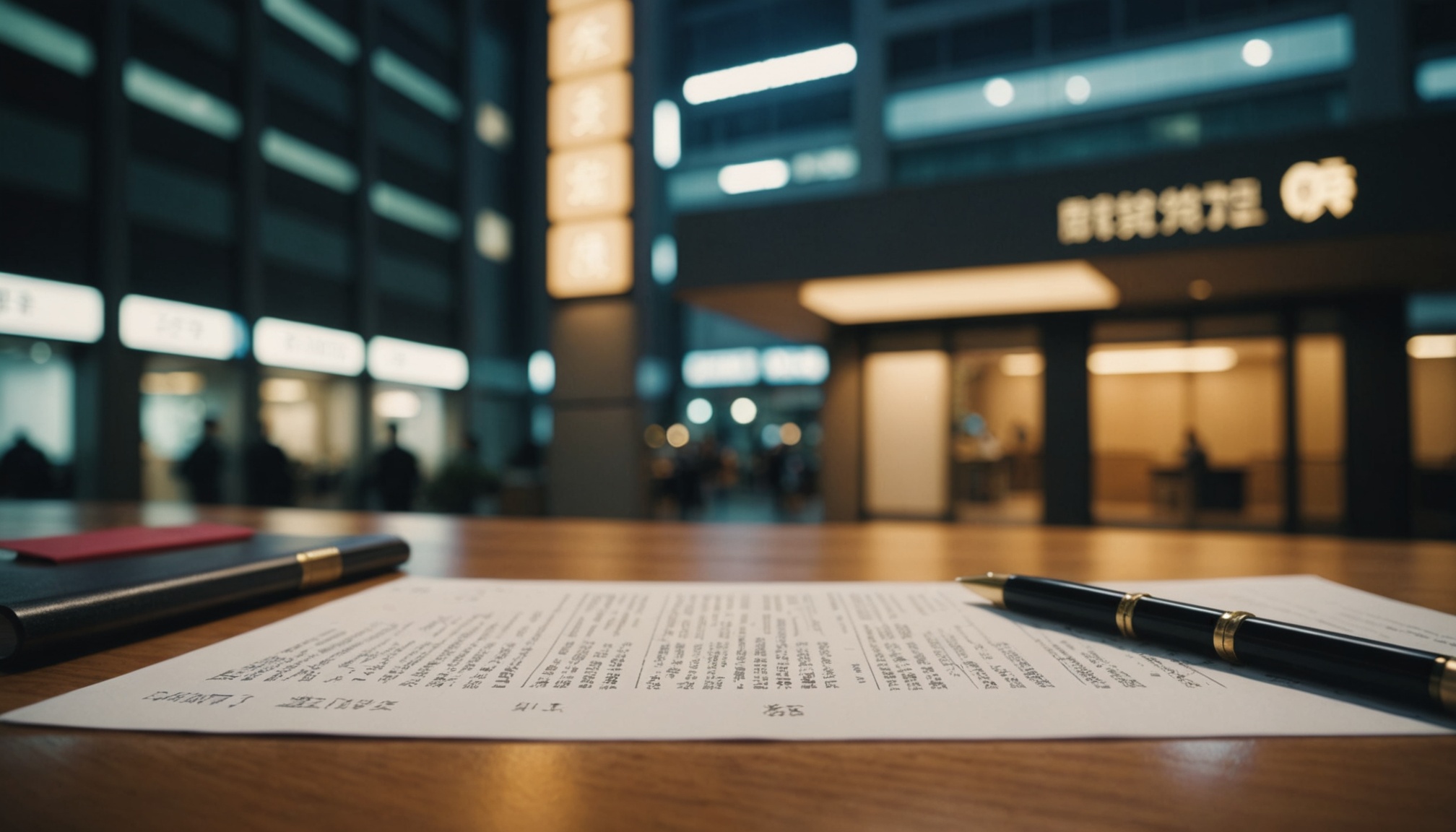公開日:2025.11.14
更新日:2025.11.17
企業生存率を高めるためには何をすればいい?資金計画の重要性についても解説

企業を経営していると、事業の将来に不安を感じることがあるかもしれません。実際、日本では、創業から5年後に生き残る企業は約81.7%、10年後には72%にまで低下します。特にベンチャー企業に限ると、10年後の生存率はわずか6.3%と、厳しい数字になっています。
企業が長期的に存続するためには、資金繰りの改善や後継者問題の解決、時代に合った事業展開など、さまざまな取り組みが必要です。資金計画は、その中でも特に重要な要素となります。
この記事では、企業生存率の詳細を説明し、それに影響を与える要因と、企業が長く存続するための具体的な方策について詳しく解説します。
この記事のポイント
- 日本企業の生存率は、創業10年で約72%、ベンチャー企業に限ると10年でわずか6.3%と厳しい現実がある。
- 企業の存続には、短期的な「キャッシュフローの悪化」と長期的な「後継者不在」や「市場の変化」が大きく影響する。
- 生存率を高める鍵は「計画的な資金調達」にあり、特に法人の場合は「無担保・無保証のビジネスローン」が有効な戦略となる。
- 資金繰りの選択肢として、法人はビジネスローン、個人事業主はファクタリングの活用が推奨される。
「もしもの時の資金」に不安はありませんか?
企業の存続には、予測不能な事態に備える「資金計画」が不可欠です。HTファイナンスは、法人の経営者様限定で、担保や保証人に頼らないビジネスローンをご提供しています。
まずは「借入枠」を無料で診断する企業生存率とは
企業を長く存続させることは、多くの経営者にとって重要な課題です。まずは、企業生存率の定義と現状について理解しましょう。
日本の企業生存率の特徴
企業生存率とは、新たに設立された企業のうち、一定期間後に事業を継続している企業の割合を示す指標です。この数値が高いほど、企業が市場環境や経営課題を乗り越え、持続的に事業を展開できていることを意味します。
経済産業省や中小企業庁などの調査によると、日本における企業の生存率は、諸外国と比較しても比較的高い水準にあります。しかし、年数が経過するにつれて徐々に低下していく傾向があり、長期的な企業存続には計画的な経営戦略が不可欠です。
企業生存率は、単なる統計数値ではなく、経営の安定性や事業の持続可能性を示す重要な指標であり、投資家や取引先、金融機関からの信頼にも直結します。
日本における年数別の企業生存率のデータ
日本における企業生存率は、創業からの経過年数によって大きく変化します。具体的なデータを見ていきましょう。
創業から5年後の企業生存率は、約81.7%です。これは、5社に1社が5年以内に廃業していることを意味します。10年後になると生存率は約72%まで低下し、およそ3社に1社が事業継続できていない計算になります。
特に注目すべきは、ベンチャー企業の生存率の低さです。ベンチャー企業に限ると、10年後の生存率はわずか6.3%、20~50年後になるとさらに0.3%まで下がります。一方、全体では、20~50年後の生存率は約55%となっており、創業期を乗り越えた企業の半数以上が長期存続に成功していることがわかります。
さらに特筆すべきは、50年以上存続している企業の割合が、約0.96%であることです。これは、100社に1社が半世紀以上の歴史を持つことを示しており、長期存続の難しさを物語っています。
海外における企業生存率との比較
日本の企業生存率は、国際的に見ても特徴的です。世界各国と比較してみましょう。
日本は「老舗企業大国」とも呼ばれ、創業100年以上の企業数が世界最多を誇ります。特に、創業200年以上の企業数は、世界全体の約4割を日本企業が占めているというデータもあります。
欧米諸国と比較すると、日本の企業生存率は全体的に高い傾向にあります。例えば、アメリカでは5年後の企業生存率が約50%、10年後では約35%といわれており、日本の数値を大きく下回ります。
この違いには、様々な要因が考えられますが、日本特有の商慣行や事業承継の文化、そして、長期的な関係構築を重視する経営姿勢が影響していると考えられます。一方で、欧米では起業と撤退のサイクルが早く、市場の新陳代謝が活発である点も特徴です。
企業生存率に影響を与える短期的要因
企業の存続には、様々な要因が影響します。まずは、短期的に企業生存率に影響を与える要因について解説します。
業績不振
業績不振は、企業存続を脅かす最も直接的な要因です。売上減少や利益率の低下は、企業活動の多くの側面に悪影響を及ぼします。
業績が悪化すると、まず資金繰りに支障をきたし、運転資金の確保が難しくなります。これにより、仕入れや人件費の支払いに遅延が生じると、取引先や従業員からの信頼を失うリスクが高まります。
また、業績不振が続くと、従業員のモチベーション低下や離職率の上昇につながり、組織力の低下を招きます。さらに、人材流出によってサービス品質が低下すると、顧客離れを加速させるという悪循環に陥りやすくなります。
業績悪化の初期段階での迅速な対応が極めて重要です。財務指標を定期的にチェックし、売上や利益の減少傾向が見られた場合は、原因分析と対策立案を早急に行う必要があります。
キャッシュフローの悪化
企業の存続において、キャッシュフローの管理は、利益確保と同等かそれ以上に重要です。実際に、「黒字倒産」ということばがあるように、利益を出していても現金の流れが悪化すれば、事業継続が困難になります。
キャッシュフローが悪化する主な原因としては、売掛金回収の遅れや在庫の過剰保有、設備投資の失敗などが挙げられます。特に成長期の企業は、売上拡大に伴って運転資金需要が増加するため、資金繰りの計画が不十分だと、急速に資金不足に陥る可能性があります。
また、季節変動の大きい業種や、プロジェクト型のビジネスモデルを持つ企業は、収入と支出のタイミングにずれが生じやすく、キャッシュフロー管理がより複雑になります。短期的な資金繰り表の作成と定期的な見直しが欠かせません。
キャッシュフロー改善のためには、請求サイクルの短縮、支払い条件の見直し、在庫の適正化などの施策が有効です。また、資金調達の多様化も重要です。従来の銀行融資だけでなく、HTファイナンスが提供するような無担保・無保証のビジネスローンは、緊急時やスピーディーな資金調達が必要な場面で大きな助けとなります。さらに、売掛金を早期に現金化するファクタリングなどの手法も検討すべきでしょう(個人事業主の方はこちら)。
人手不足
近年、少子高齢化の進行により、多くの業界で人手不足が深刻化しています。人材確保の難しさは、企業生存率にも大きな影響を与える要因となっています。
特に、中小企業やスタートアップにとって、大企業との人材獲得競争は厳しいものがあります。人手不足は残った従業員の負担増加を招き、サービス品質の低下や機会損失にもつながりかねません。
また、熟練技術者の高齢化と若手への技術伝承の問題も、多くの製造業や伝統産業で課題となっています。技術やノウハウが適切に継承されなければ、企業の競争力は徐々に失われていきます。
人手不足に対応するためには、採用戦略の見直しと働き方改革の推進が重要です。給与水準の適正化はもちろん、柔軟な勤務体制の導入や社内コミュニケーションの活性化など、従業員満足度を高める取り組みが求められます。
さらに、業務プロセスの見直しや、自動化・省力化の推進も有効な対策です。AI・IoTなどのテクノロジーを活用し、少ない人員でも効率的に事業を運営できる体制づくりを進めることが大切です。
自然災害などの予期せぬ外的要因
地震や台風、洪水などの自然災害は、企業の存続を脅かす突発的な外的要因です。日本は、地理的特性から自然災害リスクが高く、万全の備えが必要です。
自然災害は、事業所や設備の物理的な損害だけでなく、サプライチェーンの寸断による操業停止や、顧客の被災による需要減少など、間接的な影響も大きいものです。2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震では、直接被害を受けていない企業も部品供給の停止などで生産活動に支障をきたしました。
また近年では、パンデミックやサイバー攻撃、国際情勢の急変など、従来想定されていなかったリスクも増加しています。2020年の新型コロナウイルス感染症拡大は、多くの企業の経営基盤を揺るがす事態となりました。
こうした予期せぬ外的要因に対しては、事業継続計画(BCP)の策定と定期的な見直しが重要です。代替拠点の確保、重要データのバックアップ、サプライヤーの分散化など、リスク分散の観点から事業体制を再検討することが求められます。
また、適切な保険加入や緊急時の資金調達手段の確保など、財務面での備えも欠かせません。リスクマネジメントを経営戦略の一環として位置づけ、継続的に取り組むことが、企業の生存率向上につながります。
企業生存率に影響を与える長期的要因
企業の長期的な存続には、短期的な要因とは異なる様々な課題があります。ここでは、長期にわたって企業生存率に影響を与える要因について解説します。
後継者の不在
中小企業やファミリービジネスにおいて、後継者不在は、企業存続を脅かす最も大きな問題の一つです。中小企業庁の調査によると、日本の中小企業経営者の平均年齢は年々上昇し、多くの企業が事業承継の課題に直面しています。
後継者問題が生じる背景には、子どもが親の事業を継ぎたがらない傾向や、経営者自身が事業承継の準備を先送りにしてしまう心理があります。特に技術やノウハウ、取引関係などが経営者個人に依存している場合、スムーズな承継はより困難になります。
計画的な事業承継対策の早期着手が極めて重要です。後継者の選定と育成には、通常5〜10年程度の時間が必要とされており、経営者が60歳を超える前から準備を始めることが望ましいとされています。
また、親族内承継だけでなく、従業員承継やM&Aなど、様々な選択肢を視野に入れることも大切です。近年では、後継者不在を理由に黒字でも廃業する企業が増加しており、社会的な損失も大きな問題となっています。
市場の縮小
市場の縮小や構造変化は、企業の長期的な存続に大きな影響を与えます。少子高齢化による人口減少、消費者嗜好の変化、テクノロジーの進化などにより、かつては盛況だった市場が急速に縮小するケースは少なくありません。
例えば、フィルムカメラやVHSビデオデッキ、ポケットベルなど、デジタル技術の進化によって市場が消滅した製品は数多くあります。こうした変化に対応できなかった企業は、長年の実績があっても存続が難しくなります。
また、人口動態の変化も市場に大きな影響を与えます。日本の総人口は、2008年をピークに減少に転じており、多くの消費財市場は縮小傾向にあります。特に、地方の人口減少は著しく、地域に根ざした事業にとって大きな課題となっています。
こうした市場環境の変化に対応するためには、常に市場動向を注視し事業モデルを柔軟に変革する姿勢が不可欠です。自社の強みを活かした新市場開拓や、海外展開、異業種への参入なども視野に入れた戦略的な経営判断が求められます。
経営者のスキルや判断力の不足
企業の生存率に大きな影響を与える要因として、経営者自身のスキルや判断力も重要です。特に、創業者が強いリーダーシップを持つ企業では、その後の世代交代によって経営の質が低下するリスクがあります。
経営者に求められるスキルは、時代とともに変化しています。かつては、業界知識や人脈が重視されましたが、現在ではデジタル技術の理解や多様性への対応、グローバルな視点など、より幅広い能力が必要とされています。
また、環境変化のスピードが加速する中、経営判断の遅れが企業存続に致命的な影響を与えるケースも増えています。「今までうまくいっていたから」という過去の成功体験に固執し、変革を躊躇する「成功の罠」に陥る経営者も少なくありません。
経営者自身の継続的な学びと成長が、企業存続の鍵となります。業界団体や経営者コミュニティへの参加、外部専門家の活用、経営塾や大学院などでの学習など、自己研鑽の機会を積極的に設けることが重要です。
また、一人で全てを判断しようとせず、多様な視点を持つ経営チームを構築することも有効です。取締役会や経営会議の活性化、社外役員の登用なども検討すべきでしょう。
企業の「生存率」を高める、確実な一手
短期・長期の様々なリスクに対し、経営者が今すぐ打てる最も有効な対策は「資金調達力」の確保です。銀行の枠が埋まっていても、赤字決算でもご相談ください。法人経営者様の「今」を支える、無担保・無保証のビジネスローンをご用意しています。
最短即日・無担保ビジネスローンに申し込む企業生存率を高めるための資金確保の戦略
企業の存続において、資金確保は最も重要な要素の一つです。ここでは、持続可能な企業経営のための資金確保戦略について詳しく見ていきましょう。
安定したキャッシュフローを確保する方法
企業が長期的に存続するためには、安定したキャッシュフローの確保が不可欠です。売上の増加だけでなく、資金の流れを健全に保つことが重要です。
まず取り組むべきは、売掛金回収の効率化です。請求書発行の迅速化、支払い条件の見直し、早期支払いへのインセンティブ導入などが有効です。特に、大口顧客の支払いサイクルが自社のキャッシュフローに大きく影響するため、取引条件の交渉は慎重に行いましょう。
次に、在庫管理の最適化も重要です。過剰在庫は、資金を滞留させるだけでなく、保管コストや陳腐化リスクも高めます。需要予測の精度向上や、ジャストインタイム方式の導入など、在庫削減に向けた取り組みを検討しましょう。
サブスクリプションモデルの導入も、安定したキャッシュフロー確保に効果的です。従来の一時払いモデルから定期課金制に移行することで、収益の予測可能性が高まり、長期的な事業計画が立てやすくなります。
また、資金繰り表の作成と定期的な見直しも欠かせません。最低でも3か月先までの入出金を週単位で予測し、資金ショートのリスクを事前に把握することが大切です。資金繰りに余裕がある時期に設備投資や返済を集中させるなど、戦略的な資金計画を立てましょう。詳しくは「営業キャッシュフローを改善する具体的な方法」の記事も参考にしてください。
計画的な資金調達による事業継続力の強化
企業が成長し続けるためには、タイミングを見極めた計画的な資金調達が重要です。資金が必要になってから慌てて調達先を探すのではなく、事前に複数の調達手段を確保しておくことが賢明です。
資金調達の基本は、自己資金と借入金のバランスです。自己資本比率が低すぎると財務安全性が損なわれ、高すぎると資本効率が悪化します。業界の特性や成長ステージに応じた、適切な資本構成を検討しましょう。
借入においては、メインバンクとの良好な関係構築が重要ですが、複数の金融機関と取引関係を持つことで、リスク分散になります。また、短期借入と長期借入のバランスも考慮し、返済負担が特定の時期に集中しないよう注意が必要です。
成長資金の調達には、銀行融資以外にも様々な選択肢(例:独自審査のビジネスローン)があります。ベンチャーキャピタルからの出資、クラウドファンディング、公的補助金・助成金の活用、事業承継・M&A対策のための資本性劣後ローンなど、事業の特性や成長ステージに合わせた最適な手法を選ぶことが大切です。
さらに、緊急時に備えた資金調達手段の確保も重要です。コミットメントラインの設定や、ファクタリングなどの債権流動化手法についても、事前に検討しておくと安心です。
コスト削減と効率化による利益率の向上
企業の存続には、収益性の向上が不可欠です。特に、変動費と固定費の両面からコスト構造を見直し、効率化を図ることが重要です。
まず着手すべきは、変動費の削減です。仕入先の見直しや発注ロットの最適化、材料のグレードダウンなど、品質を維持しながらコストを下げる方法を検討しましょう。また、外注していた業務の内製化や、逆に社内業務のアウトソーシングなど、コスト効率の良い業務分担を模索することも有効です。
固定費の削減も重要です。オフィススペースの縮小や賃料交渉、リモートワークの活用による固定費削減など、ビジネスモデルに合わせた見直しを行いましょう。また、保険や通信費、各種サブスクリプションサービスなど、定期的に発生する経費の見直しも効果的です。
業務プロセスの見直しによる効率化も、利益率向上に大きく貢献します。IT化・自動化による人的コスト削減、ペーパーレス化による消耗品費削減、業務の標準化によるミス防止など、様々な角度からの改善が可能です。
ただし、コスト削減は、短期的な利益向上につながりますが、過度な削減は、品質低下や従業員モチベーションの低下を招く恐れがあります。特に、研究開発費や人材育成費などの戦略的投資は、長期的な企業価値向上のために必要な支出であることを忘れてはなりません。
まとめ
企業生存率を高めるためには、短期的な視点と長期的な視点の両方から対策を講じることが重要です。資金繰りの改善や安定したキャッシュフローの確保は、企業存続の基盤となり、計画的な事業承継や時代のニーズに合わせた製品・サービスの改善は、長期的な成長を支えます。
特に重要なのは、問題が表面化する前に先手を打つ姿勢です。経営環境の変化を敏感に察知し、柔軟に対応できる組織体制を整えることが、企業の生存率を高める鍵となります。まずは、自社の現状を客観的に分析し、優先度の高い課題から計画的に取り組んでいきましょう。
最短即日・無担保無保証融資
HTファイナンスの「ビジネスローン」
企業生存率を高める鍵は、安定した資金計画です。しかし、急な資金需要や成長投資の際、審査に時間がかかってはビジネスチャンスを逃します。
HTファイナンスは、東大卒・元三菱銀行出身の統括責任者が、銀行実務と30年の経験に基づき、法人様の資金調達を強力に支援します。無担保・無保証、柔軟な審査で、事業の成長を迅速にサポートします。