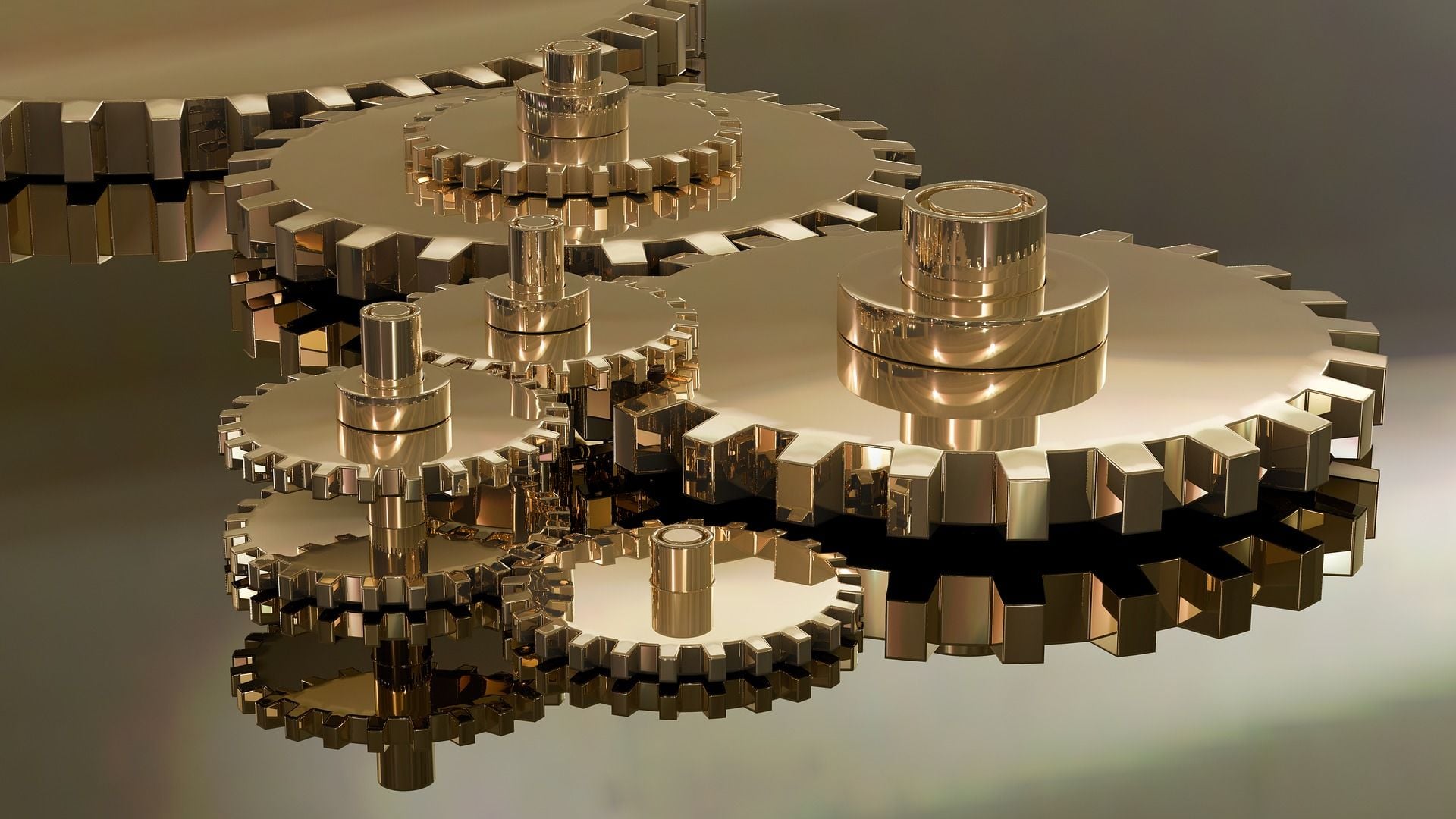公開日:2025.10.17
更新日:2025.10.17
補助金の不正な受給は詐欺罪に該当!逮捕されてしまう?申請時の注意点も解説

ニュースで、補助金の不正受給による逮捕について目にすることがあるかもしれません。補助金は、事業の推進に強力な助けとなる一方で、不適切な申請や使用は、重大な法的責任を問われるリスクがあります。また、ニュースを目にして「申請書の記載ミスが詐欺罪になるのでは」「知らずに不正を行ってしまったらどうなるのか」と不安に思っている方も少なくないでしょう。
本記事では、補助金の不正受給がなぜ詐欺罪に該当するのか、実際に逮捕された場合の流れ、経営者が取るべき適切な対応について詳しく解説します。また、申請時の具体的な注意点や、万が一不正が発覚した際の対処法についても紹介しています。
補助金の不正受給による詐欺罪
補助金の不正受給とは、虚偽の申請や不正な手段によって、国や地方自治体などから補助金を受給することを指します。これは、単なる手続きミスとは異なり、刑法上の犯罪行為として扱われます。
詐欺罪に該当する理由と量刑
補助金の不正受給は、刑法246条に定められた詐欺罪に該当します。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」に適用され、最長で懲役10年の刑罰が科される可能性があります。補助金申請時に虚偽の情報を提供することは、行政機関を欺く行為であり、それによって本来受け取る権利のない公金を受給することになるため、詐欺罪の構成要件を満たすのです。
実際の量刑は、不正受給の金額や手法、社会的影響などを考慮して決定されますが、悪質なケースでは、実刑判決が下されることもあります。
補助金適正化法による罰則
詐欺罪に加えて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)による罰則も適用される場合があります。
この法律では、補助金の不正受給に対して、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。補助金適正化法は、補助金の交付、使用、返還などに関するルールを定めた法律で、不正行為に対する行政処分の根拠となるものです。特に第29条では、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者への罰則が明記されています。
詐欺罪と補助金適正化法違反の両方で起訴されるケースもあり、法的リスクは決して軽視できません。
関係者の連帯責任
補助金の不正受給においては、直接申請を行った経営者だけでなく、不正に関与した役員や従業員、さらには外部の協力者(会計士、コンサルタントなど)も共犯として刑事責任を問われる可能性があります。
特に、組織ぐるみで計画的に不正を行った場合は、関与した全ての人物が捜査対象となり得ます。虚偽の書類作成を指示した経営者、それを実行した従業員、虚偽の証明書を発行した外部の専門家など、不正への関与度に応じた責任が問われることになります。
また、法人としての責任も問われ、両罰規定により法人に対する罰金刑が科されることもあります。
補助金不正受給で逮捕される具体的な事例
補助金の不正受給は、様々な手法で行われていますが、ここでは、実際に逮捕や摘発につながった典型的なケースを紹介します。
虚偽の申請書類の提出
補助金の不正受給で最も多いのが、申請書類に虚偽の情報を記載するケースです。例えば、実際には保有していない設備を所有していると偽ったり、事業規模や実績を水増ししたりする行為が該当します。
特に悪質なのは、事業計画書に実現不可能な内容を記載したり、全く存在しない事業について申請したりするケースです。こうした行為は、申請段階からの計画的な詐欺と見なされ、厳しく処罰される傾向にあります。
経費の水増しや架空取引
補助金受給後、実際の支出を水増ししたり、架空の取引を創出して不正に資金を流用したりするケースは少なくありません。具体的には、実際よりも高額な見積書や請求書を作成し、差額を着服する手法があります。例えば、500万円の設備導入に対して1,000万円の経費を申告し、差額の500万円を不正に得るという方法です。
また、実際には取引のない関連会社や協力会社との間で架空の契約を結び、補助金を還流させる手法も存在します。この場合、書類上では適正な支出に見えるよう偽装されますが、実際には事業に使われていないことがほとんどです。
こうした不正は、事後的な監査や取引先への調査で発覚することが多く、証拠が残りやすいため、発覚すると逮捕につながりやすい傾向があります。
事業計画の無断変更
補助金申請時に提出した事業計画と異なる用途に資金を使用することも、不正受給に該当します。補助金は、特定の目的のために交付されるものであり、その目的以外への流用は認められていません。
例えば、設備投資のための補助金を運転資金に回したり、新規雇用のための補助金で既存社員の給与に充てたりするような行為です。こうした計画変更が必要な場合は、必ず交付機関への事前相談と承認が必要です。
実際の事例では、新商品開発のための補助金を申請しながら、実際には全く異なる事業や借入金の返済に充てていたことで、逮捕された経営者もいます。このようなケースは、意図的な目的外使用として厳しく罰せられます。
雇用関連の虚偽申告
雇用創出や人材育成を目的とした補助金・助成金において、実態と異なる雇用状況を報告するケースも多く見られます。具体的には、実際には雇用していない従業員を雇用したと偽る架空雇用があります。書類上だけの雇用を作り出し、実際には誰も働いていないにもかかわらず、補助金を受給するケースです。
また、雇用条件や労働時間、賃金について虚偽の報告を行うケースもあります。例えば、実際にはパートタイムで働いている従業員を、フルタイム雇用と偽って報告するなどです。
さらに、研修や教育訓練の実施について、虚偽の報告をすることもあります。実際には実施していない研修プログラムを行ったと偽り、報告する行為がこれに該当します。
こうした雇用関連の不正は、従業員への聞き取り調査や給与明細、勤怠記録などの調査によって発覚することが多く、従業員からの内部告発がきっかけとなるケースも少なくありません。
補助金の不正受給が詐欺罪に認定されてからの流れ
補助金の不正受給が発覚した場合、どのような法的手続きが進められるのかについて、逮捕から裁判に至るまでの一般的な流れを解説します。
不正発覚のきっかけ
補助金の不正受給が発覚するきっかけは、いくつか考えられます。まず、行政機関による定期的な監査や検査が挙げられます。補助金を交付する行政機関は、交付後も事業の進捗状況や資金使途について監査を行い、特に大型の補助金の場合、監査が厳格に実施される傾向があります。
また、不正に気づいた従業員や取引先からの内部告発や通報が、捜査のきっかけとなることもあります。公益通報者保護制度の整備により、内部告発のハードルが下がっていることも影響しています。
さらに、脱税や横領などの他の経済犯罪の捜査中に、関連して補助金の不正受給が発覚することもあります。報告内容に矛盾が生じた場合、特に複数の補助金を受けている場合には、異なる機関に提出した報告書の内容に不自然な点があると、疑われやすくなります。
捜査から逮捕まで
不正の疑いが生じると、捜査は次のように進行します。
まず、行政機関による内部調査が行われ、不正の疑いが強まると、警察や検察に情報が提供されます。警察はその後、任意の事情聴取や関係者への聞き取り調査を開始し、必要に応じて、令状に基づく捜索や差押えが行われることもあります。
捜査の過程で十分な証拠が集まり、容疑者が証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合、逮捕状が請求されます。逮捕は、主に早朝に自宅や会社で行われ、容疑者の身柄が拘束されることになります。
逮捕後、最大72時間の警察による取り調べが行われ、その後、検察に送致されます。検察官は、最大20日間(延長を含む)の勾留請求を行うことができ、この期間に起訴するかどうかが判断されます。
勾留と起訴の判断
勾留は、裁判官の判断により決定され、通常は10日間、延長して最大20日間行われます。この期間中、被疑者は拘置所に留置され、弁護士以外との接見が制限されます。検察官による取り調べが連日行われ、供述調書が作成されます。
勾留期間中に集められた証拠に基づいて、検察官は起訴するかどうかを判断します。起訴することが決まった場合、詐欺罪や補助金適正化法違反などの罪名で起訴状が作成され、その後、刑事裁判が始まります。
証拠不十分や情状酌量の余地があると判断された場合、不起訴処分となることもあります。また、被害弁償や反省の態度などを考慮して、起訴猶予処分となるケースもあります。
ただし、補助金の不正受給は、公金を詐取する行為であり、社会的影響が大きい犯罪として厳しく対処される傾向にあります。特に計画的で悪質なケースや、高額な補助金を不正に受け取った場合、起訴される可能性が高くなります。
裁判の進行
起訴されると、刑事裁判が始まります。第一回公判では、起訴状の朗読が行われ、被告人は罪状認否(起訴事実を認めるか否か)を行います。その後、検察側の冒頭陳述、証拠調べ、被告人質問、弁護側の弁論、検察の求刑、最終弁論という流れで裁判が進みます。
補助金の不正受給の裁判では、不正受給の手法や金額、計画性、社会的影響、被害回復の状況などが量刑に影響します。特に悪質なケースでは、実刑判決が下されることもあります。
一般的な判決例としては、少額の場合は執行猶予付きの判決が多いですが、数千万円以上の大規模な詐欺や組織的な犯行の場合は、実刑判決となるケースが増えます。また、不正受給した補助金の返還も命じられます。
判決に不服がある場合は、控訴・上告といった上級審への不服申立ても可能ですが、事実認定については、第一審が重視される傾向にあります。
補助金の申請時の注意点
不正受給のリスクを避けるためには、申請時から適切な対応が求められます。ここでは、特に知っておくべき重要なポイントを解説します。
正確な情報提供の徹底
補助金申請において最も重要なのは、すべての情報を正確に提供することです。虚偽の情報提供は、詐欺罪に直結するため、注意が必要です。
まず、会社の財務状況や事業実績については、必ず正確な数字を報告しましょう。数字を水増しすることは、絶対に避けるべきです。「少し良く見せよう」といった気持ちから誤った情報を提供することは、後々大きな問題に繋がります。
次に、事業計画は実現可能な内容に留め、過大な成果を約束しないようにすることが大切です。魅力的に見せるために、達成不可能な計画を提出することは、後のトラブルや問題の原因となります。
また、保有設備や技術力、人材についても正確に報告しましょう。特に、専門的な資格や特許などは確認が容易であり、虚偽の記載はすぐに発覚します。
申請書類は、自社で作成・確認することが理想的ですが、もし外部に依頼する場合でも、最終的な責任は経営者にあることを忘れないでください。提出前には必ず内容を確認し、誇張や不明点がないかをチェックすることが求められます。
計画変更時の適切な対応
事業環境の変化により、当初の計画通りに進められないことは珍しくありません。
計画変更が必要となった場合は、必ず補助金交付機関に事前に相談・報告しましょう。無断で計画を変更することは、不正と見なされる可能性があります。
変更内容と理由を明確に説明し、必要な変更申請手続きを行いましょう。多くの補助金制度では、計画変更の手続きが定められているため、それに従うことが重要です。
変更が認められない場合は、補助金の一部または全部を返還することになるかもしれません。無理に当初計画を偽装することは、さらに深刻な問題を引き起こす可能性があります。計画変更に関するやり取りは必ず記録に残し、担当者名や日時、内容をメモしておくことが重要です。後々のトラブル防止に役立ちます。
適切な経費管理と証憑の保管
補助金の使途に関する透明性を確保することも非常に重要です。
補助金対象の経費は、通常の経費と区別して管理し、専用の帳簿を作成することをお勧めします。これにより、監査時に明確に説明できるようになります。
すべての支出について、領収書や請求書、発注書などの証憑書類を適切に保管しましょう。電子データだけでなく、紙の原本も保管することが望ましいものです。
取引先との契約書や仕様書なども保管し、取引の実態を証明できるようにしておきましょう。特に、関連会社との取引は厳しくチェックされる傾向があるため、取引の必要性や価格の適正さを説明できるようにしておくことが重要です。
補助金の報告期限が終了した後も、通常は5〜7年程度は証憑書類を保管することが求められます。監査はいつでも行われる可能性があることを念頭に置いておきましょう。
社内チェック体制の構築
補助金の申請や報告は、担当者一人に任せるのではなく、複数の目でチェックする体制を作りましょう。経理担当者と事業担当者の両方が内容を確認することで、ミスや不適切な処理を防ぐことができます。
補助金に関するルールやガイドラインを社内で共有し、関係者全員が理解しているか確認しましょう。特に経費の使途や報告義務について、明確なルールを設けることが重要です。
定期的な内部監査を実施し、補助金の使用状況や証憑書類の管理状況をチェックしましょう。問題点が見つかった場合は、早急に是正措置を講じることが大切です。
不明点があれば、自己判断せずに、補助金交付機関に確認する習慣をつけましょう。「知らなかった」は言い訳にならないため、疑問点はすぐに解消することが重要です。
不正発覚時の対応
補助金の不正受給に関する問題が発生した場合、初期対応が非常に重要になります。適切に対処することで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。
問題発覚時の初期対応
不正や不適切な処理が社内で発覚した場合、適切な対応を検討することが重要です。
はじめに、問題の範囲と程度を正確に把握することが求められます。どのような不正があったのか、誰が関与していたのか、金額はいくらか、期間はどれくらいかなど、詳細な事実関係を整理しましょう。
次に、関連する資料や証拠を確保し、むやみに廃棄したり改ざんしたりしないように注意します。証拠隠滅は、状況を悪化させるだけでなく、それ自体が犯罪に該当する可能性があります。
問題に気づいた時点で、すぐに専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。初期段階での適切な対応が、その後の展開に大きく影響します。
社内調査を行う場合は、調査の公平性と客観性を確保するために、問題に関与していない者や外部の専門家に依頼することも検討しましょう。
弁護士への相談
補助金の不正受給が問題となった際は、弁護士への相談が非常に重要です。問題の兆候や疑いが生じた段階で弁護士に相談することで、初期対応の方針について専門的なアドバイスを受けられます。
行政機関から問い合わせや調査の連絡があった場合、調査が始まる前に弁護士に相談し、対応方針を決めておくことが重要です。
捜索や任意の事情聴取の要請があった場合は、直ちに弁護士に連絡し、立ち会いや対応についてのアドバイスを受けましょう。
弁護士に相談する際は、すべての事実を隠さず伝えることが重要です。弁護士には守秘義務があり、正確な情報に基づいた適切なアドバイスを受けるためにも、包み隠さず状況を説明しましょう。
自主申告
不正が発覚した場合、自主的に申告することで、情状酌量の余地が生まれる可能性があります。
問題を発見したら、弁護士と相談の上、補助金交付機関に自主的に申告することを検討しましょう。自主返還の意思表示は、刑事処分を軽減する要素となりえます。
不正受給した補助金は、速やかに返還する準備をしましょう。場合によっては、加算金や延滞金も含めた返還が求められることがありますが、これに応じる姿勢を示すことが重要です。
自主申告の際は、不正の原因や再発防止策についても説明できるよう、準備しておくことが望ましいものです。組織としての改善姿勢を示すことで、行政処分や刑事処分の軽減につながる可能性があります。
ただし、自主申告すれば、必ず処分が軽くなるわけではないことに注意が必要です。特に、悪質なケースや高額な不正受給の場合は、自主申告しても厳しい処分を受ける可能性があります。
刑事手続きへの対応
逮捕や任意同行の要請があった場合は、黙秘権を行使し、弁護士と相談するまで供述を控えることもできます。初期の供述が後の裁判に大きく影響するため、慎重な対応が必要です。
勾留されている間も、弁護士との接見は権利として認められています。弁護方針や今後の対応について、十分に相談しましょう。
起訴された場合は、弁護士と協力して、証拠の収集や情状証人の準備など、裁判に向けた対応を進めます。反省の態度や被害回復の努力は、量刑に影響する重要な要素となります。
家族や従業員への影響も考慮し、会社の存続や雇用の維持についても計画を立てておくことが重要です。経営者が不在になった場合の対応策も、事前に検討しておきましょう。
まとめ
補助金の不正受給は、単なる行政上の手続きミスではなく、詐欺罪に該当する重大な犯罪行為です。最大で懲役10年の刑罰や、補助金適正化法による罰則があり、社会的信用の喪失、補助金の返還義務、入札参加資格の停止など、企業存続にも関わる深刻な影響をもたらします。
補助金を適正に活用するためには、申請時の正確な情報提供、計画変更時の事前相談、適切な経費管理と証憑の保管、社内チェック体制の構築が不可欠です。万が一問題が発生した場合は、早期に弁護士に相談し、状況に応じた適切な対応を取ることが重要です。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
事業を拡大したり新たな取り組みを始めたりする際、補助金は魅力的な選択肢ですが、審査期間や受給までの時間、使途の制限などにより、急な資金需要に対応できないこともあります。
緊急な資金ニーズに向いている方法の一つに、ビジネスローンがあります。中でもHTファイナンスのビジネスローンは、無担保無保証で利用でき、柔軟な審査を特徴としています。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
補助金不正受給などは、事業継続すら危うくなるような危険性の高いものですから、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。