公開日:2025.10.08
更新日:2025.10.08
税金の滞納の時効は何年?延滞金や減免・猶予についても紹介
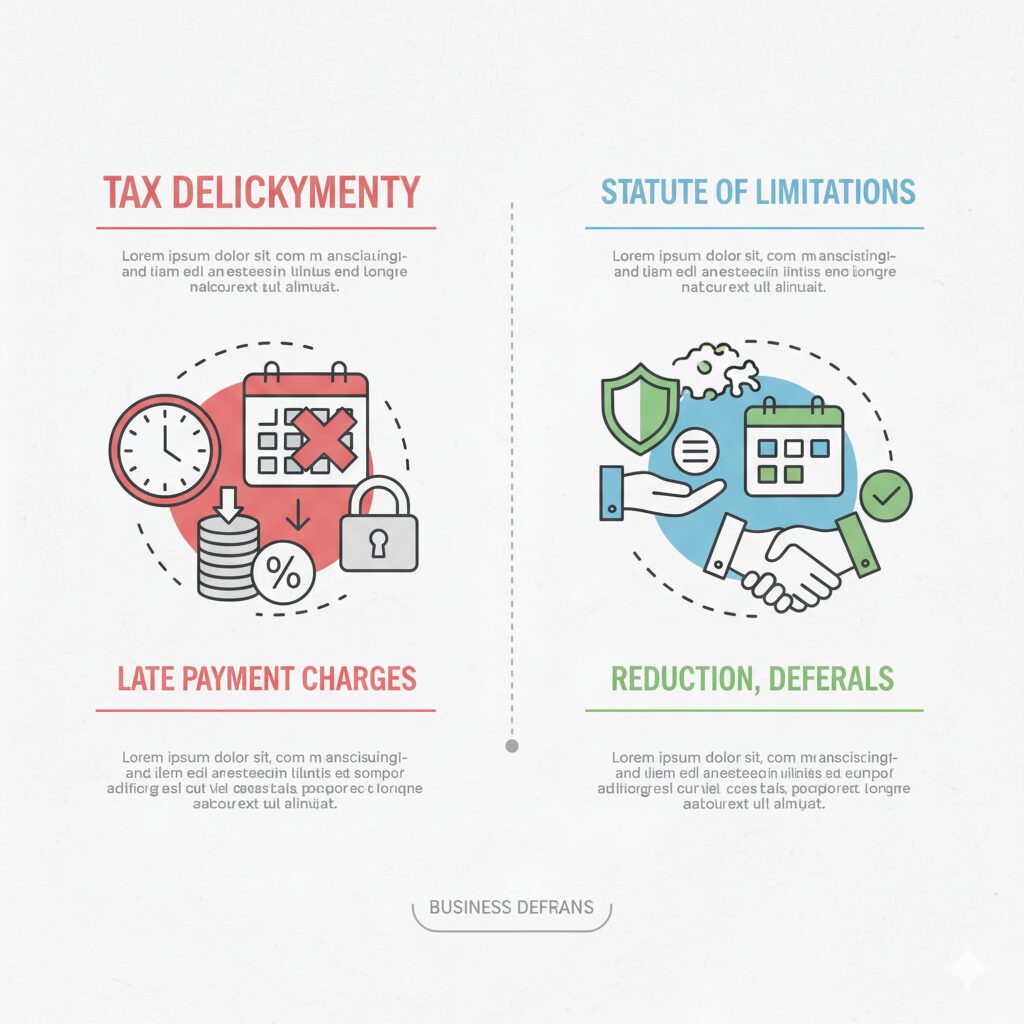
事業を運営していると、売上の低下や予期しない支出により資金繰りが悪化し、税金の納付が難しくなることがあります。このような状況では、税金の滞納をする可能性も出てくるでしょう。税金の滞納に関しても、時効という概念があります。ただし、税金滞納の時効は、単に年数が経過すれば成立するものではありません。
本記事では、税金滞納の時効期間や延滞金の計算方法、滞納した場合に税務署や自治体が取る措置について詳しく解説します。また、滞納を解消するための具体的な対処法や、減免・猶予の申請方法についても紹介します。
税金滞納の時効とは
税金滞納にも、他の債権と同様に時効が存在します。ただし、一般的な債権とは異なる特徴があります。
基本的な税金滞納の時効期間
税金の滞納に関する時効は、原則として5年と定められています。これは、国税通則法第72条に基づく規定で、税務署が徴収権を行使できる期間を指します。
この5年間というのは、納税の義務が確定した日の翌日から起算されます。納税義務が確定する日は税金の種類によって異なりますが、多くの場合は、申告期限や納付期限の日となります。
ただし、税金の種類によって時効期間が異なる点に注意が必要です。例えば、所得税の期限内申告の場合は3年、申告書の不提出や不正行為があった場合は7年と定められています。
時効が中断・リセットされる場合
税金滞納の時効は、税務署や自治体による特定の行為によって中断(リセット)されます。具体的には、次のようなケースが該当します。
まず、督促状の発送により時効は中断します。督促状は通常、納期限から50日以内に発送されるため、ほとんどの滞納ケースで時効が一度はリセットされます。
また、差押えや交付要求などの滞納処分が行われた場合も時効は中断します。これらの処分は、督促状発送後10日を経過した日以降に行われることが一般的です。
分割納付の承認を受けた場合も時効がリセットされます。分割納付の合意は、納税者側から申し出る場合が多いですが、これによって、時効期間は新たに5年からカウントし直されることになります。
時効の完成が難しい理由
実際には、税金滞納の時効が完成することは非常に稀です。その理由は、いくつか存在します。
税務署や自治体は、滞納発生後すぐに督促状を発送するのが通常の手続きです。この督促状の発送だけで時効はリセットされるため、何も対応せずに放置していても、時効の利益を得ることは難しくなります。
また、税務署は滞納者の財産調査を積極的に行い、財産が発見されれば差押え等の滞納処分を実施します。これらの処分も、時効をリセットする効果があります。
さらに、納税者が分割納付を申し出て承認された場合も、時効はリセットされます。資金繰りが苦しい状況で分割納付を選択するケースは多いですが、これによって時効の完成は遠のくことになります。
時効を狙った滞納は、現実的な選択肢にならないことを理解しておく必要があります。税務当局は徴収のための様々な手段を持っており、時効の完成を阻止するための対策を講じています。
税金滞納による延滞金の発生
税金を期限内に納付できない場合、単に未納分を後日支払えばよいというわけではなく、延滞金という追加負担が発生します。
延滞金の計算方法
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間に応じて計算されます。その利率は、2段階に分かれています。
納期限の翌日から2ヶ月以内の期間については、比較的低い利率が適用されます。2023年の場合、この期間の延滞金の利率は、年7.3%(日割り計算)となっています。
納期限から2ヶ月を超えた期間については、より高い利率が適用されます。2023年の場合、この期間の延滞金の利率は、年14.6%(日割り計算)となっています。
例えば、100万円の税金を1年間滞納した場合、最初の2ヶ月で約1.2万円、残りの10ヶ月で約12.2万円、合計約13.4万円の延滞金が発生することになります。
延滞金は日々増加し続けるため、滞納期間が長くなるほど負担は大きくなります。特に、納期限から2ヶ月を超えると高い利率が適用されるため、滞納額が急速に膨らむことになります。
※延滞金の利率は、国税庁のウェブサイトで毎年更新されています。より正確な利率を確認したい場合は、**国税庁の「延滞税の計算方法」ページ**をご参照ください。
延滞金が免除・減額される場合
一定の条件を満たす場合、延滞金が免除または減額されることがあります。特に、納付が困難になった理由や状況に応じて、特別な措置が取られることがあります。
例えば、災害などの特別な事情により納付が困難になった場合、申請により延滞金が免除されることがあります。これは、国税通則法第63条に基づく措置です。
また、納税者の責めに帰すことのできない理由で滞納が発生した場合、延滞金の免除が認められることがあります。例えば、税務署から誤った指導を受けた結果、滞納が生じた場合が該当します。
さらに、徴収猶予や換価の猶予が認められた場合、その猶予期間中の延滞金が軽減されることがあります。この場合、通常の延滞金利率ではなく、低い特例基準割合が適用されます。
延滞金の免除を受けるには、申請が必要です。自動的に免除されるわけではないため、該当する可能性がある場合は、税務署や自治体に相談することをお勧めします。
延滞金と延滞税の違い
延滞金と延滞税は似た用語ですが、厳密には異なるものです。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
延滞金は、主に地方税(住民税や固定資産税など)の滞納に対して課される追加負担です。地方税法に基づいて、自治体が徴収します。
一方、延滞税は、国税(所得税や法人税など)の滞納に対して課される追加負担です。国税通則法に基づいて、国が徴収します。
計算方法や利率は基本的に同じですが、適用される税金の種類や徴収する機関が異なります。ただし、一般的な会話では両者を明確に区別せず、「延滞金」と総称することも多いでしょう。
どちらも滞納によって発生する追加負担であるという点は共通しています。いずれにせよ、税金は期限内に納付することで、余分な負担を避けることができます。
税金の滞納をしたときの税務署・自治体の対応
税金を滞納すると、税務署や自治体は様々な手段を講じて徴収を図ります。どのような流れで対応が進むのか把握するようにしましょう。
督促状の送付と差押えの予告
税金の納期限を過ぎると、まず督促状が送付されます。督促状は通常、納期限から50日以内に発送されます。これは単なる支払いの催促ではなく、法的な意味を持つ重要な文書です。
督促状が発送されると、時効がリセットされるだけでなく、滞納処分(差押えなど)の前提条件が整うことになります。督促状の発送によって、税務署や自治体は、法的に滞納処分を行う権限を得ます。
督促状に応じない場合、次のステップとして差押え予告通知が送られてきます。これは、実際の差押え手続きの前に、最後の納付機会を与えるものです。
督促状や差押え予告は無視せず対応することが重要です。これらの通知を受け取った時点で、税務署や自治体に連絡し、納付の相談をすることで、より厳しい措置を回避できる可能性があります。
財産調査と差押えの実行
督促状に応じない場合、税務署や自治体は滞納者の財産調査を行います。財産調査は、非常に広範囲にわたって実施されます。
銀行口座や不動産、自動車などの資産だけでなく、給与や売掛金、生命保険の解約返戻金なども調査対象となります。最近では、クレジットカードやネット銀行の口座も調査されるケースが増えています。
財産が発見されると、差押え手続きが実行されます。差押えの対象は、現金や預金だけでなく、不動産、自動車、給与、売掛金、生命保険の解約返戻金など多岐にわたります。
差押えは事前通知なく実行されることもある点に注意が必要です。特に、悪質な滞納者と判断された場合や、財産隠しの恐れがあると判断された場合は、突然の差押えが行われることがあります。
滞納したという情報の信用への影響
税金の滞納は、単に延滞金や差押えといった直接的な不利益だけでなく、信用面でも大きな影響を与えます。
金融機関は融資審査の際に、税金の納付状況を確認することがあります。納税証明書の提出を求められるケースも多く、滞納があると融資が受けられなかったり、条件が悪くなったりする可能性があります。
また、公共事業の入札参加資格審査では、税金の納付状況が重要な審査項目となっています。滞納があると入札参加資格が得られず、ビジネスチャンスを失うことになります。
さらに、不動産や高額資産に差押えの登記がされると、それは公的な記録として残ります。これにより、取引先や関係者に滞納の事実が知られる可能性があります。
税金滞納は企業の社会的信用を大きく損なうことを認識しておく必要があります。一時的な資金繰りの改善のために滞納を選択することは、長期的に見ると大きなデメリットになることが多いものです。
税金を滞納した時の対処法
税金の滞納が発生した、あるいは発生しそうな場合、適切な対処をすることで状況を改善できる可能性があります。具体的な対応策を見ていきましょう。
早期の相談と分割納付の申請
税金の納付が困難になった場合、まず取るべき行動は、税務署や自治体への相談です。滞納が長期化するほど状況は悪化するため、問題が発生した時点での早期対応が重要です。
相談の際には、現在の資金繰りの状況や今後の見通しなど、具体的な情報を準備しておくと話がスムーズに進みます。収支状況が分かる資料や、今後の売上見込みなどの資料があるとより良いでしょう。
多くの場合、分割納付の相談に応じてもらえます。分割納付とは、滞納税金を一定期間にわたって分割して支払う方法です。毎月の支払い額を減らすことで、資金繰りの負担を軽減できます。
自ら進んで相談することが問題解決の第一歩です。税務署や自治体も、納税者の誠意ある対応を評価する傾向があります。滞納者が自主的に連絡してきた場合は、より柔軟な対応をしてくれることが多いでしょう。
猶予制度の活用
税金の納付が困難な場合、法律で定められた猶予制度を利用できる可能性があります。主な猶予制度には、以下のようなものがあります。
換価の猶予は、税金を一時に納付することで、事業の継続や生活の維持が困難になる場合に適用される制度です。最大で1年間(特別な事情がある場合は最大2年間)の猶予が認められます。この間、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
徴収猶予は、災害や病気、事業の休廃業などによって一時的に納税が困難になった場合に適用される制度です。こちらも、最大で1年間(特別な事情がある場合は最大2年間)の猶予が認められます。
これらの猶予制度を利用するには、所定の申請書と必要書類を、税務署や自治体に提出する必要があります。申請が認められると、猶予期間中の延滞金が軽減されるメリットもあります。
猶予制度の適用には一定の条件を満たす必要がある点に注意が必要です。単に支払いたくないという理由では認められません。実際に納税が困難な状況にあることを、客観的に示す必要があります。
減免制度の申請
一部の税金については、特定の条件を満たす場合に減免制度が設けられています。税金の種類によって異なりますが、主な減免制度は、次のようなものです。
住民税については、災害による被害や失業、廃業、病気などにより収入が大幅に減少した場合に減免が認められることがあります。各自治体によって条件や減免率は異なりますので、居住地の自治体に確認する必要があります。
固定資産税は、災害により資産が損害を受けた場合や、生活保護を受けている場合などに減免制度があります。特に災害による減免は、比較的認められやすい傾向にあります。
国税(所得税や法人税など)については、一般的な減免制度はありませんが、災害等による特別な事情がある場合は、税務署に相談することで、何らかの救済措置が適用される可能性があります。
減免の申請は速やかに行うことが重要です。多くの減免制度には申請期限が設けられており、期限を過ぎると申請自体が受け付けられないことがあります。対象となる可能性がある場合は、早めに相談しましょう。
資金調達による滞納の解消
税金滞納を解消するための方法として、資金調達も選択肢の一つです。考えられる方法として、次のようなものがあります。
ファクタリングは、売掛金を買い取ってもらうことで即座に資金化する方法です。通常の融資と異なり、企業の信用力ではなく、売掛金自体の価値で判断されるため、財務状況が厳しい企業でも利用できる可能性があります。
ビジネスローンは、事業資金として利用できる融資商品です。銀行や信用金庫などの金融機関のほか、ノンバンクのビジネスローンも選択肢となります。ノンバンクは、審査基準が比較的緩やかで、スピーディーな融資が期待できます。
資産を保有している場合は、不動産担保ローンなども検討できます。担保があることで金利が低くなったり、より多額の融資を受けられたりするメリットがあります。
資金調達は返済計画を慎重に検討することが大切です。税金滞納を解消するために新たな借入を行っても、その返済が困難になれば、問題の先送りにしかなりません。収支計画を立てた上で、適切な資金調達方法を選びましょう。例えば、**「ファクタリングの仕組み」を理解したり、「担保なしで融資を受けるコツ」**を学んだりすることが、具体的な解決策に繋がります。
企業経営者が知っておくべき税金滞納のリスク
企業経営において、税金滞納は様々なリスクをもたらします。これらのリスクを正しく理解し、適切に対応することが重要です。
会社・事業の信用の低下
税金の滞納は、企業の信用に大きな影響を与えます。特に、ビジネスパートナーや金融機関との関係において深刻な問題となります。
取引先は、安定した経営を行っている企業との取引を望みます。税金滞納が明らかになると、支払能力や経営の安定性に疑問を持たれ、取引の継続が難しくなる可能性があります。特に公共事業では、納税証明書の提出が求められることが多く、滞納があると入札資格が得られない場合もあります。
金融機関からの融資も困難になります。多くの金融機関は、融資審査の際に納税状況を確認し、滞納があると融資の拒否や条件の悪化につながります。これにより、資金繰りがさらに悪化するという悪循環に陥ることもあります。
税金滞納は企業の存続そのものを脅かす可能性があります。短期的な資金繰りのためにやむを得ず滞納する場合でも、長期的な影響を十分に考慮する必要があります。
個人に責任が及ぶ場合がある
法人税の滞納は基本的には法人の責任ですが、特定の状況では役員個人にも責任が及ぶことがあります。
法人の滞納税金について、原則として役員個人に納税義務が及ぶことはありません。法人と個人は、別の法的主体として扱われるためです。
ただし、法人が滞納処分を受けても完全に徴収できない場合で、その滞納が役員の故意や重大な過失によるものと認められる場合、第二次納税義務者として、役員個人に納税を求められることがあります。これは、国税徴収法第39条に基づく措置です。
また、源泉所得税のように、預り金的性格を持つ税金の滞納については、より厳しい対応がとられます。特に悪質なケースでは、刑事罰の対象となることもあります。
役員としての責任を正しく認識することが重要です。会社の資金繰りが厳しい状況でも、預り金的性格を持つ税金の納付は、優先すべき事項です。
税務調査が厳しくなる
税金の滞納は、税務調査の可能性を高める要因となります。税務調査に関連する重要なポイントを理解しておきましょう。
税務署は、限られたリソースで効率的に調査を行うため、調査対象を選定する際にいくつかの基準を設けています。税金滞納がある企業は、調査対象として優先される傾向があります。
特に、継続的な滞納や高額の滞納がある場合、税務署はその背景に何らかの申告漏れや不正確な申告があるのではないかと疑念を持ちやすくなります。このため、より詳細な調査が行われる可能性が高まります。
税務調査が実施されると、通常の業務に加えて調査対応の負担が生じます。資料の準備や質問への回答など、経営者や経理担当者の時間と労力が大きく割かれることになります。
適正な申告と納税が税務調査リスクを低減する最も確実な方法です。仮に、資金繰りの都合で納税が難しい場合でも、申告自体は正確に行い、必要に応じて分割納付や猶予の申請を行うことが重要です。
まとめ
税金滞納の時効は、基本的に5年ですが、督促状の発送や差押えなどによって時効がリセットされるため、実際に時効が成立することは非常に稀です。滞納が続くと延滞金が発生し、最初の2ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%という高い利率で日々増加していきます。
税務署や自治体は、滞納者に対して督促状の送付、財産調査、差押えなどの措置を段階的に実施します。これらの対応は、企業の信用に大きな影響を与え、融資や取引にも支障をきたす可能性があります。税金の滞納に困ったら、早めに相談して分割納付や猶予・減免の申請を検討し、必要に応じて適切な資金調達方法を模索することが重要です。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
税金を滞納してしまいそうな場合、資金調達を行うことで手元の現金を増やすという対処も考えられます。そういった急な資金需要の対応に適しているのが、ビジネスローンサービスです。中でもHTファイナンスのビジネスローンは、無担保無保証で利用可能であり、独自基準のスピーディーな審査を特徴としています。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
まずは、お気軽にHTファイナンスにご相談ください。









