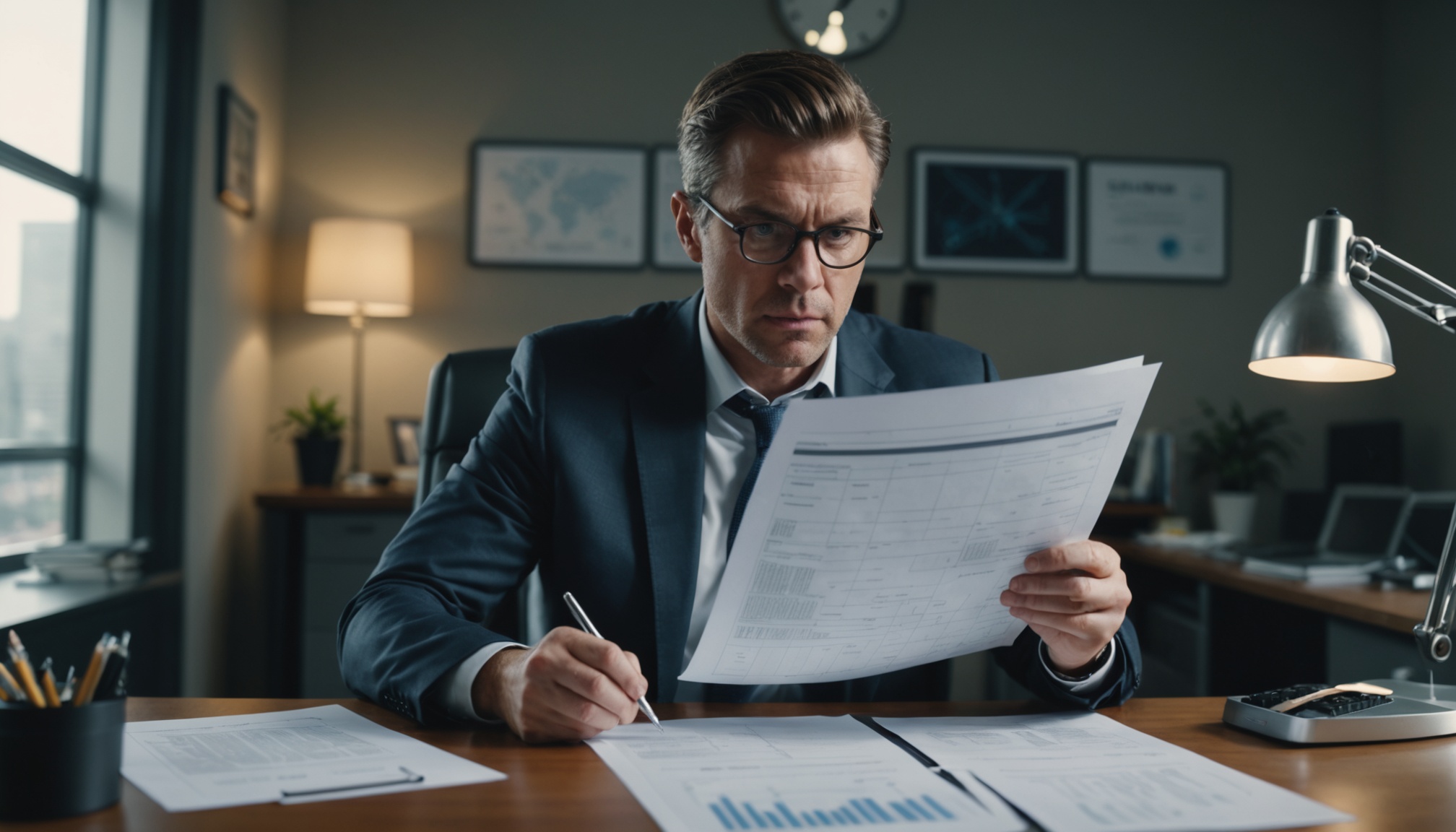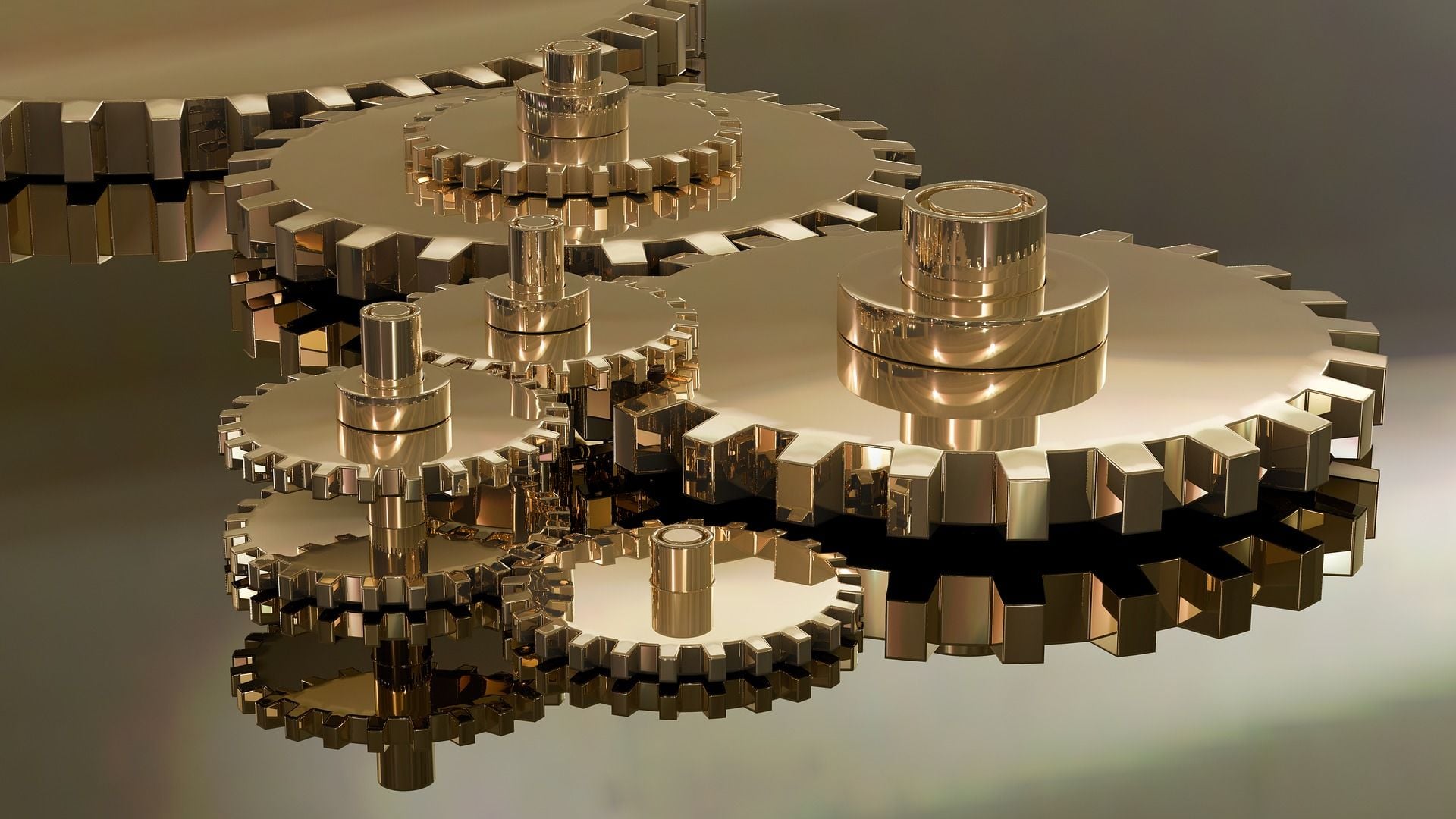公開日:2025.10.22
更新日:2025.10.22
中小企業倒産防止共済とは?加入の要件や流れ、掛け金、メリット・デメリットを紹介

取引先が突然倒産すると、企業にとっては大きな打撃になることがあります。特に長年の取引先の場合、売掛金が回収できなくなるだけでなく、事業の継続自体にも影響が出る可能性があります。このような事態に備えて設けられているのが、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)です。掛金を積み立てることで、無担保無保証での借入れができる制度となっています。
本記事では、倒産防止共済の仕組みと加入条件について説明します。また、掛金の設定方法や具体的な活用方法についても解説していきます。
倒産防止共済の基本的な仕組み
倒産防止共済は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。まずは、この制度の基本的な仕組みについて理解しましょう。
倒産防止共済の目的
倒産防止共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、取引先企業の倒産により売掛金や受取手形などの回収が困難になった場合に、資金を調達できる制度です。この制度は1978年に創設され、多くの中小企業の経営安定に貢献してきました。
制度の主な目的は、連鎖倒産の防止です。取引先の倒産によって、自社の資金繰りが急激に悪化するという事態を避けるための「セーフティネット」として機能します。
経営危機を迅速に乗り越えるための重要な手段として、多くの中小企業経営者に活用されています。緊急時の資金調達手段として、銀行融資と比較しても審査が簡易で、迅速な資金確保が可能です。
この制度の最大の特徴は、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで無担保・無保証人で借り入れができる点です。通常の融資とは異なり、資金使途の制限もないため、運転資金や設備資金など、様々な用途に使用することができます。
制度の運営主体
倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。この制度は、「中小企業倒産防止共済法」に基づいて運営されており、国の政策の一環として位置づけられています。
中小機構は、経済産業省所管の独立行政法人で、中小企業政策の実施機関として様々な支援事業を行っています。倒産防止共済もその事業の一つであり、国の信用に基づいた安定した制度となっています。
実際の窓口業務は、商工組合中央金庫(商工中金)や信用金庫、信用組合、銀行などの金融機関、また商工会議所や商工会などが行っています。各地域に窓口があるため、身近な場所で相談や手続きを行うことができます。
この制度は任意加入の共済制度ですが、法律に基づいた公的な制度であるため、制度の安定性や継続性が高いことも大きな特徴です。民間の保険などと比較しても、国の信用を背景としているため、安心感があります。
倒産防止共済の加入条件
倒産防止共済に加入するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、加入資格や対象となる事業者について詳しく見ていきましょう。
加入可能な中小企業
倒産防止共済に加入できるのは、原則として1年以上事業を継続している中小企業者です。ただし、中小企業者の定義は業種によって異なります。業種別の資本金・従業員数の基準は、以下のとおりです。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
資本金と従業員数は、どちらか一方の条件を満たせば加入することができます。例えば、製造業で資本金が5億円あっても、従業員数が300人以下であれば加入可能です。
事業継続期間の確認は重要で、原則として1年以上事業を行っていることが条件となります。新規創業したばかりの企業は、一定期間の事業実績を積んでから加入を検討する必要があります。
また、個人事業主も加入することができます。その場合は、従業員数の基準のみで判断されます。例えば、小売業を営む個人事業主であれば、従業員が50人以下であれば加入資格があります。
加入対象外となる事業者
以下のような事業者は、倒産防止共済に加入することができません。
- 大企業(上記の中小企業の定義に当てはまらない企業)
- 創業して1年未満の企業(一部例外あり)
- 金融・保険業(銀行、信用金庫、保険会社など)
- 投資業(投資専門の会社など)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
- 中小企業基盤整備機構の共済金の貸付けに係る債務を弁済していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
また、既に倒産防止共済に加入している企業の子会社や関連会社であっても、それぞれ別個の法人であれば、独自に加入することができます。グループ企業全体で見た場合、各社ごとに加入することで、より大きな保護を受けることが可能です。
農業や漁業などの第一次産業に関しては、法人化していれば加入できる場合がありますが、個別の状況によって異なるため、最寄りの窓口に相談することをお勧めします。
倒産防止共済の掛金と積立のルール
倒産防止共済の掛金や積立には、いくつかのルールがあります。制度を有効に活用するためには、これらのルールを理解しておくことが重要です。
掛金の金額設定と納付方法
倒産防止共済の掛金は、月額5,000円から20万円までの範囲内で、5,000円単位で自由に設定することができます。例えば、5,000円、10,000円、15,000円というように設定します。
掛金の納付方法は、原則として金融機関からの口座振替となります。加入時に指定した金融機関の口座から、毎月自動的に引き落とされる仕組みです。引き落とし日は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となっています。
資金状況に応じた掛金調整が可能で、途中で掛金の増額や減額を行うこともできます。例えば、業績が好調な時期は掛金を増額し、資金繰りが厳しい時期は減額するといった柔軟な対応が可能です。
掛金の積立上限と税務上の取扱い
掛金の総額には上限があり、800万円が積立限度額となっています。この限度額に達すると、それ以上の掛金の納付はできませんが、共済契約自体は継続されます。掛金が積立限度額に達した場合、それ以降は掛金の納付が自動的に停止されます。
また、一時的に掛金の納付を休止することも可能です。例えば、資金繰りが厳しい時期に掛金の納付を一時的に休止し、余裕ができた時点で再開するといった対応もできます。ただし、休止期間中も共済契約は継続されています。
掛金は税務上、全額が損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として算入することができます。これは、通常の積立金や預金とは大きく異なる点で、税制上の大きなメリットとなっています。
また、解約手当金(脱退時に返還される金額)については、掛金の納付月数が40ヶ月未満の場合は掛金の80%、40ヶ月以上の場合は掛金の全額が戻ってきます。この解約手当金は、その年の益金(法人の場合)または事業所得(個人事業主の場合)として計上する必要があります。
倒産防止共済のメリット
倒産防止共済には、中小企業や個人事業主にとって様々なメリットがあります。ここでは、その具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
無担保無保証での融資が受けられる
倒産防止共済の最大のメリットは、取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で迅速に資金を借り入れることができる点です。通常の金融機関からの借入れでは、担保や保証人が必要になることが多いですが、この制度ではそれらが不要です。
借入可能額は、掛金総額の10倍(最高8,000万円)までとなっています。例えば、掛金を800万円積み立てていれば、最大8,000万円まで借り入れることができます。これは、企業の資金繰りにとって、大きな安心材料となります。
緊急時の資金調達が容易になるため、取引先の倒産という危機的状況においても、冷静に対応することができます。一般的な融資と比較して審査期間も短く、資金を迅速に調達できる点も大きなメリットです。
また、借入れた資金の使途に制限がないため、運転資金や設備資金、他の借入金の返済など、様々な用途に自由に使用することができます。このような柔軟性は、緊急時の対応において非常に重要です。
さらに、貸付条件も有利で、貸付利率は無利子〜年0.9%(2023年4月現在)と低金利です。返済方法も、一括返済や分割返済(最長5年)など選択が可能で、企業の状況に合わせた返済計画を立てることができます。
税制上の優遇措置を受けられる
倒産防止共済には、税制上の優遇措置があります。納付した掛金は、全額が損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として算入することができます。
これは、通常の積立金や預金とは大きく異なる点です。例えば、月額20万円の掛金を納付している場合、年間240万円が損金または必要経費として計上できるため、課税所得が減少し、結果的に税負担が軽減されます。
また、解約手当金(脱退時に返還される金額)については、掛金の納付月数が40ヶ月以上の場合は掛金の全額が戻ってきます。つまり、40ヶ月以上継続することで、実質的に無料で制度を利用できることになります。
解約手当金は課税対象となりますが、解約時の事業状況によっては繰越欠損金と相殺することも可能です。税理士などの専門家と相談しながら、最適な解約タイミングを検討することも重要です。
さらに、共済金の貸付けを受けた場合、その貸付金は収入ではなく負債として扱われるため、課税対象とはなりません。また、貸付けに対する利子についても、損金または必要経費として算入することができます。
このように、倒産防止共済は、税務上も有利な制度設計となっており、資金対策と節税対策の両面で活用することができます。特に、法人税率や所得税率が高い企業にとっては、大きなメリットとなります。
倒産防止共済のデメリット
倒産防止共済にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点もあります。制度を有効に活用するためには、これらの点も理解しておく必要があります。
早期解約のペナルティがある
倒産防止共済を解約する場合、納付した掛金がすべて戻ってくるわけではありません。解約時の掛金の返還率は、納付月数によって異なります。
納付月数が12ヶ月未満の場合、解約手当金はありません。つまり、掛金が全額没収されることになります。これは、制度の安定的な運営を図るための措置ですが、短期間での解約を考えている場合は大きなデメリットとなります。
短期加入での解約損失を避けるためには、少なくとも12ヶ月以上は継続することが重要です。納付月数が12ヶ月以上40ヶ月未満の場合は、掛金総額の80%が解約手当金として戻ってきます。
納付月数が40ヶ月以上になると、掛金総額の100%が解約手当金として戻ってきます。つまり、40ヶ月以上継続すれば、掛金は全額返還されることになります。長期的な視点で考えると、40ヶ月以上継続することで、実質的なコストなしで制度を利用できることになります。
また、解約手当金は、その全額が解約した年の益金(法人の場合)または事業所得(個人事業主の場合)として計上する必要があります。そのため、解約のタイミングによっては税負担が増加する可能性があります。特に、業績が好調で利益が出ている年に解約すると、高い税率で課税される可能性があるため注意が必要です。
借入制限や運用上の制約がある
倒産防止共済からの借入れには、いくつかの制限や制約があります。まず、借入れができるのは、取引先の倒産など、法律で定められた特定の事由が発生した場合に限られます。単なる資金繰りの悪化や設備投資のための資金調達としては利用できないため、平時から総合的な資金繰りの改善策を講じておくことが重要です。
借入可能額は、掛金総額の10倍(最高8,000万円)までとなっていますが、取引先に対する売掛金等の債権額が上限となります。つまり、倒産した取引先への売掛金が300万円の場合、借入れは300万円までとなります。
また、借入申込みは、取引先企業の倒産等の事由が発生した日から6ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、その事由による借入れはできなくなります。倒産の事実を知ってからすぐに対応することが重要です。
借入れを行うと、その額に応じて掛金総額から控除されます。例えば、掛金総額が500万円で250万円を借り入れた場合、掛金総額は250万円に減少します。この控除された掛金は、借入金を完済しても復活しません。再度積み立てる必要があります。
さらに、借入れを行った場合、一定期間は新たな借入れができない場合があります。特に、貸付額が大きい場合や返済が滞っている場合は、新たな借入れが制限される可能性があります。このような制約は、緊急時の資金調達に影響を与える可能性があるため、計画的な利用が求められます。
倒産防止共済の加入手続き
倒産防止共済に加入するためには、いくつかの手続きが必要です。ここでは、加入から契約成立までの流れを詳しく解説します。
必要書類の準備
倒産防止共済に加入するためには、以下の書類が必要となります。
- 中小企業倒産防止共済契約申込書
- 掛金月額変更申出書(掛金月額を変更する場合)
- 預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書
- 印鑑証明書(個人事業主の場合は市区町村発行のもの、法人の場合は法務局発行のもの)
- 事業内容が確認できる書類(法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は事業税の課税証明書など)
申込窓口は、以下の機関となっています。
- 商工組合中央金庫(商工中金)の本・支店
- 信用金庫・信用組合・銀行の本・支店
- 商工会議所・商工会
- 中小企業団体中央会
最寄りの窓口で相談することが、初めのステップです。窓口では、制度の詳細説明や申込書の記入方法などについてアドバイスを受けることができます。特に初めて加入する場合は、不明点を解消してから申し込むことをお勧めします。
申込書類の記入には、法人印(個人事業主の場合は実印)が必要です。また、口座振替の設定には、指定する金融機関の届出印も必要となりますので、事前に準備しておきましょう。
申込みは郵送でも可能ですが、不備があると手続きが遅れる可能性があるため、できるだけ窓口で直接申し込むことをお勧めします。窓口で申し込む場合は、担当者が書類の不備をその場で指摘してくれるため、スムーズに手続きを進めることができます。
審査から契約成立まで
申込書類を提出すると、中小企業基盤整備機構による審査が行われます。審査では、加入資格の有無や申込内容の確認が行われます。審査期間は通常、2週間から1ヶ月程度かかります。
審査に通過すると、「中小企業倒産防止共済契約締結通知書」が送付されます。この通知書には、共済契約者番号や掛金月額、掛金の納付方法などが記載されています。
契約が成立すると、指定した金融機関の口座から自動的に掛金が引き落とされるようになります。引き落とし日は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
初回の掛金納付が確認されると、正式に契約が発効します。契約発効後は、「中小企業倒産防止共済手帳」が送付されます。この手帳には、契約内容や共済金の貸付条件などが記載されており、大切に保管しておく必要があります。
契約後に掛金月額の変更や住所変更などがある場合は、所定の手続きを行う必要があります。変更手続きは、加入時と同じ窓口で行うことができます。
掛金の納付状況は、年に1回送付される「掛金納付状況のお知らせ」で確認することができます。このお知らせには、掛金の納付累計額や解約手当金の額などが記載されています。
なお、倒産防止共済は任意加入の制度ですので、いつでも解約することができます。解約する場合は、「中小企業倒産防止共済解約申出書」を提出します。解約手当金は、申出書の提出から約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
倒産防止共済の貸付条件
倒産防止共済からの借入れには、特定の条件があります。ここでは、借入れの対象となるケースや貸付条件について詳しく見ていきましょう。
貸付対象となる場合
倒産防止共済からの借入れが可能となるのは、以下のような取引先の倒産等のケースです。
| 対象となる事由 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 法的整理の場合 | 破産手続開始の申立 民事再生手続開始の申立 会社更生手続開始の申立 特別清算開始の申立て |
| 私的整理の場合 | 銀行取引の停止処分 内整理の開始 特定調停の申立 |
| 災害等による不渡りの場合 | 災害、経済情勢の急激な変動等の影響により手形・小切手を不渡りにした場合 |
| 大型倒産の影響による場合 | 大企業等の倒産に伴い、中小企業者の債権の回収が困難となった場合 |
ただし、単なる代金の支払遅延や取引先の夜逃げなどは、借入れの対象とはなりません。法的な倒産手続きや、客観的に確認できる事実が必要です。
適切な倒産認定書類の準備が重要です。例えば、法的整理の場合は裁判所の受理証明書、手形・小切手の不渡りの場合は不渡事故報告書などが必要となります。これらの書類がないと、借入れの申請ができません。
また、借入申込みは、取引先企業の倒産等の事由が発生した日から6ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、その事由による借入れはできなくなります。倒産の事実を知ってからすぐに対応することが重要です。
さらに、取引先との取引開始時期も重要です。共済契約の成立前から取引を行っている取引先については、契約成立日から6ヶ月を経過しないと借入れの対象とはなりません。新規の取引先については、取引開始から1年以上経過している必要があります。
貸付額の計算方法と返済条件
倒産防止共済からの借入可能額は、以下の3つの条件のうち最も少ない額となります。
- 掛金納付総額の10倍(最高8,000万円)
- 回収困難となった売掛金債権等の額
- 回収困難となった売掛金債権等の額が掛金納付総額の10倍を超える場合は、掛金納付総額の10倍の額に相当する額
例えば、掛金納付総額が500万円で、回収困難となった売掛金債権等の額が300万円の場合、借入可能額は300万円となります。
貸付条件は、次のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付利率 | 無利子〜年0.9%(貸付金額や返済方法によって異なる) |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済(最長5年) |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入れを行うと、その額に応じて掛金総額から控除されます。控除される金額は、貸付額の10分の1です。例えば、300万円を借り入れた場合、掛金総額から30万円が控除されます。この控除された掛金は、借入金を完済しても復活しません。再度積み立てる必要があります。
借入金の返済は、一括返済または分割返済を選択することができます。分割返済の場合、最長5年(60回)までの返済期間を設定することができます。毎月の返済額は、貸付額と返済期間によって決まります。
返済方法は、口座振替となります。毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に指定口座から自動的に引き落とされます。返済が滞ると、延滞利息(年14.6%)が発生するため注意が必要です。
なお、借入金は繰上返済することも可能です。繰上返済をする場合は、「共済金貸付繰上返済申出書」を提出します。繰上返済によって返済期間を短縮することで、利息の負担を軽減することができます。
まとめ
倒産防止共済は、取引先の倒産リスクから中小企業や個人事業主を守るための重要なセーフティネットです。掛金を積み立てておくことで、いざという時に無担保・無保証人で迅速に資金を借り入れることができるこの制度は、事業継続のための強力な味方となります。もちろん、これ以外にも様々な銀行以外の資金調達方法も存在するため、自社の状況に合わせて複数の選択肢を検討することが大切です。
本記事では、制度の基本的な仕組みから加入条件、掛金のルール、メリット・デメリットまで詳しく解説しました。資金繰りに不安を感じている経営者の方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。まずは最寄りの窓口に相談し、自社の状況に合わせた最適な掛金設定や加入のタイミングを検討することをお勧めします。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
経営セーフティ共済(倒産防止共済)は素晴らしい制度ですが、加入してすぐに活用できるわけではなく、また取引先の倒産という特定条件下でしか借入できないという制約があります。日々の資金繰りに困っている、あるいは急な資金需要が発生している場合の資金調達には、ビジネスローンの方が向いていることが多いでしょう。HTファイナンスでもビジネスローンサービスを提供しており、無担保無保証で利用可能である点、そして柔軟な審査基準を採用している点を強みとしています。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないためにも、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。