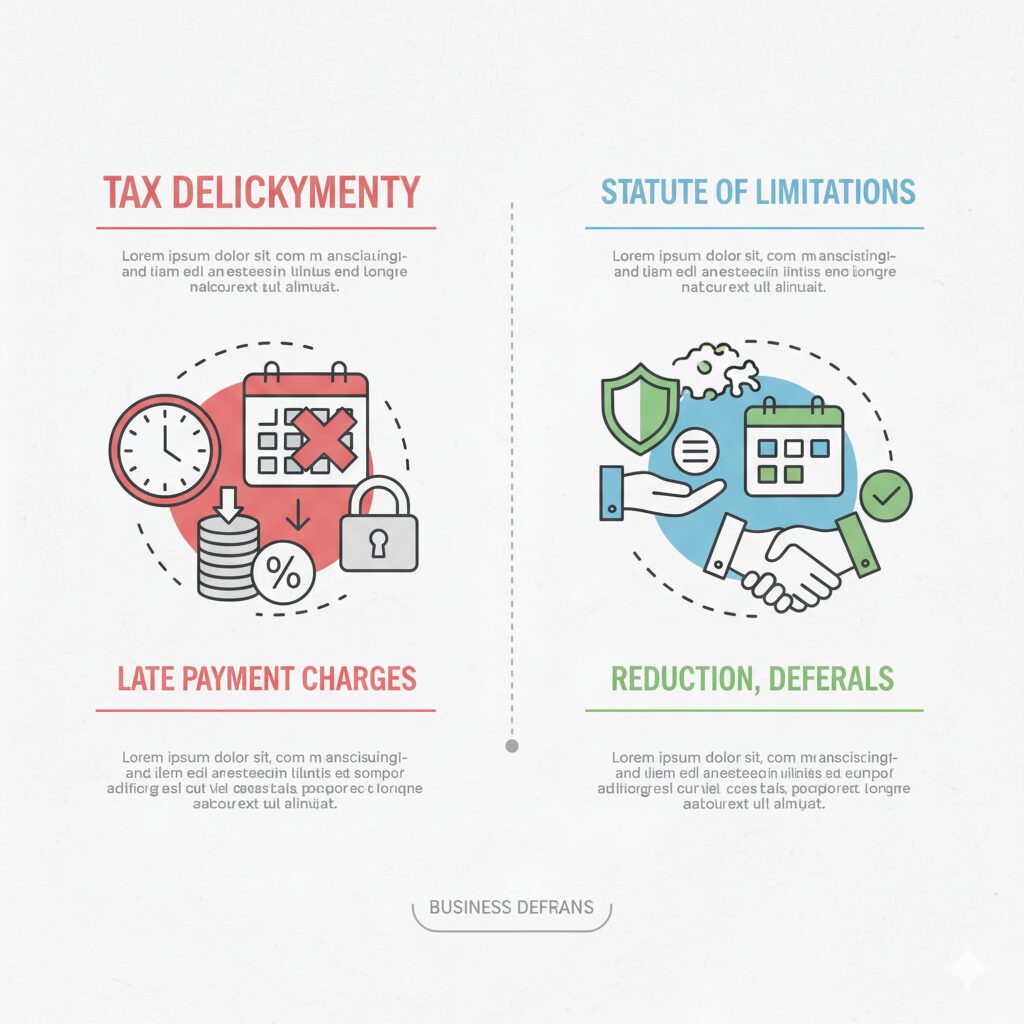公開日:2025.10.24
更新日:2025.10.24
催促状はどのように書けばよい?法的効力や送付のタイミング、NG例まで徹底解説
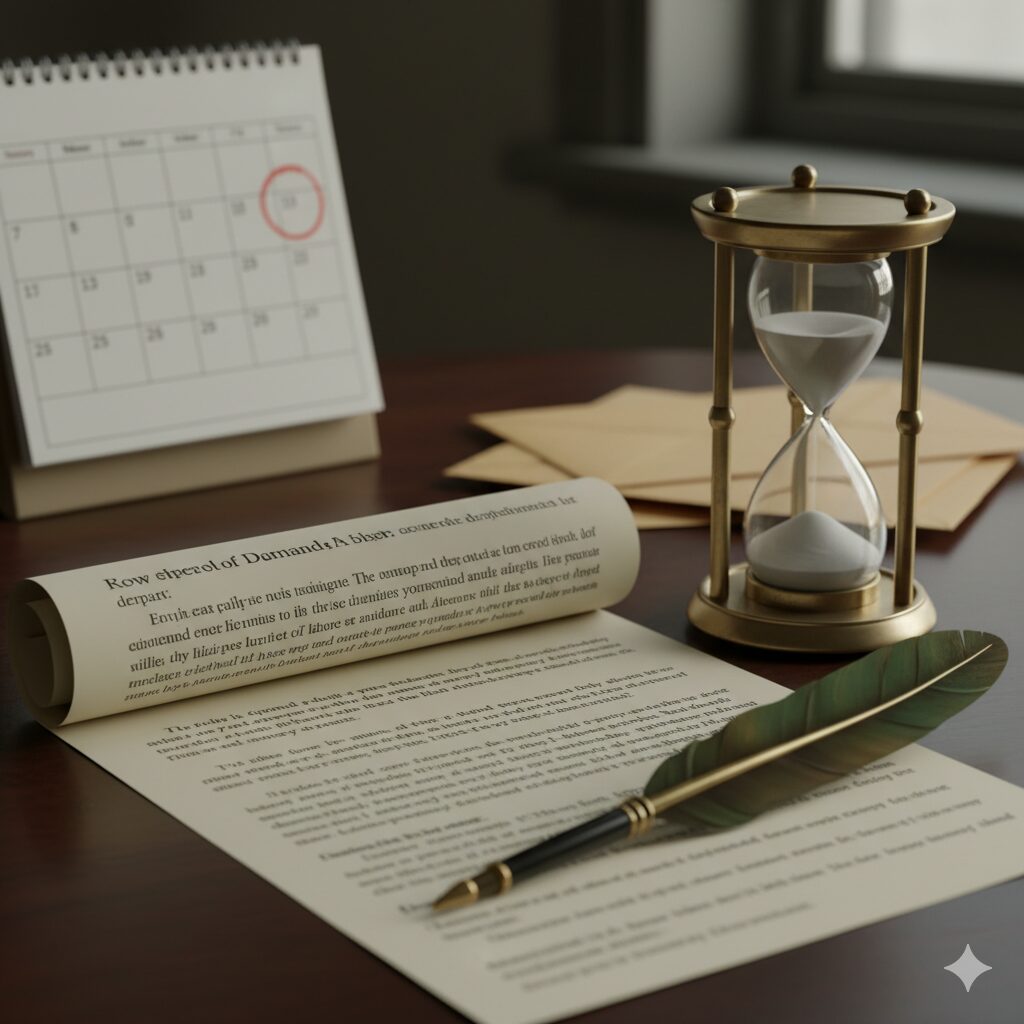
取引先への売掛金回収で、入金が期日を過ぎた場合の催促に困る方が少なくありません。ビジネスにおいて、売掛金の回収は早期に取り組むべき課題ですが、その際どのように催促するかというのは非常に難しい問題です。あまり強く迫ると取引関係に支障をきたすかもしれませんし、かといって弱腰では支払いが先延ばしにされる恐れもあります。
この記事では、催促状の書き方から法的効力、送付のタイミング、避けるべき表現まで詳しく解説します。適切な催促状を作成・送付するための基本知識を身につけることで、スムーズな債権回収を実現しましょう。また、催促状が届いた側の対応方法についても触れていますので、双方の立場から理解を深めることができます。
催促状とは
催促状は、支払期限を過ぎた取引先に対して支払いを促すための文書です。
ビジネスの現場では、商品やサービスを提供した後に料金を支払ってもらう取引が一般的です。しかし、支払期日を過ぎても入金がない場合、何らかのアクションを起こす必要があります。そのファーストステップとして活用されるのが、催促状です。
催促状を作成する目的
催促状は、未払いとなっている債権について、債務者に支払いを促す文書です。その主な目的は、債務者に支払い義務の存在を再認識させ、速やかな支払いを促すことにあります。
法的な強制力はないものの、支払いの意思確認と喚起という重要な役割を担っています。また、支払いが遅れている事実を公式に記録する意味もあります。
催促状は、単なるリマインダーとしての機能だけでなく、今後の法的手続きへの準備段階としての意味も持ち合わせています。万が一、法的な措置に発展した場合に、適切な催促の履歴があることは、債権者側に有利に働くことがあります。
催促状が活用される場面
催促状が活用される代表的なビジネスシーンとしては、次のようなケースが挙げられます。
まず最も一般的なのは、商品納品や役務提供後の売掛金回収です。請求書に記載された支払期限を過ぎても入金がない場合、催促状を送付して支払いを促します。
また、賃貸物件のオーナーが家賃滞納者に対して支払いを求める場合や、フリーランスの方が報酬の支払いを受けていない場合にも催促状は有効です。
さらに、個人間の金銭貸借においても、返済が滞っている場合には、催促状を活用することで支払いを促す効果が期待できます。ビジネスの規模や業種を問わず、債権回収の初期段階で幅広く利用されています。
催促状と督促状の違い
催促状と督促状は似た役割を持ちますが、いくつかの重要な違いがあります。
両者の違いを理解することで、状況に応じた適切な文書を選択できるようになります。また、段階的な債権回収プロセスを効果的に進める上でも重要な知識です。
表現の強さや送付タイミングの違い
催促状と督促状の最も大きな違いは、表現の強さとニュアンスにあります。催促状は比較的穏やかな表現で支払いを促し、取引関係の維持に配慮した内容となっています。
一方、督促状はより強い表現で支払いを求め、場合によっては法的措置への言及を含むこともあります。段階的な強度の違いがあることを理解しておきましょう。
送付のタイミングについても違いがあります。通常、催促状は支払期限経過後の初期段階で送付され、それでも支払いがない場合に督促状へと移行します。つまり、催促状→督促状→法的手続きという流れで、段階的に対応が強化されていくのが一般的です。
法的効果の違い
法的効果の面では、催促状と督促状は、多くの共通点を持っています。どちらも単独では法的強制力を持たず、あくまでも支払いを促す文書です。
また、どちらも債権の消滅時効を中断(現在の民法では「完成猶予」)する効果があります。具体的には、催促状や督促状を送付することで、債権の消滅時効が6ヶ月間延長されます。
ただし、法的な位置づけに微妙な違いがあります。「督促」という言葉には法律用語としての側面があり、裁判所を通じた「支払督促」という法的手続きもあります。一方、催促はより一般的な用語で、法的手続きとの直接的な結びつきは弱いといえるでしょう。
催促状の法的効力
催促状は、法的にどのような効力を持つのでしょうか。この点を正しく理解することで、効果的な債権回収戦略を立てることができます。
催促状自体には強制力はありませんが、債権管理において重要な法的意味を持っています。ここでは、催促状の法的側面について詳しく見ていきましょう。
消滅時効への影響
催促状が持つ最も重要な法的効力は、債権の消滅時効に関するものです。民法の規定により、債権者が債務者に対して催促状などで請求を行うと、消滅時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
これは令和2年4月の民法改正以降、従来の「時効の中断」から「時効の完成猶予」という考え方に変わりました。時効の延長効果があるため、債権を守るために定期的な催促が有効です。
ただし、催促状による時効の完成猶予は、一時的なものです。6ヶ月以内に訴訟の提起などの法的手続きを行わなければ、再び時効の進行が始まります。そのため、長期にわたる債権回収では、催促状の送付だけでなく、状況に応じて法的手続きへ移行することも検討する必要があります。
債務の承認と証拠としての価値
催促状に対して債務者から返答があった場合、その内容によっては「債務の承認」となる可能性があります。債務者が借金の存在を認める返信をすれば、それは債務の承認となり、時効は更新(リセット)されます。
また、催促状とその送付記録は、将来的に裁判などの法的手続きに進展した場合の重要な証拠資料となります。適切に催促を行ってきた経緯を示すことで、債権者としての誠実な対応を証明できます。
このような法律の側面を考慮すると、催促状は単なる支払い要請の文書ではなく、債権管理における重要な法的ツールといえます。送付日時や内容を記録として残し、可能であれば配達証明付きの郵便など、送付の証拠が残る方法を選ぶことが賢明です。
効果的な催促状の書き方
催促状は、債権回収の第一歩であり、その書き方によって効果が大きく左右されます。
ここでは、相手に確実に伝わり、かつ取引関係を損なわない催促状の書き方について解説します。基本的な構成要素から表現のポイントまで、実践的な内容を押さえていきましょう。
必須の記載事項
効果的な催促状には、以下の要素を必ず含めるようにしましょう。まず、宛先(会社名・担当者名)と差出人(自社名・担当者名・連絡先)を明記します。これにより、誰から誰へのメッセージであるかが明確になります。
発行日も重要です。後々のやり取りや法的手続きの際に、いつ催促を行ったかの証拠となります。日付の明確化は、債権管理において非常に重要です。
催促の対象となる取引の詳細(請求書番号、取引日、商品・サービス内容)、未払い金額、本来の支払期限も明記します。これにより、どの取引に関する催促なのかが相手に伝わります。
また、具体的な支払期限(催促状送付から1週間後など)と支払方法(振込先口座情報など)も記載しましょう。相手が行動しやすいよう、明確な指示を提供することが大切です。
効果的な文章表現のポイント
催促状の文面は、相手に不快感を与えず、かつ支払いの必要性を明確に伝えるバランスが重要です。まずは丁寧な言葉遣いを心がけましょう。感情的な表現や命令口調は避け、ビジネスマナーを守った表現を使用します。
文章の冒頭では、未払いの事実を客観的に伝えます。「〇月〇日を期限とした請求書について、現時点でお支払いが確認できておりません」といった表現が適切です。
本文では、支払いの必要性を論理的に説明します。単に「払ってください」ではなく、「取引条件に基づいたお支払いをお願いいたします」など、契約や合意に基づいた請求であることを示すと効果的です。
結びの部分では、具体的な対応を促します。「〇月〇日までにお振込みいただくか、お支払いが困難な事情がございましたら、ご連絡ください」など、相手に行動を促す内容を含めましょう。
また、長文よりも、簡潔で要点を押さえた文章の方が相手に伝わりやすいため、不必要な説明は避け、簡潔明瞭な表現を心がけることも大切です。
催促状のNG表現と注意点
催促状を作成する際には、避けるべき表現や法的リスクがあります。
効果的な催促と良好な取引関係の維持を両立させるためには、これらの注意点を押さえておくことが重要です。ここでは、催促状作成時の落とし穴と回避方法について解説します。
避けるべき表現
催促状において避けるべき表現として、まず脅迫的な言い回しが挙げられます。「支払わなければ法的措置を取る」「信用情報に傷がつく」などの表現は、脅迫と受け取られる可能性があります。
感情的な表現も避けるべきです。「なぜ支払わないのか」「誠意がない」などの非難めいた表現は、相手の反感を買い、かえって支払いを遅らせる原因となりかねません。感情を抑えた冷静な表現を心がけましょう。
また、事実と異なる内容や誇張表現も問題です。「すでに法的手続きを開始した」(実際には開始していない場合)などの虚偽の内容は、信頼関係を損なうだけでなく、場合によっては、法的責任を問われる可能性もあります。
法的リスクを避けるための配慮
催促状の作成・送付にあたっては、いくつかの法的リスクに注意する必要があります。まず、個人情報保護の観点から、封書の表面に「催促状」「支払いのお願い」などと明記することは避けましょう。これは、債務者のプライバシーを侵害する可能性があります。
また、第三者(家族や職場の同僚など)に債務の存在を知らせるような方法で催促することも避けるべきです。これは、債務者の名誉やプライバシーを侵害する行為となり、不法行為責任を問われる可能性があります。
さらに、頻繁すぎる催促や深夜・早朝の連絡も、債務者への嫌がらせと捉えられる恐れがあります。民法上の権利行使であっても、その方法が社会通念上不相当であれば、権利の濫用として違法と判断される可能性があるのです。
催促状を送る際は、相手の立場や感情に配慮し、あくまでも事実に基づいた冷静な内容とすることが、法的リスクを避けるための最善の方法です。支払いを促すという目的を果たしつつも、相手の人格を尊重する姿勢を保ちましょう。
催促状の送付方法
催促状をいつ、どのように送れば最も効果的なのでしょうか。適切なタイミングと送付方法を選ぶことで、回収率を高めることができます。
ここでは、実務に即した催促状の送付タイミングと、各送付方法のメリット・デメリットについて解説します。
効果的な送付タイミング
催促状を送付するベストなタイミングは、支払期限から5営業日〜1週間程度経過した時点です。あまり早すぎると相手に焦りを与えてしまい、遅すぎると債権回収の遅延につながります。
また、月初めや給料日後などの、資金繰りが比較的良好な時期を狙うのも効果的です。相手企業の資金状況を考慮した送付が、回収成功率を高めます。
年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇前は避けるべきです。休暇中に催促状が埋もれてしまう可能性があります。また、金曜日の午後に送付すると週末を挟むことになり、対応が遅れがちになるため、月曜日から木曜日の送付が望ましいでしょう。
催促状の効果がない場合は、10日〜2週間程度の間隔を空けて、より強い表現の督促状へと段階的にエスカレーションしていくことをお勧めします。
送付方法の選択
催促状の送付方法には、郵送、FAX、メール、手渡しなど、様々な選択肢があります。それぞれに特徴がありますので、状況に応じて最適な方法を選びましょう。
郵送は公式性が高く、特に配達証明付き郵便や内容証明郵便を利用すれば、送付の事実を証明できます。ただし、到着までに時間がかかるデメリットがあります。
メールは即時性があり、やり取りの記録も残りやすいメリットがあります。ただし、迷惑メールとして処理されたり、相手に見落とされたりするリスクがあります。開封確認機能の活用や、重要なメールであることを件名に明記するなどの工夫が必要です。
FAXは、即時性と文書としての形式を兼ね備えていますが、現在では利用頻度が下がっている点に注意が必要です。
どの方法を選ぶにせよ、送付日時や内容の記録を保管しておくことが重要です。将来的に法的手続きに移行する可能性も考慮し、催促状のコピーや送信記録、相手からの返答などは、すべて整理して保管しておきましょう。また、複数の方法を併用することで、確実に相手に届ける工夫も効果的です。
催促状のテンプレートと活用例
効率的に催促状を作成するためには、状況に応じたテンプレートの活用が有効です。
ここでは、実際のビジネスシーンで使える催促状のテンプレートと、状況別の活用ポイントを紹介します。自社の状況に合わせて、カスタマイズしてご活用ください。
催促状の基本テンプレート
以下は、一般的な催促状のテンプレートです。必要に応じて、内容を調整してご利用ください。
文書上部には、日付、宛先(会社名・担当者名)、差出人(会社名・部署・担当者名・連絡先)を記載します。件名は「請求書のお支払いについて」など、目的が明確に伝わるものにしましょう。
本文では、まず丁寧な挨拶から始め、取引内容と未払い金額を明確に示します。「平素より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。さて、20XX年XX月XX日付請求書(請求書番号XXXX)の金額XXX,XXX円につきまして、お支払い期限の20XX年XX月XX日を過ぎておりますが、現時点でお支払いが確認できておりません。」
次に、支払いを促す文章を入れます。「つきましては、20XX年XX月XX日までに下記口座へのお振込みをお願い申し上げます。」振込先情報や連絡先も明記しましょう。
最後に、支払い困難な場合の対応についても触れると良いでしょう。「なお、お支払いに関してご事情がございましたら、お手数ですが上記担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。」
状況別の文面アレンジ
催促状は、取引状況や相手との関係性に応じて、文面をアレンジすることが効果的です。以下に、いくつかの状況別のアレンジ例を紹介します。
初めての遅延の場合は、穏やかな表現を心がけましょう。「今回初めての督促となりますが」といった前置きを入れると、相手も受け入れやすくなります。
長期の取引先の場合は、これまでの良好な関係性に触れると効果的です。「長年のお取引に感謝申し上げます。今後とも良好な関係を継続したく」などの文言を加えることで、相手の協力を得やすくなります。
2回目以降の催促では、少し強めの表現を使うことも検討しましょう。「前回20XX年XX月XX日付でもお支払いのお願いをさせていただきましたが」など、過去の催促歴に言及すると効果的です。
高額な未払いがある場合は、分割払いの提案を含めると解決につながることがあります。「一括でのお支払いが難しい場合は、分割払いなどのご相談も承ります」といった柔軟な対応姿勢を示すことで、支払い協議の糸口になります。
どのようなアレンジをする場合でも、事実に基づいた冷静な表現を心がけ、相手の立場を尊重する姿勢を忘れないようにしましょう。適切にカスタマイズされた催促状は、債権回収と取引関係維持の両立に役立ちます。
催促状送付後の対応
- 支払遅延の発生
- 【STEP1】催促状の送付
- 【STEP2】電話での状況確認
- 【STEP3】督促状の送付
- 【STEP4】内容証明郵便での最終督促
- 【STEP5】法的手続きへの移行を検討
催促状を送付した後の対応は、債権が回収できるかどうか左右する重要なポイントです。
ここでは、催促状送付後に考えられる状況と、それぞれに応じた適切な対応方法について解説します。状況を見極めながら、次のステップへ進むための知識を身につけましょう。
支払いがない場合の対応
催促状を送付しても支払いがない場合、状況に応じて段階的に対応を強化していく必要があります。まず、催促状送付から1週間程度経過しても反応がない場合は、電話での確認が効果的です。
電話でのフォローアップでは、「催促状は届いていますか?」「支払いが遅れている理由はありますか?」など、事実確認と状況把握を心がけましょう。この段階で支払いの意思が確認できれば、具体的な入金日を確認しておくと良いでしょう。
電話連絡でも解決しない場合は、より強い表現の督促状を送付します。2回目以降の督促では、これまでの経緯を明記し、より具体的な期限を設定するとともに、支払いがない場合の対応(法的手続きの検討など)についても言及することが一般的です。
さらに支払いがない場合は、内容証明郵便での最終督促を検討します。これは法的手続きの前段階として、公式に支払い請求を行う重要なステップです。内容証明郵便には、取引の詳細、未払い金額、最終支払期限、期限を過ぎた場合の対応(法的手続きへの移行など)を明確に記載します。
法的手続きへの移行
複数回の催促・督促にもかかわらず、支払いがない場合は、法的手続きへの移行を検討する段階となります。ただし、法的手続きは時間とコストがかかるため、その判断は慎重に行う必要があります。
法的手続きへの移行を検討する際には、まず未払い金額と回収コストのバランスを考慮しましょう。少額の場合、法的手続きのコストが回収額を上回る可能性があります。
また、相手の支払い能力も重要な判断材料です。相手が経営難に陥っている場合、法的手続きを経ても回収できない可能性があります。可能であれば、相手の財務状況を調査することも検討しましょう。
法的手続きとしては、支払督促、少額訴訟、民事訴訟などの選択肢があります。支払督促は、裁判所を通じて支払いを命じる比較的簡易な手続きです。少額訴訟は、60万円以下の請求に適用でき、原則1回の審理で判決が出る迅速な手続きです。より高額な場合や複雑な事案では、通常の民事訴訟となります。
法的手続きへの移行を決断した場合は、弁護士への相談が推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、最も効果的かつ効率的な回収方法を選択できるでしょう。
催促状が届いた場合の対応
催促状を受け取る側の立場になった場合、適切な対応が求められます。
ここでは、催促状を受け取った際の基本的な対応方法と、状況別の具体的なアクションについて解説します。適切な対応は、信用の維持と良好な取引関係の継続につながります。
受け取った催促状への基本的な対応
催促状を受け取ったら、まず内容を確認し、事実関係を精査することが大切です。請求内容が正しいかどうか、支払い期限や金額に誤りがないかをチェックしましょう。
請求内容に問題がなければ、速やかな支払い対応が基本です。支払いが遅れていることを認識していなかった場合でも、まずは相手に連絡を入れ、状況を説明した上で、できるだけ早く支払いを行いましょう。
支払いを行った後は、その旨を相手に通知すると良いでしょう。振込明細書のコピーを送付するなど、支払いの証拠を提示することで、誤解を防ぐことができます。
また、催促状の内容に不明点や疑問点がある場合は、放置せずに相手に問い合わせることが重要です。コミュニケーションを取ることで、多くの問題は解決に向かいます。
支払い困難な場合の交渉方法
資金繰りの問題などで即時の支払いが困難な場合は、誠実な対応が特に重要です。まず、支払いが遅れている事実を認め、相手に対して真摯に謝罪しましょう。
その上で、支払い計画を提案することが効果的です。例えば、「〇月〇日に一部、残りを〇月〇日に支払う」など、具体的な分割払いの提案を行うことで、相手の理解を得やすくなります。
交渉の際は、一方的な要求ではなく、双方が受け入れられる条件を見つけることが大切です。無理な約束をして再び履行できなくなるよりも、現実的な計画を提案し、それを確実に守ることが信頼回復につながります。
また、支払い困難な状況が一時的なものであれば、その原因と今後の見通しを説明することも有効です。例えば、「大口顧客からの入金が遅れているが、来月には状況が改善する見込み」といった説明は、相手の理解を得やすくします。
なお、合意した支払い計画は、必ず書面化し、双方で確認することをお勧めします。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。支払い計画を守ることで、取引関係の維持だけでなく、信用の回復にもつながるでしょう。
催促状に関するよくある質問
ここでは、催促状に関してよく寄せられる質問と、その回答をまとめました。実際の現場で直面する可能性のある疑問点を解消し、より効果的な債権管理に役立てましょう。
催促状の送付回数と頻度
催促状を何回送るべきか、またどのくらいの頻度で送るべきかという質問は多く寄せられます。一般的には、最初の催促状を送ってから10日〜2週間程度間隔を空けて、2回目、3回目と送付するのが適切です。
あまりに頻繁に送りすぎると、相手に嫌がらせと捉えられるリスクがあります。一方、間隔を空けすぎると、債権回収の意思が伝わりにくくなります。バランスの取れた頻度で送付することが重要です。
また、催促状→督促状→内容証明郵便という具合に、段階的に強い表現の文書に移行していくのが一般的です。3回程度の催促・督促でも支払いがない場合は、法的手続きへの移行を検討する段階と言えるでしょう。
個人・法人への送付における違い
個人と法人では、催促状の送付における注意点が異なります。個人への催促では、プライバシーへの配慮が特に重要です。封筒の表面に「催促状」などと記載せず、第三者に債務の存在が知られないよう注意しましょう。
また、個人の場合、消費者保護の観点から過度な催促は避けるべきです。特に消費者契約の場合は、貸金業法や割賦販売法などの規制も考慮する必要があります。
一方、法人への催促では、社内での処理遅延も考慮する必要があります。請求書が適切な部署に届いていない可能性もあるため、責任者への直接連絡が効果的な場合もあります。
法人の場合、支払管理のシステムや承認フローがあるため、支払日の見通しを確認することも重要です。また、経理処理の都合上、月末締め翌月払いなどの支払いサイクルがある場合は、それに合わせた催促が効果的です。
どちらの場合も、相手の状況や事情を考慮した上で、適切な方法とタイミングで催促することが、円滑な債権回収につながります。単なる機械的な催促ではなく、相手との関係性や状況に応じた柔軟な対応が求められるのです。
まとめ
催促状は、債権回収における重要なツールであり、適切に活用することでスムーズな資金回収を実現できます。本記事では、催促状の基本的な役割から書き方のポイント、送付のタイミング、法的効力まで幅広く解説しました。
催促状作成の際は、事実に基づいた冷静な表現を心がけ、相手の立場を尊重することが大切です。また、催促状が届いた側も、誠実な対応と速やかなコミュニケーションが、問題解決の鍵となります。催促状の送付から支払いの確認まで、一連のプロセスを適切に管理することで、ビジネス関係を損なうことなく債権を保全できるでしょう。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
資金繰りの改善は、支払い遅延を防ぎ、催促状を受け取る状況を回避するための根本的な解決策です。一時的な資金不足で、取引先からの信用を失わないためにも、柔軟な資金調達手段を確保しておくことが、経営の安定につながります。HTファイナンスのビジネスローンは、無担保無保証で利用可能であり、審査基準も柔軟であるため、すぐに調達したいというニーズに応えやすいのが特徴です。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
まずは、お気軽にHTファイナンスにご相談ください。