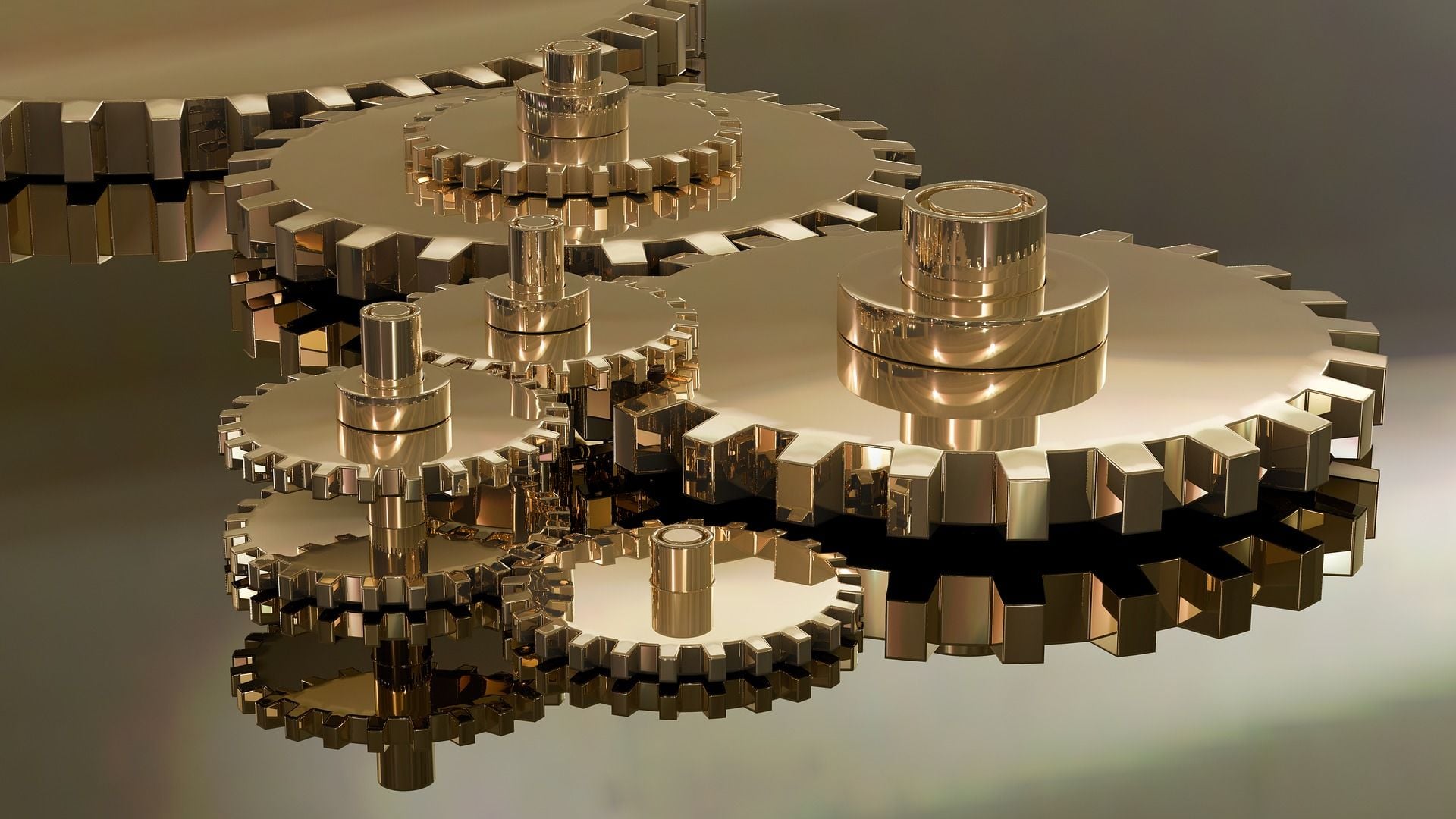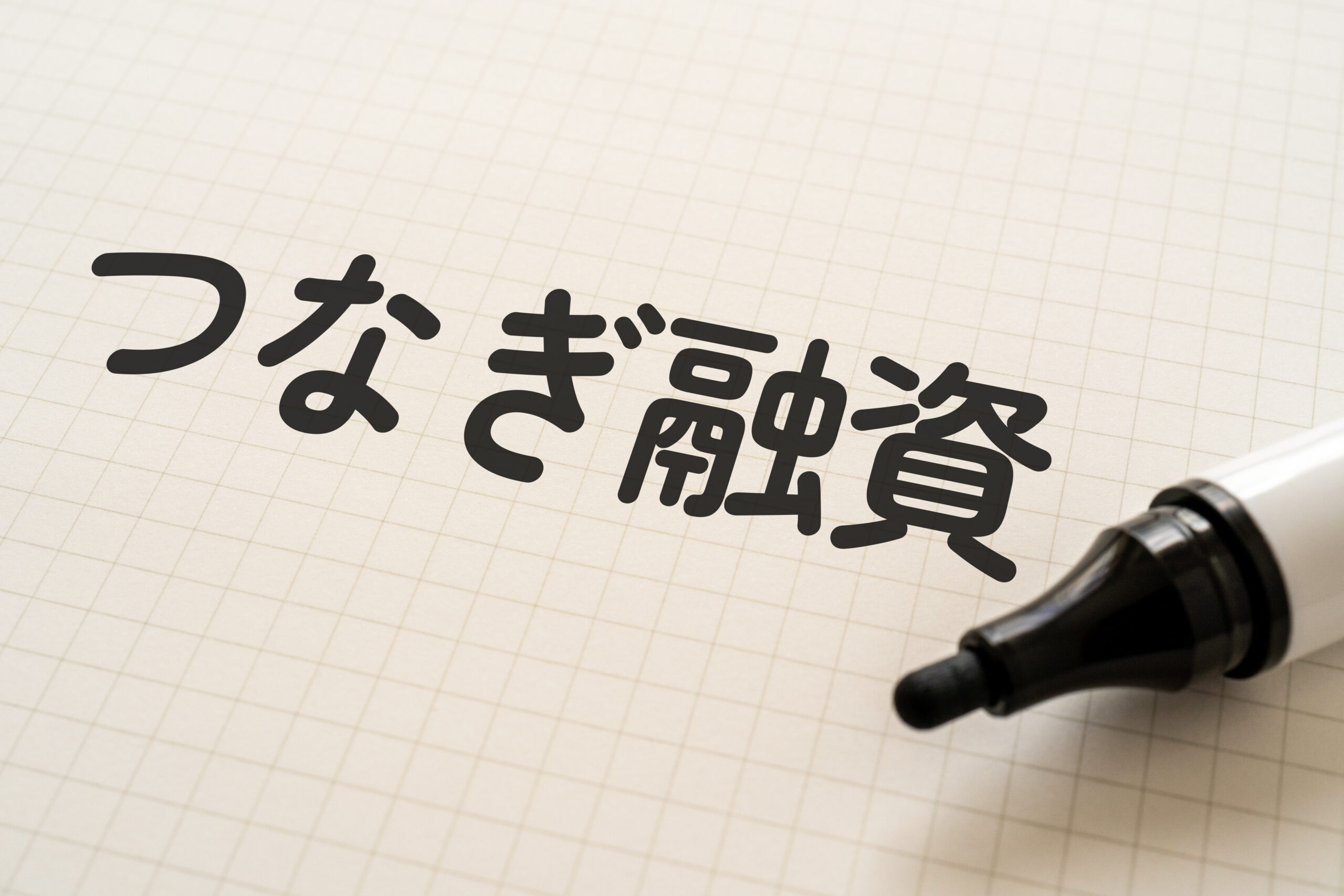公開日:2025.10.16
更新日:2025.10.16
手形取立は期日の何日前までに行うべき?手形の資金化の流れについても紹介

事業を営んでいると、取引先から約束手形を受け取ることがあるかもしれません。そんなとき、手形は期日を過ぎると取立ができなくなり、資金回収に支障が出るため、銀行への持込時期や取立期限を正しく理解しておく必要があります。
本記事では、手形取立の期限や適切な持込時期について説明するとともに、資金化までの手続きの流れを解説していきます。また日本では、「紙の手形(約束手形・小切手)」の利用が、2026年度末(つまり2027年3月末)までに実質的に廃止される予定です。ただし、電子化された決済手段(電子記録債権=「でんさい」や銀行振込など)は、引き続き使用可能です。
手形取立の基本
手形取立とは、受け取った手形を銀行に持ち込み、支払期日に振出人の口座から資金を引き落として、自社口座に入金してもらう手続きです。この取立には、いくつかの重要なルールがあります。
手形取立の期限はいつまでか
約束手形の取立には、明確な期限が定められています。一般的に、支払期日当日を含めて3営業日以内に銀行へ持ち込む必要があります。
ここで重要なのは、「営業日」の考え方です。営業日とは、銀行の窓口が開いている平日のみを指し、土曜日・日曜日・祝日は含まれません。
例えば、手形の支払期日が水曜日の場合、取立可能な期間は、水曜日・木曜日・金曜日の3日間となります。仮に支払期日が金曜日の場合は、金曜日・月曜日・火曜日が取立期間となります(土日は銀行休業日のため)。
この期限を過ぎてしまうと、銀行での手形取立ができなくなります。その場合は、振出人に直接支払いを請求する必要が生じ、回収リスクが高まってしまいます。
手形取立の期限を過ぎることのリスク
手形取立の期限を過ぎてしまうと、どのようなリスクが生じるのでしょうか。第一に、銀行による取立サービスが利用できなくなります。これにより、自動的に資金回収ができなくなるため、自社で振出人に対して支払請求をしなければなりません。
振出人との関係性によっては、督促が取引関係に影響を与える可能性もあります。また、万が一振出人の資金繰りが悪化していた場合、直接請求では回収が難しくなることも考えられます。
さらに、期限切れの手形については、不渡りと同様の扱いにはなりませんが、手形交換所での取立ができないため、決済の確実性が大きく低下します。これは、企業の資金計画にも大きな影響を与えかねません。
このようなリスクを避けるためにも、手形の支払期日と取立期限を常に把握し、計画的に銀行へ持ち込むことが重要です。
手形取立の最適なタイミング
手形取立には期限がありますが、その中でも、どのタイミングで銀行に持ち込むのが最適であるかについて解説します。
支払期日当日の取立が最適
手形取立において、支払期日当日に銀行へ持ち込むのが最も理想的です。なぜなら、手形は支払期日になって初めて支払いの義務が発生するため、この日に取立を行うことで、最も確実に資金回収ができるからです。
また、支払期日当日に取立を行うことで、資金化までの時間を最短にすることができます。企業の資金繰りにおいては、少しでも早く資金を回収することが重要であり、支払期日当日の取立は、その点でも優れています。
支払期日当日に取立を行うもう一つのメリットとして、取立忘れのリスクを最小化できる点が挙げられます。期限の3営業日目まで待つと、担当者の病欠や急な業務などで取立を忘れるリスクが高まります。
支払期日以降の取立
事情により支払期日当日に銀行へ持ち込めない場合でも、期日を含む3営業日以内であれば取立は可能です。しかし、できるだけ早い段階での持込が推奨されます。
例えば、支払期日が月曜日の場合、取立期限は水曜日までとなりますが、火曜日には持ち込むようにしましょう。最終日の水曜日まで待つと、突発的な事態で持込が困難になるリスクがあります。
また、取立期限が週をまたぐ場合は、特に注意が必要です。例えば、支払期日が金曜日の場合、取立期限は火曜日までとなりますが、週末を挟むことで、担当者が取立を忘れるリスクが高まります。このような場合は、社内でのリマインド体制を強化するなどの対策が有効です。
取立忘れのリスクを防ぐためには、手形の支払期日を事前に把握し、スケジュール管理を徹底することが重要です。カレンダーへの記入やリマインダーの設定など、自社に合った管理方法を確立しましょう。
手形取立の実務上の注意点
手形取立を確実に行うためには、いくつかの実務上の注意点があります。これらを押さえることで、取立忘れや期限切れのリスクを大幅に減らすことができます。
効果的な手形管理
手形を確実に管理するためには、システム化されたアプローチが効果的です。支払期日を社内カレンダーに明記するといった、基本的な対策から始めましょう。
具体的には、手形を受け取った時点で、その支払期日と取立期限を会社のカレンダーシステムに登録します。紙のカレンダーを使用している場合は、支払期日を赤字で、取立最終期限を青字で記入するなど、視覚的に分かりやすくすることも有効です。
また、手形管理台帳を作成し、受取日、振出人、金額、支払期日、取立予定日、取立完了日などを記録することで、複数の手形を一元管理することができます。最近では、手形管理専用のソフトウェアやアプリも多数存在するため、業務量に応じて導入を検討するとよいでしょう。
担当者が複数いる場合は、責任の所在を明確にし、定期的に手形の管理状況を確認する体制を整えることも重要です。万が一の担当者不在時にも対応できるよう、バックアップ体制も整えておきましょう。
銀行営業日と営業時間の確認
手形取立を行う際には、銀行の営業日と営業時間を事前に確認することが非常に重要です。特に祝日や年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇期間を挟む場合は、注意が必要です。
最近では、銀行によって営業時間が異なることも多く、支店によっては窓口営業時間が短縮されている場合もあります。また、一部の銀行では、土曜日に限定的なサービスを提供していることもありますが、手形取立に関しては、通常、平日のみの対応となっていることがほとんどです。
取引銀行の営業カレンダーや営業時間を事前に確認し、計画的に持込スケジュールを立てることで、期限切れのリスクを回避できます。特に、複数の金融機関を利用している場合は、それぞれの営業スケジュールを把握しておくことが大切です。
期限切れ時の対応
万が一、手形取立の期限を過ぎてしまった場合に備え、対応策も事前に把握しておくことが重要です。期日を過ぎた場合の回収方法をあらかじめ準備することで、資金回収の遅延を最小限に抑えることができます。
期限切れの手形については、振出人に直接連絡し、支払いについて協議する必要があります。その際、振込や現金による支払いを依頼することになります。振出人との良好な関係を維持するためにも、丁寧な対応を心がけましょう。
また、今後同様のミスを防ぐための社内体制の見直しも重要です。なぜ期限を過ぎてしまったのか原因を分析し、再発防止策を講じることで、手形管理の精度を高めることができます。
取立期限切れが頻発する場合は、手形管理の責任者を明確にする、デジタル管理ツールを導入する、定期的なチェック体制を強化するなどの対策を検討しましょう。また、将来的には、電子記録債権への移行も視野に入れると良いでしょう。
手形の資金化の流れ
手形の資金化は、単に銀行に持ち込むだけでなく、いくつかのステップを経て完了します。このプロセスを理解することで、資金計画をより精緻に立てることができます。
手形受取から資金化までの流れ
手形の資金化プロセスは、大きく分けて4つのステップから成ります。手形受取から資金化までの全体像を把握することで、スムーズな資金管理が可能になります。
第一段階は、「手形受取」です。取引先から約束手形を受け取る際には、金額、支払期日、振出人名などの記載内容を必ず確認しましょう。特に支払期日は、手形取立のスケジュール管理において最も重要な情報です。
第二段階は、「銀行への持込」です。支払期日当日、または、支払期日を含む3営業日以内に銀行窓口へ手形を持ち込みます。この際、取立依頼書などの必要書類を準備する必要があります。また、自社口座のある銀行と手形の支払場所が異なる場合は、取立手数料が発生することがあります。
第三段階は、「取立手続き」です。銀行が、手形交換所を通じて手形の取立手続きを行います。この過程では、振出人の口座から資金が引き落とされ、手形の正当性が確認されます。
最終段階は、「資金化」です。手続き完了後、手形金額が自社口座に入金されます。入金のタイミングは銀行によって異なりますが、一般的には取立手続き完了後、当日または翌営業日に入金されることが多いでしょう。
手形取立に必要な書類の準備
手形を銀行に持ち込む際には、いくつかの書類や準備が必要になります。必要書類をあらかじめ準備しておくことで、スムーズな取立手続きが可能になります。
まず必要になるのは、「取立依頼書」です。これは、銀行に手形の取立を依頼するための書類で、通常は銀行窓口に用意されています。手形番号、振出人、金額、支払期日などの情報を記入します。
次に、手形裏面への「裏書」が必要です。裏書とは、手形の所有権を譲渡するための記載で、会社名と社印(または代表者印)を押印します。裏書がない場合、銀行で取立手続きができないことがあるため注意が必要です。
また、銀行によっては、通帳の持参を求められることもあります。これは、特に入金口座の確認のためのものです。初めて取立を行う場合や、取立先の銀行と自社の取引銀行が異なる場合は、事前に必要書類を確認しておくと安心です。
さらに、銀行印(届出印)も必要になることが多いでしょう。取立依頼書には、通常、銀行印の押印が求められます。手形と合わせて印鑑も持参するよう心がけましょう。
入金までにかかる時間
手形を銀行に持ち込んでから実際に入金されるまでには、一定の時間がかかります。入金タイミングを正確に把握して資金計画を立てることが重要です。
一般的に、同一銀行内での取立(自行取立)の場合、支払期日当日に銀行窓口に持ち込めば、同日または翌営業日には入金されることが一般的です。これは、最も早いケースです。
一方、異なる銀行での取立(他行取立)の場合は、手形交換所を通じた処理が必要となるため、通常2〜3営業日程度かかることがあります。また、地域によっても手形交換のスケジュールが異なるため、地方の銀行間での取立では、更に時間がかかる場合もあります。
資金繰り計画を立てる際には、このような入金タイムラインを考慮し、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。特に、月末の支払いや重要な資金需要がある場合は、手形の入金タイミングを正確に把握しておくことで、資金ショートを防ぐことができます。
また、銀行によっては、取立手数料が発生する場合があります。特に他行取立の場合は、手数料が高くなることが多いため、資金計画を立てる際にはこのコストも考慮に入れましょう。
手形取立を適切に行うために知るべきポイント
手形取立には、様々な課題やリスクが伴います。これらを事前に認識し、適切な対策を講じることで、円滑な資金管理が可能になります。
取立忘れを防ぐための対応
手形取立における最大のリスクの一つが、「取立忘れ」です。複数のリマインダーシステムを活用することで、このリスクを大幅に軽減できます。
まず、デジタルカレンダーとアラート機能の活用が効果的です。手形を受け取った時点で、支払期日とその1〜2日前にリマインダーを設定します。Google CalendarやOutlookなどのツールを使えば、担当者のスマートフォンにも通知を送ることができます。
次に、手形管理専用の一覧表やスプレッドシートを作成し、定期的にチェックする習慣をつけることも重要です。この一覧表には、手形番号、金額、振出人、支払期日、取立期限、担当者などの情報を記載し、取立状況を「未取立」「取立済」などのステータスで管理します。
また、組織として「手形取立日」を設定するのも効果的です。例えば、「毎週月曜日は手形チェックの日」といったルールを設け、その日にすべての手形の状況を確認する習慣をつけることで、取立忘れのリスクを大幅に減らすことができます。
さらに、担当者が不在の場合のバックアップ体制も整えておくことが重要です。責任者を明確にし、不在時の対応フローを事前に決めておくことで、人的要因による取立忘れを防ぐことができます。
手形紛失時の対応
手形を紛失してしまった場合、適切な対応が必要です。紛失時の正しい手続きを知っておくことで、損失を最小限に抑えることができます。
手形紛失に気づいたら、まず振出人に連絡し、紛失の事実を伝えます。その上で、「公示催告手続」という法的手続きを行います。これは、裁判所に申し立てを行い、手形の無効を宣言してもらうプロセスです。
公示催告手続きでは、申立書を裁判所に提出し、裁判所が官報などで公示します。一定期間(通常は60日)経過後、除権決定が下され、手形が無効となります。この除権決定を持って、振出人に支払いを請求することができます。
ただし、この手続きには時間がかかるため、振出人との良好な関係がある場合は、話し合いによる解決も検討しましょう。例えば、紛失した手形の支払いを停止し、新たな手形を発行してもらうといった対応も可能です。
手形紛失のリスクを減らすためには、受け取った手形の保管方法も重要です。金庫など安全な場所に保管し、取立のために持ち出す際には細心の注意を払いましょう。また、手形の写しを取っておくことで、紛失時の対応がスムーズになります。
銀行休業日と支払期日が重なる場合の対応
手形の支払期日が銀行休業日と重なる場合には、特別なルールが適用されます。銀行休業日の前営業日が実質的な支払期日となるという点を理解しておきましょう。
手形法の規定により、支払期日が銀行休業日にあたる場合、その前営業日が実質的な支払期日となります。例えば、支払期日が日曜日の場合、前営業日の金曜日が実質的な支払期日となります。
この場合の取立期限も、実質的な支払期日から数えて3営業日以内となります。上記の例では、金曜日(実質的支払期日)、月曜日、火曜日の3営業日以内に銀行に持ち込む必要があります。
このルールは、特に連休前の支払期日に注意が必要です。例えば、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの長期休暇前の支払期日については、前倒しになることを念頭に置き、早めの対応を心がけましょう。
また、実質的な支払期日が前倒しになることで、振出人の資金準備が間に合わないリスクも考えられます。特に、新規取引先や資金繰りが厳しいと思われる取引先の場合は、事前に支払日の確認を行うことも検討すべきです。
まとめ
手形取立は、支払期日当日を含む3営業日以内に行う必要があり、この期限を過ぎると銀行での取立ができなくなります。最も効率的なのは、支払期日当日に銀行へ持ち込むことですが、やむを得ない場合でも期限内に確実に取立を行うことが重要です。日頃から支払期日のスケジュール管理を徹底し、確実な資金回収を心がけましょう。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
事業を運営する中で、迅速な資金調達が必要になることがあります。そのようなときに頼りになるのが、無担保無保証で利用可能であり、スピーディーな審査を特徴としているHTファイナンスのビジネスローンです。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、経営者の皆様の負担を大きく減らすことができます。
事業拡大のチャンスを逃さないためにも、まずはお気軽にHTファイナンスにご相談ください。