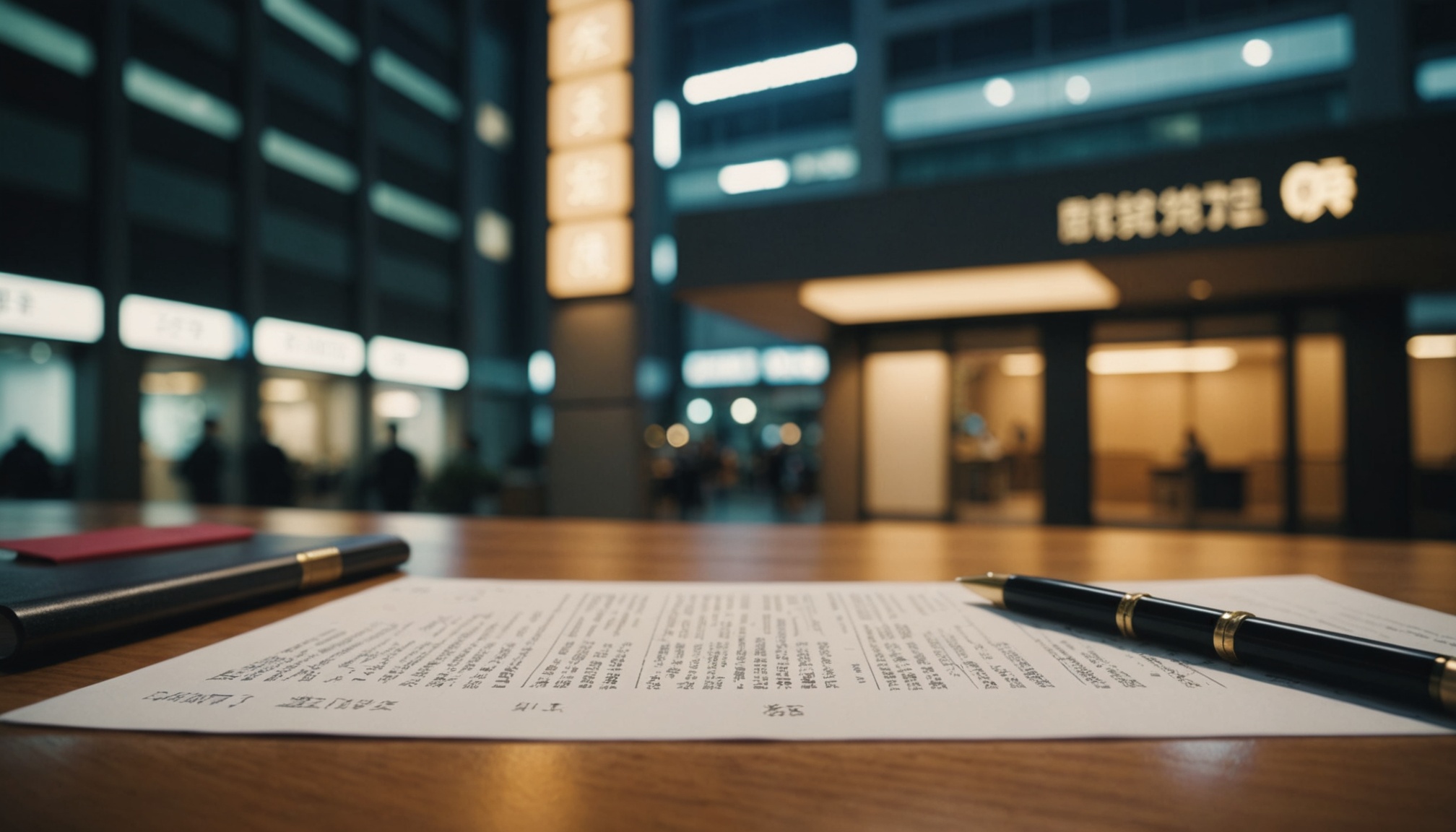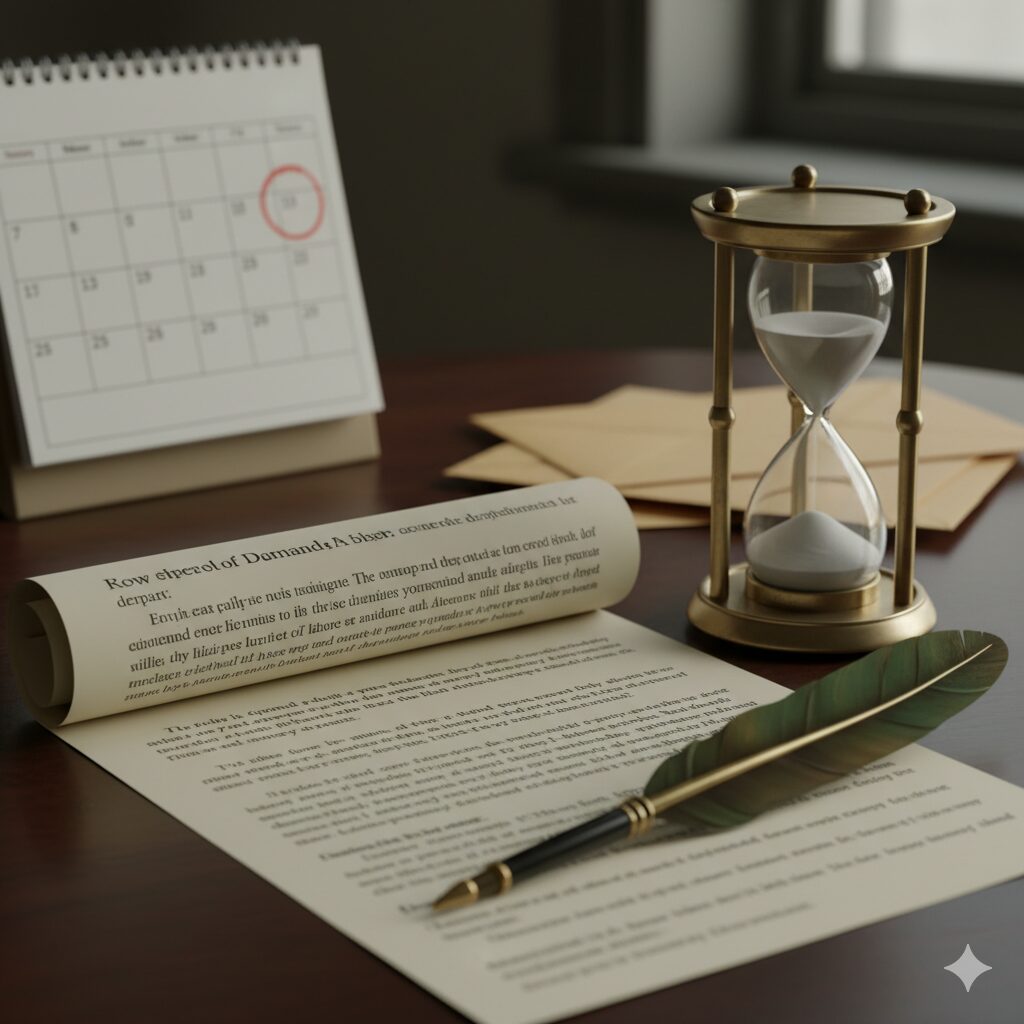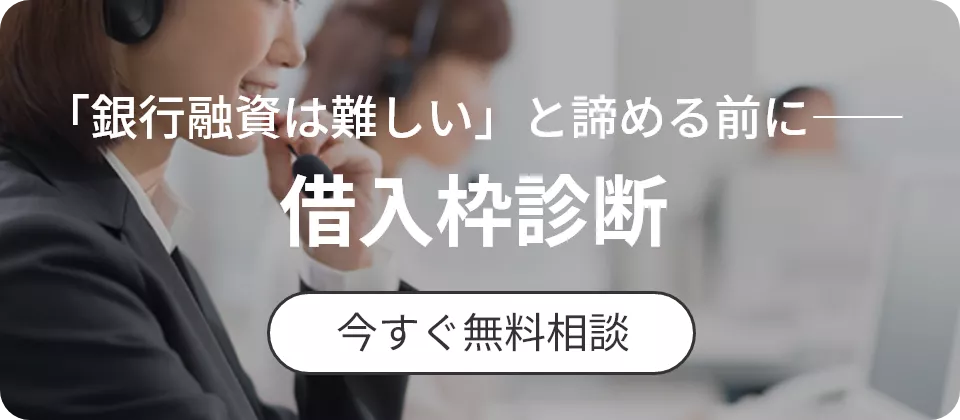公開日:2025.08.12
更新日:2025.08.12
相続税が支払えないときは?融資、相続放棄など、考えられる対応を解説
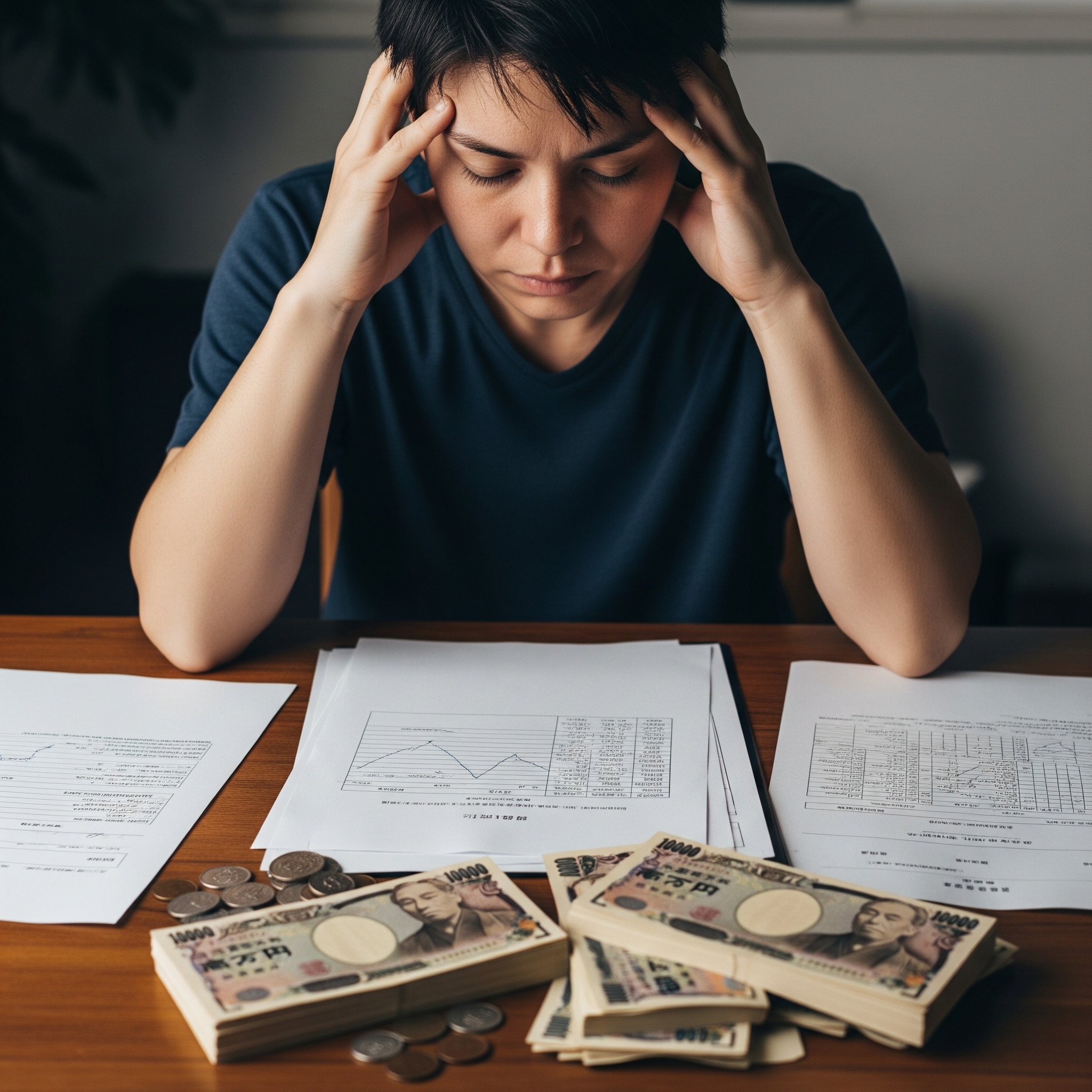
相続税の納付期限が迫っているにもかかわらず、手元に十分な現金がないために支払いが困難になることがあります。不動産や自社株式などのように、簡単には現金化できない資産を相続した場合、相続税の支払いに必要な資金が不足することは珍しくありません。相続税の支払いが遅れると延滞税が課され、最終的には財産が差し押さえられる可能性もあります。
この記事では、相続税を期限までに支払えない場合の具体的な対処方法を解説します。延納や物納制度の活用、金融機関からの融資の受け方、不動産売却による資金調達など、それぞれの方法のメリットやデメリット、具体的な手続きや必要書類についても詳しく説明します。
相続税が支払えない場合のリスク
相続税の納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限までに支払いができない場合、さまざまなリスクが発生します。
延滞税の発生
相続税の納付が期限を過ぎると、延滞税が課されます。延滞税の税率は年間約7.3%(令和5年時点)で、納付すべき税額に応じて日割りで計算されます。長期間支払いが遅れると、当初の税額に加えて、多額の延滞税が発生することになります。
例えば、相続税額が1,000万円の場合、1か月延滞するだけで約6万円の延滞税が発生することになります。延滞期間が長くなればなるほど、支払総額が膨らんでいくため、早急な対応が必要です。
財産の差押え
相続税の未納が続くと、税務署は督促状を送付します。それでも納付がない場合、最終的には、相続した財産が差し押さえられる可能性があります。差押えの対象となるのは、預貯金、不動産、有価証券などあらゆる財産です。
差押えられた財産は公売にかけられ、その売却代金が相続税の支払いに充てられます。公売は、市場価格より低い金額で売却されるケースが多く、資産価値を大きく損なう結果となることもあります。
また、差押えは信用情報にも影響するため、将来的な融資を受ける際にも不利になる可能性があります。このような事態を避けるためにも、納付期限内に何らかの対応をすることが重要です。
相続税の支払いに困ったときの対応
相続税の支払いに困った場合、いくつかの対応策があります。
延納制度の活用
延納制度とは、相続税を一定期間にわたって分割して支払うことができる制度です。納付すべき相続税額が10万円を超え、一時に納付することが困難と認められる場合に申請できます。
延納の期間は、相続財産の種類によって異なります。不動産や取引相場のない株式などが相続財産の大部分を占める場合は最長20年、それ以外の場合は最長5年の分割納付が可能です。
延納を申請するには、納付期限までに税務署に「相続税延納申請書」を提出する必要があります。また、延納期間中は利子税が発生する点に注意が必要です。令和5年の利子税率は、年1.6%程度となっています。
延納申請には、原則として担保の提供が必要です。相続した不動産や有価証券などが担保として認められますが、これにより資産の活用が制限される場合もあります。
物納制度の利用
物納とは、現金の代わりに相続した財産そのもので相続税を納付する制度です。延納をしても金銭で納付することが困難な場合に限り認められます。
物納できる財産には優先順位があり、国債や地方債などの有価証券が第一順位、不動産や船舶などが第二順位、株式や出資持分などが第三順位となっています。原則として、上位の順位の財産から物納に充てる必要があります。
物納を申請するには、納付期限までに「相続税物納申請書」と必要書類を税務署に提出します。物納申請が認められるかどうかは、財産の管理処分の難易度や将来的な価値変動リスクなどを考慮して判断されます。
物納の最大のメリットは、現金を用意する必要がない点です。しかし、物納される財産が時価よりも低く評価されるリスクもあります。特に、国が管理しにくい財産(権利関係が複雑な不動産など)は、物納が認められにくい傾向があります。
不動産売却による資金調達
相続した不動産を売却して、相続税の支払資金を調達する方法も一般的です。特に、相続した不動産に居住する予定がない場合や、複数の不動産を相続した場合は、売却を検討する価値があります。
不動産売却のメリットは、比較的まとまった資金を調達できる点です。ただし、売却までには一定の期間がかかるため、納付期限に間に合わない可能性がある点は考慮すべきです。
不動産の売却を検討する場合は、相続税の申告期限が迫っている状況では、一時的に融資を受けて納税し、その後売却代金で返済するという方法も選択肢となります。
また、不動産を売却する際には、譲渡所得税(キャピタルゲイン税)が発生する可能性がある点も忘れてはなりません。相続開始から3年10か月以内に売却する場合は、被相続人の取得費を引き継げる特例があるため、税理士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続税が支払えないときの融資による対応
相続税の支払いのために融資を受けることも有効な選択肢です。ここでは、金融機関からの融資について詳しく見ていきましょう。
銀行の相続税対応ローン
多くの銀行では、相続税の納付を目的とした専用ローン商品を提供しています。これらのローンは、一般的に「相続税対応ローン」や「相続税納税ローン」などと呼ばれています。
銀行の相続税対応ローンの特徴は、比較的低金利で融資を受けられる点です。一般的に、金利は年1.5%〜3.0%程度で、固定金利タイプと変動金利タイプがあります。
融資限度額は、金融機関によって異なりますが、500万円から数億円まで幅広く設定されています。返済期間は、通常5年から20年程度で、繰り上げ返済も可能な商品が多くあります。
銀行ローンの審査では、安定した収入があることが重視されるため、職業や年収などの情報が重要になります。また、担保として相続した不動産などを設定するケースも多いでしょう。
信販会社やノンバンクの融資
銀行以外にも、信販会社やノンバンク(消費者金融など)から融資を受ける方法があります。これらの金融機関は、銀行に比べて審査基準が比較的緩やかなケースが多いものです。
信販会社やノンバンクの融資の特徴は、審査が早く、担保不要で融資を受けられる場合があることです。しかし、銀行よりも金利が高く設定されており、年5%〜15%程度の金利が一般的です。
融資限度額は一般的に数百万円程度ですが、複数の金融機関を利用することで、必要な資金を調達することも可能です。ただし、過剰な借入れは返済負担が大きくなるため注意が必要です。
信販会社やノンバンクからの融資は、短期的な資金調達には有効ですが、長期的には金利負担が大きくなる点を考慮する必要があります。将来的に、相続した不動産の売却などで返済する予定がある場合の、「つなぎ融資」として検討するとよいでしょう。
親族からの借入れ
親族から資金を借りる方法も選択肢の一つです。親族間の借入れは、フォーマルな手続きが少なく、柔軟な返済条件で合意できる可能性があります。
親族からの借入れの場合、利息をつけない無利子での借入れも可能ですが、税務上の注意点があります。無利子または市場金利よりも著しく低い利率での貸付けは、貸主から借主への「経済的利益の供与」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
この問題を避けるためには、借用書を作成し、市場金利に準じた利息を設定することが望ましいものです。また、定期的に返済を行い、その記録を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
親族からの借入れは、金融機関の審査を通過できない場合の選択肢として有効ですが、家族関係に影響を与える可能性もあるため、返済計画をしっかり立てた上で検討することが重要です。
相続税のための融資における審査
相続税の支払いのための融資を受ける際には、金融機関の審査を通過する必要があります。ここでは、審査の基準や準備すべき書類について解説します。
審査で重視されるポイント
相続税のための融資審査では、いくつかの重要なポイントがあります。まず、申込者の返済能力が評価されます。これには、安定した収入や職業、勤続年数などが含まれます。
銀行やノンバンクでは、年収に対する借入れ金額の割合(年収倍率)が一つの基準となります。一般的には、年収の5〜7倍程度が融資の上限とされることが多いでしょう。
次に、申込者の信用情報も重要です。過去に債務の延滞や滞納があると、審査に通りにくくなります。信用情報機関に登録されている情報をチェックすることが一般的です。
また、担保となる資産の価値も審査の重要なポイントです。特に不動産を担保とする場合、その立地や市場価値、流動性などが評価されます。自社株を担保とする場合は、企業の財務状況や将来性が審査されることもあります。
必要書類
相続税の支払いのための融資を申し込む際には、以下のような書類が必要となります。
まず、本人確認書類として、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが必要です。また、収入を証明する書類として、源泉徴収票や確定申告書、給与明細書などが求められます。
相続税関連の書類としては、相続税の申告書や納付書、遺産分割協議書などが必要です。これらの書類により、実際に支払うべき相続税額や相続した財産の内容を確認します。
担保とする資産がある場合は、不動産の登記簿謄本や評価証明書、株式であれば株主名簿や財務諸表などが必要になります。事前に必要書類をリストアップして準備することで、スムーズな申込みが可能になります。
融資の申込み方法は、金融機関によって異なりますが、多くの場合はウェブサイトからの申込みや電話での仮審査の後、来店して正式な申込みと書類提出を行います。審査期間は、通常1週間から2週間程度ですが、金融機関や融資内容によって異なります。
審査通過のために押さえるべきポイント
相続税融資の審査を通過するためには、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、複数の金融機関に同時に申し込むことは避けたほうがよいでしょう。信用情報機関に多数の照会記録が残ると、信用リスクが高いと判断される可能性があります。
また、返済計画を具体的に立てておくことも重要です。相続した資産の売却予定や将来の収入見込みなど、どのように返済していくのかを明確にしておくと、審査担当者に対して返済能力をアピールできます。
さらに、担保となる資産がある場合は、その資産の価値を正確に把握しておくことも大切です。必要に応じて不動産鑑定評価書を取得するなど、資産価値を客観的に示す資料を用意することで、より有利な条件での融資を受けられる可能性が高まります。
審査に不安がある場合は、事前に金融機関の担当者に相談することも有効です。相続税の支払いは、多くの人が直面する課題であり、金融機関側も相談に乗ってくれることが多いでしょう。
その他に考えられる対応
ここまで紹介した延納、物納、融資以外にも、相続税が払えない場合には検討すべき特殊な対応策があります。状況によっては有効な選択肢となる可能性があるので、理解しておきましょう。
一部分割協議による対応
相続人が複数いる場合、相続税の納付に必要な現金部分だけを先に分割協議で決定する、「一部分割協議」という方法があります。これにより、相続税の納付期限までに、必要な現金を確保することが可能になります。
例えば、預貯金や現金などの流動性の高い資産を、相続税の支払いが必要な相続人に優先的に割り当て、不動産や株式などの換金しにくい資産については、後日改めて協議するという方法です。
この方法のメリットは、相続税の納付期限に間に合わせつつ、残りの財産分割を慎重に検討する時間が確保できる点です。特に事業承継が絡む場合など、財産分割に時間をかけて検討する必要があるケースで有効です。
ただし、一部分割協議を行う場合でも、相続人全員の合意が必要です。また、先に分割した財産と後から分割する財産の価値バランスなどを考慮する必要があります。将来的な分割協議がスムーズに進むよう、一部分割の段階でも専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続放棄による対応
相続財産よりも相続税額のほうが大きくなる可能性がある場合、相続放棄を検討する価値があります。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続税の納付義務も発生しません。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるため、相続財産や債務の状況を早期に把握することが重要です。
相続放棄のメリットは、相続税だけでなく被相続人の債務も引き継がなくて済む点です。特に、被相続人に多額の借金があるケースなどでは有効な選択肢となります。
ただし、相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。また、相続財産すべてを放棄することになるため、一部の財産だけを相続するといった選択はできません。さらに、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移るため、家族間の関係に影響を与える可能性もあります。
申告期限の特例の活用
通常、相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされていますが、特定の状況では、申告期限の延長が認められることがあります。
例えば、相続財産が確定していない場合や、災害などの特別な事情がある場合には、税務署長の承認を得ることで、申告・納付期限を延長できる可能性があります。
また、遺言書が発見されていなかったり、相続人間で遺産分割協議が長引いたりする場合には、「申告期限後申告」の特例を利用できることもあります。この場合、後から発見された財産についての追加申告が可能です。
さらに、相続税の納付が困難な特定の事業用資産については、納税猶予制度を利用できる場合があります。特に中小企業の事業承継では、自社株式等に係る相続税の納税猶予制度が適用できる可能性があります。
これらの特例や猶予制度は、適用条件が細かく定められているため、適用可能かどうかは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。状況によっては、大幅な納税負担の軽減や期限の延長が可能になる場合があります。
相続税の支払いに関する専門家への相談
相続税の支払いに関する対応策を検討する際は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。ここでは、どのような専門家に相談すべきか、また相談するタイミングについて解説します。
税理士への相談
税理士は、税務の専門家として、相続税の申告や納付に関する具体的なアドバイスを提供できます。特に、相続税の節税策や各種特例の活用方法に精通しており、状況に応じた最適な対応策を提案してくれます。
税理士に相談するメリットとして、まず相続財産の適正な評価が挙げられます。不動産や自社株などの評価方法は複雑ですが、適切な評価により相続税額が変わる可能性があります。
また税理士は、延納や物納の申請手続きをサポートしてくれます。必要書類の作成や税務署とのやり取りを代行してもらえるため、複雑な手続きを確実に進められるメリットがあります。
さらに、相続税の納付だけでなく、相続後の資産運用や将来の相続対策についても総合的なアドバイスを受けられます。財産の構成を見直すことで、次の世代への相続をスムーズにする提案も期待できます。
ファイナンシャルプランナーへの相談
ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人の資産設計や資金計画の専門家です。相続税の支払いに関しては、特に資金調達の方法や返済計画について、具体的なアドバイスを提供します。
FPに相談するメリットとして、まず、さまざまな金融商品やローンの比較検討が挙げられます。銀行や信販会社などの融資商品の中から、最適な選択肢を見つけるサポートをしてくれます。
また、相続税の支払いだけでなく、生活設計全体を考慮した返済計画の立案も期待できます。長期的な家計の視点から最適な資金計画を提案してくれるため、無理のない返済が可能になります。
さらに、FPは保険や投資などの金融商品にも詳しいため、相続した資産の活用方法や将来の資産形成についても、幅広いアドバイスを受けられます。相続税の支払い後の資産管理についても相談できる点が大きなメリットです。
まとめ
相続税の支払いに困った場合、延納や物納といった制度の活用、金融機関からの融資、相続財産の売却など、さまざまな選択肢があります。どの方法が最適かは、相続財産の内容や相続人の経済状況、将来の資産活用計画などによって異なります。
重要なのは、納付期限に間に合うよう早めに対応を検討することです。延滞税や財産差押えのリスクを避けるためにも、相続発生後はできるだけ早く専門家に相談し、自分の状況に最適な対応策を見つけましょう。延納や物納の申請は納付期限までに行う必要があり、融資を受ける場合も、審査に時間がかかることを考慮する必要があります。
最短即日の無担保無保証融資!HTファイナンスのビジネスローン
相続税の納付期限が迫っている場合など、急な資金調達が必要な状況では、迅速に利用できる融資サービスが有効です。中でも、無担保無保証で手続きも簡単なHTファイナンスのビジネスローンであれば、最短で即日の資金調達が可能になっています。
HTファイナンスは、東大法学部出身で三菱銀行での実務経験を持つ三坂大作が統括責任者として、企業の資金調達と経営戦略の支援に取り組んでいます。
銀行実務とコンサルティングで培った経験を活かし、無担保無保証の融資やファクタリング、財務改善など、お客様の経営課題に合わせた最適な解決策をご提案しています。また、スピーディーで柔軟な審査体制により、成長に必要な資金を迅速にお届けできます。
お申し込みに必要な書類は最小限に抑え、オンラインやお電話でのやり取りを中心に進めていますので、皆様の負担を大きく減らすことができます。
まずは、お気軽にHTファイナンスにご相談ください。