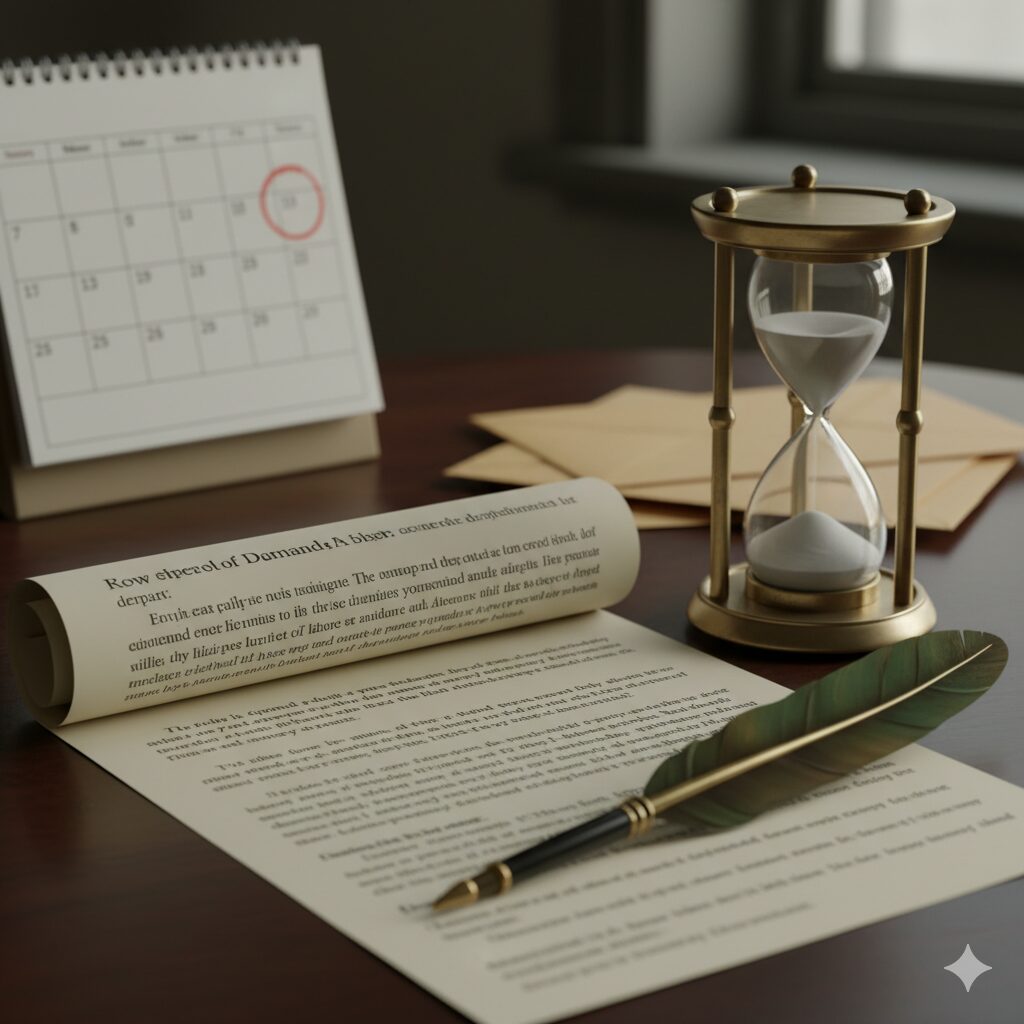公開日:2025.11.07
更新日:2025.11.07
中小企業の借入金利の平均はどのくらい?低めで借りるためのポイントも紹介

中小企業を経営していると、事業拡大や運転資金の確保のために、融資を検討することがあります。その際、借入金利の平均水準について把握した上で、融資を受ける必要があります。
借入金利は、企業の財務状況や金融機関によって大きく異なります。現在の中小企業の平均金利は、約1%以下で推移していますが、金融機関の種類や審査結果によっては、年率18%という高金利になることもあります。
本記事では、中小企業の借入金利の平均や金融機関別の金利目安、金利を低く抑えるためのポイントを詳しく解説します。また、金利上昇に備えた対策や、銀行以外の資金調達方法についても紹介しますので、効率的な資金調達の参考にしてください。
この記事のポイント
- 中小企業の平均借入金利は、近年**約1%以下**で推移しているが、金融機関や信用力によって大きく変動する。
- 金融機関別の金利目安は、民間銀行(0.9~15%)、政府系(約1~2%)、ノンバンク(3~18%)と幅広い。
- 低金利で借りるには「財務状況の改善」「具体的な事業計画」「金融機関との関係構築」が重要。
- 銀行融資が難しい場合、ファクタリングより**無担保無保証のビジネスローン**が将来的な信用構築にも繋がり推奨される。
自社の「適正金利」や「借入可能額」を知りたい方へ
銀行融資が難しい、または金利交渉にお悩みではありませんか?
HTファイナンスなら、無担保無保証で最短即日の資金調達が可能です。まずは無料の「借入枠診断」をお試しください。
中小企業の借入金利の平均
まず、中小企業が直面している借入金利の現状について確認していきます。
法人融資の金利幅と平均値
中小企業向けの法人融資における金利は、幅広い範囲で設定されています。一般的に、法人融資の金利は、年率1%から18%程度まで大きな幅があります。
日本銀行の統計によると、中小企業向け貸出の平均金利は、近年1%以下で推移しています。この数値は、主に銀行などの金融機関からの融資に基づいたものです。
ただし、この平均値はあくまで目安であり、実際の借入金利は企業の信用力によって大きく変動することを理解しておく必要があります。
金利に影響を与える主な要因
借入金利は、様々な要因によって決定されます。企業の財務状況は、その中でも最も重要な要素の一つです。売上高や利益率、自己資本比率など、財務指標が良好であれば、低い金利で融資を受けられる可能性が高まります。
また、業種やビジネスモデルも金利に大きな影響を与えます。安定した収益が見込める業種は、リスクが低いと判断されるため、比較的低い金利設定となることが多いものです。特に、顧客や市場に対して堅実な事業展開をしている企業は、金利面でも有利な条件を提示されやすいでしょう。
さらに、融資を受ける金融機関の種類によっても金利は異なります。一般的に、銀行などの預金取扱金融機関は、ノンバンクよりも低い金利で融資を提供しています。金融機関が提供する金利は、融資のリスクをどのように評価しているかにも影響されるため、選択する金融機関によって、条件が変わることも理解しておくと良いでしょう。
近年の金利動向と今後の見通し
日本では長らく低金利政策が続いていましたが、近年は金融政策の転換により、金利上昇の兆しが見られます。
2023年以降、日本銀行はマイナス金利政策の修正を検討し始め、市場金利にも影響が出始めています。このような金融環境の変化は、中小企業の借入金利にも影響を与える可能性があります。
今後数年間で金利が上昇傾向に転じる可能性があるため、中長期的な資金計画を立てる際には金利上昇リスクを考慮することが重要です。
金融機関別の借入金利の目安
借入を検討する際は、金融機関によって金利が大きく異なることを理解しておくことが重要です。
民間銀行の借入金利の目安
都市銀行や地方銀行などの民間銀行では、一般的に年率0.9%から15%程度の範囲で金利が設定されています。ただし、優良企業であれば、1%前後という低金利で融資を受けられることが多いでしょう。
都市銀行は、地方銀行と比較して若干金利が低い傾向にありますが、その分審査基準も厳しくなります。一方、地方銀行は、地域密着型の営業を展開しており、地元企業との関係性を重視する傾向があります。
民間銀行の特徴として、審査は厳格だが金利は比較的低めという点が挙げられます。財務状況が良好で事業計画がしっかりしている企業には、有利な条件で融資を提供することが多くあります。
政府系金融機関の借入金利の目安
日本政策金融公庫などの政府系金融機関では、一般的に年率1.08%から1.9%程度の金利が設定されています。これは、民間銀行の金利と比較しても低い水準です。
政府系金融機関の融資は、特に、創業期の企業や特定の政策目的に合致する事業に対して、優遇金利が適用されることがあります。例えば、環境対策や災害復興、海外展開などの分野では、特別な低金利プログラムが用意されています。
また、政府系金融機関では、財務基盤が十分でない中小企業に対しても、事業の将来性や社会的意義を評価して融資を行うケースがあります。政策金融機関は民間では対応しにくい分野をカバーする役割を担っています。
ノンバンク系金融機関の借入金利の目安
消費者金融やビジネスローン専門の貸金業者などのノンバンク系金融機関では、年率3%から18%程度の金利が一般的です。銀行や政府系金融機関と比較すると、金利は高めに設定されています。
ノンバンク系の特徴は、審査のスピードが速く、銀行では融資を受けづらい企業でも資金調達できる可能性がある点です。財務状況に課題がある企業や創業間もない企業でも、事業の将来性や担保・保証人の有無などを、総合的に判断して融資を行います。
ただし、高金利のため返済負担が大きくなるリスクがあります。短期的な資金ニーズには対応できますが、長期的な資金調達手段としては、慎重に検討する必要があるでしょう。
借入金利1%の違いが与える影響
一見小さく見える金利の差も、長期的には企業経営に大きな影響を与えます。
年間返済額への影響
金利の違いがどれほど返済額に影響するのか、具体的な数字で見てみましょう。例えば、5,000万円を5年間で借り入れた場合、金利が1%違うだけで返済総額は約130万円変わってきます。
さらに借入額が大きくなると、その差はより顕著になります。1億円の借入であれば、金利1%の差は年間で約100万円、5年間では約500万円の違いになります。
日銀の金融政策変更による0.25%の金利上昇だけでも、借入額3億円の企業では、年間約68万円の利息負担増加につながる可能性があります。小さな金利差が積み重なると大きな負担になることを認識しておくべきです。
経常利益への影響
金利の上昇は、企業の経常利益にも直接影響します。例えば、年商5億円、経常利益率4%(2,000万円)の企業が3億円の借入を行っている場合、金利が0.25%上昇すると、年間約68万円の追加コストが発生します。
これは経常利益の約3.4%に相当し、企業の収益性を圧迫する要因となります。特に利益率の低い業種では、わずかな金利上昇でも経営を圧迫する可能性があります。
さらに、金利負担の増加は新規投資や人材採用の抑制につながることもあり、長期的な企業成長に影響を与える可能性もあります。
資金繰りへの影響
金利の上昇は、月々の返済額増加につながるため、企業の資金繰りにも影響します。例えば、3,000万円を5年間で借り入れた場合、金利が2%から3%に上昇すると、月々の返済額は約12,500円増加します。
この金額は小さく見えるかもしれませんが、複数の借入がある場合や景気後退期には、この増加分が資金繰りを圧迫する要因になりえます。
特に季節変動が大きい業種や、売上サイクルと返済サイクルにギャップがある企業では、金利上昇による返済負担増加が資金ショートのリスクを高める可能性があります。
低金利で借入するためのポイント
金利負担を軽減するためには、事前の準備と戦略的なアプローチが重要です。
財務状況の改善
金融機関は、融資審査において、企業の財務状況を最も重視します。そのため、財務内容の改善は、低金利融資を受けるための基本です。
まず、自己資本比率の向上が重要です。自己資本比率が高いほど、企業の安全性が高いと評価されます。利益の内部留保や増資などを通じて、自己資本を増やす取り組みが有効です。
次に、収益性の向上も大切です。売上総利益率や営業利益率などの指標が良好であれば、返済能力が高いと判断されます。不採算部門の見直しや原価管理の徹底などを通じて、利益率を改善しましょう。
決算前に財務状況を整理することも効果的です。棚卸資産の適正化や売掛金の早期回収、不要な固定資産の処分などを行い、バランスシートを改善することで、金融機関からの評価が高まります。
具体的な事業計画の提示
融資を申し込む際は、具体的な事業計画を提示することが重要です。金融機関は、将来の返済可能性を重視するため、説得力のある事業計画があれば、低い金利での融資を受けられる可能性が高まります。
事業計画には、市場分析や競合状況、自社の強みなどを明確に記載しましょう。特に資金使途と投資回収計画は、具体的な数字で示すことが大切です。例えば、設備投資であれば、その設備によってどのように生産性が向上し、いつまでに投資回収できるかを明確にします。
また、リスク要因とその対策についても言及すると、金融機関の信頼を得やすくなります。複数のシナリオを想定した計画を準備することで、不測の事態にも対応できる企業という印象を与えることができます。
金融機関との良好な関係の構築
低金利融資を受けるためには、金融機関との良好な関係構築も重要です。日頃からのコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことで、融資条件が有利になる可能性があります。
定期的に、企業の状況や業界動向について情報共有を行いましょう。良い状況だけでなく、課題や懸念事項も率直に伝えることで、金融機関は企業の誠実さを評価します。
また、融資担当者が変わっても継続的な関係を維持できるよう、経営者だけでなく財務担当者も金融機関とのパイプを持つことが望ましいものです。金融機関を単なる資金提供者ではなくビジネスパートナーと位置づける姿勢が、長期的な関係構築につながります。
融資審査で必要な準備
融資を受けるためには、審査に必要な書類をしっかり準備することが重要です。
基本的な必要書類
融資審査に必要な基本的な書類には、企業の財務状況や事業内容を把握するために必要不可欠なものがあります。まず、決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)は、過去3期分が一般的に求められます。これらの書類を準備することで、金融機関は、企業の財務状態を正確に評価できます。また、法人税確定申告書や法人事業概況説明書も合わせて準備しておくと良いでしょう。
さらに、代表者の個人資産や負債状況を示す資料も求められる場合があります。代表者の確定申告書や資産負債明細書などを用意することで、融資審査がスムーズに進みます。
最新の試算表を提出することも重要です。決算から時間が経過している場合、企業の直近の財務状況を示すために、できるだけ新しい試算表を準備しておくことが求められます。これにより、金融機関に最新の情報を提供でき、信頼性が高まります。
事業計画書
低金利融資を受けるためには、単なる数字の羅列ではない、説得力のある事業計画書を作成することが重要です。事業計画書は、金融機関に対して、資金の使途と返済能力を明確に示すためのツールです。
事業計画書には、企業の基本情報や経営理念、事業内容の説明に加え、市場分析や競合状況、自社の強みなどを具体的に記載します。また、資金使途や返済計画、収支予測などの財務計画も詳細に示す必要があります。
特に重要なのは、資金調達の目的と効果を明確にすることです。例えば、設備投資の場合は、その設備によってどのように生産性が向上し、収益増加につながるかを、具体的な数字で示します。客観的なデータに基づく説得力ある計画を立てることが、金融機関の信頼を得るポイントです。
資金繰り表
融資審査において、資金繰り表は、企業の返済能力を示す重要な資料です。過去の実績だけでなく、今後の資金繰り予測を示すことで、返済計画の実現可能性を金融機関に理解してもらうことができます。
資金繰り表は、月次での収入と支出を詳細に記載します。売上の季節変動や大口支払いのタイミングなども明確に示し、資金不足に陥る可能性がある時期とその対策も記載するとよいでしょう。
特に重要なのは、返済計画との整合性です。新たな借入による返済負担が、月々の資金繰りに無理なく組み込まれていることを示す必要があります。緻密な資金繰り計画を提示することで返済能力を証明することが、低金利融資獲得の鍵となります。
金利上昇に備えた対策
近年の金融政策変更により、金利上昇の可能性が高まっています。企業としては、事前に対策を講じることが重要です。
固定金利と変動金利の適切な選択
融資を受ける際は、固定金利と変動金利のどちらを選択するかが重要な検討ポイントとなります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況に合わせて判断する必要があります。
固定金利は、借入期間中の金利が変わらないため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。金利上昇が予想される局面では、固定金利を選択することで、将来の金利上昇リスクを回避できます。
一方、変動金利は、現時点では固定金利より低く設定されていることが多いですが、市場金利の変動に応じて借入金利も変動するため、将来的に返済負担が増加するリスクがあります。
金利上昇局面では固定金利への借り換えを検討することも有効な戦略です。ただし、借り換えには手数料などのコストがかかる場合もあるため、総合的に判断する必要があります。
借入期間の調整と分散
金利上昇リスクに備えるもう一つの方法は、借入期間の調整と借入時期の分散です。すべての借入を同じタイミングで行うのではなく、時期や期間を分散させることでリスクを軽減できます。
例えば、設備投資などの長期資金は固定金利で調達し、運転資金などの短期資金は変動金利で調達するという組み合わせも考えられます。また、借入の更新時期が一時期に集中しないよう、計画的に借入時期を分散させることも重要です。
金利上昇が予想される局面では、長期の資金調達を前倒しで実行することも検討価値があります。借入のポートフォリオを多様化することで、金利変動によるリスクを分散させることができます。
資金調達手段の多様化
金利上昇リスクに備えるためには、銀行融資以外の資金調達手段も検討することが重要です。多様な資金調達手段を持つことで、金利変動の影響を受けにくい財務体質を構築できます。
例えば、リースやクレジットを活用することで、設備投資の初期負担を軽減できます。また、ファクタリングや売掛債権担保融資など、売掛金を活用した資金調達方法も検討価値があります。
さらに、自己資本の充実も重要です。内部留保の蓄積や増資などを通じて自己資本比率を高めることで、借入依存度を下げることができます。資金調達手段の多角化を進めることで、金利上昇時にも柔軟に対応できる体制を整えましょう。
銀行融資が通らない…でもファクタリングは避けたい経営者様へ
「銀行の審査が厳しい」「すぐに資金が必要」「ファクタリングは手数料が不安」
そのお悩み、HTファイナンスの「無担保・無保証ビジネスローン」が解決します。
金融機関での実務経験豊富な専門家が、貴社の状況に最適なプランをご提案します。
銀行以外の資金調達方法
(HTファイナンスなど)
金融機関から貴社へ資金を提供
(契約:金銭消費貸借契約)
貴社から金融機関へ元本+利息を返済
特徴:
・資金の「借入」である。
・返済実績が**信用情報として蓄積**される。
・金利は「年率」で計算される。
(ファクタリング会社)
貴社が持つ「売掛金」をファクタリング会社に売却し、手数料を引いた代金を得る。
ファクタリング会社が取引先から売掛金を回収する。(※2社間の場合は貴社経由)
特徴:
・資産(売掛金)の「売却」である。
・借入ではないため、**信用情報は蓄積されない**。
・手数料が「月利」や「1回ごと」で設定され、**実質年率が高額**になりやすい。
銀行融資以外にも、中小企業が活用できる資金調達方法は多様化しています。
ファクタリング
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を売却して即時に資金化する方法です。銀行融資と異なり、審査基準は企業の信用力よりも売掛先の支払能力が重視されるため、財務状況に課題がある企業でも利用しやすいという特徴があります。
ファクタリングには、売掛先に債権譲渡の通知をする3社間ファクタリングと、通知をしない2社間ファクタリングがあります。売掛先との関係を考慮して選択するとよいでしょう。
ファクタリングの手数料は、一見1%~10%程度と低く見える場合がありますが、これは月利や取引ごとの手数料であることが多く、年率に換算すると数十%になるケースも少なくありません。銀行融資の金利(年率)と比較する際は注意が必要です。 ファクタリングはあくまで売掛債権の「売却」であり「融資」ではないため、信用情報には影響しませんが、手数料負担が大きく、長期的な資金調達には不向きな場合があります。**審査期間が短く即日資金化できる**メリットはありますが、あくまで短期的な資金繰り改善手段と捉えるべきでしょう。
アセットファイナンス
アセットファイナンスとは、企業が保有する資産を活用して資金調達を行う方法です。不動産や設備、在庫などの資産を担保に融資を受けたり、資産そのものを売却して資金化したりする手法が含まれます。
例えば、セール・アンド・リースバックは、自社で保有する設備や不動産をリース会社に売却し、そのまま賃借することで資金を調達する方法です。バランスシート上の資産は減少しますが、即時に多額の資金を調達できるメリットがあります。
また、ABL(動産・債権担保融資)も有効な手段です。在庫や機械設備、売掛金などを担保に融資を受けることができます。保有資産の価値を最大限に活用することで、通常の融資よりも多くの資金を調達できる可能性があります。
ノンバンク系ビジネスローン
ノンバンク系金融機関が提供するビジネスローンは、審査基準が銀行よりも柔軟で、財務状況に課題がある企業でも利用できる可能性があります。特に、創業間もない企業や急速に成長している企業にとって、有効な選択肢となります。
ノンバンク系ビジネスローンの特徴は、審査スピードの速さと柔軟な融資条件にあります。最短で即日融資が可能なサービスもあり、急な資金需要に対応できます。
金利は銀行融資と比較すると高め(年率3%~18%程度)ですが、これは銀行が対応しにくいリスク(無担保・無保証など)を引き受けるためです。しかし、ファクタリングの実質年率と比較した場合、中長期的な利用ではノンバンク系のビジネスローンの方が総コストを抑えられる可能性があります。
特にHTファイナンスが提供するような無担保無保証のビジネスローンは「融資」であるため、**着実な返済実績を積むことで企業の信用力が向上し、将来的な銀行融資の条件改善にもつながる可能性があります。急な資金需要への対応と、将来の信用構築の両面で戦略的な活用が求められます。まとめ
中小企業の借入金利は、現在平均1%以下で推移していますが、金融機関の種類や企業の財務状況によって大きく異なります。民間銀行では0.9%~15%、政府系金融機関では1.08%~1.9%、ノンバンク系では3%~18%が一般的な金利帯です。
借入金利を低く抑えるためには、財務状況の改善や具体的な事業計画の提示、金融機関との良好な関係構築が重要です。また、金利上昇に備えて、固定金利と変動金利の選択や借入期間の調整、資金調達手段の多角化も検討すべきでしょう。今後の金融環境の変化に対応するためにも、自社に最適な借入戦略を構築し、定期的に見直していくことをお勧めします。
最短即日の無担保無保証融資なら
HTファイナンスにお任せください
中小企業の資金繰りや急な資金需要に、銀行融資のスピード感では間に合わないケースが多くあります。
HTファイナンスのビジネスローンは、無担保・無保証で利用でき、柔軟な審査基準と迅速な対応が強みです。
元銀行員である統括責任者(三坂)をはじめ、金融のプロが貴社の事業性を正しく評価し、最適な資金調達をサポートします。事業拡大のチャンスを逃さないためにも、まずはお気軽にご相談ください。