創業支援融資が借りられない!!
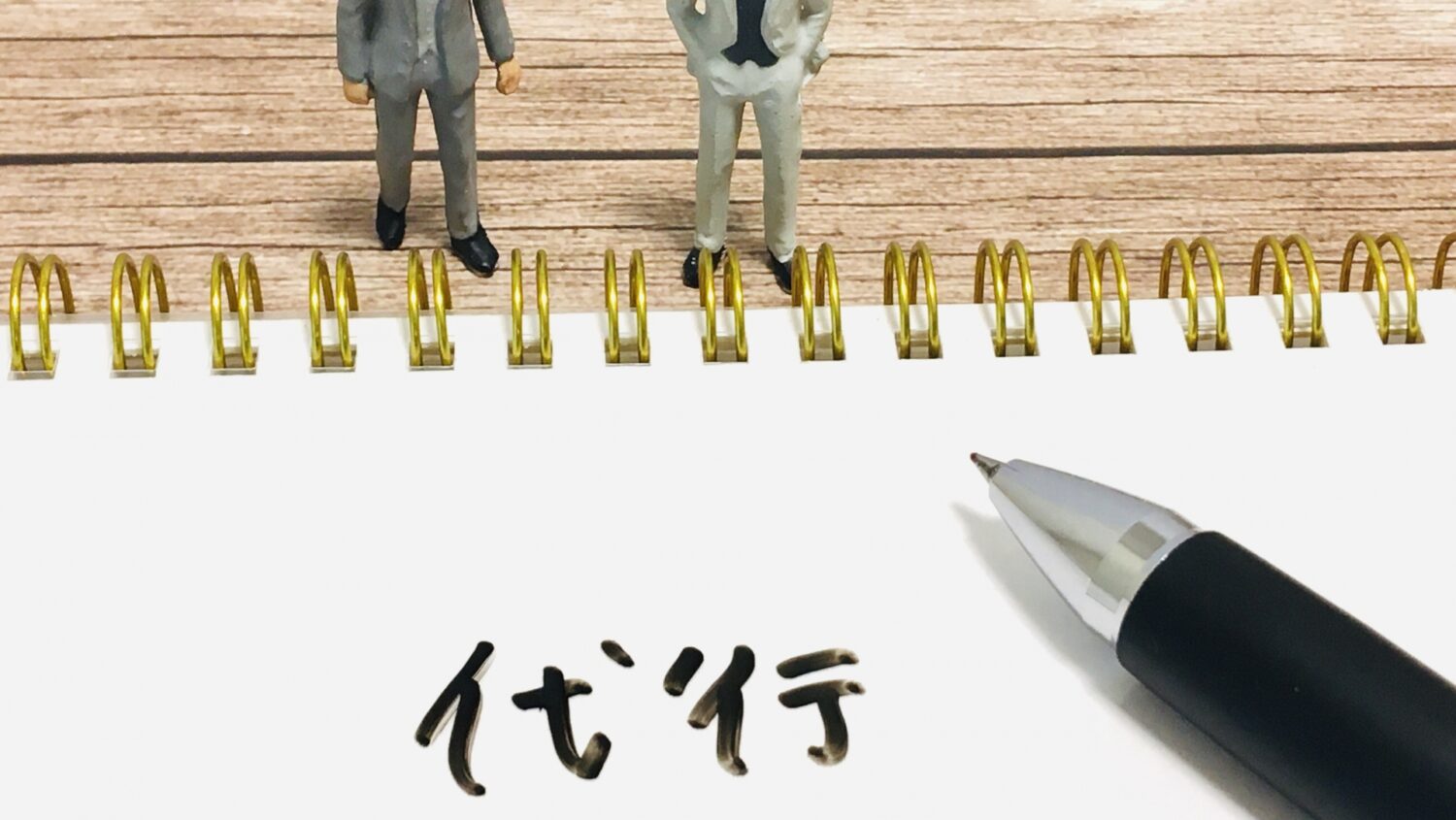
創業支援融資は、新たに事業を始めようとする起業家や中小企業者にとって、重要な資金調達手段の一つです。創業期は、事業計画を実行に移すための資金が不足しがちで、特に自己資金が限られている場合には、外部からの資金調達が必要不可欠です。そんな中で、創業支援融資は、事業をスタートさせるための一助となり、ビジネスの成功へと繋がる可能性を秘めています。しかし、現状の創業支援融資にはさまざまな課題も存在します。今回は、創業支援融資の現状、課題、そして今後の展望について詳しく解説していきます。
創業支援融資とは?
創業支援融資とは、主にこれから事業を立ち上げようとする個人や法人に対して、金融機関や政府系機関が提供する融資のことを指します。事業の運転資金や設備投資など、創業初期に必要となる資金を借り入れるための手段であり、借入条件は比較的緩やかであることが特徴です。
日本においては、政府系金融機関や地方自治体などが提供する創業支援融資が多く、起業家や中小企業向けの融資制度も豊富に存在しています。その中でも代表的なものには、以下のような制度があります。
1-1. 日本政策金融公庫(JFC)の創業融資
日本政策金融公庫は、創業支援融資を提供する最大の機関であり、創業したばかりの企業にとっては、非常に利用しやすい融資先です。特に、創業資金を借り入れる際には、担保や保証人を求めない場合が多く、低金利で融資を受けることができるため、多くの起業家が利用しています。
1-2. 地方自治体の創業支援融資
各地方自治体でも、地域経済の活性化を目的とした創業支援融資を行っているところがあります。自治体ごとに支援内容が異なるため、地域の特性に応じた融資制度が提供されています。例えば、地方創生や地域の特産品を使った事業を行う場合、自治体独自の低金利融資や助成金が提供されることがあります。
1-3. 民間金融機関の創業支援融資
民間の銀行や信用金庫、信用組合なども創業支援融資を提供しています。日本政策金融公庫に比べると金利がやや高い場合もありますが、柔軟な条件で融資を受けられる場合もあり、民間金融機関との取引実績がある場合には、スムーズに融資を受けることができることがあります。
創業支援融資の利用状況
近年、起業家支援の動きが活発になり、多くの創業支援融資の利用者が増加しています。特に、若年層や女性の起業家が増えており、創業支援融資の需要は高まっています。政府や地方自治体の支援も充実しており、融資制度はますます多様化しています。
2-1. 近年の創業者数の増加
特に新型コロナウイルスの影響で、多くの人々がフリーランスや自営業を選択し、起業するケースが増加しました。政府や自治体は、そのような起業家を支援するために、創業支援融資や助成金を拡充し、起業の敷居を低くする取り組みを強化しました。結果として、創業支援融資の利用者数は増加傾向にあり、特にITやサービス業を中心に新規事業が多く立ち上げられています。
2-2. 銀行の融資状況
従来の銀行の融資審査は、創業初期の企業にとっては厳しいものでしたが、最近では銀行も創業支援融資を積極的に行うようになり、特に事業計画書の内容に重点を置いた審査が行われています。金融機関が求める事業計画は、過去の実績に基づいたものよりも、将来のビジョンや市場分析、収益モデルの明確さが重要視されています。そのため、これから事業を始めようとする起業家にとっては、事業計画書の作成が融資を受けるためのカギとなります。
創業支援融資の課題
創業支援融資の利用は進んでいるものの、依然としていくつかの課題があります。
3-1. 審査の厳格さ
創業支援融資に関しては、政府系金融機関でも審査が厳しく、資金調達が難しいと感じる起業家も少なくありません。特に、過去に事業経験がない場合や信用履歴が不十分な場合には、融資を受けることが難しい場合があります。創業期の企業は、どれだけ素晴らしいビジネスアイデアを持っていても、実績がないため、融資審査が通りづらいという現実があります。
3-2. 融資金額の限度
創業支援融資は、基本的には少額の融資が主流です。例えば、日本政策金融公庫の創業融資は、融資金額に上限が設定されており、事業を始めるための資金としては十分な金額ではない場合もあります。特に、製造業など設備投資が必要な事業の場合、融資金額が不十分であると感じることがあります。
3-3. 起業家の認識不足
起業家が創業支援融資の利用方法や申請手続きに不慣れなことも多く、情報収集不足が原因で支援融資を利用できないケースもあります。事業計画書の作成や審査のポイントについて十分に理解していないことが、融資を受けられない一因となることもあります。また、申請手続きが煩雑であると感じることも、融資申請をためらう原因となっています。
今後の展望と解決策
4-1. より柔軟な融資制度の導入
今後、創業支援融資の審査基準がさらに柔軟になることが期待されています。特に、社会的インパクトの大きい事業や革新的なビジネスモデルを持つ企業に対しては、今後も融資制度が拡充される可能性があります。また、地方自治体においても、地域経済を活性化させるために、地域特性に合わせた柔軟な融資制度がさらに増えていくことが予想されます。
4-2. 起業家教育の強化
創業支援融資を有効に活用するためには、起業家自身のビジネススキルや知識が重要です。起業家教育や支援プログラムがさらに充実し、事業計画書の作成支援や融資審査を通過するためのノウハウを学ぶことができる機会が増えれば、創業支援融資の利用率は高まるでしょう。
4-3. 資金調達の多様化
創業支援融資以外にも、クラウドファンディングやエンジェル投資家からの支援を受ける方法もあります。これらの方法と創業支援融資を組み合わせることで、より多くの資金を調達することが可能です。今後は、資金調達手段の多様化が進むことで、起業家が自分に合った方法で資金調達を行うことができるようになるでしょう。
まとめ
創業支援融資は、起業家にとって事業のスタートを切るために非常に重要な資金調達手段であり、政府系金融機関や民間の金融機関によって多くの支援が行われています。しかし、審査基準の厳しさや融資金額の限度、起業家の認識不足など、いくつかの課題も存在します。今後は、より柔軟で多様な融資制度が導入され、起業家教育の充実や資金調達手段の多様化が進むことで、創業支援融資の利用がさらに広がることが期待されます。
ヒューマントラスト株式会社では、2期目以降の法人様を対象に、多種多様な資金調達のサポートをエージェントさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談お待ちしております。
支援実績12,000社以上!ヒューマントラストの資金調達トータルサポート
ヒューマントラストは、これまで12,000社を超える法人・個人事業主様の資金調達を支援してきました。
個人事業主専門ファクタリングやビジネスローン、銀行融資・法人ファクタリングの調達支援などをワンストップでご提供しており、最短即日での現金化や融資にも対応しています。
とくに、売掛先へ通知しない2社間ファクタリングは、最短15分ほどで資金をご用意できるため、急な経営ニーズにも柔軟に対応可能です。
必要書類も最小限に抑え、オンラインやお電話でのお手続きを中心に進められますので、遠方にお住まいの方やお忙しい経営者の方でも気軽にご利用いただけます。
まずは専門スタッフが状況を丁寧にヒアリングし、それぞれに最適なプランをご提案いたしますので、資金繰りにお困りの際はぜひヒューマントラストまでご相談ください。

