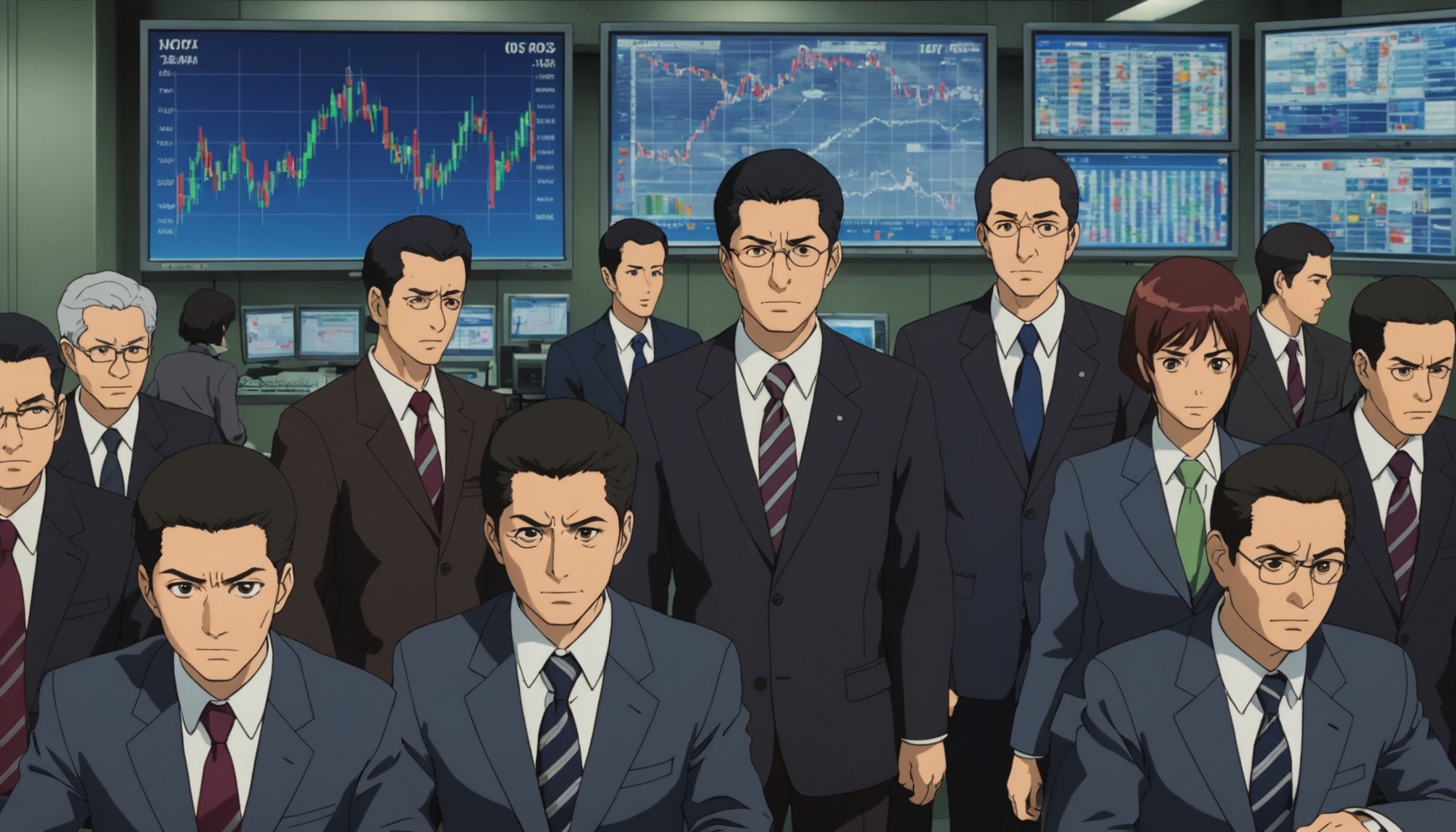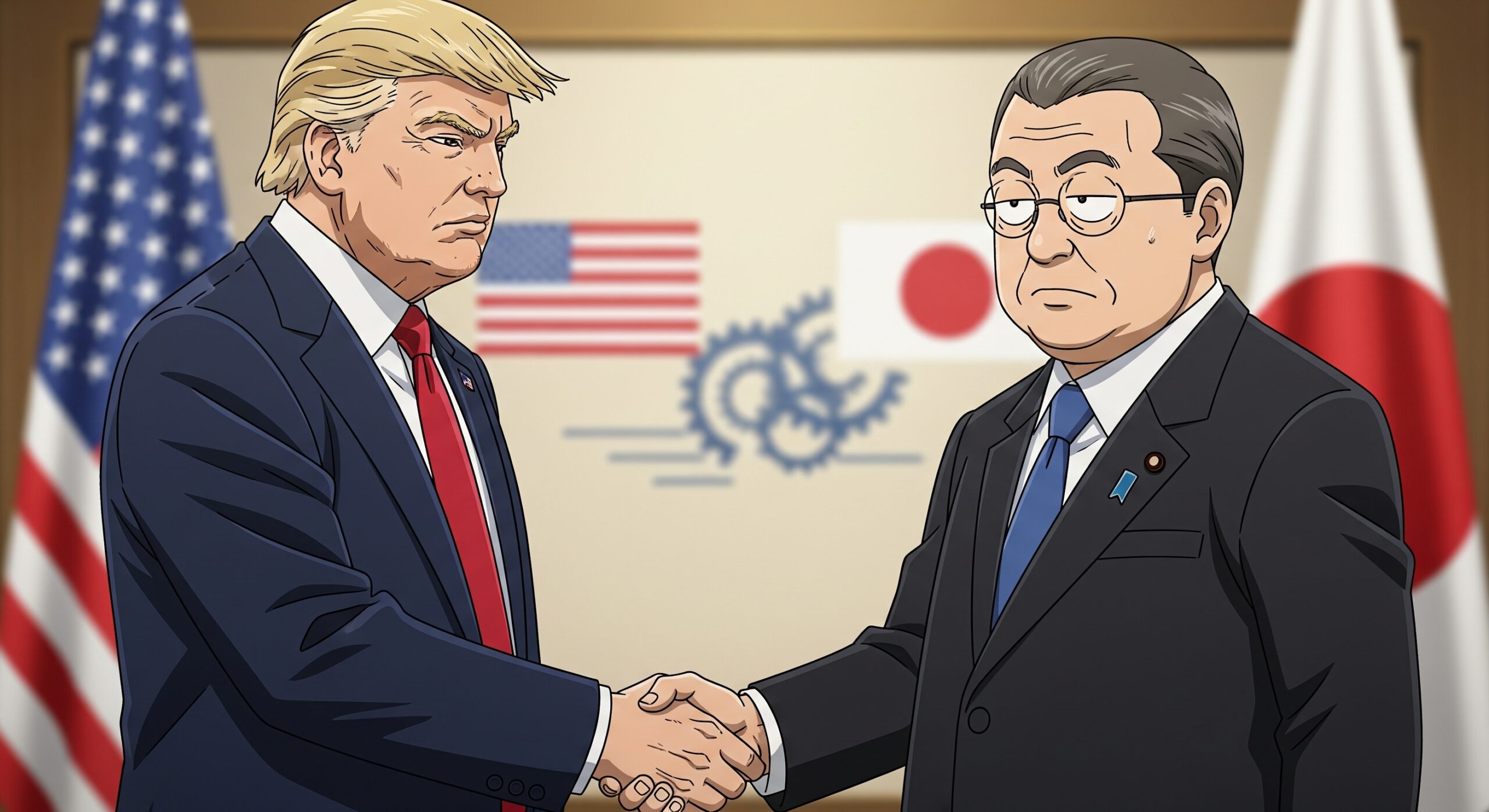公開日:2025.05.26
更新日:2025.05.27
日本の経済状況とMMTの適用可能性
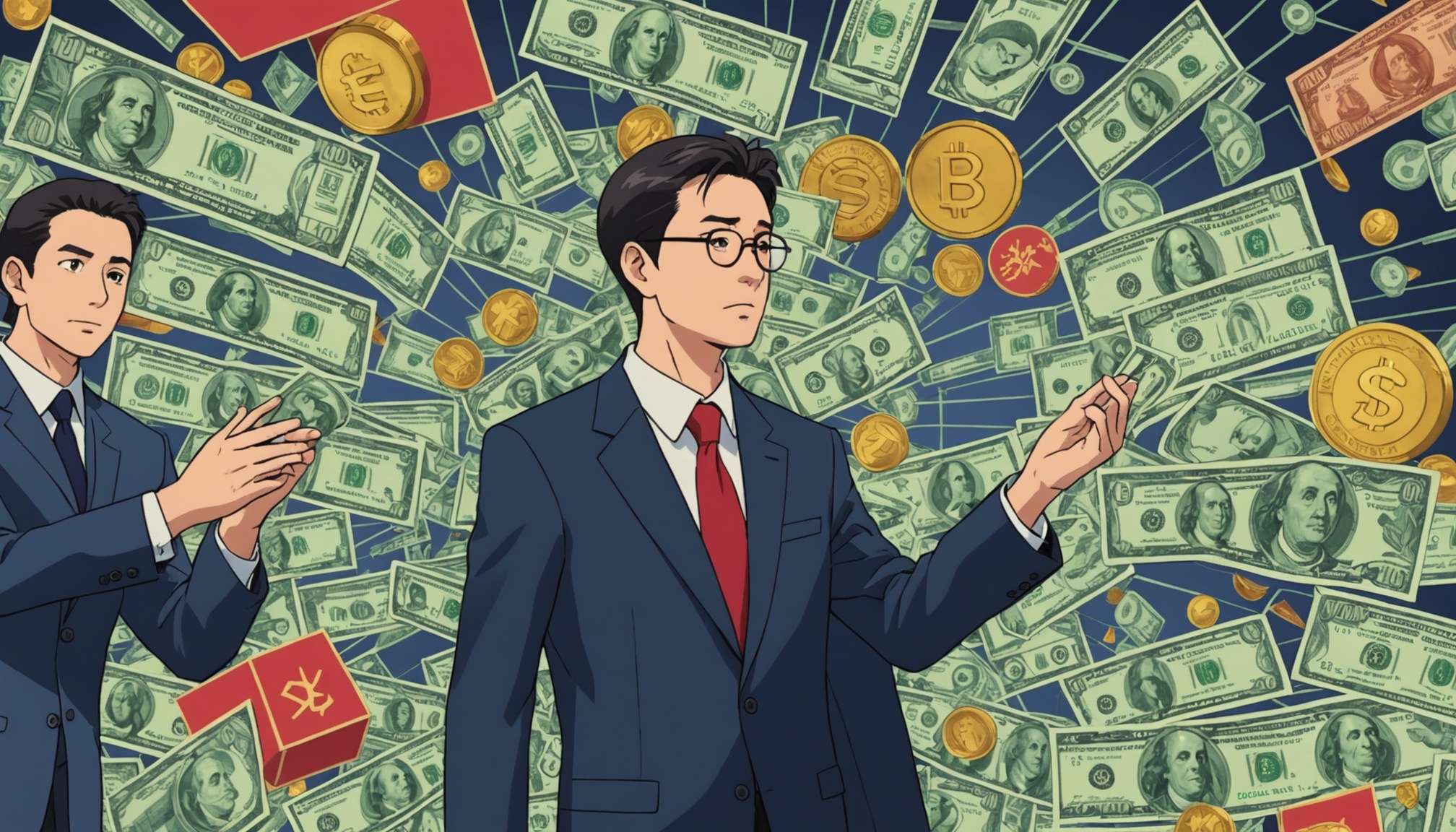
MMT概論
MMTの歴史
MMT(現代貨幣理論:Modern Monetary Theory)は、20世紀後半から21世紀にかけて発展した経済理論で、特に2008年のリーマンショックに続く世界金融危機以降、注目を集めました。MMTの理論的なルーツはケインズ経済学(1930年以降:政府支出による有効需要創出)、チャートリズム(1905年:貨幣は国家が発行し、税によって貨幣価値が決まる)、ファンクショナリズム財政論(1940年代:政府財政は経済全体の需要調整機能が重要である)と言われており、かなり歴史は長いと言えます。こうした理論的背景をベースとして、1990年代に理論体系が整備されました。このMMTは、2008年のリーマンショックの後、「財政赤字を気にせずに政府が国内需要・景気を下支えするべき」という議論の根拠理論になったのです。特に当時のアメリカの民主党進歩派の政策に影響を及ぼしたと言われています。その後コロナパンデミックに対応するために、各国政府が財政支出を拡大するMMT的政策を実行しました。ポストコロナの現状では、「現在のインフレ(物価上昇)はMMT的政策の結果」だという批判があります。その意味では、日本の現在の「財務省解体論」や「消費税減税」と言った主張は、MMTによって理論武装出来る側面があるのです。
MMTによる論理的主張とは?
このMMTの基本的な主張は、次のようになります。
- 政府は自国通貨を発行できる限り、財政赤字を問題視する必要はない。
- 税は財源ではなく、インフレ調整や通貨価値維持のために必要。
- 完全雇用を目指し、インフレについては税制や政策によりコントロールする。
さらに、MMTは「国が自国通貨で国債発行が可能であれば、借金(財政赤字)を心配しすぎる必要はない」という考え方を特徴としています。簡単に言うと、
- 国はお金を作れる
国(たとえば日本政府)は、自国通貨(日本円)を発行できるので、理論上「お金が足りないから破産する」ことはない。
- 税金は“財源”ではなく“物価調整”のため
MMTでは、税金は政府支出のためというよりも、インフレ(物価の上昇)を抑えるための機能で活用する手段である。
- 財政赤字は悪ではない
政府が支出を増やして経済を活性化し、雇用が増えるなら、財政赤字(借金)があってもよい。
以上の具体例としては、「不況で失業者が多いときに、政府が公共事業を増やして人を雇えば、経済が元気になる。政府は借金をしてでもそれをやるべき。」というのがMMTの立場になります。
| 誤解・批判 | MMTの考え |
|---|---|
| 国の借金が多いと破綻する? | 自国通貨建てなら破綻しない |
| 無限にお金を刷るとハイパーインフレになる? | インフレが起きたら税金で抑える |
| 借金は将来世代にツケを回す? | 今の経済を良くすることで将来も助ける |
このようにMMTは、「政府はもっと積極的にお金を使って経済や消費者を支えるべき」と主張する新しい経済理論です。特に不況や雇用不足のときに注目されています。
ただし、すべての場面で万能ではなく、「貨幣の供給過剰によってインフレになりすぎたらどうするか」などの課題があると言われています。
こうしたMMTを現在の参議院選挙前の日本の状況に照らして検証してみましょう。
日本の経済状況とMMTの適用可能性
日本では長引く経済停滞が話題に上がる一方、近年はインフレ率が上昇傾向を見せています。これに伴い、政府による経済対策や財政政策が注目されており、「物価高対策」や「消費税減税」「ガソリン暫定税率廃止」など、具体的な対応策への期待が高まっています。こうした中、MMT(現代貨幣理論)が再注目されています。MMTは既述の通り、政府債務を自国通貨でまかなえる国は財政出動に強みを持ち、過度なインフレを引き起こさない範囲なら支出を拡大できると主張します。この考え方は強力な「インフレ対策」とも捉えられますが、実際に日本で適用するには慎重な経済状況の分析が必要だと言えます。
日本経済の30年を振り返る
日本は1980年代にバブル経済を迎え、国内総生産が世界的にも高水準で推移していました。しかし、その後のバブル崩壊で、多くの投資が焦げ付いて国民の資産価値が下落し、日本全体の「経済成長戦略」が急速にしぼみ、大きな経済成長方針の転換が必要となりました。1990年代から2000年代初頭は、失われた10年、失われた20年と呼ばれ、企業も個人消費も伸び悩むデフレ状況が続きました。当時の政権や財務省は景気刺激のための「金融政策」や「経済刺激策」を打ち出しましたが、大胆な「財政出動」をためらった面もあります。当時の政策決定の背景と、当時からすでに言われていた「消費者物価指数」の推移や「インフレ対策」が現在の物価高とどのような連関があるのか検証する必要があると言えます。
経済成長の停滞期とその背景
まず、日本の経済成長が停滞していた大きな背景として、バブル経済の崩壊後に企業が過度な債務整理に追われた点が挙げられます。銀行の不良債権処理に伴い貸し渋りが広がり、必要な設備投資も控えられました。その後、雇用の調整や賃金の伸び悩みによって消費が低迷し、日本全体で「経済危機対応」の遅れが指摘されました。また、世界的な産業構造の変化に追随できず「経済指標」も低迷し、多くの国民が経済成長への実感を失っていったのです。
バブル崩壊後の影響と政策変遷
バブル崩壊後、政府は多面的に「金融政策」を活用しようとしましたが、名目金利の引き下げだけでは限界が見えました。続いて、公共事業主体の財政支出を行う「財政政策」を中心とする経済対策が打ち出されます。ただし、多くの財政出動が不十分な箇所に配分されたとも言われ、思ったほど成果が出なかったのです。この時期を通じて日本政府の経済政策は慎重になりすぎる傾向にあり、インフレを恐れるあまり経済成長の機会を逃したとの指摘もあります。
現在の物価高の原因と特徴
近年の物価上昇の原因は海外要因と国内要因が絡み合った結果と考えられます。特に、エネルギー価格や原材料価格の国際的な上昇に加え、国内の人件費アップや円安による輸入コスト増大も要因です。その一方で、消費者が価格上昇を許容しつつある状況もあり、企業は値上げをしやすくなっています。こうした国内需要と国際情勢の変化が、日本における物価高の加速を後押しした側面があります。この物価高はコストプッシュ型インフレと言われ、根本的な原因は、製品・商品・サービスの原価上昇を価格転嫁した結果だと言えます。ここで、政策立案者がまず理解すべきは、今回の物価高が一時的なものなのか、ある程度持続するインフレ傾向なのかという点です。市民の「減税要望」や「物価高対応」を検討するうえでも、現状を正確に見極める必要があります。
国内外の要因とその相互作用
まず、エネルギーや食料品など生活に必要な輸入品の値段上昇が、原油価格や国際物流の混乱に伴って深刻化しています。国内では人口減少と人手不足も相まって、人件費を引き上げざるを得ない企業も多く、これらが総合的に価格へ転嫁されやすい状況を作り出しています。加えて、円安が進行すると輸入コストがかさみ、日本のインフレ率はさらに上昇しやすくなっています。こうした複数の要因が合わさって「物価指数」に影響を与えているのです。
インフレの現状と経済への影響
一連の複合的な物価上昇の原因によって、消費者物価指数は直近で上昇傾向を見せ、企業も製造コスト高を価格に反映しやすくなっています。一見、デフレ状態からの脱却に見えますが、賃金の上昇が物価と同じ水準で進んでいなければ、実質的な購買力が下がり、個人消費が落ち込むリスクがあるのです。これが、「手取りを増やせ」という主張につながります。「政府債務=国債発行高」の拡大が心配される場面でもありますが、現実には経済成長を伴わないインフレでは「経済安定」が遠のく恐れがあると言えます。
MMTの理論と現状の政策とのズレ
MMT(Modern Monetary Theory: 現代貨幣理論)では、通貨発行権を持つ政府が主権通貨建ての国債を発行できる限り、理論上は大規模な財政政策が可能だと説明されます。一方で政府の経済対策は、インフレを過度に警戒するあまり、大胆な減税措置や積極的な財政出動を避ける傾向があります。両者のズレは経済学者や政策提案を行う専門家の間でも度々議論になっています。特に、日本でMMTを適用すると、失われた成長期を取り戻すために、一気の財政注入が検討される可能性がありますが、同時にインフレ対策との整合性が問われます。
MMTの基本概念とその適用性
MMTの主眼は、自国通貨を発行できる政府が適切にお金を供給すれば、失業や景気後退を軽減できるという点にあります。ただし、そのお金の使い道が無計画であれば、必要以上の流動性が市場に供給されてマイルドなインフレどころか、急激なインフレに傾くリスクもあります。したがって、MMTを実践するには、公共投資や設備投資の優先度をきめ細かく設定し、中長期 経済計画の視点を持つ必要があります。
現行政策との比較分析
現状の日本政府の経済政策は、インフレ率がやや上昇している段階で、財政赤字の拡大を警戒する姿勢にあります。そのため、積極的な「財政出動」を主張するMMTの立場とは乖離があるのが現状です。特に「減税要望」が根強い世論に対して、現行政策では大幅な税制変更を躊躇する動きも見られます。今後の「経済予測」から考えても、再度のデフレに陥るリスクと、インフレがコントロール不能になるリスクをどう両立させるかが命題となるのかもしれません。
政府や財務省が考慮すべき政策提案
ここでは短期レベルと中長期レベルに分けて政府の経済対策を具体的に検討してみます。日本は世界的なサプライチェーンの変動に影響を受けやすいため、臨機応変な「短期経済対策」と「中長期経済計画」の両方が不可欠です。短期的には「物価高対応策」として、消費者負担を軽減する施策や、輸入原材料への補助金が検討されています。中長期的には、産業構造を成長分野にシフトさせるための「経済成長戦略」が求められます。
短期レベルでの対応策
第一に、輸入コスト増大による価格転嫁を緩和するため、エネルギー関連や基礎的な食料品への補助金やポイント還元を導入する手があります。また、生産者側のリスクを軽減する金融緩和政策や融資枠の拡大も有効でしょう。こうした取り組みは即効性が高く、国民が感じる負担を減らす効果が期待できます。加えて、消費税減税についても「減税要望」が強い社会状況を踏まえて検討するべきでしょう。
中長期的な戦略の構築
中長期的には、企業のイノベーション促進を目指す経済成長戦略がカギとなります。ITや環境技術など、世界的競争力を高められる分野を優先的に支援し、国内の経済指標を改善していくことが重要です。併せて、社会インフラや教育への投資を充実させることで、製造資本や人的資本の生産性を底上げし、将来的な供給能力を強化する必要もあるでしょう。失業対策とも連動させれば、需要と供給がバランスした、安定的な穏やかなインフレへと誘導することが出来るでしょう。こうした政策提案を円滑に実行するため、政府内で明確な意思決定プロセスを築き、長期的な視野で定期的に評価・見直しを行う仕組みが求められます。現状の政府施策が特定の利権構造の維持に見える状況では、なかなかこうした議論も偏った意見になりがちなのは、大変残念なことだと思います。
まとめ:MMTを活用した日本経済の再生への道
MMT(現代貨幣理論)は大胆な財政拡大を理論的に支える一方、インフレコントロールや資源配分の適切性が伴わないと貨幣価値が急激に下落し、経済成長に対しては逆効果になり得ます。しかし、日本は長期にわたるデフレ傾向と経済停滞を経て、あらたな成長軌道を描く極めて重要なターニングポイントにあると言えます。物価高騰が現実化している今だからこそ、短期のインフレ・物価高騰対策を徹底しつつ、同時に経済の安定成長を図る施策が重要だと思います。大胆な「財政出動」と「金融政策」、そして産業構造改革を組み合わせることで、持続的な好循環に入れる可能性があります。政策立案者や省庁の政策担当者は、国民の負担を最小化しながら将来的な成長を促すビジョンを明確に描く必要があります。本記事で示した短期および中長期の「政策提案」を踏まえて、日本が再び活気ある経済を実現することを期待します。
こうした政府施策の一つ一つが、企業の持続可能な成長戦略立案と関連してきますので、その内容を加味した経営施策をヒューマントラストはお客様企業と考えていきたいと思います。