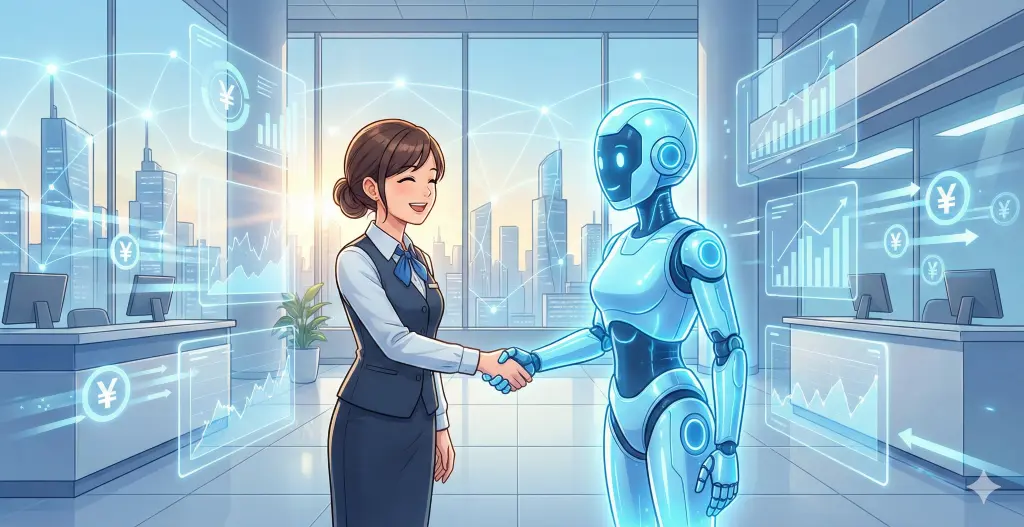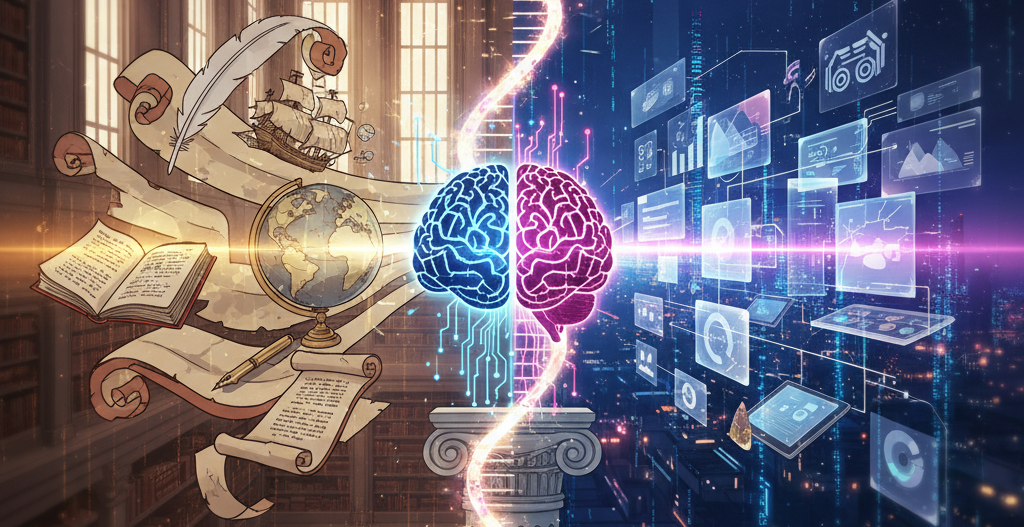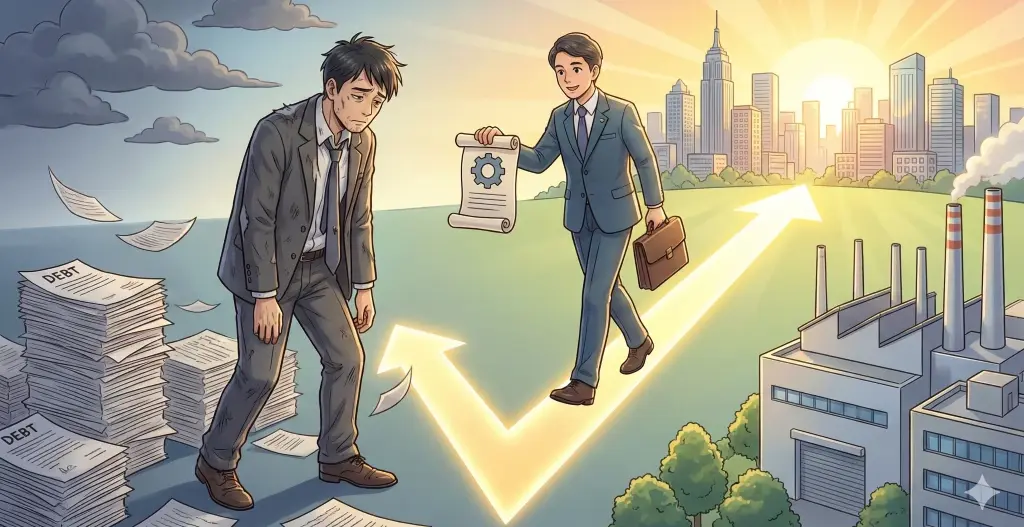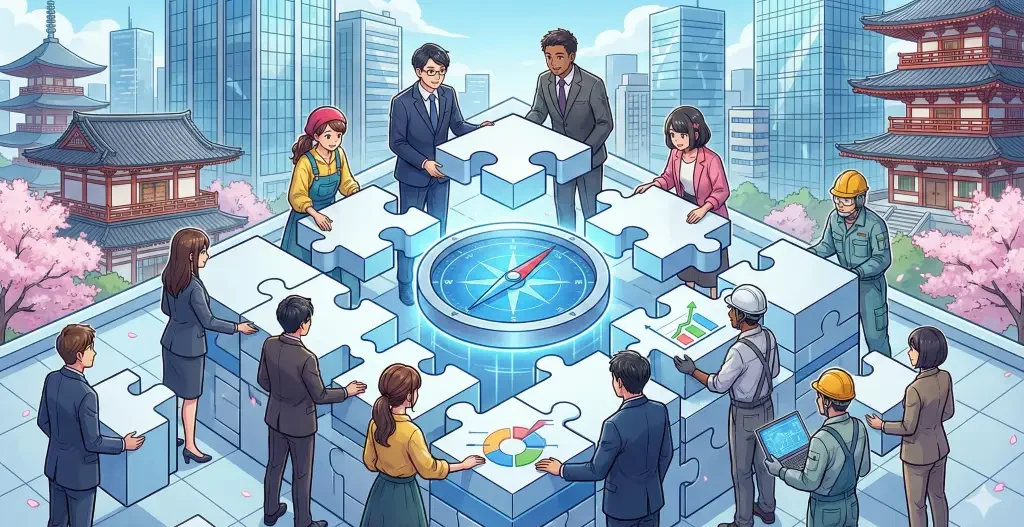公開日:2025.11.07
更新日:2025.11.07
DXとは何か?からDX認定制度まで:「3つの視点」を徹底解説

先日、ある会社の社長さんから「DX認定制度」を活用して認定取得したいというお話がありました。DX(デジタルトランスフォーメーション)は2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授によって提唱されたコンセプトです。
この記事のポイント
- DXとは単なるIT化ではなく、ビジネスモデルや企業文化を変革し競争優位を確立する経営戦略である。
- DX推進には、デジタル知見と自社のビジネスを深く理解した「DX人材」の育成・確保が不可欠である。
- 経済産業省の「DX認定制度」は「デジタルガバナンス・コード」に基づき、企業のDX経営を評価する仕組みである。
- 認定の鍵となる「3つの視点」とは、「経営ビジョンとの連動」「As Is-To Beギャップの把握」「企業文化への定着」を指す。
DX推進には「戦略」と「資金」が不可欠です
DX推進は、今や企業の持続的成長に欠かせない経営戦略です。しかし、多くの経営者が「何から手をつければいいか分からない」「推進するための投資資金をどう確保するか」という課題に直面しています。
ヒューマントラストは、30年以上の実績を持つ資金調達のプロであり、国の認定支援機関(経営革新等支援機関)です。
貴社の経営ビジョンに寄り添い、DX戦略の立案から必要な資金調達まで、ワンストップでサポートします。
そもそもは、急速に進化発展する情報通信技術によって、人々の生活が未来に向けてよりよい方向へ進化させる(トランスフォーメーション)ことが可能であるというコンセプトです。ビジネス用語という形ではなく、社会的、地球環境的視点から世界が目標とする活動の幅広い領域に及ぶテーマとして生まれました。
これをビジネスの視点で定義すると、「情報通信技術の進化発展によって急速に変化するビジネス環境が、産業構造やビジネスモデルの変革を企業に要求する。」ことと言えるでしょう。その中で、企業間の競争状況も変化しますし、ビジネスチャンスや既存事業の脅威が表裏になって出現していきます。こうしたビジネス環境の変化に対応するために情報通信技術の急速な進化発展を活用しようというコンセプトだと言えるでしょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か
具体的には、経済産業省のホームページでは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としています。
実は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の具体的なイメージは、なかなか掴みにくい面があります。現在の業務推進においては、多くのデジタルデバイスが活用され、企業の事業活動のいわゆる「IT化」が進んでいます。IT化とDXはそのレベルが相当異なります。IT化からDXにいたるまでには、いくつかのステップが想定されます。
まずは、「デジタイゼーション(Digitization)」です。これは、会社の各社員、各部署が、デジタルデバイス(パソコン、スマートフォン、パッドなど)を装備し、従来、紙ベースで管理していた業務をデータベース化したり、手作業で対応していた業務をデジタルコントロールによりオートメーション化したりすることを指します。つまり、従来、人間の手作業だった部分を、IT技術で置換することです。
これが進化すると「デジタライゼーション(Digitalization)」となります。デジタライゼーションは、デジタイゼーションとは異なり、既存の業務プロセスのIT化に止まりません。既存の製品・商品・サービスからビジネスモデルそのものの変革につなげていきます。フィルムを使った従来のカメラがデジタルカメラに置き換えられたり、音楽や映画の鑑賞が、CDやDVDの購入からデジタル配信に変化したりすることがデジタライゼーションの例だと言えるでしょう。それが、さらにDXにまで進化していけば、従来の企業のパーパス(社会的存在意義)の内容にも影響を与えるようになると思われます。新しい製品・商品・サービスの開発においても情報通信技術やAI、ロボテックスなどを駆使することで、従来の事業イメージとは異なる新しい事業の構築や既存事業の進化革新に繋がる訳です。
こうしたDX(デジタルトランスフォーメーション)の促進は、多くの場合、企業の実施する事業を持続可能するためのイノベーションの推進と繋がります。簡単な例示で言えば、手書き帳簿で管理していた顧客情報が、顧客情報のデータベースに構築され、それを社員全員が共有する。顧客情報の精度を上げるために、外部の情報サービス会社と契約することで、取引情報を瞬時に更新するシステムに進化させ、販売時点で顧客の信用情報を確認することも可能になります。
製品・商品・サービスなどの販売に際しても、在庫や納期の確認、販売価格の調整、販売記録入力と同時に売上債権として記帳処理が同時完了するシステムにつなげることになり、顧客との商談情報をベースに新しい製品・商品・サービスの開発につなげることも実施します。もちろん、会社の有する財務資本、人的資本、製造資本、知的資本、社会・関係資本、自然資本とのバランスを測定し、事業戦略や経営計画に反映させることも必要になります。DXは、会社が社会で存在する形を変革し、変化する社会やビジネスの環境の中でも、企業が持続可能な収益向上や事業発展を促す力の源泉となる施策だと言えます。
現代の情報通信技術の進化発展は、すでにAIやロボテックスを取り込んださまざまなサービス展開に繋がっています。皆さんが親しんでいるSNSにおける動画配信に、さまざまなテロップが付きますが、それもAIによる自動テロップが装備されています。スマートフォンを使用した電子商取引の領域は、一般的な商品売買を超えて、金融取引から健康管理にまで、世界中の専門知識や情報と繋がっています。ある意味で、デジタル犯罪の増加もその影響力の範疇だと言えるでしょう。
情報通信技術の進化発展は、企業の事業活動の高速化を促し、人的資本の効率的な活用を達成します。単純なIT化、デジタイゼーションに止まらず、これからの技術進歩によって新しい製品・商品・サービス・ビジネスモデルが次々に生まれてくると考えられます。
DX人材に必要な素養
「DX人材がいない」と諦めていませんか?
DX推進の鍵は「人材」ですが、中小企業が大企業のように専門人材を確保するのは容易ではありません。
重要なのは、外部の専門家(認定支援機関)を活用しつつ、社内の人材を育成し、全社的なDX文化を醸成することです。
ヒューマントラストは、貴社の「人・組織」の課題にも目を向け、実現可能なDX推進体制の構築をご支援します。
こうしたDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進には、DX人材と言われる人的資本が必要です。企業の事業活動をDX化するためには、やはり企業内にDX推進するダイナモ(原動力)が必要です。では、DX人材とはどのような素養を必要とするかを検討してみたいと思います。
DXの目的が、企業の持続可能な競争優位を確保発展させることですから、DX人材は、単なる「ITオタク」では困ります。企業の未来を構築するための戦略的な思考を、デジタル技術と組み合わせ、企業のもつ各種の経営資本の効率的な活用を実現できる人材である必要があります。経営産業省のホームページの「DXレポート2」では、DX人材を次のように定義しています。
「自社のビジネスを深く理解した上で、データとデジタル技術を活用してそれをどう改革していくかについての構想力を持ち、実現に向けた明確なビジョンを描くことができる人材」※1
要するに、デジタル技術に関する知見を有し、企業の現状と顧客や市場の状況を把握し、企業にとって最適な事業戦略を構築する能力を有するのがDX人材だと言えるわけです。
具体的に、DX人材に求められる職務上の責任としては、次のようなものが想定されます。
想像力&創造力
企業の事業のビジョンを見据えた現状理解(想像力)と、現時点とビジョン距離感を埋めていく事業モデルの想像力が必要です。その上で、事業計画を策定し、企業内における具体的な課題設定を行います。
臨機応変で柔軟な対応力
策定した計画が、想定通りに進まないことは事業運営では当然のことで、その時の臨機応変な対応力が必要になります。そうした対応を実施するにしても、企業の見据えるビジョンがブレることがないようにする対応力が求められます。
チームワーク・動員力
DXは一人の力で達成できるものではなく、その作業は、プロダクトマネージャー、デザイナー、システム設計、データサイエンティスト、システムエンジニア、プログラマーなどの力の集合体だと言えます。しかも、その一部は、社内だけでなく優秀な社外の人材との協業も必須になります。そうしたチームを編成組織し、社内外の人材を巻き込んでいく動員力がDX人材に必要な素養だと言えます。
不撓不屈の精神
DXの構築は、最後まで貫徹する精神力を必要とします。重要な経営戦略であるとの認識が必要で、会社としても、創業以来の重大事業計画になる可能性があります。従って、DXの他社事例を参考にしながら慎重に進める必要がありますが、慎重になりすぎ失敗を恐れすぎるとDXは停滞します。ある程度の試行錯誤を覚悟しつつ不撓不屈の精神でDX達成を推進する精神力が必要です。
事業領域・作業内容の言語化能力
DXには、会社の多くの経営資本を投入する必要がありますので、会社内では、各経営資本の従来までの管理活用を横断的に棚卸しし、改革を進めていかなくてはいけません。
会社では、製造一筋、企画畑、経理畑、営業畑、人事畑などと部署別の業務ブロックが形成されているケースが多いです。このような多種多様な人材をDXで統合させていく必要があります。しかもDXに関わる外部契約会社の存在もありますので、こうしたチーム全体、会社全体にDXを浸透させるためには、DXに関わる事業領域や作業内容を、分かりやすく言語化することがDX人材には求められます。
DX人材には、こうした素養が必要だと考えられます。こうした素養をもち、主体的に考え行動でき、ピンチには強行突破すら覚悟できるような精神力をもったDXのプロジェクトマネージャーが存在すれば、DXの推進とそれによる企業の持続可能な事業発展は、半分成功したと言えるでしょう。
大企業のように、多くの人材を擁する場合と異なり、中小企業がDXを推進する場合は、デジタイゼーションからデジタライゼーションを丁寧に実施し、社内にDX人材の育成を進めるところから実施する必要があるでしょう。その上で、重要な事業戦略としてのDX推進を経営計画に取り込んでいけるような体制整備をした上で、スタートすることが重要だと考えられます。
※1 経済産業省「DXレポート2」
経済産業省「DX認定制度」とは
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、会社の事業全体に大きな影響を及ぼし、現在から未来に向けた会社の持続可能性を高める目的で実施する重要な経営戦略です。従来の業務内容の改変だけではなく、会社の事業内容自体の変革を伴うケースも多いと言えます。当然、DXを推進するプロジェクトリーダーには、会社の事業内容全体の把握をベースにした高い推進力と調整能力が求められます。
このようなDXは、日本の会社の競争優位性を向上させるための施策として、経済産業省が着目しています。
実際に、経済産業省は、「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」を改訂し、DX認定制度に関わる認定基準を変更しました。そして2024年12月から、新しい認定基準に基づいたDX認定制度をスタートさせたばかりです。
この改定について、経済産業省は、「DX経営による企業価値向上」を目的としており、「DX経営に求められる3つの視点、5つの柱」を整理しています。このベースとなっているのは、「⼈的資本経営の実現に向けた検討会報告書〜⼈材版伊藤レポート2.0〜」で、2020年9月に経済産業省の「持続的な企業 価値の向上と人的資本に関する研究会」の成果として経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート」による企業価値向上に関わる人的資本の役割が議論の中心になっています。
DXといった会社業務のデジタル化をスタートラインとする事業戦略を、企業の保有する人的資本の生産性向上と捉えるところが、日本におけるDX推進の根本的な経営思想だと言うことです。※1つまり、DX経営についても、人事・人的資本の課題として捉えることが重要だという訳です。
内容的には、次のようになります。
(1)2010年代以降の日本におけるコーポレートガバナンス改革の延長線上にDX経営があること。
(2)企業価値創造の中心的な議論は、従来の有形資産から無形資産に移行しており、無形資産の最も重要なものは、人的資本であるということ。
(3)企業価値創造・向上を目指すためには、人事・人材変革が必須であるという認識が高まり、企業投資を実行する機関投資家と人事担当者の対話が重要になってきているということ。
以上をまとめるとDX経営を実現するということは、つまり、人事を管理するという発想ではなく、人的資本の効率的運用による企業の生産性向上を実現することにより、企業価値が創造され向上するという発想の転換が必要だと提唱されていると言えます。
※1 令和4年5月「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~」
DX経営に求められる「3つの視点」
DX経営を支える「3つの視点」と「5つの柱」
DX経営の基礎となる「3つの視点」
- 経営ビジョンとDX戦略の連動(DXの目的を明確にし、経営トップがコミットする)
- As Is-To Beギャップの定量把握と見直し(現状と理想の差をデータで把握し、改善を続ける)
- 企業文化への定着(DXを一過性のプロジェクトで終わらせず、全社の文化にする)
具体的な実践項目「5つの柱」
- 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定(未来像を描く)
- DX戦略の策定(未来像への道筋を立てる)
- DX戦略の推進(組織・人材・システムを整備する)
- 成果指標の設定・DX戦略の見直し(KPIで進捗を測る)
- ステークホルダーとの対話(内外に発信し、フィードバックを得る)
このようにDX経営を実践するに際しては、人的資本の戦略的活用が大前提であるという認識から、企業内のガバナンスの改新や企業文化の発展的変化が実現できているのかが、DX認定の重要な審査項目になってきていると思料されます。その中で、より具体的な3つの視点と経営体制の5つの柱が、次のように提起されています。※2※3
<3つの視点>
- 経営ビジョンとDX戦略の連動
- As Is-To Beギャップの定量把握と見直し
- 企業文化への定着
<5つの柱>
- 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
- DX戦略の策定
- DX戦略の推進と
⇒組織作り、デジタル人材の育成確保、ITシステム、サイバーセキュリティ - 成果指標の設定とDX戦略見直し
- ステークホルダーとの対話
まずは、3つの視点からです。DX経営にかかわる3つの視点は、DX経営を企業価値の向上に結び付けるために必要だとしています。
1. 経営ビジョンとDX戦略の連動
会社は創設以来、自身の事業活動に関して将来の企業像としての経営ビジョンを設定することが重要です。これは、3~5年と言った中長期の経営計画ではなく、企業の社会的な存立意義を会社の内外に標榜することにつながります。
企業が「ありたい姿」は、現時点で企業を取り巻くビジネス環境を踏まえた、さまざまな研究機関や国際組織によるガイドラインの中で見つけることができます。その意味では、各種の経営課題に対する国際規範や法定基準は、その重要な指標だと言えます。
その中で、DX経営に関わるデジタル・ガバナンス・コードは、企業の存立意義を言語化する上で、極めて有益な指針だと言えるでしょう。こうした企業の将来像(経営ビジョン)から思考をはじめて、企業の事業活動の現時点での到達点を評価する作業をバックキャスティングと言います。DX経営とは、このバックキャスティングの思考過程の中で、現時点での企業の事業状況と経営ビジョンを橋渡しし、会社の実情から将来的な経営ビジョンにつながる事業戦略の立案と実施が重要になります。
DX戦略の行く先が会社の経営ビジョンを見通すための羅針盤の役割が重要だというのが、「経営ビジョンとDX戦略の連動」の意味だと言えます。経営ビジョンとDX戦略の連動の具体例を探すには、上場企業が年次ごとに発行する統合報告書の記載を見てみるといいと思います。
以前、ある大手の製造業者から、会社のキャッチフレーズを考えるというプロジェクトがありました。このプロジェクトは、企業の経営ビジョンを考えるうえで大変有効だと思います。
企業のキャッチフレーズというのは、実は、経営ビジョンを最も短い言葉で表現したものだといえます。例えば、SONYのキャッチフレーズは「For The Next Generation(次世代のために)」です。これは、情報通信技術やAI、ロボテックなどの創造する将来の世代の社会に貢献することを宣言しています。
たしかに、かつてウォークマンやβビデオのように先進的で社会変革につながるような製品を生み出してきたSONYは、いまでもその姿勢を持ち続けて企業活動を実践していると思われます。DX戦略にもっとも馴染む企業としてSONYは軸がぶれていないと感じるキャッチフレーズだと言えるでしょう。
では、同じ業界のPanasonicのキャッチフレーズはどうでしょうか?「A Better Life, A Better World(よりよい生活よりよい世界)」です。着実な進歩を続け、よりよい世界の創造に寄与することを経営ビジョンとしています。SONYとは異なり、派手さはありませんが、現実世界の改善に資する企業の覚悟を表現したものとして、企業ブランドの大きな信頼感につながるキャッチフレーズだと言えるでしょう。
ユニクロ(ファーストリテーリング)は、日本語のキャッチフレーズです。「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」。まさに人々の日常に必須アイテムである衣類から、世界の幸せを創造していこうという意気込みにつながるキャッチフレーズです。品質、価格、流通、店舗運営など、ユニクロのビジネスモデルのDX経営化は常に進化し続け、世界的なブランドにまで成長していると言えるでしょう。
ディズニーランドのオリエンタルランドは、正にディズニーらしいキャッチフレーズです。「50年、100年先の「夢・感動・喜び・やすらぎ」のために」。この言葉を読めば、どの企業のキャッチフレーズかは、誰でも想像つくのではないでしょうか?
このように企業の経営ビジョンは、50年先、100年先の世界を見据えたものであり、DX経営は、その未来に向けての事業戦略を紡いでいくことだと言えるわけです。これらの企業キャッチフレーズは、その会社の企業文化や伝統について、直感的に読み手にアピールしてきます。
このように経営ビジョンは、言語化、可視化されてはじめてDX戦略と連携されることになります。会社の内外に、その会社の事業活動を認知してもらうことは、実は大変重要な経営戦略です。それは、このデジタル・ガバナンス・コードの中に「ステークホルダーとの対話」という項目があることでも理解できます。もちろん、企業ごとに業種も市場環境も異なりますから、どのようなDX戦略が適しているかは、各社の重要な検討項目ですが、DX経営を実践し、DX認定を目指すためには、経営ビジョンからバックキャスティングした事業計画に落とし込み、その道程を言語化、可視化することが大変重要であるのです。
※2 2024年9⽉ 経済産業省 商務情報政策局「DX認定」の認定基準改訂のポイント
※3 2024年9月改定 経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0」
2. As Is-To Beギャップの定量把握と見直し
この視点は、一見すると分かりにくいかもしれませんが、実際のDX戦略を企画策定していく上でのスタートラインの話です。
そもそも、DX戦略は、会社の企業文化の変革すら伴うような大きな事業戦略になりますから、社長をはじめとする経営陣がリーダーシップをとる必要があります。その上で、経営ビジョンとの連携を意識しつつ、会社における重要なデジタル面の課題について、具体的なアクションプランを策定し、プランの実践計画から、その成果の効果測定のためのKPI(Key Performance Indicator=ビジネス目標の達成度を測定するための数値的指標)を設定しなくてはいけません。
そのプロセスのスタートラインが「As Is(現状)」で、DX戦略に関わる施策の実施で目指すべき目標が「To Be」となるのです。As Isを変革し、To Beを達成することがDX戦略の目的であるという、実に分かりやすい話が「As Is-To Beギャップの定量把握と見直し」なのです。
実務的には、経営ビジョンに近づいていく過程で、業務プロセスや製品・商品・サービスの開発や提供に関して障害となる会社のデジタル課題を抽出し(現状把握)し、本来あるべき業務プロセスや生産性向上施策を達成するためのDX戦略の立案実施が重要だということです。
このように説明すると当然のことですが、実は、DX戦略のスタートラインとも言うべき、この視点は、日常業務の中では失われがちです。多くの企業では、既存の業務プロセスや製品・商品・サービスに関して、一定の成功体験があるケースが多く、人間の性質として「変化を嫌う」傾向があります。実は、この「変化を嫌う」傾向が、会社のDX経営の推進には大きな障害になります。
例えば、かつて手書きが主流だった業務プロセス(金融機関の稟議書作成など)は、人為的エラーも多く、生産性が低い状態でした。しかし、PCやシステムが導入されデジタル化が進むと、当初は新しいツールへの抵抗感(「変化を嫌う」傾向)がありながらも、結果として業務効率は飛躍的に向上します。この「変化への抵抗」こそが、DX推進における大きな障害の一つです。
現代の情報通信技術の進化発展、AIやロボテックの登場は、かつてのPC導入時とは比較にならないほどの大きな変化をもたらします。生成AIによる業務プロセスの言語化や可視化は、目を見張るものがあります。在宅勤務に使用されるWEB会議なども、コロナ禍のおかげで定着しましたし、それは、政府が提唱する「働き方改革」にとっては、一つの大きな原動力だと言えるでしょう。
会社の「As Is」を把握し、「To Be」を目指すという話は、実は、DX戦略に関わる情報通信技術の高速な進化発展との追いかけっこです。「As Is」と「To Be」のギャップを常に測定し、こまめな修正を加え続けることがDX経営には重要になるというのが、この2つ目の視点だと言えます。こうしたDX戦略の実施に関しては、正直な話、一社員だけでKPIを設定し計測し、見直し作業を継続することはできません。チームとしてDX戦略に取り組みながら、日常的な業務フローの中で、不断の業務としてKPIの継続的確認ができるデジタルシステムの導入や専門的な外注先との協業も必要だと言えます。その際に、目標とする経営ビジョンとの整合性の視点が重要であることは、論を待ちません。
3. 企業文化への定着
ここまでDX戦略は、経営ビジョンと連携しなくてはいけないことを説明してきました。そのために、毎日の業務推進に関してKPIを設定し、日常的に「As Is」と「To Be」のギャップの検証を実施する重要性も視点に含まれています。
こうしたDX戦略の推進が企業の業務活動に定着することがDX戦略の目的ですが、究極的には、DX戦略とあらためて称する必要もなく、DXを会社の行動基準として会社に定着させることが、DX戦略の戦略的目標であると言えるでしょう。
多くの会社で、新しい事業戦略をプロジェクト化して、一定期間の間にプロジェクトを企画策定、計画実践、結果検証を進めていくことはよくあることです。DX戦略も会社に導入するためには、やはり社長をはじめとする経営陣の主導のもとに、プロジェクトとしてスタートすることがほとんどです。
会社のプロジェクトは、法制や外部経済状況などのビジネス環境の変化に対応して、否応なく立ち上げる場合と、会社の持続可能な将来(経営ビジョン)を見据えて立ち上げる場合で、プロジェクトに関わるスタッフのモチベーションが異なると思います。外部環境に対応するためのプロジェクトは、会社存亡に直結するという危機意識からプロジェクトの効率的な推進が極めて重要になり、関係するスタッフの危機感も大きいものがあります。ですが、会社の持続可能な未来(経営ビジョン)を見据えたプロジェクトは、極めて自律的なもので、プロジェクトの規模も期限もKPIも会社の自主性に委ねられる側面が大きいものです。
こうした自律的なプロジェクトは、往々にして、「別に喫緊の課題ではない。」とか「現業が忙しいから後にしよう。」などという考え方によって、徐々に優先順位が下がっていってしまう危険性があります。
例えば、かつてのCSR(企業の社会的責任)への取組も、当初は一過性のプロジェクトとして立ち上がり、その取り組み方や情報開示は企業によって千差万別でした。総務部門などが兼任するケースや、担当者一人の勉強会参加に留まるケースもあり、企業文化として定着させることの難しさがありました。業界の景気動向に左右され、CSR活動が停滞した時期もありましたが、SDGsなどの持続可能性への関心が高まるにつれ、CSRは再び経営戦略として重要視されるようになりました。インパクト投資のように企業活動の社会性が評価されるようになり、今やCSRは企業活動に当然のものとして定着しています。
このCSRの例と同様に、DX戦略も捉えることができます。人間には「変化を怖れる」傾向があり、新しい経営戦略の考え方を、先行的かつ自律的に推進するためには、大変大きなエネルギーが必要になります。人材的にも、資金的にも、DX戦略の策定から実践、そのモニタリングから進化発展を鑑みれば、必要となる会社の経営資本はなかなか見通せるものではないと思われます。それでも、DX戦略を実践したいくつかの企業が、飛躍的な成長と持続可能な経営ビジョンの実現に向かっている状況から、DX戦略の導入が必要だという流れがビジネス環境の変化として、多くの会社の経営陣に実感されてきているのが現在状況だと言えるでしょう。
経済産業省もDXを後押しするための多くの施策を発表していますし、デジタル・ガバナンス・コードのような行動指針も定められているわけです。その意味で、DX戦略を実施することが、企業文化として定着させなくてはいけないという3つ目の視点は、DXプロジェクトを一過性にしてはいけないという警鐘だと捉えることができます。
デジタル・ガバナンス・コードにある3つの視点(経営ビジョンとDX戦略の連動、As Is-To Beギャップの定量把握と見直し、企業文化への定着)は、DX戦略を会社が実施する上での、基本的なガイドラインで、その具体的な方策については、その先にある5つの柱で説明されています。DX認定を獲得するためには、このようなガイドラインに即したDX戦略の策定、実践、検証のサイクルをキチンと回していることが重要であり、その内容を評価されることが重要になります。
まとめ
「DX認定制度」の取得を、本気で目指しませんか?
記事で解説した「3つの視点」の整理や、「5つの柱」の策定は、専門的な知見が必要です。
ヒューマントラストは、経済産業省認定の「経営革新等支援機関」として、貴社のDX認定取得を強力にバックアップします。
認定取得は、企業の信用力向上や、補助金・税制優遇の活用にも繋がります。まずはお気軽にご相談ください。
本記事では、DX認定制度の基盤となる「DXの定義」「DX人材の素養」、そして経済産業省が示す「3つの視点」について解説しました。
DXが単なるIT化ではなく、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革し競争優位を確立する経営戦略であることを確認しました。
また、DX認定で重視される「3つの視点」は、DXを実践する上での大前提となるガイドラインです。
- 1. 経営ビジョンとDX戦略の連動:DXを企業の将来像(ビジョン)と結びつける
- 2. As Is-To Beギャップの定量把握と見直し:現状(As Is)とあるべき姿(To Be)の差を測り、改善し続ける
- 3. 企業文化への定着:DXを一過性のプロジェクトで終わらせず、組織の文化として根付かせる
まずはこの3つの視点を自社に当てはめ、DX推進の土台を固めることが、企業価値向上への第一歩となります。