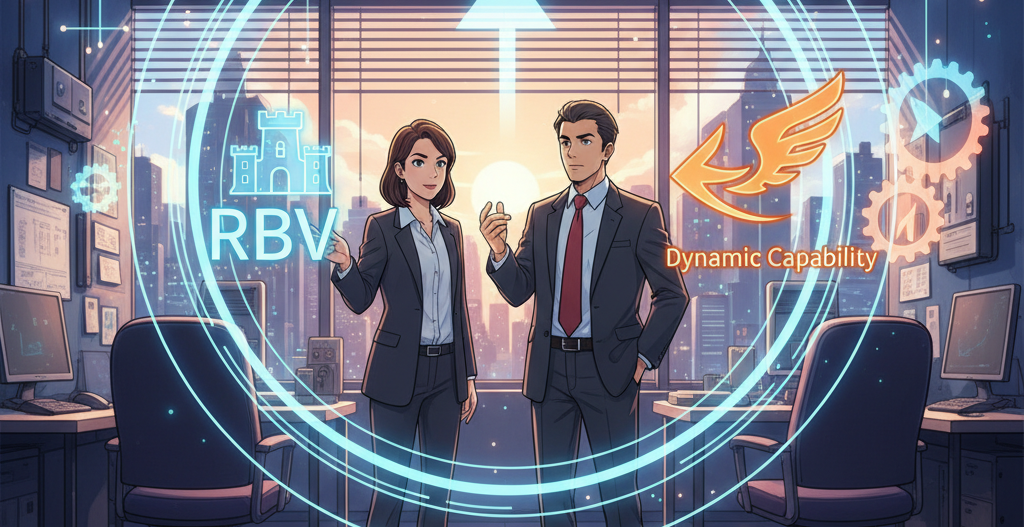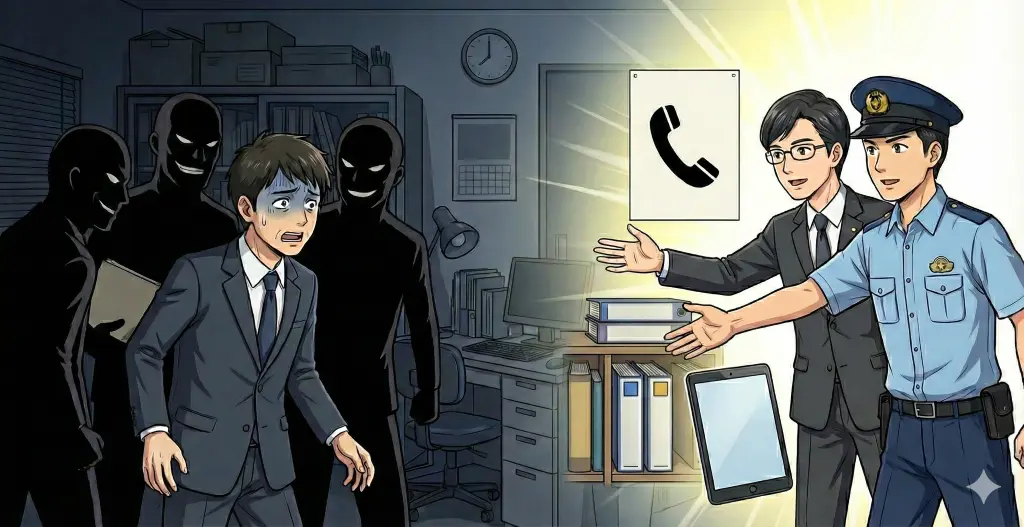公開日:2025.11.10
更新日:2025.11.12
DX認定制度「5つの柱」とは? まず取り組むべき「ビジョン・戦略・推進体制」の要点

「DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は理解しているが、自社で推進するとなると、何から手を付ければよいか分からない」
「経済産業省の『DX認定制度』に興味はあるが、認定取得のための具体的な基準や準備が分からない」
こうした悩みを抱える経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。
DX推進は、やみくもに進められるものではありません。経済産業省は、企業がDX経営を実践する上での明確なロードマップとして「デジタル・ガバナンス・コード」を定めており、その中核となるのが「5つの柱」です。
本記事では、この「5つの柱」について、DX推進の土台作りから具体的な実行体制の構築まで、特に重要となる「柱1」から「柱3」までに焦点を当てて徹底解説します。
経済産業省がDX認定制度の基準として定める「デジタル・ガバナンス・コード」では、DX経営に求められる具体的な実践項目として「5つの柱」が提示されています。
DX認定を獲得するためには、このガイドラインに即した戦略の策定、実践、検証のサイクルを回していることが重要であり、その内容が評価されます。
5つの柱とは、次の通りです。
- 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
- DX戦略の策定
- DX戦略の推進
- 3-1.組織づくり
- 3-2.デジタル人材の育成・確保
- 3-3.ITシステム・サイバーセキュリティ
- 成果指標の設定・DX戦略の見直し
- ステークホルダーとの対話
この記事のポイント
- DX認定の「5つの柱」とは、①ビジョン、②戦略、③推進体制、④成果指標、⑤対話、の5項目です。
- 本記事では、特にDXの土台となる「柱1:経営ビジョン」「柱2:DX戦略」を解説します。
- さらに、実行の核となる「柱3:推進体制」について、「組織づくり」「人材育成」「IT・セキュリティ」の3側面から詳解します。
- これらの基準を理解することが、DX認定取得への第一歩となります。
DX推進の「戦略」と「投資資金」、
一度に解決しませんか?
「5つの柱」に沿ったDX戦略の策定は、専門的な知見が必要です。
また、DX推進にはITシステムや人材育成への「投資」が不可欠です。
ヒューマントラストは、国の認定支援機関としてDX戦略策定をご支援すると同時に、30年以上の実績を持つ金融のプロとして必要な資金調達もサポートします。
経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
DX戦略は、会社の未来像(経営ビジョン)と連携していなくてはいけません。それは、会社の持続可能な企業成長発展を目指すのがDX戦略の目的だからです。その視点から、DX認定に関して、まずは、経営ビジョンを策定し、その実現を目指したビジネスモデルの策定が、最重要項目になるわけです。
基本的事項(柱となる考え方)
デジタル・ガバナンス・コードでは、次のような記載になっています。
「企業は、データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化が自社にもたらす影響(リスク・機会)も踏まえて、経営ビジョン及び経営ビジョンの実現に向けたビジネスモデルを策定する。」
分かりやすく言えば、「企業を取り巻くビジネス環境は、情報通信技術の進化発展によって大きく変化しており、そのために企業の競争状況は激しさを増しています。その中に存在する、ビジネスリスクとビジネスチャンスを把握した経営ビジョン(会社の未来像)を確認し、その実現に向けたビジネスモデルの策定が必要です。」ということになります。
企業の収益環境は、21世紀に入って既存の製品・商品・サービスがそのまま市場で通用することは無くなってきています。例えば、インターネットの普及にともなうSNSの拡大発展により、さまざまな情報発信手段が一般化することによって、新聞、テレビといった既存メディアの限界が言われるようになりました。
人々の行動原理を左右する情報システム自体の変革が進行しています。今後は、生成AIなどに代表されるような人間の知的活動を補完するような情報提供も多様化することが予想されます。結果として「オールドメディア」と言われる新聞、雑誌、テレビの情報提供のビジネスモデルは変革せざるを得ない状況になっていると考えられます。
既存の日本の社会的、経済的制度を規定してきた各種の法制に関しても、時代の要請に合わせた改正が予想されますし、その中で、ビジネスモデルの改革が必要となると言えるのです。そのような中でも、企業のキャッチフレーズに代表されるように、長期に亘って会社の行動指針となるべき会社の経営ビジョン(会社の未来像)とビジネスモデルの策定はDX戦略においてはスタートラインだと言えるわけです。
認定基準
DX企業認定を取得するためには、上記の「柱となる考え方」を軸とする内容を会社として公表する必要があります。デジタル・ガバナンス・コードにおいては、次のように示されています。「データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化の影響も踏まえた経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を公表していること。」
具体的には、会社の機関承認(取締役会など)を得た文書の策定公開、もしくは、機関承認を得た会社の方針に基づいて策定された文書の公開という形式要件が必要になります。
望ましい方向性
望ましい方向性としては、会社の経営に関わる中期事業計画や統合報告書に、DX戦略の推進実践に向けた基本的事項に記載されている経営ビジョンやビジネスモデルが明確に記載されている必要があります。
さらに、社内的に、会社の推進するDX戦略によって、既存のビジネスモデルの強みと弱みの明確化とその強化改善が記載されていること、社外的には、多様な主体(個人、非営利法人、地方政府、国など)とデジタル技術を通じた情報やデータの共有がなされていることで新しい価値創造につながっていること、加えてデジタル技術を活用したDX戦略の連携によって、業界的、社会的、地球的課題への取組がなされていることなどが、DX戦略による会社経営の望ましい方向性として例示されています。
DX戦略の策定
DX認定を取得するためには、当然のことですが、会社の実施するDX戦略を明示的に策定する必要があります。
基本的事項(柱となる考え方)
デジタル・ガバナンス・コードでは、次のように記載されています。
「企業は、データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化も踏まえて目指すビジネスモデルを実現するための方策としてDX戦略を策定する。」
デジタル・ガバナンス・コードに一貫する思想だと言えますが、企業がDX戦略を策定実施しなくてはいけないのは、情報通信技術の進化発展にともない、企業をとりまくビジネス環境が激変しているからであるというのが基本的なロジックです。
このロジックに沿った形で、企業の経営ビジョンを実現するための新しいビジネスモデルをDX戦略を駆使して創造しましょうということです。逆に言えば、この目的に沿った形で情報通信技術を活用することがDX戦略であるということです。
認定基準
DX戦略が会社の機関承認を付した形で公開されていることが認定基準になります。実は、このDX戦略の公開については、その内容的な詳細度合いについての具体的な基準がありません。
しかしながら、当該DX戦略が、実際の会社のビジネスモデルの変革にどのように作用しているのかは説明しなくてはいけないと言えるでしょう。そもそもDX戦略は全社的なプロジェクトであるケースが多いために、経営ビジョンの関わるビジネスモデルの変革を支えるDX戦略の策定内容については一定以上の具体性が具備されている必要はあると思われます。
望ましい方向性
DX戦略の策定内容については、会社ごとに独自性があると考えられます。各社が自社のオリジナルの経営ビジョンを持ち、そのためにビジネスモデルの変革を達成することがDX戦略策定の目的です。その結果として、激しく変化するビジネス環境の中で、自社の競争優位性を確立することが、企業にとっての持続可能性につながることが重要となります。
その視点からDX戦略に関わる望ましい方向性が、デジタル・ガバナンス・コードには例示されています。その中では、経営者自身の主導性、DX戦略による製品・商品・サービスの改革自体が大きな会社資産であること、を唱えています。その中で、DX戦略の内容的な特性を次のように推奨しています。※1
- 企業は、社会の状況変化や課題を迅速に把握・予測し、柔軟に対応するために、自社の保有データを発掘・整理・管理する能力を高めている。
- データに基づく判断を心掛けるなど、経営陣が、目指すビジネスモデル実現に向けてデータを活用している。
- サプライチェーン内の取引先や多様な企業とのデータ連携を行うとともに、データガバナンスに関する法令やガイドライン等に従っている。
- データとデジタル技術を活用して既存ビジネスの変革を目指す取組(顧客関係やマーケティング、既存の製品やサービス、オペレーション等の変革による満足度向上等)が明示されており、その取組が実施され、効果が出ている。
- データとデジタル技術を活用して新規ビジネスの創出を目指す取組が明示されており、その取組が実施され、効果が出ている。
以上をまとめると、DX戦略の策定内容には、経営陣が主導するプロジェクトチームの組成、DX戦略に活用する情報やデータの効率的な活用、DX戦略に関わる情報やデータの整理及び管理の励行とコンプライアンス、DX戦略の成果物である製品・商品・サービス・ビジネスモデルの市場に対するプラスの効果、DX戦略による新規ビジネスの創出が、DX戦略の内容として策定されている必要があると言えます。
DX戦略の推進
策定されたDX戦略が、会社においてどのように推進実践されるかを明示的に開示することがDX認定には必須条件になります。この項目は、DX戦略の具体的な実践に関わる内容になるので、項目として、「組織づくり」、「デジタル人材の育成・確保」、「ITシステム・サイバーセキュリティ」に分かれています。
基本的事項(柱となる考え方)
デジタル・ガバナンス・コードにおいては、次のように記載されています。
「企業は、DX戦略の推進に必要な体制を構築するとともに、外部組織との関係構築・協業も含め、組織設計・運営の在り方を定める。」
DX戦略は、企業に新しい企業価値創出を促進し、競争優位性を確保し、持続可能性を高めることを目的としています。従って、全社的なプロジェクトとして設計する必要があるものです。
その重要性から、DX戦略を会社が実施するためには、効率的で生産性を高めた戦略推進組織が重要となります。社内の経営資源だけでDX戦略が効率的に推進できないという判断があれば、外部組織との連携や協業もDX戦略の「組織づくり」には不可欠です。
認定基準
DX戦略の推進に関わる「組織づくり」は、効率的かつ生産性を向上させる方向で組成するする必要がありますが、その組織内容も、会社の機関承認と付した形で公開されていることが、認定基準となっています。
望ましい方向性
DX戦略は、どんなに優れて美しい戦略を策定しても、その実施を担うプロジェクトチームの組成(「組織づくり」)が不完全では、効率的で生産性を高めるような事業推進につなげることはできません。デジタル・ガバナンス・コードにおいては、効率的で生産性の高いDX戦略を実践するための「組織づくり」を例示しています。
- まず、第一にDX戦略は、全社プロジェクトとしての会社組織上の位置づけが必要だとされます。経営陣が主導するプロジェクトとしての位置付けを前提とする組織づくりが必要とされています。
- 続いて、DX戦略自体の専門性や情報通信技術の高速進化などに鑑みて、自前主義ではなく、オープンイノベーションの活用、外部アドバイザーやパートナーとの連携、スタートアップ企業との協業などを必須要件としています。DX戦略は、会社の伝統的な企業文化の改革も必要となる可能性の高い企業戦略ですから、経営資本を総動員する必要があると言えます。
- 自前主義を排するということは、外部の経験、知見、スキル、アイディアなどを積極的に取り込んでいくことを指しますが、そのためには、会社にはそれらを受容する企業風土や能力が必要となります。
- 効率的かつ生産性の高い推進を実現するためには、DX戦略組織にプロットされた個人、チームのそれぞれに明確なアサインメント(役割)と権限が規定されていなくてはいけません。
- DX戦略に関する予算措置は、従来の事業推進に関わる予算とは別枠で確保されていなくてはいけません。DX戦略推進に関する予算は、一定金額、一定割合を設定されていることが重要です。
- DX戦略に割り当てる財務資本(投資)に関しては、コストとして認識されるものではなく、資産として認識されていることが重要です。その上で、資産の運用効率としてDX戦略の成果を測定することになります。
- 以上のようにDX戦略の策定から実施推進については、効率的な組織づくりをベースとして、人材面、予算面、推進権限面など、従来の企業の業務形態を抜本的に変革する必要があります。これは、会社の組織カルチャーの大きな変革を促すことになりますので、DX戦略に関わる挑戦的な社員のマインドセットが重要になります。
- 行動指針には、経営ビジョンの実現につながるDX戦略に関わるIT・デジタル技術に関する知識や情報を積極的に受容検証実装する内容も含まれます。
- DX戦略に関わる組織には、DX推進部署に管理者を設定し、その権限と責任の規定が必要です。デジタル・ガバナンス・コードには次のような責任者の任命が定められています。
- DXの推進をミッションとする責任者 (Chief Digital Officer)
- 製品・研究開発など技術の統括責任者 (Chief Technology Officer)
- ITに関する統括責任者(Chief Information Officer)
- データに関する責任者(Chief Data Officer)
- DX推進部署の責任者と経営陣は、DX戦略の推進に関して、経営会議など定期的なコミュニケーションを実施することで、全社的なDX戦略の進捗状況の情報共有を行うこととしなくてはいけません。
DX戦略に限らず、会社が実施する戦略的プロジェクトは、戦略内容の巧拙と共に、戦略を実施する「組織づくり」が極めて重要です。組織は単純な組織図だけではなく、それに関連する管理系統、権限と責任、予算措置などが必要となります。その意味で、DX戦略のように、会社にとって最重要なプロジェクトの「組織づくり」は、DX企業認定の重要な認定基準だと言えます。
デジタル人材の育成・確保
会社の計画する全てのプロジェクトの成否は、推進する人材の育成と確保にかかっていると言っても過言ではないでしょう。情報通信技術の進化発展により、業務プロセスの定型化、マニュアル化、自動化がすすむことで、ある意味で最適解を導くことが容易になってきています。
中小零細企業でも、高速で変化するビジネス環境に対応し、経営効率を上げ、生産性を向上させ、収益拡大につなげている企業はたくさん存在しています。
一方で、外部環境の変化による業態改革や業務プロセス改善を怠ってしまえば、大手企業と言えども、経営体制の抜本的な見直しを迫られます。例えば、自動車業界の劇的な変化に対応するため、大手企業同士が経営統合を模索するケースは、ビジネス環境の激変を如実に表しています。個社レベルでの対応が難しくなる中、具体的かつ企業イノベーションを活用した戦略転換と経営判断が、持続可能な企業の発展に寄与すると考えられます。
その文脈で見ても、最終的な企業の方向性を経営判断するのは、経営陣=「人」である訳で、その礎となる各種のプロジェクトの成否も、担当責任者=「人」の判断に大きく依存していると言えるのです。
戦国武将・武田信玄の言葉に「人は城、人は石垣、人は堀」とあるように、組織の強さを「人」に求める考え方は古くから存在します。DX戦略といった、いかにも現代的なプロジェクトの本質とも言える「デジタル人材の育成・確保」という柱の内容は、経営者であれば納得できるものでしょう。
基本的事項(柱となる考え方)
これは、「DX戦略の推進には、それに必要な人材を育成・確保しなくてはいけない。」という内容です。当たり前のことですが、これが非常に難しい課題です。そもそも、DX戦略という比較的新しい概念を理解しているIT技術者は多くありません。
DX戦略においては、デジタル技術の素養や知見は所与のものとして扱われます。その上で、会社の従来の事業全般に関する経験や知識を有し、さらにはマネジメント的なセンスも求められるのが、DX戦略の推進責任者だと言えるわけです。
しかも、DX戦略は全社的な取り組みになるケースも多いので、各業務部門、部署との調整事項や横断的情報共有など、コミュニケーションやプレゼンテーションのスキルも必要となります。
認定基準
「デジタル人材の育成・確保」に関する認定基準も、中期事業計画や統合報告書などの機関決定された文書において公開されている必要がありますが、実際の施策に関しては、細かく設定されていません。
「人」に関わる経営課題は、DX戦略に限らず、常に会社の持続的な成長発展の基本として経営課題であることは変わらないと言えます。
望ましい方向性
- デジタル人材という定義をどのように考えるかを会社として明確化する必要があります。一般的には、経済産業省が デジタルスキル標準(令和6年7月改訂)※2 を発表しており、これに沿ったデジタルスキルを保有した人材ということになるかと思います。
- デジタルスキル標準においては、会社がDX戦略を推進するために、全社的なデジタルリテラシーのレベルを設定しています。つまり、DX戦略人材ではない、経営陣を含む会社のすべてのビジネスパーソンが、「DXリテラシー標準」をクリアしている必要があるとしています。
- このような全社的なDXリテラシー標準の達成による会社のデジタルスキルの底上げをベースとして、DX戦略の推進に関与する責任者であるDX推進人材に対応する「DX推進スキル標準」を定めることになります。
- 「DX推進スキル標準」については、人材育成システムの構築、リスキリングの促進、実践的学習の実現、デジタルスキルの見える化を実施します。DX推進を実践する人材類型としては、以下のように定義されます。
- ◎ビジネスアーキテクト: DXプロジェクトの目的を理解設定し、関係者をコーディネートする司令塔。
- ◎データサイエンティスト: データ活用による業務改革や新サービス実現のため、データ収集・解析の仕組みを設計・実装・運用する。
- ◎デザイナー: ビジネス視点、顧客・ユーザー視点を集約し、製品・サービス・ビジネスモデルの方向性をデザインする。
- ◎ソフトウェアエンジニア: DX戦略から生まれる新しい製品・サービス・ビジネスモデルを市場に提供するため、システム・ソフトウェアを設計・構築・運用する。
- ◎サイバーセキュリティ: DX戦略の安全性を高め、リスクマネジメントの責任を負う。
- このようなDX戦略の推進に関わるDXリテラシーの標準の全社的普及及びデジタル人材の育成・確保について、経営者や役員の意識改革が必要となります。
- 社員に対するデジタルリテラシーの向上を継続的に実施し、DXによる業務改革を進めるために、関連する教育システムやリスキリングに対する支援策が策定されていることが大切です。
- 生成AIなどの最先端技術をフォローアップできるよう、必要なスキルや人材を常にキャッチアップし、関連する人材の育成・確保のための施策(社内育成、中途採用、外部リソースとの連携など)を講じている必要があります。
- DX戦略の推進に必要な人材の有するスキルや知見が、適切な資格試験などの標準に照らして明確に評価される体制整備を進めるとともに、社内における権限及び責任を明確化した組織化や人事制度が構築されている必要があります。
DX戦略の推進は、やはり会社の人的資本を中心とした「人」の力が絶対的に必要です。その意味で、「デジタル人材の育成・確保」はDX戦略を立案する際の最優先で解決するべき経営課題になります。
発展進化の急速な情報通信技術、デジタルソリューション領域では、新しいアイディアがどんどん出てきますので、その時点時点でのDX戦略推進の「As Is」と「To Be」の検証作業は、会社のDXの成否に関わる重要なポイントだと言えるでしょう。
「DX人材がいない」は、
外部パートナーの活用で解決できます
記事で解説した通り、DX人材の確保・育成は最重要課題です。しかし、すべてを自社で賄う必要はありません。
ヒューマントラストのような認定支援機関を外部パートナーとして活用し、「組織づくり」や「人材育成」の仕組みを整えることが、中小企業のDX成功の鍵となります。
ITシステム・サイバーセキュリティ
DXは基本的に発展進化する情報通信技術が必須です。ですので、DXに活用するITシステムの内容と、企業の事業防衛のためのサイバーセキュリティについては、DX戦略の策定の内容として必要不可欠になります。
基本的事項(柱となる考え方)
デジタル・ガバナンス・コードには、次のように記述されています。
「企業は、DX戦略の推進に必要なITシステム環境の整備に向けたプロジェクトやマネジメント方策、利用する技術・標準・アーキテクチャ、運用、投資計画等を明確化する。」
「経営者は、事業実施の前提となるサイバーセキュリティリスクに対して適切な対応を行う。」
ITシステムの整備は、大変難しい作業だと言えます。既存の業務を改革し、新しい製品・商品・サービス・ビジネスモデルの提供を目指すという観点からは、将来的にどのようなITシステムが必要であるかを検討することは、経営計画と経営ビジョンが高度に連携している必要があるからです。
従来の会社の業務プロセスに合わせたITシステムの整備だけでは、DX戦略の実施による未来型のITシステムへの転換は期待できません。最初のベースとなるITシステムには、機能的な発展拡張を想定した柔軟性を確保する必要があります。
ITシステムの開発手法(ウォーターフォール vs アジャイル)
ウォーターフォール型開発
- 特徴:滝の水が流れるように、工程を一つずつ完了させながら進める。
- メリット:全体の計画や予算が立てやすい。大規模な基幹システムに向く。
- デメリット:途中の仕様変更が困難。開発期間が長期化しやすい。
アジャイル型開発
- 特徴:「計画→設計→実装→テスト」を機能単位で短期間に繰り返す。
- メリット:仕様変更に柔軟に対応できる。素早いリリースが可能。
- デメリット:全体のスケジュールや予算の厳密な管理が難しい。
こうした議論は、ITシステムの開発方法との関係性も考慮する必要があります。システム開発の手法は、ITシステムの全体像を完全な形で設計し、計画的に開発を実施するケース(ウォーターフォール型開発)と、ITシステムの機能を分解し、トライアンドエラーを前提として「開発-テストラン-修正-テストラン-実装」を繰り返しながらシステムの精度や機能性を向上させるケース(アジャイル型開発)に大別されます。
実際のDX戦略に活用するITシステムに関わる設備投資としては、基本的なITシステムに関してはウォーターフォール型開発によりベースを固め、そこからの精度や機能性、生産性向上を進めるためのITシステムについては、アジャイル型開発を進めることになります。
また、こうしたITシステムの開発に関しては、企業の事業推進の安全性を高度に担保するためのサイバーセキュリティ機能も具備していなくてはいけません。製品・商品・サービス・ビジネスモデルの安定的かつ安全な提供は、企業防衛と言うだけではなく、それらを利用するユーザーや消費者の安全も保全する重要な役割を担っています。
認定基準
DX認定のためには、ITシステムの整備方針について、明確に示されていることが必要な認定基準となります。基本システムと特殊機能システムに分けて、それぞれの開発方針や設備投資予算、開発期間、実装時期を明確にする必要があります。
尚、サイバーセキュリティに関しては、経済産業省が独立行政法人情報処理推進機構による「サイバーセキュリティ経営ガイドラインver3.0」※3を発表しています。このガイドラインに基づいてセキュリティシステムを構築運用することができます。
このガイドラインにおいては、サイバーセキュリティの範囲を従来の外部からのサイバー攻撃に限定せず、内部統制、コーポレートガバナンス、ステークホルダーへの情報開示、サプライチェーンなどに拡大されています。こうした拡大するサイバーセキュリティ対策の実施と、実際の内部監査を含むセキュリティ監査の報告書が、機関承認を付けた形で提出されている必要があります。
望ましい方向性
- 会社のITシステムは、DX戦略の基礎ですが、経営実態に即した整備、運用が必須です。ITシステムやその中の情報資産の現状チェックとして、一定頻度をもって効率性、生産性などの視点をもって分析検証することが求められます。
- ITシステムを進化発展させるに際して、技術的な複雑化やブラックボックス化が進むことは、全社的なDX戦略の推進にはマイナスになります。セキュリティを確保しながら、ある程度のITシステムの簡素化や運用上のオープン化は必要です。
- 会社のITシステムは、最新のデジタルシステムとの連携、統合などが必要になることが予想されます。その際には、既存システムやデータ、業務プロセスとの円滑な連携や移行が達成できているかの検証分析をする体制になっていることが重要です。
- サイバーセキュリティの効果的な実施をするために、重要な経営課題としてサイバーセキュリティを位置付け、そのための技術的かつ実務的な責任者を設定し、必要な予算措置と人材確保をする必要があります。
- こうしたサイバーセキュリティ体制は、関連するセキュリティ計画や実施状況の一定頻度のモニタリングなどが整備されている必要があり、万一、サイバー事故が発生した場合には、サプライチェーンの保全や取引先、ユーザーなどの安全性の確認対策を早急に公表することも重要です。
ITシステムの整備に関しては、サイバーセキュリティの施策を必ず装備する必要があります。前向きなDX戦略として、新しい情報通信技術を取り込み、企業の生産性、収益力を高めると同時に、DX戦略を足元から崩壊させるリスクであるサイバー攻撃やサイバー事故の防御、予防に関わる施策が重要であることは当然です。
中小企業レベルでのDX戦略においても、会社の持続可能な成長を達成するためには、サイバーセキュリティの内容については、十分な検討をする必要があると言えるでしょう。
「DX認定制度」の取得を、
国の認定支援機関がサポートします
DX認定の取得は、税制優遇や補助金の加点、企業の信用力向上に直結します。
ヒューマントラストは、経済産業省が認定する「経営革新等支援機関」です。
「5つの柱」に基づいた戦略策定から申請支援、その後の資金調達まで、貴社のDX経営をワンストップでご支援します。
まとめ
本記事では、DX認定制度の「5つの柱」のうち、DX推進の土台と実行体制の核となる「柱1」から「柱3」までを解説しました。
これら3つの柱は、DXプロジェクトにおける「設計図」と「実行部隊」そのものです。
- 柱1:経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
DXを推進する「目的(Why)」と「未来像」を明確にします。 - 柱2:DX戦略の策定
ビジョンを実現するための具体的な「計画(What)」を策定します。 - 柱3:DX戦略の推進
戦略を実行するための「リソース(How)」、すなわち「組織づくり」「人材育成・確保」「ITシステム・セキュリティ」を整備します。
DX認定を目指す第一歩として、まずはこの3つの柱を自社の経営に当てはめ、DX推進の強固な土台を築くことが重要です。
※1 2020年9月 経済産業省 デジタル・ガバナンス・コード3.0
※2 2024年7月改訂 経済産業省 デジタルスキル標準
※3 独立行政法人情報処理推進機構「サイバーセキュリティ経営ガイドラインver3.0」