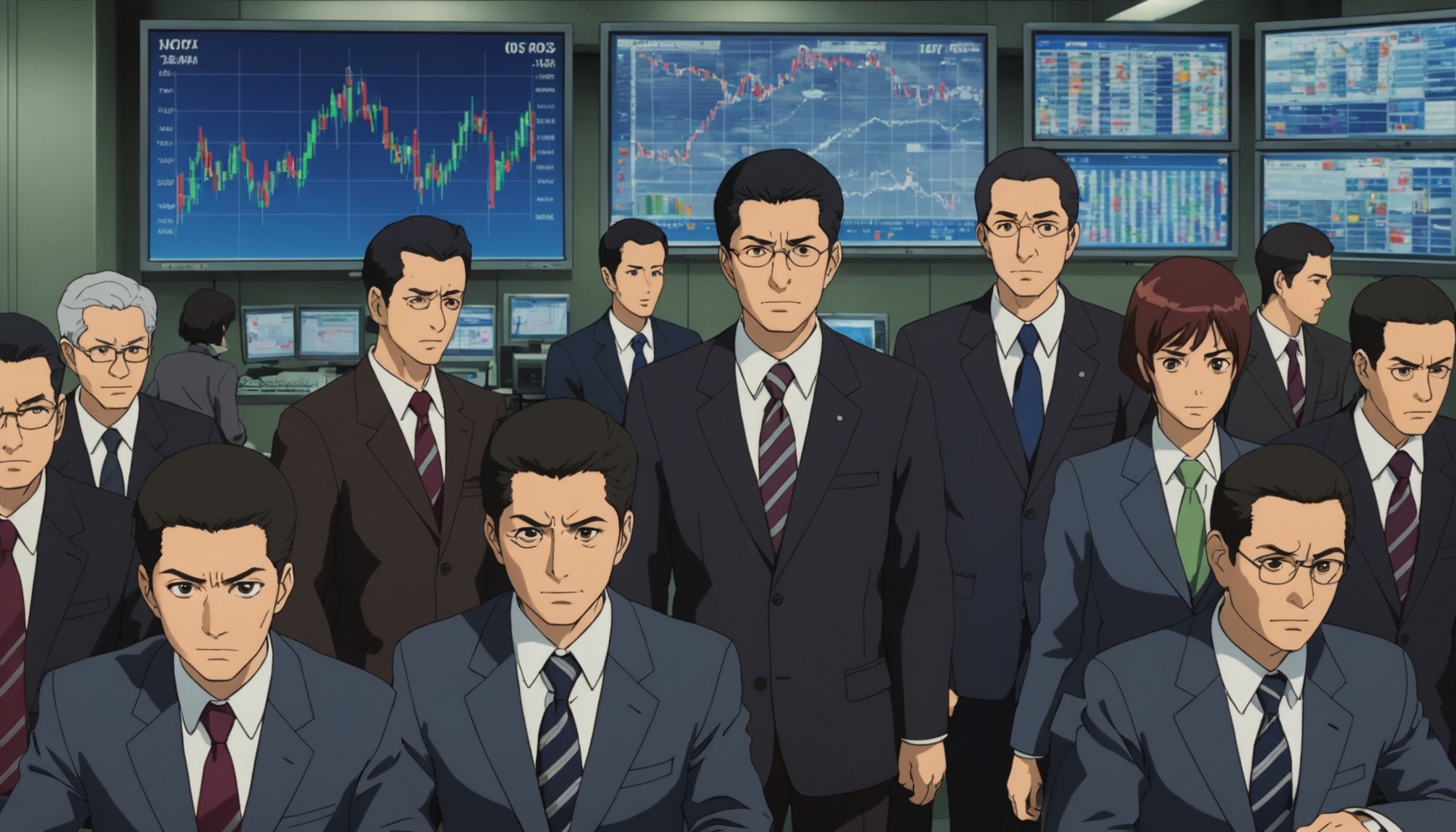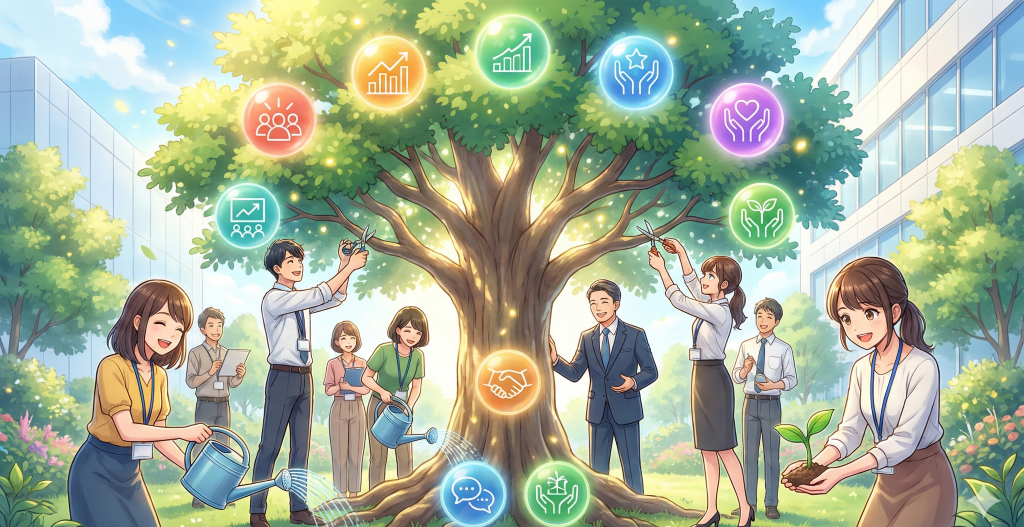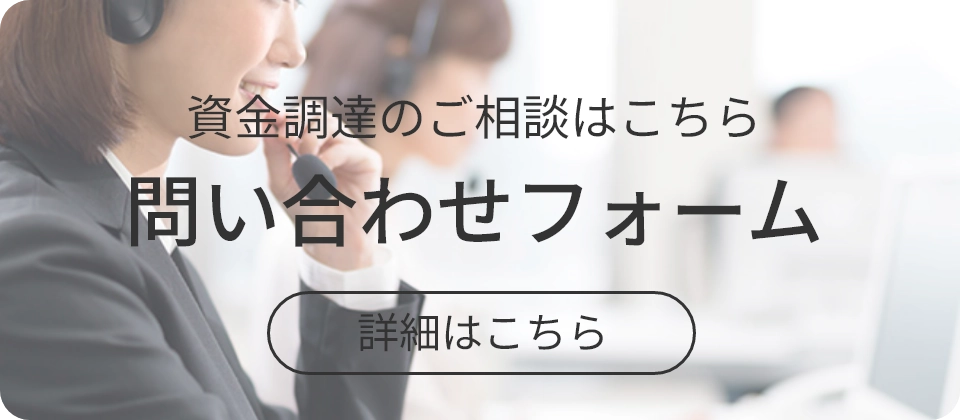公開日:2025.11.06
更新日:2025.11.06
ファクタリングの基本とは?中小企業の資金調達・資金繰り改善に

中小企業を中心とするコンサルティングのお客様の中で、もっとも件数の多い相談内容が「資金繰りの改善」「資金調達」だと言っても過言ではありません。
伝統的に資金調達には、3つのカテゴリーがあると言えます。
コンサルティングのお客様である中小企業やスタートアップ企業の資金繰りや資金調達の相談に対しては、この3つの資金調達方法を組み合わせて、短期、中長期の対応策をアドバイスすることが多くあります。
そこで、今回のコラムでは、資金調達方法の一つとして「ファクタリング」をご紹介します。
この記事のポイント
- ファクタリングは、売掛債権(請求書)を売却して早期に資金化する「資産の売却」です。
- 融資(負債)ではないため、担保・保証人が不要で、財務体質を悪化させません。
- 取引先に通知不要な「2社間」と、手数料が安い「3社間」の仕組みがあります。
- 手数料の高さや依存リスクも存在するため、資金繰り改善の手段として計画的に利用することが重要です。
「自社の売掛債権、資金化できる?」
その疑問、専門家が最短即日で回答します
ファクタリングは、融資とは異なる「新しい資金調達の選択肢」です。
まずは貴社の状況を伺い、最適な資金繰り改善策をご提案します。
ファクタリング取引の歴史的考察
ファクタリングの語源と誕生
そもそも「ファクタリング=Factoring」とはどのような歴史のある取引なのでしょうか?
ファクタリングの語源は、英語の「Factor」の現在進行形「Factoring」です。英語の「Factor」は「要因」「要素」というのが中心的な意味ですが、それ以外に「代理人」という意味があります。つまりFactoringとは「代理行為」という意味なのです。このFactoringという取引は、16世紀にイギリスで生まれたと言われています。イギリスの商人が、アメリカ大陸の植民地との交易に利用したとされています。
当時のFactor=代理人は、市場の情報提供、商品の仕入販売、信用調査、信用リスクの引受、代金の前払金融、販売台帳の作成、未回収債権の取立などを業として行っていました。内容的には、現代のファクタリング会社も、ほぼ同じ業務内容だと言えます。
代理人(Factor)の役割の変化
18世紀から19世紀のファクター(代理人)は当時のイギリスの主要輸出品目であった繊維製品の製造業者のエージェントとして、委託された繊維製品の保管と販売を担当していました。その際にファクターは、製品販売を行う前に、製品の買主の信用調査を実施し、信用度合いに合わせて製造業者に代金を支払っていました。その意味では、ファクターは今の商社のようなビジネスを展開していたのです。背景として、新大陸アメリカにおいては、移住者向けの製品をイギリスから輸入する必要があったことがあり、このファクターの活動範囲は、さまざまな製品やサービスに拡大していったのです。20世紀になって、アメリカ自体の産業発展もあり、イギリスをはじめとするヨーロッパからアメリカへの製品輸出は低調になっていきます。この流れでファクターは、ヨーロッパ産製品の販売代理事業を行わなくなり、アメリカの買主の信用調査と販売代金に対する資金提供(金融事業)に特化するようになったのです。
金融サービスとしての確立と普及
当時のファクターは、アメリカのニューヨークを中心に繊維産業事業者を主要な顧客としてビジネスを拡大させており、1960年代にはイギリス、フランス、ドイツなどに支店を開設しているファクターもいたほどに活況を呈していました。
こうしたファクターの活動は、アメリカで大きく発展した後に、20世紀後半では、ヨーロッパ全域で展開され、日本をはじめとする東アジアやオーストラリアにおいてもファクターが誕生していくことになります。このように、ファクターの活動が現在のファクタリングの原点でありますので、ファクタリングは、実際の貿易による製品販売のように、確定した製品やサービスの売上がベースとなる取引だと言えるのです。
ファクターの金融サービス提供の側面は、次第に大規模な商業金融機関として成長していくことになり、銀行などの金融機関とファクタリング会社の提携が進んでいきます。現時点では、ファクタリング会社の約8割が銀行系になっています。
このようにファクタリング取引の原点は国際的な貿易取引にあったのですが、その後の進展普及によって、ファクタリングのお客様が取引先に販売した売掛債権を償還請求権なしで買い取る信用保証+金融機能の方式が形成されて今日に至ると言えます。
ファクタリング取引の現状
日本で普及が遅れた背景
日本におけるファクタリングは、1970年代に銀行系のファクター(ファクタリング会社)が設立されていったのですが、商社による商社金融、手形取引の普及といった欧米とは異なる商慣行や金融システムによって、ファクタリング取引自体の普及発展は極めてマイナーな状態だったと言えます。特に、日本においては売掛債権の譲渡というファクタリング取引には、信用低下のイメージが拭えないことも影響があると言えるでしょう。以上をまとめると、
1.商社の販売機能と商社金融がファクタリング的な取引機能を担っていたこと
2.売掛債権譲渡に対する抵抗感が強かったこと
3.手形取引が決済手段として広く活用されていたために、企業の資金繰り調整と手形割引による金融対応が可能だったこと
4.売掛債権譲渡に関わる登記手続きなどの第三者対抗要件の確保制度が未整備だったこと
5.売掛先(第三債務者)に関わる信用調査に関わる調査機関の整備が遅れていたために調査コストが高額になってしまっていたこと
などの要因によって、日本のファクタリング取引は欧米ほどの普及がなかったと言うことです。
そもそも、日本のファクタリング会社の多くが銀行系であったことは、銀行の金融サービスである手形割引(償還請求権付手形買い取り)と競合関係にあるという矛盾を抱えていたことも要因として言えるでしょう。
普及の転機と近年の動向
日本では、昭和48年(1973年)のオイルショック後の不況の中で、金融緩和、低金利時代が到来することになり、銀行の本業収益である利ざや確保が厳しくなりました。それに合わせて、銀行が金融取引に当たらないファクタリング取引(売上債権の譲渡)の収益性に着目し、中小企業向けサービスの一環として、ファクタリング取引の普及に注力するようになります。加えて、商社自体が商社金融的なサービスを縮小するようになり、また企業間の決済手段としての手形取引が、事務効率、管理コスト高騰などの理由から縮小していく傾向になったことも、中小企業を中心とする売掛債権の早期資金化ニーズに対応する資金調達手段としてのファクタリングに注目が集まる要因だったと言えるでしょう。
さらに、電子商取引(EC=E-コマース)の拡大や債権譲渡登記制度の開始(平成10年=1998年)によって、ファクタリング取引を利用する企業が増加していくことになったのです。
世界と日本の市場規模
近年、このファクタリング市場は世界的に拡大傾向にあります。2023年の世界のファクタリング市場規模は約3兆8,500億米ドル(568兆円)と推計されており、2027年には4兆7,992億米ドル(708兆円)に達すると予測されています。(出典:株式会社グローバルインフォメーション「ファクタリング市場:タイプ別、産業別-2024年~2030年の世界予測」)日本の市場規模も、2023年度で約5.7兆円と推計されており、今後も成長が見込まれています。(出典:アンクパートナーズ合同会社「2024年版 ファクタリング市場の現状と展望」)
資金繰り改善の鍵となる“売掛債権”の活用法
このような古い歴史的背景のあるファクタリング取引ですので、企業活動のもつ本質的な資金需要に対応するシステムとして生まれてきたと言えます。従って、現在の商取引においても拡大していくのは当然だと言えます。特に、中小企業やスタートアップ企業にとって、持続可能な経営のための生命線である資金繰りについて、ファクタリング取引の必要性は高まっているのが現実です。日々の運転資金や仕入れ資金、人件費や設備投資など、多岐に亘る資金需要に対応するためには、ファクタリングという資金調達手段に対する期待は大きくなっていると言えるでしょう。このコラムでは、ファクタリングの基本的な考え方とその仕組みや種類、メリット・デメリット、そして中小企業にとっての活用可能性についてお話しようと思います。
ファクタリングとは何か?
現在の商取引におけるファクタリングとは、企業が保有している売掛債権(未回収の請求書)をファクタリング会社に売却し、早期に資金化するサービスです。売掛先からの入金を待たずに現金化(販売代金の現金化)ができるため、「資金繰りの改善策」として活用されています。例えば、月末締め翌月末払いといった一般的な商取引において、商品の納品やサービス提供後にすぐ現金が手元に入るわけではありません。売掛金の入金までのタイムラグは、企業にとって資金不足の原因となることが多くあります。こうした場合に、ファクタリングを利用すれば、数日〜1週間程度で現金を手にできるため、キャッシュフローを円滑に保つことが可能となるのです。
資金調達の3つのカテゴリー
ここで、資金調達の全体像について触れておきます。伝統的に資金調達には、3つのカテゴリーがあると言えます。
1つ目は「手持ちの資産を売却する方法」です。これは、簡単に言えば、手持ちの時計でも不動産でも車でも、売却してお金に変えるということです。ファクタリングは会社の資産である売上債権を売却することですので、このカテゴリーに入ります。
2つ目は「誰かからお金を借りてくる方法」です。これは、いわゆる借金ですね。貸し手は金融機関かもしれませんし、ご家族や親戚の方かもしれません。とにかく、お金を誰かから条件を決めて(もしくは決めずに)借りてくることです。
3つ目は「活動(事業)に必要な資金を提供する方法」です。これはお金を借りてくるのではなく、出資と言う形で提供してもらう方法です。借金とは異なり、返済する必要はない資金になりますが、活動(事業)による儲けが出たときには、それ相応の儲けをお金の提供者に分配する必要があります。
こうした3つのカテゴリーは、会計的には貸借対照表の3つの部に対応しています。1は「資産の部」、2は「負債の部」、3は「資本の部」に対応した資金調達方法です。
ファクタリングの仕組みとプレイヤー
ファクタリングには主に以下の三者がプレイヤーとして登場します。
・売掛債権保有企業(債権譲渡人)
・売掛先(第三債務者)
・ファクタリング会社(債権譲受人)
ファクタリング契約では、売掛債権をファクタリング会社が買い取り、ファクタリング会社が売掛債権保有者に代金を支払います。その後、売掛先からの支払いはファクタリング会社に行われる(もしくは、債権譲渡人による回収代行)という流れになります。このファクタリングのスキームは極めて単純ではありますが、ファクタリングには大きく分けて3社間ファクタリングと2社間ファクタリングという仕組みがあります。
・3社間ファクタリング
売掛先(第三債務者)の同意・承諾のもと、売掛債権を譲渡する方式です。透明性が高く、売掛債権を買い取るファクタリング会社としてはリスクが低いため、手数料が比較的安くなります。しかし、取引先(売掛先)への通知が必要なため、取引先に「資金繰りが苦しい」と思われてしまうリスクがあります。
「2社間」と「3社間」の仕組みの違い
2社間ファクタリング (取引先に非通知)
- STEP 1: 貴社がファクタリング会社へ売掛債権を売却(譲渡)。
- STEP 2: ファクタリング会社が貴社へ買取代金を即時入金。
- STEP 3: 貴社が売掛先から売掛金を通常通り回収。
- STEP 4: 貴社が回収した売掛金をファクタリング会社へ送金。
- メリット: 取引先に知られず、スピーディに資金化できる。
- デメリット: 手数料が3社間より高くなる傾向がある。
3社間ファクタリング (取引先の承諾あり)
- STEP 1: 貴社がファクタリング会社へ申込み。売掛先に債権譲渡の承諾を得る。
- STEP 2: 貴社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で契約。
- STEP 3: ファクタリング会社が貴社へ買取代金を即時入金。
- STEP 4: 売掛先がファクタリング会社へ売掛金を直接支払い。
- メリット: ファクタリング会社のリスクが低く、手数料が安い。
- デメリット: 売掛先の承諾が必要で、資金化に時間がかかる。
・2社間ファクタリング
売掛先に通知することなく、ファクタリング会社と債権者(企業)のみで売掛債権の譲渡契約を行う方式です。柔軟でスピーディに契約できるため、スタートアップ企業や個人事業主などに人気があります。一方で、償還請求権なしの契約であった場合には、債権回収リスクをファクタリング会社が抱えるため、3社間ファクタリングよりも手数料は高くなることが多いです。この2社間ファクタリングでは、3社間ファクタリングにあるような取引先からの同意・承諾は不要ですので、取引先に知られることなく売掛債権の現金化を実施できる点も、メリットと言えます。
ファクタリングのメリット
そもそもファクタリングには、売掛債権の回収を代行するという商取引の歴史がありますので、売掛債権の回収に関わる事務管理をファクタリング会社に代行させるメリットがあります。それ以外にも、現代的な視点では、次のようなメリットがあります。
① 資金繰りの改善
売掛金の期限における入金を待たずに資金化できるため、運転資金が不足しがちなタイミングでも安心して経営を継続できます。ファクタリング取引の資金繰りを安定化させる効果は、中小企業やスタートアップ企業のように、一般的な金融機関からの借入(銀行融資等)を獲得することが難しいケースでは極めて効果的かつ重要です。特に、事業会社にとっては金融機関からの借入は、審査に時間がかかることも多く、スピード重視の経営戦略には不適合だと言えます。その意味でもファクタリング取引のメリットは大きいです。
② 負債ではない(バランスシートに影響しない)
ファクタリング取引は売掛債権という資産の売却であるため、借入金のように負債として計上することはありません。財務体質の健全性を保ちながら資金調達できる点は、大きな魅力です。企業にとって負債の増加(借入金の増加)は、経営指標を悪化させる原因になります。負債の拡大は、自己資本比率を低下させるだけでなく、総資産の膨張の原因ともなり、会社の生産性向上にもマイナスの影響があります。
③ 担保・保証人が不要
融資(借入金=負債)と異なり、ファクタリング取引では不動産担保や個人保証を求められることは基本的にありません。ファクタリング取引が「資産の売却」であることがその理由です。担保や保証人が不要であるということは、中小企業にとって大きな心理的ハードルを取り除くことになり、より事業の推進に集中できる経営環境づくりに寄与すると言えます。
ファクタリングのデメリットとリスク
事業を行っていると、さまざまな取引を実施することになります。事業推進に関わる取引のすべてにデメリットとリスクがあるように、ファクタリング取引にも、メリットとデメリットがありますので、その認識を確認しておく必要があります。
① 手数料が高い
特に2社間ファクタリングでは、手数料が5%〜20%程度と高めに設定されることがあります。頻繁に利用すれば、この高額な手数料(コスト負担)が経営を圧迫する可能性もあります。取引自体の収益力との関係を吟味した上で、ファクタリング取引を利用しないと、手数料で利益が圧迫されます。
② 売掛先(第三債務者)の信用に依存する
ファクタリングの審査では、売掛金の内容や売掛先(第三債務者)の信用が重視されます。取引先(売掛先)が小規模だったり、信用力が低かったりすると、審査に通らないこともあります。売掛先の信用調査が、取引の拡大には重要ですので、その点についても取引を開始する際には注意する必要があります。
③ 繰り返し利用の依存リスク
ファクタリング取引は、利用すると現金化のスピードというメリットのために、一時的な資金繰り対策としては有効です。しかしながら、その利便性や即時性に頼って、ファクタリングに依存した経営が常態化すると、高額な手数料(経費)がかさみ会社全体の収益力が低下します。資金繰りの一時的な解決策としてのファクタリング取引という認識は常時持っているべきです。資金繰りの改善という経営戦略を抜本的に策定実施しないと、会社経営自体の持続可能性に対するリスクになります。
手数料、依存リスク…
ファクタリングの不安は専門家にご相談ください
デメリットを読んで不安に感じた方もご安心ください。ヒューマントラストは、貴社の状況を分析し、ファクタリングに依存しない「根本的な経営改善」までを見据えてサポートします。
ファクタリングの主な利用シーン
ファクタリング取引のメリット、デメリットを認識した上で、実際のファクタリング取引の利用シーンを想定してみることは、経営戦略上、有効だと言えます。
・突発的な仕入れ資金の確保
・急な資金ショートの回避
・成長加速期のキャッシュ確保(特に急激な運転資金の増加)
・銀行融資の審査待ち期間のつなぎ資金
・赤字決算や税金滞納などで金融機関の融資が難しいとき
特に、創業間もない企業や、黒字倒産を避けたい中小企業にとって、ファクタリングは有力な資金戦略となり得ます。このようにファクタリング取引の利用は、企業経営上の経常的な資金繰りとは異なるシーンでの活用が望ましいと言えます。経常的な事業プロセスの中での資金繰りについてファクタリング取引を活用した場合には、並行して借入金や収支ズレの改善などを実施し、ファクタリング取引のメリットを最大限利用できる場面を想定しておくことが重要だと言えます。ファクタリング取引に依存する経営は、抜本的な経営改善施策の策定も並行して進めていくことをお薦めします。
ファクタリング会社の選び方と注意点
ファクタリング取引の市場規模は、年々拡大しており、参入してくるファクタリング会社も年々増加傾向にあります。その中には、質の高いサービスを提供する事業者もあれば、手数料が不透明であったり、法外な条件を突きつけてくる悪質業者も存在します。
ファクタリングを装った違法な「ヤミ金融」も問題視されており、金融庁からも注意喚起がなされています。契約内容を精査し、信頼できる事業者を選ぶことが極めて重要です。(参考:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」)
選定時のチェックポイント
ファクタリング会社の選定にあたっては以下のようなポイントをチェックする必要があります。
・費用の明示性(手数料の内訳など)
・売掛先(第三債務者)との関係性への配慮
・契約内容(遅延時の対応やリコース条項の有無)
・過去の実績・信頼性・口コミ
また、財務コンサルタントや会計士、税理士など、専門家のサポートを得ながら導入を検討することも重要です。ファクタリング会社の多くは、銀行やノンバンクの系列であることは、信用のおけるファクタリング会社であると言えます。独立系のファクタリング会社でも業歴や取扱い実績などを基準にして、ファクタリング会社の選定をする必要もあるでしょう。また、ファクタリング取引を実施する際には、手数料、サービス内容、リコースの有無、2社間か3社間か、など2~3社のファクタリング会社を比較してみることも必要です。
ファクタリングによる経営改善とまとめ
ファクタリングはあくまで“資金繰り手段の一つ”にすぎません。しかしながら、実はこの仕組みを通じて「キャッシュフロー経営」「資産の流動化」「資金調達の多様化」「取引条件の改善」など、経営戦略そのものを見直すポイントが明確化され、経営改善の重要な機会になります。
例えば、ファクタリングをきっかけに、
・売掛サイトの短縮交渉
・売上の安定化施策(契約形態の見直し等)
・会計処理の見直し(資金繰り表の精緻化)
といった取り組みにつながれば、資金調達の問題を超えた企業体質の強化へとつながっていくのです。ファクタリング取引は、16世紀に起源をもつ歴史ある企業間取引形態ですが、「信用を資金に変える」という意味では、極めて現代的な資金調達手段であると言えます。特に売掛債権という“見えない無形資産”を有効活用できる点は、中小企業や個人事業主にとっても利用可能であり、資金繰り対策として大きな武器となります。一方で、短期的な資金確保だけに終始せず、「なぜ資金が不足するのか」「キャッシュフローをどう改善すべきか」「資金調達のバリエーションをどうするべきか」といった事業継続に関わる根本的な経営課題と向き合う契機だという認識が重要です。ファクタリング取引を資金繰りの窮地を救う“その場しのぎ”の弥縫策にとどめずに、“経営改善のチャンス”ととらえることで、より前向きな経営にシフトし、自社の持続的な成長の基礎作りとなる可能性を秘めているのです。
私たちヒューマントラストでは、ファクタリングの要望にもお応えしつつ、ファクタリング会社の推薦から、資金繰りを中心とする経営改善計画の策定、ビジネスローンの提供から、金融機関からの融資に関わるコンサルティング、一般的な経営戦略コンサルティングまで、幅広いコンサルティングメニューを準備して、中小企業やスタートアップ企業の持続可能な成長をサポートしています。
元銀行員・現役経営コンサルタントが
貴社の資金調達を直接サポートします
記事で解説した通り、ファクタリングは経営改善の「チャンス」です。
累計12,000社以上の支援実績を持つヒューマントラストが、貴社に最適なプランをご提案します。