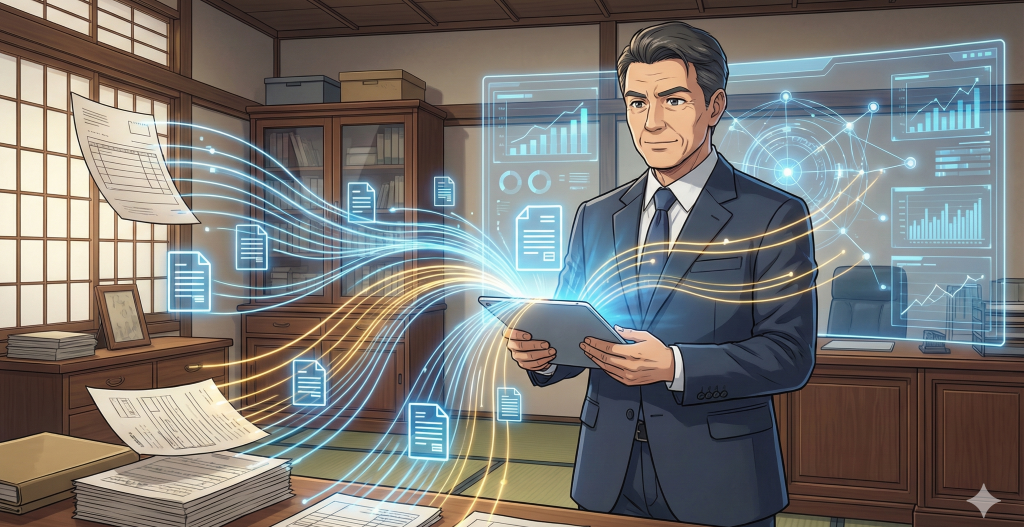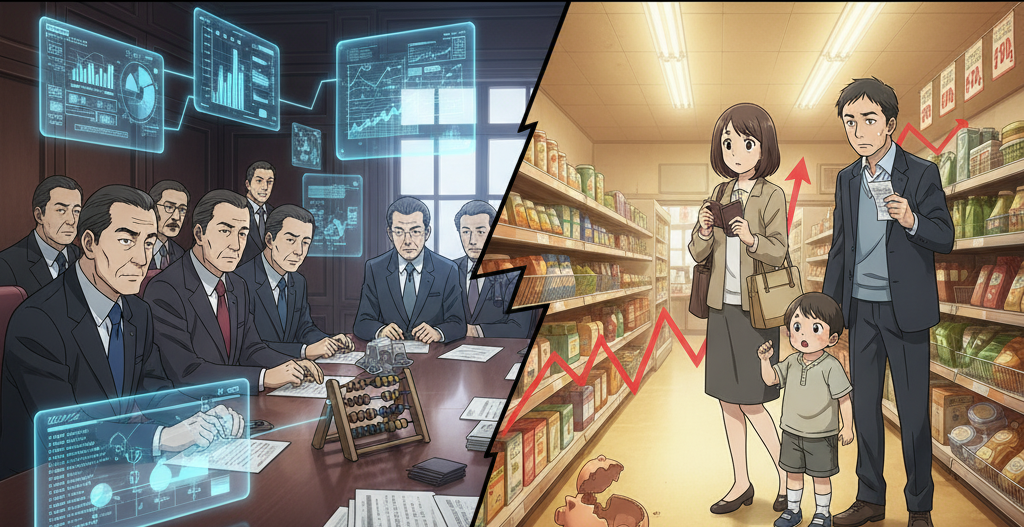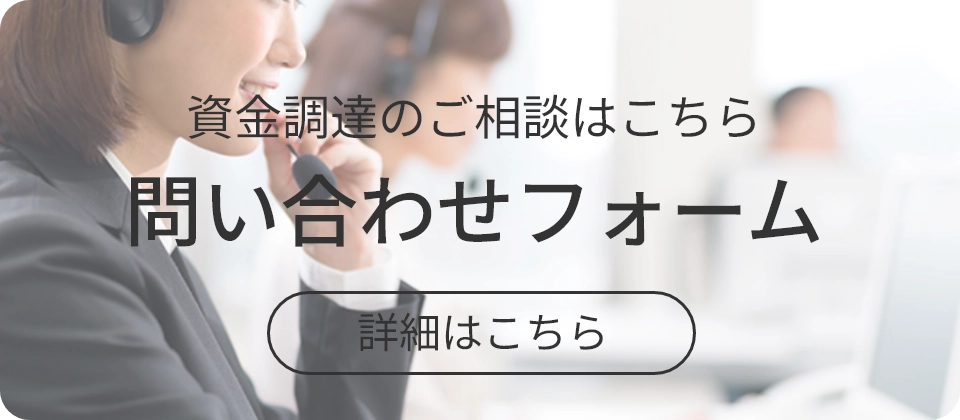公開日:2025.11.11
更新日:2025.11.11
「ESGは他人事ではない!」中小企業が今すぐ取り組むべき理由と具体策

「ESG」という言葉を聞いて、「それは大企業の話で、うちのような中小企業には関係ない」と思っていませんか?
近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営は、大企業だけのものではなくなりました。むしろ、中小企業こそ「他人事ではない」重要な経営テーマになっています。
なぜなら、取引先である大企業からサプライチェーン全体でのESG対応を求められたり、金融機関が融資判断にESGの視点を取り入れたり、さらには消費者の意識が変わり、「環境や社会に配慮しない企業」が選ばれにくくなっているからです。
今回のブログは、なぜ中小企業が”今すぐ”ESGに取り組むべきなのか、その具体的な理由と実践しやすい具体策、そして得られるメリットについて解説します。
この記事のポイント
- ESGは「取引先」「金融機関」「採用」の観点で、中小企業にこそ直結する経営課題である。
- 「現状の見える化」から始め、国や自治体の「補助金・助成金」を活用すればコスト懸念は解消できる。
- 「ESGウォッシュ」を避け、誠実な取り組みと発信が「未来への投資」として企業の信頼を築く。
- 専門家(認定支援機関)の支援で、ESG戦略と「資金調達」を連動させることが成功の鍵となる。
ESG経営の「はじめの一歩」でお悩みですか?
「何から手をつければ?」「自社でもできる?」
ESGの基本から資金調達まで、認定支援機関の専門家が無料でアドバイスします。
そもそもESGとは?
ESGとは、企業が長期的な成長を遂げるために考慮しなくてはいけない経営に関わる3つの要素です。21世紀になって議論になってきた持続可能性(サステナビリティ)の課題として、投資家が企業の価値を測る指標として使い始めた背景もあり、今や企業経営のスタンダードとなりつつあります。
- 環境(Environment):気候変動対策(CO2排出削減)、資源の有効活用、廃棄物管理など
- 社会(Social):労働環境の改善、人権尊重、地域社会への貢献、ダイバーシティ推進など
- ガバナンス(Governance):透明性のある経営、コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントなど
これらの要素を考慮したESG経営は、企業の持続可能性を高め、さまざまなステークホルダー(利害関係者)からの信頼を得ることにつながる、というのがESGの本質的な評価基準になっています。
なぜESGは「他人事」ではないのか?中小企業が直面する4つの現実
「メリットは分かったが、まだピンと来ない」という経営者様もいらっしゃるかもしれません。ここでは、ESGが中小企業の経営に直結する「4つの現実」について、さらに深掘りします。
1. 取引先(サプライチェーン)からの要請
最も現実的な影響がこれです。近年、大企業は自社のCO2排出量だけでなく、取引先(サプライチェーン全体)の排出量(Scope3)まで管理・開示することを求められています。
その結果、大企業は取引先である中小企業に対し、「環境に配慮した部品を使っているか」「人権侵害にあたる労働をさせていないか」といった調査や、具体的な取り組み(例:ISO14001の取得、CO2削減目標の設定)を求めるケースが急増しています。
これは、「ESGに対応できない企業は、取引先として選ばれなくなる(取引を打ち切られる)リスク」が現実化していることを意味します。逆に言えば、いち早く対応することで「選ばれるサプライヤー」としての地位を確立できます。
2. 金融機関・投資家からの評価の変化
以前は「担保・保証」や「決算書の数字」が中心だった金融機関の融資審査も大きく変わりました。
現在、多くの金融機関が「ESG融資」や「サステナビリティ・リンク・ローン」といった金融商品を提供しています。これは、企業のESGへの取り組みや目標達成度に応じて、金利を優遇するというものです。
金融機関は、ESGに取り組まない企業を「将来的な気候変動リスクや人権リスク(=不祥事リスク)を抱えた、返済能力に懸念のある企業」と見なし始めています。ESGへの取り組みは、安定した資金調達に不可欠な「企業の信用力」そのものになりつつあります。最新の中小企業の資金調達戦略については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
3. 採用市場での圧倒的優位性
深刻な人手不足に悩む中小企業にとって、ESGは「採用戦略」の切り札となり得ます。
特にミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若い世代は、報酬だけでなく「その企業が社会的に意義のある仕事をしているか」「倫理的か」を非常に重視します。
「劣悪な労働環境」「地域社会との不和」「環境汚染」といったイメージ(これらはまさにESGのSやEの課題です)を持つ企業から、優秀な人材は真っ先に離れていきます。働きやすい職場づくり(S)や環境配慮(E)をアピールすることは、他のどの採用広告よりも強力なメッセージとなります。
4. コスト削減とリスク回避
ESGへの取り組みは、短期的なコスト削減にも直結します。
- 環境(E):省エネ機器の導入やペーパーレス化は、光熱費や消耗品費を直接削減します。
- 社会(S):働きやすい職場づくりは、従業員の離職率を低下させます。これにより、採用コストや新人教育コストを大幅に削減できます。
- ガバナンス(G):法令順守やリスク管理体制の整備は、将来起こり得たかもしれない不祥事や事故を防ぎ、莫大な損害賠償や信用の失墜といった「最大のコスト(リスク)」を回避することにつながります。
中小企業でも実践できる!具体的なESG取り組み例
では、中小企業における具体的なESG取り組みとはどのようなものが想定されるでしょうか?ESGを実践するには、大きな投資だけでなく、日々の地道な行動が重要です。中小企業が実践しやすいESGの取り組みを紹介します。
中小企業の「ESG」取り組み具体例
E (Environment) : 環境
- LED照明・省エネ機器光熱費という「コスト削減」に直結
- ペーパーレス化消耗品費削減と業務効率化
- 廃棄物の削減・分別処理コストの削減
S (Social) : 社会
- 働き方改革(残業削減・リモート)で離職率低下
- 健康経営の推進従業員の満足度・生産性向上
- 地域貢献活動地元での「信用」獲得
G (Governance) : ガバナンス
- コンプライアンス強化不祥事リスクの回避
- BCP(事業継続計画)策定有事の際の「信用維持」
- 積極的な情報開示金融機関・取引先との信頼構築
1. 環境(E)領域
- エネルギーの効率化:LED照明の導入、省エネ機器への入れ替え、空調温度の適正管理
- 再生可能エネルギーの活用:社用車をハイブリッド車やEVにする、小規模な太陽光発電の導入やグリーン電力の契約
- 廃棄物管理:リサイクルの推進、廃棄物の分別徹底、仕入れの見直しによる食品ロスや廃材の削減
- 持続可能な資源利用:紙の使用削減(ペーパーレス化)、環境に優しい資材(例:FSC認証紙)の使用
2. 社会(S)領域
- 働きやすい職場づくり:ワークライフバランスの推進(残業削減)、リモートワークや時差出勤の導入
- 従業員の健康管理:健康診断の実施、メンタルヘルス対策、ストレスチェックの実施(健康経営)
- 多様性の促進:女性や外国人、高齢者の雇用促進、育児・介護支援制度の充実
- 地域貢献活動:地元のイベントへの参加・協賛、NPOとの協力、清掃活動
3. ガバナンス(G)領域
- コンプライアンスの強化:法令順守のための研修実施、社内規定(就業規則など)の整備
- リスクマネジメントの徹底:災害対策(BCP:事業継続計画の策定)、データセキュリティの向上、業務リスクの洗い出し
- 透明性のある経営:可能な範囲での財務情報の開示、社内ガバナンスの強化及び可視化(意思決定プロセスの明確化)
中小企業の「ESGはじめの一歩」実践ロードマップ
「具体策は分かったが、結局、明日から何をすれば?」という経営者様も多いでしょう。ESGは大掛かりなプロジェクトである必要はありません。まずは「はじめの一歩」を踏み出すことが重要です。
ステップ1:現状の「見える化」
まずは自社の現状を知ることから始めます。難しく考えず、集められる数字を確認してみましょう。
- 環境(E):月々の電気代、ガス代、水道代の請求書を確認する。ゴミの廃棄量やコピー用紙の購入量(コスト)を把握する。
- 社会(S):従業員の残業時間、有給休暇の取得率、過去1年間の離職率を計算してみる。
- ガバナンス(G):就業規則が最新の法令に合っているか確認する。
ステップ2:簡単な「サステナビリティ宣言」の策定
「見える化」で自社の強みや弱みが見えてきたら、「わが社として何を目指すか」を簡単な言葉でまとめてみましょう。立派なレポートである必要はありません。
例えば、「わが社は〇〇(本業)を通じて、〇〇(環境・社会)に貢献します」「従業員が働きやすい職場No.1を目指します」といった簡単な宣言を、自社のウェブサイトや会社案内に掲載するだけでも、社内外への大きなメッセージとなります。
ステップ3:小さな目標設定と実行
最初から大きな目標を立てる必要はありません。従業員全員で取り組める、達成可能な「小さな目標」を設定して実行します。
例:「コピー用紙の使用量を前年比10%削減する」「オフィスのエアコン設定温度を1度見直す」「月1回の地域清掃活動に参加する」
この「見える化 → 宣言 → 実行」という小さなサイクルを回していくことが、ESG経営の確実な第一歩となります。
中小企業のESG経営 成功事例
具体的なイメージを持っていただくために、いくつかの中小企業の事例をご紹介します。
事例1:製造業の省エネ対策
ある中小企業の製造業では、工場の照明をすべてLEDに切り替え(ステップ3)、年間の電力消費量を30%削減(ステップ1)し、コスト削減に成功しました。また、廃棄物の削減とリサイクルの推進により、環境負荷を低減させました。(Eとコスト削減)
事例2:働き方改革による人材確保
IT関連の中小企業では、「働きやすさ」を宣言し(ステップ2)、フレックスタイム制やリモートワークを柔軟に導入した結果、社員の満足度が向上し、離職率が低下しました。これにより、採用難の時代において優秀な人材の確保と生産性の向上を両立させています。(Sと採用)
事例3:透明性のある経営
あるサービス業の企業では、財務情報を定期的に公開し、社内の意思決定プロセスを明確にしたことで、取引先や顧客からの信頼を獲得しました。これにより、安定的な受注につながっています。(Gと信用)
ESG導入の壁?「コスト懸念」を乗り越えるには
このように、中小企業にとってもESGは避けて通れない重要な経営戦略です。
しかしながら、こうしたESG経営については、「コストアップ要因になるのではないか」と懸念されることが多くあります。確かに、LED照明への切り替え、省エネ機器の導入、人事制度の改定など、一時的なコスト(設備投資や研修費用)がかかる場合もあります。
解決策:補助金・助成金の徹底活用
この初期コストの壁を乗り越えるために、国や自治体は中小企業向けの豊富な支援策を用意しています。ESGへの取り組みは、これらの補助金・助成金の申請テーマとして非常に強力です。
- 省エネルギー投資促進支援事業費補助金:工場のLED化や高効率な空調・ボイラーへの更新など、(E)領域の設備投資に幅広く使えます。
- 事業再構築補助金:例えば、「環境配慮型の新製品開発」や「サステナブルな新サービス展開」など、ESGを切り口とした新しい取り組みに活用できます。
- IT導入補助金:ペーパーレス化を進めるための会計ソフトや勤怠管理システムの導入に活用できます。(EとSの両方に貢献)
- 働き方改革推進支援助成金:リモートワーク導入や残業削減のためのツール導入など、(S)領域の環境整備に使えます。
これらの補助金・助成金は、多くの場合「事業計画書」の作成が必要です。「自社のESGの取り組みがどう事業成長につながるか」を明確に示す必要があり、ここがファイナンスの専門家の腕の見せ所でもあります。補助金に強い「事業計画書」の作成方法については、こちらをご覧ください。
ESG経営の実践に関わるさまざまな経営課題については、「~すべき」という“べき論”は禁物だと認識しています。まずは「自社の本業とシナジーがあり、かつ着手しやすいところから始める」という現実的なアプローチと、こうした公的支援をうまく活用することが重要です。
ESGの「コスト懸念」を「資金調達」で解決
「使える補助金が知りたい」「事業計画書が書けない」…
認定支援機関である私たちが、補助金・助成金の活用から最適なファイナンスプランまで、ワンストップでご提案します。
ご注意:「ESGウォッシュ」と見なされないために
最後に、非常に重要な注意点があります。それは「ESGウォッシュ」です。
「ESGウォッシュ」とは、実態が伴っていないにもかかわらず、環境や社会に配慮しているかのように見せかける(=Greenwash)ことを指します。例えば、「実際は労働環境が悪いのに、ウェブサイトだけで『健康経営』を謳う」「環境負荷の高い製品なのに、一部だけを取り上げてエコであるかのように宣伝する」といったケースです。
こうした見せかけの取り組みは、一度発覚すれば、消費者や取引先、金融機関、そして従業員からの信頼を根本から失うことになり、取り組む前よりもはるかに深刻なダメージを受けます。
重要なのは、背伸びをしないことです。中小企業が大企業と同じレベルの開示を求められることはありません。むしろ、「今はここまでだが、将来的にここまで目指す」という誠実な姿勢と、小さな取り組みでも着実に実行し、それを正しく情報発信することが評価されます。
ガバナンス(G)の根幹は、この「誠実さ」と「透明性」にあると言えるでしょう。
まとめ:ESGは「他人事」ではない。「未来への投資」として今すぐ始めよう
ご紹介してきたように、ESG経営はもはや大企業だけのものではありません。中小企業にとっても、もはや「他人事」ではなく、持続的な成長のために「今すぐ」取り組むべき重要な経営戦略です。
実は、ESG経営を実践することに伴う一時的なコストアップ要因について、ファイナンスでカバーしていくことで、結果的には、生産性向上と収益アップにつなげることができます。
金融支援の審査担当の現場では、決算書(財務情報)をベースとする融資審査が多いのが現実ですが、徐々に事業性評価(非財務情報)のウェイトも大きくなりつつあります。ESGへの取り組みは、まさにこの「事業性評価」の核となる部分です。
社会的な存在である企業が、存続するべき存在であり続けることが、従業員や取引先、株主、借入先などの身近なステークホルダーの中長期の信用の醸成につながるのです。
HTファイナンスでは、単純な融資審査だけではなく、事業の社会性や将来性(まさにESGの視点)もファイナンスプランの設計に活用していきます。
「ESG経営の第一歩を踏み出したいが、何から手をつければ良いか分からない」「補助金を活用したいが、事業計画の作り方が分からない」という経営者様。その事業戦略とリンクした資金調達に関しても、気軽にHTファイナンスにご相談いただきたく思います。
ESGは「コスト」ではなく「未来への投資」です。「他人事」と捉えず、持続可能な未来への第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?
ESGは「未来への投資」。信頼できるパートナーと始めませんか?
ESG戦略の策定から、補助金を活用した資金調達、事業計画の実行まで。
累計12,000社以上の支援実績を持つヒューマントラストが、御社の持続的成長を伴走支援します。