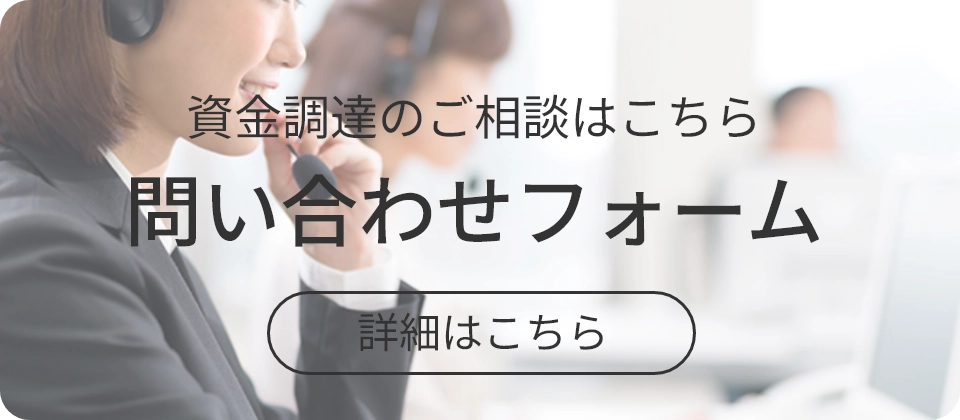公開日:2025.12.30
更新日:2025.12.30
【CSRと企業経営】利益至上主義からの脱却と、持続可能な成長へのパラダイムシフト

平成15年(2003年)頃、今からおよそ20年前の日本企業は、株価や時価総額に極めて敏感な時期にありました。
当時は、投資家から毎期の「増収増益」を強く求められ、ROA(総資産利益率)やROE(純資産利益率)といった財務指標の向上が、経営の至上命題とされていた時代です。
しかし現在、その評価軸は「利益至上主義」から「CSR(企業の社会的責任)」へと大きく変容しました。本記事では、かつての経営が抱えていた矛盾と、持続可能な成長へのパラダイムシフトについて解説します。
この記事の要約
- 20年前の「利益至上主義」は人口減少社会において構造的な限界を迎えた
- 企業が国家を超える経済力を持ったことで、社会的責任(CSR)が不可欠に
- 日本企業の伝統的な「三方よし」の精神こそが、現代のサステナブル経営の鍵
財務指標偏重の経営が招いた「成長の限界」と矛盾
結論:短期的な財務指標(ROE等)への偏重は、企業の持続可能性を損ない、人口減少市場において「成長の限界」という構造的な矛盾を招きました。
米国式経営への過度な適応とその弊害
2000年代初頭に見られた財務指標への偏重は、日本企業が米国式のキャッシュフロー経営や、短期的な収益を重視する投資家の行動原理に適応しようとした結果、過剰反応を起こしていた側面があります。
数値化しやすい財務データのみを経営の前面に押し出す一方で、数値化できない経営資源、独自の経営手法、あるいは企業の伝統や存在意義といった「見えざる資産」を評価の外側に置いてしまう傾向が強まりました。その結果、短期的な収益至上主義に陥り、長期的な視点での企業価値を見失うケースも少なくありませんでした。
「右肩上がり」神話の崩壊と市場の現実
当時、「増収増益」こそが企業の至上命題とされていましたが、冷静に分析すれば、企業が永遠に右肩上がりの成長を続けることには構造的な無理があります。
特に日本国内を市場とする場合、人口は頭打ちを経て減少傾向にあります。需要層である人口が減少する中で、同じ製品を同じペースで販売し続けるだけでも困難が伴います。当然、企業収益の成長には物理的な限界が訪れます。
さらに、技術革新やトレンドの変化に伴い、市場で求められる製品やサービスは常に流動的です。そのような環境下で「右肩上がりの成長」を堅持しようとすれば、同業他社をM&Aで吸収して市場占有率を無理やり上げるか、リスクを冒して新しい事業領域へ進出する以外に道はありません。
また、縮小する国内市場に見切りをつけて海外進出を図る手段もありますが、そこにはグローバル企業との熾烈な競争環境が待ち受けています。このように、市場環境や人口動態を鑑みれば、株価維持のために「常に増収増益が必要である」とする要求は、本来合理的とは言い難いものです。
平成15年頃の利益至上主義、および株主至上主義には、明らかに大きな矛盾が内在していました。視点を地球規模に広げれば、すべての企業が永続的に拡大再生産を続ければ、いずれ「地球環境の限界」という壁に衝突することは自明の理です。
企業が国家を超えた日:1999年の衝撃的なデータ
結論:国家予算を超える規模の巨大企業が出現したことで、企業活動が社会や環境に与える影響力が無視できなくなり、社会的責任(CSR)を問う声が必然的に高まりました。
20世紀型の企業評価と「会社は株主のもの」論
CSR(企業の社会的責任)という概念が経営の表舞台に登場する以前、利益至上主義的な経営においては、企業の社会貢献は次のような論理で語られていました。
- ・社会規範としての法令順守(コンプライアンス)
- ・人々の需要に対応する有用な製品やサービスの提供
- ・増収増益による高額納税を通じた社会への利益還元
- ・企業の事業活動を支える株主利益の最大化
これら4つの要素を活性化させ、高い株価と時価総額を実現することこそが「評価される企業」であるという考え方です。ここには「会社は出資者である株主のものである」という所有権の概念が根底にあり、雇用や納税を通じて社会還元している以上、それ以外の活動はコストでしかなく、不必要であると断じられていました。
20世紀においては、この考え方が一般的であり、「最適な資源(モノ、ヒト、カネ、情報)配分によって生産を最大化し、社会的価値を生むことが企業価値の源泉である」と認識されていました。資本主義諸国も、会社法制や税制、規制緩和などを通じて、このモデルを積極的に後押ししてきました。
国家GDPを凌駕する巨大企業の出現
20世紀を通じて成長を続けた企業群の中から、国家の経済規模をも凌駕する「スーパーパワー」が現れ始めました。1999年の統計記録を見ると、その衝撃的な事実が浮かび上がります。
「世界TOP100のスーパーパワーランキング(各国のGDPと企業の売上高を比較したもの)」においては、トップ100のうち、企業が51社、国が49か国という逆転現象が起きていました。
【1999年 GDP&売上高ランキング(単位:億ドル)】
上位には国家が並びますが、中位以降には巨大企業が食い込んでいます。
- 1位:アメリカ(8,708)
- 2位:日本(4,395)
- (中略)
- 23位:GM(ゼネラルモーターズ)(176)
- 24位:デンマーク(174)
- 25位:ウォルマート(166)
- 26位:エクソンモービル(163)
- (中略)
- 37位:三井物産(118)
- 38位:三菱商事(117)
- 39位:トヨタ自動車(115)
- 40位:GE(ゼネラル・エレクトリック)(111)
このように、巨大化した企業は経済力を武器に社会的影響力を強め、国家を超える存在となりました。現在のGAFA(Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon)などはその現代版と言えます。
企業がこれほどまでの力を持ち、世界経済に影響を与えるようになったからこそ、公共・公正・公平といった「社会的価値」や「責任」を企業にも負担させるべきだという議論が生まれるのは、歴史的な必然でした。
理想の経営を実現するための「資金」準備は万全ですか?
CSRやSDGsへの取り組み、従業員への還元など、持続可能な経営を行うには安定した財務基盤が不可欠です。貴社の状況に合わせた最適な資金調達プランを無料で診断します。
CSRの誕生:利益至上主義の限界と世界的潮流
結論:環境破壊や格差拡大などのグローバル課題に対し、SDGsや京都議定書などの国際的な枠組みが整備され、企業経営にサステナビリティの実装が不可欠となりました。
顕在化したグローバルな課題
第2次世界大戦後の経済成長の中で、「企業は株主のもの」「納税と雇用で責任は果たしている」という論理は、20世紀末に限界を迎えます。企業の巨大化とともに、その活動による弊害が地球規模で顕在化したからです。
- ・途上国における資源や労働力の搾取
- ・環境破壊や人権侵害
- ・先進国と途上国の貧富格差の拡大
- ・世界規模での安全保障や治安の悪化
これらに加え、情報技術の進化による監視の目、市民社会の台頭、先進国の少子高齢化、そして各国の財政逼迫などが重なり、政府だけでは解決できない課題が山積しました。その結果、企業に対しても事業活動の持続可能性(サステナビリティ)について責任を負わせるべきであるという潮流が主流となっていったのです。
「成長の限界」からSDGsへの道程
この流れを決定づけたのは、いくつかの歴史的な転換点です。
まず、1972年にローマクラブが報告書『成長の限界』を発表し、「人口増加や環境汚染を放置すれば人類は破局する」と警鐘を鳴らしました。同年の国連人間環境会議では「環境と開発の両立」が謳われ、1987年の国連ブルントラント委員会では「持続可能な発展(Sustainable Development)」という概念が導入されました。「将来世代のニーズを損ねることなく、現在のニーズを満たす」という考え方の誕生です。
その後、1992年の地球サミットを経て、1997年の京都議定書採択へと繋がります。ここでは温室効果ガスの削減目標が具体的に決議されました。南北問題や足並みの乱れはありつつも、この一連の流れが、今日の「SDGs(持続可能な開発目標)」という世界共通の言語へと結実しています。
日本におけるCSRの変遷と「三方よし」への回帰
「コスト」から「経営戦略」へ
日本で「CSR(企業の社会的責任)」という言葉が経営コンサルティングの現場で使われ始めた約20年前、その受け止められ方は現在とは全く異なるものでした。
当時は、CSR活動といえば「企業収益にはプラスにならないボランティア」「コスト増加の要因」という認識が大半を占めていました。多くの企業では広報部が担当し、単なる企業PRの一環として扱われるか、「予算を出すからNPOに任せておけばいい」といった対応が一般的でした。担当者すらいない企業も珍しくありませんでした。
伝統的経営思想との融合
しかし現在では、国連のSDGsバッジを身につけるビジネスパーソンが溢れ、CSRやサステナビリティへの取り組みは企業として「当然の責務」となっています。企業規模を問わず、社会貢献を意識した経営方針を掲げる会社が増加しています。
外務省「JAPAN SDGs Action Platform」
かつて、某投資家による「カネもうけは悪いことですか?」という発言が注目を集め、企業の収益活動に対してネガティブなイメージが先行した時期もありました。しかし、日本には古来より「会社は社会の公器」や近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」といった伝統的な経営思想が根付いています。欧米式の「会社は株主のもの」というドライな考え方に対し、違和感を抱く土壌があったとも言えます。
現在進行している新しい企業経営の形は、一周回って、日本の伝統的な経営思想に近いものへと回帰しているのではないでしょうか。
社会貢献を実施する企業が社会から支持され、持続・成長し、さらに大きな貢献を行う。この好循環を生み出す経済社会の構築こそが、20世紀型の利益至上主義・株主至上主義の弊害を克服し、世界規模での人々の幸福に資する道であると言えます。
経営パラダイムの転換
従来の経営(20世紀型)
- 優先順位株主利益・短期収益(PL脳)
- 評価指標売上高、ROE、時価総額
- CSRの扱いコスト、ボランティア
これからの経営(三方よし)
- 優先順位全ステークホルダー・持続可能性
- 評価指標ESG、信用力、社会貢献度
- CSRの扱い成長戦略、投資対象
あわせて読みたい:「経営戦略」だけで勝てない理由とは?VUCA時代に成長企業が実践する「経営管理」の真髄
まとめ
20年前には「コスト」と見なされていたCSRは、今や企業存続に不可欠な「経営戦略」の中核をなしています。財務的な透明性を高めつつ、社会的な課題解決にも取り組む姿勢こそが、現代の企業評価のスタンダードとなりました。
かつての利益至上主義がもたらした教訓と、日本企業が本来持っていた「三方よし」などの倫理観が融合し、今、新たな経営の形が生まれつつあります。経済的価値と社会的価値の両立を目指すこの流れこそが、これからの企業が目指すべき持続可能な成長のモデルと言えるでしょう。